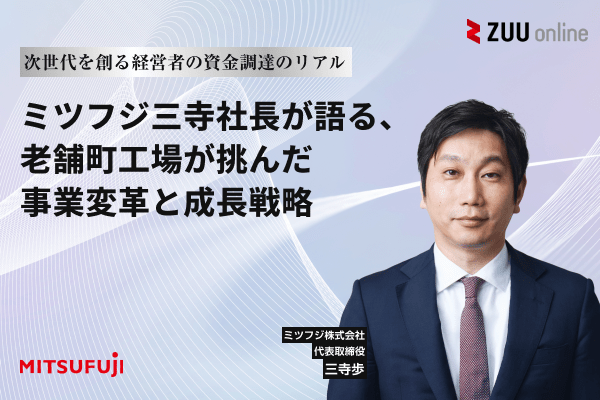
2025年の職場の熱中症対策義務化に伴い、特許取得済の独自アルゴリズムを搭載し、作業者の猛暑リスクをリアルタイムで可視化できるスタンドアロン型のリストバンド「hamon band」の最新モデル「hamon band S」を今年4月に発売。すでに大林組、ヤマト運輸、ダスキンなどの大手建設・物流会社で20万台以上の導入実績あり。さらに同年6月にe-SIM搭載のスマートウオッチ型新モデル「hamon band N」、8月には2022年に発表した「MITSUFUJI 03」のリニューアルモデルを発表。猛暑リスクだけでなく、ストレスや体調、転倒検知なども可視化し、労働環境の改善に寄与している。
資金調達の戦略的意義 ミツフジが見据える事業成長の転換点

ーー今回、大型の資金調達をするに至った背景について改めてお聞かせください。
当社は、ウェアラブル市場が大きくなってきたことと売り上げが大きく伸びてきたこのタイミングで、ODM※1やOEM※2の会社を目指すのか、それとも自分たちのブランドを輝かせて世界で勝負をするのか、大きな意思決定が必要になりました。
加えて、技術のパラダイムシフト※3が起きており、当社が長年取り組んできた導電性繊維の事業に、新たなチャンスが訪れました。ウェアラブルと電磁波シールドの産業資材という2つの分野が、経済安全保障※4の観点からも重要視されています。この大きな波に乗るためには、研究開発と大規模な人材採用への投資が不可欠であり、そこに踏み込むかどうかについても意思決定をする必要がありました。
最終的に、非常に数字が伸びているこのタイミングで、もう一段大きな成長をしたいという思いから、今回の資金調達を決断しました。
※2 相手会社の発注品の、相手先ブランドの形をとった生産
※3 ある時代において当然とされていた認識、思想、価値観が、革命的または劇的に変化すること
※4 重要な技術や物資の供給網を確保し、他国への過度な依存を減らすことで、国の安全を守る考え方
参考:ZUU Funders、12.5億円規模の新ファンド『ZUUターゲットファンド for ミツフジ投資事業有限責任組合』を組成
ーーこれまでも何度か資金調達にチャレンジされてきたかと思いますが、資金調達そのものに対してや、今回の資金調達で苦労されたことはありますか?
資金調達という意味では、夢や可能性だけで出資してくれるわけではなく、蓋然性がより強く求められるようになってきていることは難しい点だと感じています。事業会社が事業シナジーや可能性を信じて出資してくださるケースはありましたが、これまで大型の資金調達で大きな成長ステージに乗せるというところまでは至りませんでした。また、VC(ベンチャーキャピタル)ごとに蓋然性の基準が異なり、前回も苦労しました。
今回は、大型調達を目標に取り組みましたが、やはり蓋然性の問題にぶつかりました。「売り上げが上がったら出資する、しかし売り上げを上げるには資金が必要だ」という、いわゆる「鶏と卵」の状態をどう打開するかが最大の課題でした。
ーーそのような中で、投資家やパートナーに思いを伝え、信頼を勝ち取るために大切にされたことは何でしょうか?
当社は新規事業に取り組んでいるという意味ではスタートアップですが、事業歴でみるとスタートアップではありません。VCの中には最初から難しいと判断するところもあれば、「これまでの苦労を乗り越えてきたのであれば、今後も問題を乗り越えていくだろう」と信じてくださる方もいらっしゃいました。
大切にしてきたことは、当社が苦労してきたことも、どんなことが起きたかも正直にお話ししたことです。直近のトラックレコードも正直にお話しし、この会社が将来何をしようとしているのか、未来を信じて、一緒にやっていこうと言ってくださる方が今回パートナーになってくださったと思っています。
ーー論理や数値でお話する部分と、事業に対して情熱でお話する部分、その両立がやはり大事ということでしょうか?
そうですね。数字ばかりの話をすると、「社長は、どうなりたいんですか?どんな未来を作りたいんですか?」と聞かれることがあります。そこを大事にしてほしいという投資家の方も多くいらっしゃり、今回は、その部分をきちんとお伝えできたと思います。
資金調達が拓く未来の扉 ミツフジ社が描く成長戦略
ーー今回調達された資金は、具体的にどのような分野に投資されるのでしょうか?
主には、研究開発体制の強化と、ウェアラブルの市場が大きくなってきているため、営業体制の強化の2つを中心に考えています。また、営業、開発ともに海外経験がある人材を既に採用していますので、この結果として海外展開も同時に狙っていく取り組みを進めていきたいと考えています。
これまで、売り上げ拡大が先行し、社内体制やITインフラ、海外展開に向けての人材採用などが後回しになり、現場の負担が大きくなっていました。また弊社のお客様はほとんどがエンタープライズ企業です。そのようなお客様と向き合い様々なご要望や経営課題への対応ができる経営幹部の採用などの体制づくりが急務でした。
ーー御社の強みであるウェアラブルIoTソリューションは、すでに熱中症対策で多くの企業に導入されていると思います。今後、その先にはどのようなイノベーションを起こし、どんな社会課題を解決できるとお考えですか?
熱中症対策は法制化されたので、法律に対応する企業様のお役に立てるウェアラブル製品を企画・販売していきます。また、日本は超少子高齢社会という課題先進国です。世界中で同時に少子高齢化が進む中で、医療や介護の分野では、自動化やコスト削減が求められます。
当社は、これらのサービスの最前線での会社だと思っています。医療・介護分野で自動化が起きる、もしくはAIによる診断サービスが入る際に使っていただけるデバイスやアルゴリズムを開発し、提供していきたいと思っています。
熱中症対策は日本が世界を先行していますので、日本で技術を確立し、今後海外展開も図っていきたいと考えています。すでに海外の大手ウェアラブルベンダーからも協業の申し入れが来ているため、そういったところも活用し、すでにあるブランドとの連携も進めていきたいと考えています。

ーー将来的にはIPOも視野に入れているかと思います。今回の資金調達も踏まえ、IPOの先の成長に向けて、どのようなマイルストーンを置かれていますか?
現在、最短でIPO(株式公開)ができるよう社内の準備を進めています。その目的は2つあり、まず投資家の方にイグジットポイントを作るという経営者としての責任があります。もう一つは、世界に挑戦できる体制をしっかり作ることです。資金の基盤を強化した上で、開発体制を構築し経営していきたいと思っているため、上場後まずは資金を調達し、透明性の高い会社にした上で成長させていくことを目標に取り組みたいと思っています。
ZUUとのパートナーシップが拓く、成長の新たな扉
ーー今回、数ある支援仲介会社の中から当社に決めていただけた理由や、きっかけをお聞かせいただけますか?
ZUU社が幅広い視野で多くの企業を見てこられた中で、当社の可能性を信じてくださったことが大きいです。ZUU社の顧客層は、ZUU社にとって最も大切な財産だと思いますが、そのお客様に自信を持って当社をご紹介いただけたのが、お付き合いさせていただく一番のきっかけでした。本当に素晴らしいご縁をいただいたと思っています。
ーー実際に当社の資金調達支援活動において、どのようなメリットがあったと感じていらっしゃいますか?
事業会社では投資家に対して「当社は絶対にできます!」と言い切れない部分があります。そうした中で、ZUU社は中立的な立場で、適切な情報の整理とアドバイスを投資家の方にしてくれたと思っています。これにより、当社だけでは伝えきれない熱意や可能性を、投資家にきちんと伝えていただくことができました。
他にも、ZUU社にご紹介いただいた企業や投資家様から、実際に発注をいただくことが増えています。また、以前より接点を持ちたかったが、なかなか機会がなかったという会社さんとも、ZUU社を介すことで新たにつながりを持つことができました。このように、事業を共にするパートナーを得られたことが、本当に素晴らしいチャンスだったと思っています。
―ー今後、当社のサービスやネットワークをどのように活用していきたいとお考えですか?
ZUU社はメディアもお持ちですし、事業会社から見ると素晴らしい顧客基盤とプロフェッショナルなファイナンスサービスを持っています。今後、当社がリソースを割けない部分を補完していただいたり、メンターとしてご一緒していただけると非常にありがたいです。
また、「右に行くか左に行くか」という時に、「この選択肢があるよね」というように、二手三手先の正解を一緒に見つけていきたいです。他にも、ZUU社のネットワークを通じて、シナジー効果を見込める方をご紹介いただくなど、今後の広がりを作っていただけることを期待しています。
資金調達を検討中の経営者の方々へ
ーー最後に、資金調達を検討されている経営者の方々へ、アドバイスをお願いします。
経営者は、資金が必要な状況になるとどうしても視野が狭くなり、焦りから「とにかく出資してくれる人、お金が集まればいい」と考えがちかと思います。しかし、それでは本質的ではないと思います。
デット(借入)ではなくエクイティ(出資)という選択をするのには必ず理由があり、例えば、短時間で大規模な資金が必要であったり、あるいは借入では解決できない課題があったりします。
大切なのは、「何のためにお金を集めて、何のために成長するのか」という事業のストーリーや計画を立てることだと思います。これがなければ、誰も見向きもしてくれないと思います。資金調達の環境が厳しくなっている時期だからこそ、そういった部分のアドバイスを受けながらしっかり構築していくことが重要になると思います。