本記事は、橋本 之克氏の著書『100円のコーヒーが1000円で売れる理由、説明できますか?』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。
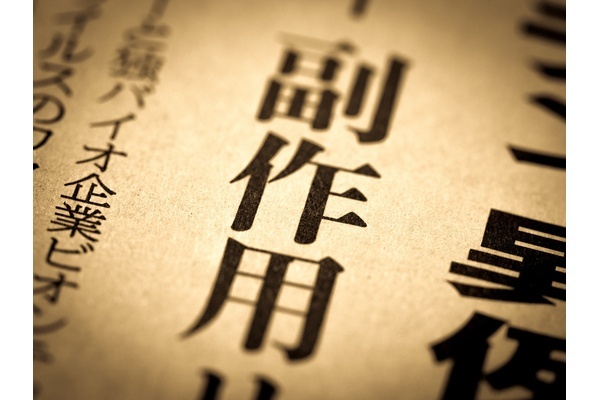
「住宅ローンは当たり前」という考え方の落とし穴
住宅ローンは「サラ金」と同じ?
住宅ローンは、金融機関が売り手となる「金融商品」の1つです。
家を買うにあたって住宅ローンはつき物、借りるのが当然、という認識を持つ人は多いかもしれません。まわりを見ても、借りている人が多いのではないでしょうか。
そういう商品に対しては、内容などをよく見極めずにお金を払ってしまいがちです。
それ以前に住宅ローンのような金融商品は、感覚的にわかりにくいため、詳しく調べるのを敬遠してしまう傾向があります。
しかし、その特徴や扱い方を確認することは、「いい買い物」のために不可欠です。家を買うとなれば、数千万円の現金を持っているか、親などから無利子で借りられる人以外は、住宅ローンを借りることになります。ほかに選択肢はありません。このような商品の利用動機も、住宅ローン独特のものです。
国土交通省の住宅市場動向調査によれば、住宅ローンの平均返済期間は、分譲戸建てで32.8年、分譲マンションで29.7年です。
仮に、住宅購入に必要な金額を4,500万円として、固定金利2%の35年ローンを組んだとします。シミュレーションすると、返済総額は6,260万8,560円で、利息分は1,760万8,560円です。4,500万円の住宅を取得するために、約1,800万円のお金を余計に払う必要があるということです。
もちろん、4,500万円の現金を持っていれば、この支払いは不要です。持たざる者にとっては厳しい、ある意味では格差が広がる仕組みと考えることもできます。
このローンという金融商品は、お金を借りる側が、利息という形で貸し出す金融機関に費用を払います。キャッシングやカードローンと構造は同じです。
さらにいうと、2000年ごろまで世の中に横行していた「サラ金」とも、基本的には同じ金融商品です。可能ならば利用を避けるべき商品でしょう。
住宅ローンを借りれば、返済義務を負います。同時に、返済が滞れば家を失うリスクを負うことになります。返済は平均30年以上の長期間にわたるものです。この間、リストラ、事業の失敗、ケガや病気などで、返済が難しくなる可能性はゼロではありません。長く返済が滞れば家を失い、さらに最悪の場合は借金が残ることもあります。
最近は、夫婦で家を買う場合などに、2人の収入を合わせた金額を収入とする「収入合算」や、1つの家を買うために2人がそれぞれ債務者となる、「ペアローン」などの住宅ローンもあります。ともに借入額を増やせるため、より高額の家を買うことができます。
しかし、リスクも同時に高くなります。どちらか一方の収入が途絶えると、途端に返済が厳しくなります。また、このご時世では離婚も増えていますが、そうなった場合、通常以上に面倒が増えることは間違いありません。夫婦仲よく健康で、返済まで30年以上、働き続けることが必要条件なのです。
これらが、住宅ローンに伴うリスクです。ローンのリスクを背負うことにより、人生におけるほかのリスクを避ける必要に迫られます。
たとえば、収入が不安定になりかねない起業や独立の判断には、慎重にならざるを得ません。転居を伴う転職の場合は、ローン支払い中の現住居をどう扱うか悩むでしょう。住宅ローン返済中は、ある程度、人生における自由を手放さざるを得ないのです。
「フレーミング効果」で行動が変わる
一方で、住宅ローンにはいい面もあります。
貯金をし続けることで、家の購入資金を貯めるのは簡単ではありません。住宅ローンによって強制的に支払い続けなければならない状況に置かれることで、家という高額な買い物ができるという効果もあるのです。
かつて大和証券グループによる、行動経済学をテーマとしたストーリー仕立てのテレビCMシリーズがありました。その中の1つは、以下のようなものです。
床屋内の場面で、主人が、お店で働く青年に給料を渡しています。主人は「この給料の2割を貯金するように」と青年に言うと、彼は「無理だ」と答えます。次に主人が「この給料の8割で暮らしてごらん」と言い換えると、青年は「やってみる」と答えました。同じ行動なのに、言い方によって、可能だと思えたり不可能だと思えたりするわけです。
ここでは、行動経済学における「フレーミング効果」が影響しています。
これは同じ内容であっても、問題の提示の仕方、焦点のあて方により、人の判断や選択が変わるという心理的バイアスです。
仮に、家を買うために収入の2割を貯金しようと考えても、強い意志がなければ途中で挫折する可能性があります。初めから難しいと考えて、住宅購入をあきらめてしまうかもしれません。しかし、住宅ローンで引き落とされた残りの8割で暮らすのは、貯金ほどは難しく感じないでしょう。
さらに、住宅ローンを借りれば、心理的プレッシャーを受けることになります。仮に、住宅ローンの返済が何度も遅れれば、金融機関が個人を評価する際の信用力が低下します。その後の人生に影響しかねませんので、これは1種のペナルティです。これを避けるために日々のムダづかいを控えて、返済し続けることになるでしょう。
このように、住宅ローンにはいい面も悪い面もあります。リスクがあるのも事実ですが、十分な現金を持たず家を買うなら、受け入れるしかありません。
ただし、リスクがあることは認識しておく必要があります。必要なのは、可能な限りリスクを減らすことです。
返済額より借入額を見て判断するリスク
ここからは、行動経済学の知見を活用して、住宅ローンに関わるリスクを見ていきます。まず「借りている金額を甘く見てしまう」リスクです。
「アンカリング効果」について、これは、最初に提示された数字などが基準となって、無意識にその後の判断に影響を与える効果です。
たとえば、スーパーなどで、もとの値段が消されて値引き後の額が書かれているのは、アンカリング効果による安さの演出です。
欲しい家を見つけて、住宅ローンを検討する場合、最初に意識する数字は「借入額」でしょう。家の価格や諸経費などから、まず借りる金額を算出します。
次に、返済プランをシミュレーションします。その際は、月々やボーナスの「返済額」に注目するでしょう。払い続けることができるのか、判断しなければなりませんから。
その過程で、一応「総返済額」を目にするでしょう。借入額よりも、かなり大きい金額であり、これが実際に支払わなければならない金額です。
したがって、この金額を支払っていく覚悟を持つ必要があります。
返済が滞るような事態が起きた場合に、背負わなければならないのは「借入額」ではなく「返済額」です。しかし、アンカリング効果が働くと、より安い「借入額」が頭に残ります。無意識に自分の負債を軽く考えてしまう可能性があるので、注意が必要です。
また、別のリスクとして、借り換えなどによる「返済負担軽減の機会を逃す」ことがあげられます。「メンタル・アカウンティング」の影響で起きるものです。これは、支払い方法などによって、感じるお金の価値が変わる心理的バイアスでした。
通常の住宅ローンは、銀行口座から自動引き落としなどで支払うことが多いでしょう。この自動的な支払い方は、社会保険や税金など、日常生活に必要な諸経費と同じです。
メンタル・アカウンティングの影響で、これらの支払いを同じ“くくり”で考えてしまう可能性があります。つまり、「初めに決められたとおりに払うのが当たり前」と認識してしまうリスクがあるのです。
社会保険や税金などは、支払う先や金額は決まっています。一方、住宅ローンは、借り換えで返済先を変えることができます(金融機関による審査を通る必要はありますが)。よく探せば、返済負担を軽くすることも可能でしょう。
金融機関によっては、住宅ローン契約者向けに、キャッシュバックや振込やATM利用の手数料無料などの特典を用意しています。これらの機会を逃してはいけません。
ちなみに、最初の借入時点における金融機関選びにも、注意が必要です。家を買った経験がないと、住宅販売会社などがすすめる提携金融機関の中から選びがちです。
たしかに、その場合は、手間が少なくて済みます。しかし、ほかの金融機関より金利が高いかもしれません。わずかな金利の違いでも、返済額に大きく影響します。
また金融機関によっては、借り入れ時に加入する団体信用生命保険(住宅ローン契約者に万が一のことがあった際にローン残高がゼロになる保険)の補償内容が、ほかよりもすぐれている場合もあります。金融機関選びの参考にするといいでしょう。住宅ローンは超高額の取引ですから、漫然と借り入れや返済をおこなうのでなく、主体的に取り組むことが重要です。
「計画錯誤」が理想と現実のギャップを生む
もう1つ、住宅ローンに関わるリスクとして、「長期の計画に失敗する」ことがあります。頭金を貯める、繰り上げ返済をするなど、さまざまな計画を立てる際に「計画錯誤」の影響を受ける可能性があるのです。
これは計画を立てるにあたって、目標を達成するまでに必要な時間、労力、お金などを、実際よりも少なく見積もりすぎる心理的バイアスです。
人は誰でも、無意識のうちに、計画を甘く立ててしまうものなのです。これは、計画性がない人や努力が足りない人だけではなく、誰にでも起こり得ることです。
対処方法は、いくつかあります。その1つは「目標に至るまでの手順や要素を、細かく分解し、個々に必要な時間や行動などを見積もる」ことです。
プロセスを分割(アンパックと呼びます)し、その結果を総合して、全体を見積もるのです。
たとえば、ざっくりと5年で頭金を貯めるといった感じでひとまとめにするのではなく、1年ごとあるいは1か月ごとに貯める金額、毎月の減らすべき出費など、要素を細かく具体化するのです。
このプロセスを入れることで、計画の精度は高まります。
ほかの対処方法として、ありきたりではありますが、あらかじめ余裕のある計画を立てることなども、効果があります。
行動経済学の知識を活用してリスク軽減を
金融商品全般にもいえることですが、住宅ローンの大きな特徴は「形がない」商品だということです。ゆえに、車のように乗り心地をたしかめたり、ビールのようにのど越しを味わったりすることができません。
もう1つの大きな特徴は、「数字の組合せ」でできていることです。
住宅ローンの要素を大まかにいえば、金利、借入可能額、返済期間、諸費用などでしょう。これらの組合せで「どんな住宅ローンか」が決まります。さまざまな金融機関が住宅ローンを提供していますが、付帯サービスなどに若干の違いはあっても、基本的な要素はどれも同じです。
こういった特徴がある住宅ローンは感覚的に理解しにくく、「自分にとっていい商品を見つけにくいものだ」と認識しておくことが必要です。
また、住宅ローンを一度借りたら、利息を含めた返済額は膨大な金額になります。
返済が滞るリスクがあり、人生における自由が奪われる可能性もある危険な商品です。
しかしながら、現金を持たずに家を買うためには必要不可欠です。返済の強制力が、逆に高額の支払いを可能にする側面もあります。
特徴をあげていくほど、住宅ローンが特殊な商品であることがおわかりでしょう。効果は高いが副作用の危険もある、いわば劇薬のようなものと考えていいかもしれません。
この商品の「いい買い方」は、可能な限りリスクを減らすことです。借入額を正しく認識し、負担軽減の機会を逃さず、長期計画を誤らないことが必要なのです。
その際は、行動経済学における心理的バイアスの知識を活用して、自分自身の行動をチェックしてください。ローンを借りる際は、ぜひ漫然とではなく主体的に選び、関わりましょう。約30年後、無事に完済して、返済から解放される快さを味わってください。
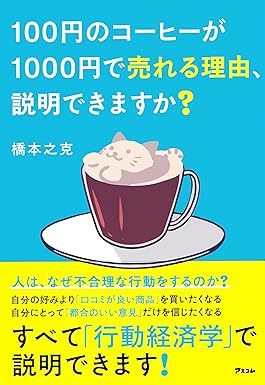
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
昭和女子大学「現代ビジネス研究所」研究員、戸板女子短期大学非常勤講師、文教大学非常勤講師を兼任。『世界は行動経済学でできている』(アスコム)、『世界最先端の研究が教える新事実 行動経済学BEST100』(総合法令出版)、『ミクロ・マクロの前に 今さら聞けない行動経済学の超基本』(朝日新聞出版)などの著書や、関連する講演・執筆も多数。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
