本記事は、橋本 之克氏の著書『100円のコーヒーが1000円で売れる理由、説明できますか?』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

「やめたいのに、やめられない!」の正体
酒や煙草をなかなかやめられないワケ
1961年の名画「ティファニーで朝食を」では、主演俳優のオードリー・ヘップバーンが、黒いカクテルドレスに身を包んで長いキセルから煙草を吸っていました。
昭和の人気刑事ドラマ「太陽にほえろ!」でも、松田優作が演じるジーパン刑事は、犯人に撃たれた瀕死の状態で、最後の1本を吸おうとしました。また、シャンパンからウイスキーまで、さまざまな酒が、ドラマの雰囲気を醸し出すために一役買っています。
煙草や酒などの嗜好品は、かつては人々の好感度を高める要素でした。ところが、今やこれらは、すっかり世の中の悪役になってしまったようです。
煙草の煙のタールには60種類を超える発がん物質が含まれ、体中を循環しつつ、さまざまな病を引き起こすことが明らかにされています。
また、酒に含まれるアルコールは体内の粘膜を直接刺激し、さらに体内で生まれるアセトアルデヒドには発がん作用もあることが知られるようになりました。
一方で、これらは家計を圧迫する要因でもあります。
このところ、煙草は頻繁に値上げされています。
仮に1箱20本入り550円の煙草を1日に1箱吸うとすると、30日で約1万6,500円、1年で約20万円もかかる計算です。
酒も同じです。1本200円の缶ビールも、飲み始めれば本数は増えてしまいがち。
ましてや、外で飲めば1軒で何千円、場所によっては何万円とかかってしまいます。
健康から財布まで、さまざまな弊害のある酒や煙草をやめようと思いながら、意思に反してやめられない人も多いのではないでしょうか。
こういった場合は、「現在志向バイアス」が働いている可能性があります。現在志向バイアスが働くと、人は目の前にある事柄を実際以上に評価してしまいます。将来得られる喜びや利益よりも、目の前にある喜びや利益を優先するのです。
将来に健康を損なうリスクや、時間とともに積み重なる外食のコストよりも、今の一服の心地よさ、酒場の雰囲気や酔って感じる高揚感を選んでしまいます。
現在志向バイアスは、日本のことわざ「明日の百より今日の五十」にも通じます。
夏が来るまでに痩せようと決めたのに、目の前のケーキを我慢できない、という現象もこのバイアスによるものです。
このような判断は、太古の昔、人間の文明が発達する以前から続く脳の働きによるものと考えられています。
当時は十分な食料も得られず、獣に襲われるなどの危険の中で生きていたため、明日の命もわからなかったわけです。
目の前にあるものは食べるべきであり、その本能に従って行動した者だけが生き延びられたのです。目の前の利益を大切にすることは、現在では不合理な判断になり得ますが、太古の昔には合理的な判断でした。
脳の働きによるバイアスは、なかなか自分で意識することができません。気づかないまま、健康を害したり、お金を使いすぎたりしてしまいます。
したがって、このような心理が自分の心の中で働いているかもしれないと気づくことは、自分をコントロールする第一歩になります。
この気づきによって、喫煙や酒場通いの頻度を改善できれば、お金の節約にもつながることでしょう。
日常のストレスが私たちにお金を使わせる
ただし、単に酒や煙草をやめれば生活もお金の使い方も問題解消となるかというと、必ずしもそうではありません。
習慣的に酒や煙草を愛用していた人が急にそれらをやめたとき、反動が出る場合があるからです。
今の世の中はストレスを生む原因があふれています。世界的な景気停滞は収入に影響しますし、コロナ禍など疫病の流行は日常行動を制限します。
それでなくても、仕事や家庭が、つねに順風満帆とはいかないのが人生です。そういった中で生きるには、何かしら憂さをはらすものが必要になります。
「健康や節約のために」と酒や煙草をやめた結果、ストレスが溜まってパチンコなどのギャンブルや、ソーシャルゲームにお金をつぎ込んでしまう可能性もあり得ます。
場合によっては、元の木阿弥どころか、むしろお金を使いすぎてしまうかもしれません。
何かに没頭することで、疲れを癒し、気分転換することは精神衛生上よいものです。
ドライブ、DIY、動物を飼う、旅行をするなど、さまざまな趣味は生活を円滑にし、ストレスを解消してくれます。
酒や煙草も、気分の転換や精神の安定に役立つという点では、趣味と同じ効用があります(もちろん健康を害しない限りにおいて、という条件付きですが)。
しかし、健康的な趣味であっても、長く続けて深めていくにつれて、欲しい物は増えていくでしょう。
たとえば、軽量かつ高性能になった釣り具、バトルゲームで使える強力なアイテム、愛犬に着せたいかわいいコスチュームなど、見回せば買いたいものは次々に現れます。
これらを買い続けていけば結局、酒や煙草よりももっと多くの金額がかかっても不思議ではありません。
「習慣的な買い物」は散財につながる
酒や煙草を嗜むにしろ、趣味を楽しむにしろ、精神的に必要なことにお金を費やすことはムダではありません。
いちばんの問題は、自分でコントロールできない散財です。
経済面や健康面の影響も考慮したうえで判断する買い物ならば、それは自分でコントロールできる買い物だといえます。問題なのは、何も考えずお金を払い続けてしまうことです。
こうした「習慣的な買い物」が、ダメな買い物になりがちです。
1箱の煙草でもソーシャルゲームの課金でも、1回あたりの金額は払えない額ではありません。
ですが、現在志向バイアスに支配された脳は、目の前のことしか見えなくなります。
一瞬の楽しみや満足を安い額で手に入れたことに満足し、長期的な損得を考えずに繰り返して買い続けてしまいます。
それが自然な習慣になったときには、知らず知らず「ダメな買い物」をしている状態になるのです。
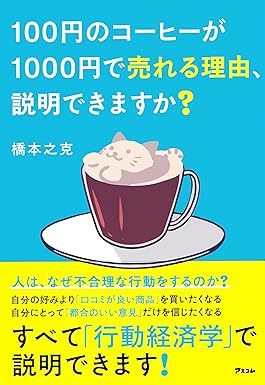
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
昭和女子大学「現代ビジネス研究所」研究員、戸板女子短期大学非常勤講師、文教大学非常勤講師を兼任。『世界は行動経済学でできている』(アスコム)、『世界最先端の研究が教える新事実 行動経済学BEST100』(総合法令出版)、『ミクロ・マクロの前に 今さら聞けない行動経済学の超基本』(朝日新聞出版)などの著書や、関連する講演・執筆も多数。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 「返品無料」の罠! 衝動買いを引き起こす“ある効果”の正体とは
- 「クチコミ」に騙されるな! あなたの判断を狂わせる3つの心理効果
- 「賢い節約」が浪費に変わる瞬間! 巨大カートのコストコに学ぶ消費心理
- 「やめたいのに、やめられない」の正体:あなたを支配する脳の罠
- 得した気分に要注意! 賢い人が知る「フレーミング効果」とは
- 住宅ローンは「サラ金」と同じ? 約1,800万円損する仕組みの真実
