本記事は、橋本 之克氏の著書『100円のコーヒーが1000円で売れる理由、説明できますか?』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

私たちが「無料」につられてしまうメカニズム
流行の発信はカリスマ店員からインフルエンサーへ
一般人でありながら、その姿や一挙手一投足が影響を与える「インフルエンサー」は、世の中のトレンド作りにおいて、大きな影響力を持っています。こうした存在の源流と呼べるのは、2000年ごろに一世を風靡した「カリスマ店員」ではないでしょうか。
「カリスマ」という言葉は、1999年の「新語・流行語大賞」トップ10にランキングされました。当時は、渋谷109が若い女性における流行の発信地でした。テナントの「エゴイスト」「ココルル」「ミジェーン」などの人気ブランドの店舗では、カリスマ店員が自分たちのブランドの服を着こなし、それらは飛ぶように売れました。
その後、メディアもショップも、アナログからデジタルにシフトしていきます。1つの番組や記事を誰もが見るマスメディアは衰退し、無数にあるネットの記事が、人々の主要な情報源となりました。リアルな店舗のシェアも、ネット通販に浸食されていくことになります。
この状況に輪をかけて、2020年には新型コロナウイルス感染症の流行が、買い物行動に影響を及ぼしました。不要不急の外出に対する自粛が要請され、リアルな店舗に足を運びにくくなったことで、ネットを用いた買い物がさらに増えていったのです。
「無料」という言葉が持つインパクト
何かを買う際に、ネット通販は便利です。商品を選んで決済し、届くのを待てばいいのですから。しかしながら、洋服や靴などの微妙なサイズ合わせが必要なアイテムや、色や風合いなどによって好みが分かれるアイテムは、購入前に商品を確認できないと不安なものです。
この不安を解消するためには「返品無料」のサービスが有用です。サイズが合わなかった商品などは買い直すことができ、失敗を回避できます。通販のショップやサイトによっては返送にかかる費用まで無料なところもあり、その数を増やしています。
売り手にとってはコストのかかる仕組みですが、ユーザーの安心感を増すためには有効です。
このサービスの大きな魅力は、その名の通り、商品を取り替えるために返送する費用が「無料」である点です。
人の心理において、「無料」が及ぼす影響は大きいものがあります。
米国デューク大学のダン・アリエリーは、この影響力を確かめる実験をおこなっています。通りに出したテーブルに、チョコレートを2種類並べて販売しました。
1つは高級なトリュフのチョコレート、もう1つはごく普通のキスチョコです。高級チョコを定価の半額の15セントで、キスチョコを1セントで売ると、73%のお客は高級チョコを選びました。
次に、それぞれを1セントずつ値引きし、高級チョコを14セントで、キスチョコを無料で提供しました。すると、69%のお客が、無料のキスチョコを選んだのです。格安で食べられる高級チョコよりも、無料のチョコレートを選んだことになります。値下げの額も価格差も同じままなのに、結果は逆転しました。
このように「無料」には強いインパクトがあるのです。したがって、買い物において返品送料が無料であることは、注目される要素の1つです。
とはいえそれは、万が一商品が合わなかった場合の不安を解消してくれる仕組みであり、積極的に商品を買う理由には、ならないように思えます。
しかし、「返品無料」は、実は買いたい気持ちにさせる仕組みでもあるのです。
一度手にすると手放せなくなる「保有効果」とは
返品無料であれば、迷った商品を気軽に送ってもらうことができます。商品が届いたら試着し、それを家族や知人にチェックしてもらうこともできます。
また、すでに持っている自分の洋服と合わせてみることも容易です。その結果、商品をあたかも自分の所有物のように実際に手に取り、検討する中で、徐々に愛着がわいてきます。この愛着の強さは「保有効果」によるものと考えられます。
これは、自分が保有する物に高い価値や愛着を感じ、手放したくないと感じる心理現象です。人は無意識に「手放すことを損」「手に入れることを得」ととらえるのです。
すると「損失回避」によって手放すことを避けようとします。それはすなわち、保有する物の価値を高く感じるということです。
この法則は、ノーベル経済学賞受賞者のリチャード・セイラーが、自身が籍を置く大学の教授の言動からヒントを得たといわれています。
その教授はワインを好み、収集していました。彼は、過去に自らが5ドルで買ったワインが100ドル以上の値をつけても売り渋り、同じワインを追加で買う際には35ドルでもお金を出し渋ったそうです。自分の手元にあるワインの価値を高く評価する彼の態度が、経済学の教授と思えないほど極端だったといいます。そして、その様子が「保有効果」の発見につながったのです。
教授の心の中では、ワインを売る場合の心理はどのようなものなのでしょうか。仮に、彼のワインの一般的な価格(=価値)が100ドルだったとしましょう。
もし、これを売るならば100ドル得ることができ、喜びや満足を感じることでしょう。それと同時に100ドルのワインを手放すことになり、悲しみや不満を感じます。数字上は、このワインと1,000ドルのお金は同じ価値なので、問題なく交換できるはずです。
しかし損失回避が働くと、この取引で感じる喜びと悲しみの量は同じではありません。研究によると、悲しみは喜びの2倍以上大きいと推定されています。だから教授は、ワインの売り買いに消極的になるのです。
返品無料だからという理由で、とりあえず買う洋服や靴の場合でも、まったく同じような現象が起こります。
買うときは返品することを前提にしていたとしても、手元にあるあいだは自分の保有物です。無意識に愛着がわいてきます。面白いもので、取り寄せて手元に置くという自らの行動を通じて、自分自身の購買意欲を高めていることになるのです。
「返報性の原理」で返品を申し訳なく思ってしまう
では「返品無料」による買い物は「いい買い物」といえるのでしょうか。
まず、自分が望むサイズやデザインの商品を確認したうえで買える点は、買い手にとっていい仕組みだといえます。これは、売る側が返品されるリスクを負っているからこそ成立するサービスです。ありがたく享受すればいいでしょう。
ただし、買い手も、自分の心理に返品が無料であることの影響力、保有効果が働く可能性を認識しておく必要があります。
さらには「返報性の原理」も働くかもしれません。返報性の原理とは他人から何らかの施しを受けた際に、「お返しをしなければならない」「お返しをしなければ申し訳ない」などと考えてしまう心理作用です。
たとえば、スーパーで試食をしたらなんとなく買わなければいけない気がするのは、返報性の原理によるものです。この心理によって、返品無料にしてもらうのが申し訳ないから買おう、と考えてしまう可能性があるのです。
「ダメな買い物」を避けるためには、自分の心理に影響する要因を把握しておく必要があります。そのうえで、気に入った商品や必要なものを買えばいいのです。感謝すべきは感謝し、自分が買うべきものだけを買うのが「いい買い物」です。
「試せる安心」がつくり出す新しい買い物の形
一方、返品に伴うコストを負担しなければならないということは、売り手にとっては利益を削ることを意味します。現在は、このサービスを導入するネットショップが多いので、競合への対抗上、やむをえず採用しているケースもあることでしょう。
しかし、返品無料サービスをクレーム解消と同じ「ネガティブな印象を打ち消す取組み」で終わらせるべきではないと思います。むしろ、安心な買い物を、買い手に提供するポジティブな機会にできるのが理想です。
その仕組みを取り入れているのが、株式会社トニーセイムジャパンによる眼鏡ブランド「trico」です。
tricoは「お顔の小さな女性」のために生まれたメガネブランドです。ターゲットは「メガネ屋さんに行っても顔のサイズに合うメガネがほとんどない」、「サイズの合うものは、好みのデザインじゃないことも多い」といった悩みを抱える女性です。
こうした買い手のために、ネット通販サイトに「試着サービス」が用意されています。好みの商品が最大3点まで無料で配送され、1週間試すことができます。購入手続きをする必要があるものの、商品を返却すれば代金はすべて返金されるため、利用者の負担はありません。
この商品のターゲットである「小顔の女性」は、過去に眼鏡のサイズに対して不満を感じた経験があると考えてよいでしょう。実際に試着できることで、一般的な眼鏡利用者以上に大きな安心を感じることができます。さらに、試着サービスを利用して商品を実際に身につけることで、保有効果の心理が生まれます。手放したくないと感じて、購入につながるわけです。
ただし「返品無料」や「試着サービス」のポイントは、「買い手に自由な選択を提供する」ことです。それによって売り手と買い手とがWin-Winの状態になることが重要です。双方が満足することで、継続的に取引を続ける理想的な関係が生まれるのです。
現代は、買い物に関する情報の伝わり方や内容が多様化しています。ネットやデジタルでの販売も増え、かつてのアパレルブランドのカリスマ店員と顧客のような、密な関係も望みにくくなりました。
だからこそ、買い手が自由にゆったりと商品を選んで身につけ、結果的にその体験を提供する売り手もうるおうような、落ち着いた関係はますます重要になるのではないでしょうか。
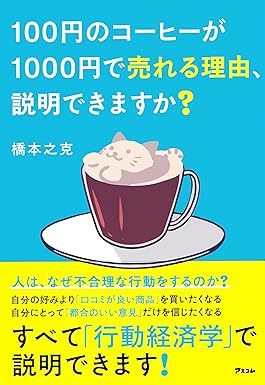
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
昭和女子大学「現代ビジネス研究所」研究員、戸板女子短期大学非常勤講師、文教大学非常勤講師を兼任。『世界は行動経済学でできている』(アスコム)、『世界最先端の研究が教える新事実 行動経済学BEST100』(総合法令出版)、『ミクロ・マクロの前に 今さら聞けない行動経済学の超基本』(朝日新聞出版)などの著書や、関連する講演・執筆も多数。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 「返品無料」の罠! 衝動買いを引き起こす“ある効果”の正体とは
- 「クチコミ」に騙されるな! あなたの判断を狂わせる3つの心理効果
- 「賢い節約」が浪費に変わる瞬間! 巨大カートのコストコに学ぶ消費心理
- 「やめたいのに、やめられない」の正体:あなたを支配する脳の罠
- 得した気分に要注意! 賢い人が知る「フレーミング効果」とは
- 住宅ローンは「サラ金」と同じ? 約1,800万円損する仕組みの真実
