本記事は、橋本 之克氏の著書『100円のコーヒーが1000円で売れる理由、説明できますか?』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

得した気分になる「数字の仕掛け」に踊らされないコツ
「ポイント10%還元」と「10%割引」はどっちが得か?
ポイントを貯める理由は何かと聞かれれば、多くの人は「お得だから」と答えるでしょう。積極的に「ポイ活(ポイント活動)」をしている人も増えています。
しかし、このポイントに関して、多くの人が勘違いをしています。
たとえば「ポイント10%還元」と「10%割引」を比較すると、どちらが得でしょう?
多くの人は「同じ10%だから、どちらも同じだけ得」と答えるのではないでしょうか。
正解は「10%割引のほうが得」です。
わかりやすく、1万円払って買い物をしたと仮定します。
ポイント10%の場合、1,000円分のポイントが加算されます。これを次回以降の買い物で使えば、お金を支払うことなく1,000円分の商品を手に入れることができます。
この一連の買い物において、支払ったお金は1万円で、手元には1万1,000円分の商品が残ります。1万1,000円分の商品を買うにあたって、値引きされた金額は1,000円ですから、割引率は1,000円÷1万1,000円×100=約9.1%です。
一方、10%割引の場合は、1万円分の商品が1,000円値引きされますから、これを9,000円支払って手に入れることになります。当然、割引率は10%になりますから、ポイント10%還元よりも得なのです。
ポイント還元に似たスタンプカードの場合も、まったく同じ勘違いが起きがちです。
「10回通ってスタンプが10個貯まると1回無料」は「10%割引」と同じだけの得に思えるかもしれません。
では、具体例で考えましょう。1回あたり1,000円のマッサージを想定します。
10回通って1万円払うと次の1回分は無料です。つまり11回分のマッサージを1万円で受けられて1,000円割引されたことになるので、割引率は1,000円÷1万1,000円×100=約9.1%です。
10%割引よりも割引率が低いのです。
私たちがポイントを貯めたくなる理由
このように感覚と実態がずれるのは、「10%」という共通の数字が示されていることが原因です。行動経済学における「フレーミング」の影響によるものです。これは同じ事柄でも、記述や表現の仕方によって、受け取られ方が異なってしまう心理的バイアスです。
今回の例のように、異なる内容が提示の仕方で同じように受け取られるのも、フレーミングの影響です。フレーミングは英語でいう「枠(フレーム)」に由来しており、まるで一定の枠を通して物事を見ているかのように、誤った解釈をしてしまうというものです。
それと同時に「ポイント」の仕組みには、買い手にとって損を忘れさせるほどの魅力があるとも考えられます。一般的なネット販売や航空会社などのポイントサービスに見られる魅力点を、いくつか以下にあげていきます。
① ポイントを貯める楽しみがある
② ポイントの収集状況に応じてランクが上がり、優遇措置を受けられる
③ 会員限定の割引や、キャンペーンなどのメリットがある
ポイントサービスは、売り手が買い手を顧客として維持し続けるための手段です。
そのために売り手は、システムの提供費用やポイントの源泉となる資金などのコストを負担します。そのうえで、ポイントサービスの仕組みは、買い手に対して「有形無形の保有物」を提供するという特徴があります。具体的には、以下の3つです。
① 収集で増えていくポイントそのもの
② 買い手個人のステイタス
③ 得をするチャンス
行動経済学の視点で見ると、これらが買い手を引きつける理由になります。
さらに、買い手の心の中に、すでに解説した「保有効果」の心理が働きます。自分が保有するモノに高い価値や愛着を感じ、手放したくないと感じる心理です。
この心理は、お金やモノなどの有形物だけでなく、身につけたスキル、自分の評価など無形物に対しても働きます。買い手は、ポイント、ステイタス、チャンスの3つに対して、保有していない他人からは理解できないほど、高い価値を感じるのです。
積み上がっていくポイントの数値は、まるで自分自身の努力を示す点数であるかのように思えます。一度手に入れたステイタスや、会員限定キャンペーンに参加する権利も、手放すことのできない大切なものに見えるのです。
Win−Winの関係をつくるポイントとの付き合い方
ここまでは、ポイントが人々の心理に与える影響について解説してきました。
では、このポイントサービスというマジックめいた仕掛けに、積極的に参加する必要があるのでしょうか。
その答えについては「その仕掛けは、誰が何のために仕掛けているのか」「それを知ったうえで賛同できるかどうか」で判断すべきでしょう。
たとえば、2020年に実施された「Go To Eat」キャンペーンで考えてみましょう。これは、国が新型コロナウイルスの感染予防対策に取り組む飲食店の需要を喚起し、同時に食材を供給する農林漁業者を支援するキャンペーンです。
その一環である「プレミアム付食事券」は「販売額の25%を国が負担する(例:1万2,500円の食事券を1万円で購入可能)」という特典がありました。「25%お得」というアピールです。
この仕組みを「割引」で表現するとどうなるでしょうか。
もし、1万2,500円分の食事をして代金が1万円で済んだならば、差額の2,500円は、本来払うべき1万2,500円の20%なので「20%割引」となります。
ところが、国は「20%割引」でなく「25%お得」を前面に出しています。どちらの言い方も間違いではありません。では、なぜこういう言い方をするのでしょう。
国がおこなうキャンペーンの目的は、消費者により多くお金を使ってもらうことです。それが外食産業や農業などの第1次産業を救うことになるからです。こういった目的があれば、お得感の強い数字をアピールすることは善である、といえるのではないでしょうか。消費者として参加することも、また善だと考えられます。
では改めて、保有効果を活用したポイントサービスを、どうとらえるべきか考えてみましょう。
たしかに、ポイントサービスは買い手の無意識に働きかけ、行動を操作する仕掛けです。ただ、結果的に、買い手が心理的なメリットを得ていることも事実です。
ポイントが貯まる際の期待感や達成感、重要顧客としての待遇でくすぐられるプライド、限定されたメンバーとして希少な購入チャンスを得られる喜びなど、ポイントサービスによってさまざまな心理的メリットを体験できます。
ですから、ポイントを貯めて顧客であり続けるのも一つの選択です。それが、顧客の囲い込み目的であっても、メリットを感じるならば気にする必要はありません。Win-Winの大人の関係が成立するのは、決して悪いことではないでしょう。売り手の立場であれば、積極的に顧客との関係作りをするべきです。
2025年時点のポイント勢力図は、「楽天ポイント」「dポイント」「PayPayポイント」「Pontaポイント」「Vポイント(2024年にVポイントとTポイントが統合)」など5大ポイントへの集約が進んでいます。たしかに、利用者にとって、貯めやすく使いやすいポイントは便利です。
一方、地域の個性ある小規模の流通サービス業が、独自のポイントカードを発行しているケースもあります。むしろ、小規模な企業のポイントサービスのほうが、カードの券面デザインなどで個性を発揮できるかもしれません。
ポイントサービスが、金銭的なやり取りの道具としてだけでなく、売り手と買い手の関係作りに活用されるのはいいことだと言えるでしょう。
では逆に、買い手にとっての「ダメなポイ活」はどんなものでしょうか。
まずフレーミングに惑わされて、本当に得な選択がどれかわからない状況です。あるいは、保有効果とは何かも知らず、漫然とポイントを貯めている状況もよくありません。
最近、売り手側が買い手の「無意識の心理」に仕掛けるケースが増えています。また、その手法も多様になり、洗練されてきました。
買い手側も、自分の心理がどのように働くかを知っておかなくては、相手と同じレベルに立つことができず、よい関係を結ぶことが難しいでしょう。「いい買い物」「いいポイ活」をしたいのであれば、知識を備えることは必要条件だといえそうです。
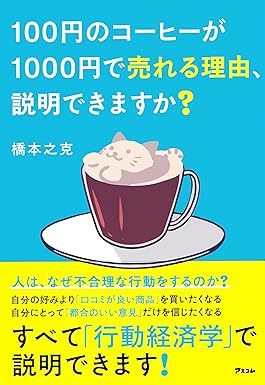
東京工業大学卒業後、大手広告代理店を経て1995年日本総合研究所入社。自治体や企業向けのコンサルティング業務、官民共同による市場創造コンソーシアムの組成運営を行う。1998年よりアサツーディ・ケイにて、多様な業種のマーケティングやブランディングに関する戦略プランニングを実施。「行動経済学」を調査分析や顧客獲得の実務に活用。
2018年の独立後は、「行動経済学のビジネス活用」「30年以上の経験に基づくマーケティングとブランディングのコンサルティング」を行っている。携わった戦略や計画の策定実行は、通算800案件以上。
昭和女子大学「現代ビジネス研究所」研究員、戸板女子短期大学非常勤講師、文教大学非常勤講師を兼任。『世界は行動経済学でできている』(アスコム)、『世界最先端の研究が教える新事実 行動経済学BEST100』(総合法令出版)、『ミクロ・マクロの前に 今さら聞けない行動経済学の超基本』(朝日新聞出版)などの著書や、関連する講演・執筆も多数。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
