「残業をしなければならない会社というのは、それだけ競争力が弱いということです。不況だろうが、為替レートが変動しようが、赤字にならない。そういう競争力の強い会社は、月の残業時間が10時間以下なのです。1カ月の営業日が20日だとすると、1日平均30分以下。実質的には残業がないと言っていいでしょう」(坂本氏)
「社員は自主的に残業している」は本当か?
坂本氏の研究室による約7,500社への調査では、残業時間が日常的に長い会社で業績が安定的に高いところはなかったそうだ。
「その理由は山ほどあります。
まず、残業は社員を疲労困憊させます。そして、家族や友人との憩いのひと時も奪う。そういう状態が続くと、会社への帰属意識や愛社心が低下して離職者が増えます。残業時間の長さと離職率はきれいに相関しています。
また、社員が残業をすると割増しした残業手当を支払わなければなりませんが、残業して作った商品やサービスは割増しした料金で売れるわけではありません。残業をすればするほど収益を悪化させるわけです。
さらに、工場の現場などでは、残業時間が長くなると注意力が散漫になって事故につながりかねません。だから、社員はミスをしないことや自分の身体を守ることに精一杯になってしまい、新商品や新技術に関するアイデアが生まれません。
今お話ししたことをすべて逆にした会社を考えてみてください。社員が元気で、家族や友人と過ごす時間を十分取れて、愛社心が強ければ、会社を辞めるわけがありません。収益性も高く、新商品もどんどん出てくる。そんな会社なら、業績が上がるに決まっています」(坂本氏)
ならば、残業削減は労使の利害が一致するところのはずだ。それなのに、なぜ簡単には進まないのか。
要因の1つに、残業手当を生活費に充てている社員の存在がある。編集部の調査でも、「残業代が減ることによる収入減がなければ、残業時間を短くしたい」という人の割合が、「残業代が減っても残業時間を短くしたい」という人を上回った(グラフ5)。
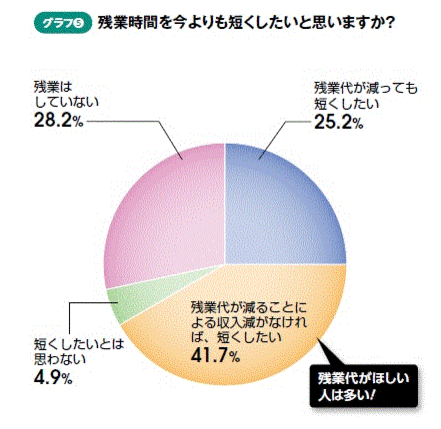
坂本氏は、この問題についてこう話す。
「残業ゼロの重要性を話すと、『わが社の社員は、やれと言っていないのに、好きで残業をしているんです。やめろと言うとモチベーションを下げてしまう』と言う経営者がよくいます。そういう経営者には『給料はどのくらい払っていますか?』と聞くのですが、そのほとんどが低賃金なのです。だから残業手当を生活費の一部にせざるを得ない。生活を守るための残業を『好きでやっている』とは言いません。
給料をきちんと払っている場合は、さらに『残業に協力したかどうかが人事評価の対象になっていませんか?』と聞きます。残業しないとボーナスに響いたり、昇格できなかったりすれば、当然、残業をしようとしますから。
人事評価とも関係ないのに残業が好きでたまらない社員がいるなら、『その社員と面談して、じっくり話したほうがいい』と勧めます。借金を背負っているなど、私生活に深刻な問題を抱えている可能性が高いからです」(坂本氏)
社員の側が残業削減に反対しているように見えても、そのほとんどは、実は会社側の問題だということだ。
「残業したら罰金」で業績を向上させた企業
編集部の調査では、会社員の過半数が「長時間労働は効率を下げるので、成果を上げるためにはむしろ避けるべきだ」と答えている。ただ、「成果を上げるために長時間労働は必須ではないが、他に方法がなければするべきだ」と答えた人も約4割いる(グラフ6)。長時間労働が成果を上げるのか、逆に下げるのかは、世の中の会社員たちの間で意見が分かれていると言えるだろう。
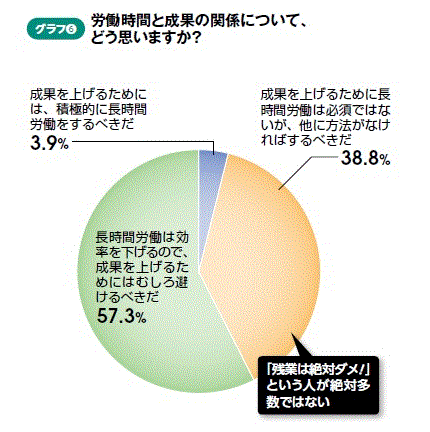
坂本氏は、「『業績が良くなったら残業時間を短くしたい』と言う経営者がときどきいるのですが、それは順序が逆です」と指摘し、残業削減によって業績を向上させた会社の例を挙げた。