2004年、1929(昭和4)年から銀座の一角で異彩を放ってきた歴史的建造物が立て替えられた。ただし、ファザード(建物の正面部分)は旧建築が保存され、脈々とその歴史が受け継がれてきていることを象徴している。
ビルの1階には米国の高級百貨店チェーンであるバーニーズ・ニューヨークが出店しているが、その玄関とは別の場所でもガードマンが厳重に警備する脇から人の出入りが見られる。通常のオフィスビルのエントランスとは趣が異なり、独特の厳粛なムードが漂う。
緊張で顔を強ばらせながらエントランスを通過し、エレベーターに乗って9階で下りると、向かって左手にレトロなスタイルのフロントがある。ここでフロント係の女性にアポイントがある旨を告げると、テキパキと確認作業を進めて奧へと通される。
目の前に広がる空間は、歴史的建造物の室内がそのまま残されているようだ。英国のクラブハウスを手本にチューダー朝ゴシック様式の歴史主義を基調としつつ、外観にアールデコの意匠を取り入れた昭和初期の建築の典型例だという。
案内されたのは社員と来訪者との談話室で、バスケットボールのコート程度のスペースがある。重厚な造りの椅子に腰掛けて待っていると、アポイントを取っていた社員が現れた。
社員と言っても、この場所で働いているわけではない。ここは日本で最初にできた実業家のための社交場である一般財団法人の交詢社で、社員とは同組織への入会者のことを意味するのだ。
目次
福沢諭吉が設立し、慶應義塾とともに運営に心血を注いだ交詢社
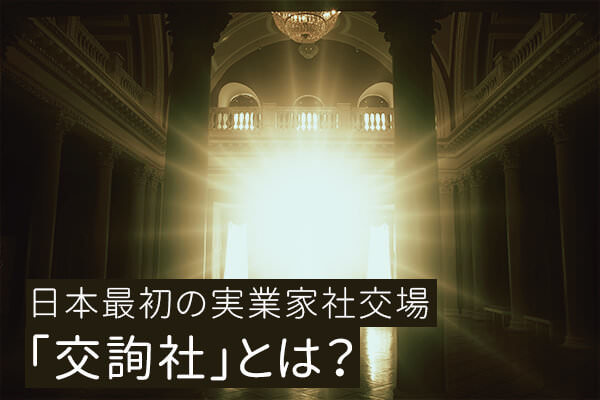
福沢諭吉と言えば、誰しもすぐに連想するのは「学問のすゝめ」や慶應義塾大学、あるいは1万円札といったところではないだろうか? 交詢社が真っ先に頭に浮かんだという人は、そう多くないはずだ。
明治時代を迎え、あえて自らは政府の要職に就かなかった福沢諭吉は、慶応義塾、日刊新聞「時事新報」、交詢社という3つの事業に心血を注いだという。このうち、「時事新報」は昭和の初めに廃刊となり、残る2つは現存している。
もっとも、あまりにも著名な慶應義塾と比べれば、交詢社はいささか影が薄いというのが実情だろう。銀座に「交詢社通り」と呼ばれる界隈があることは知っていても、交詢社がどんな目的で何を行っている組織なのかを理解している人は限られていそうだ。
交詢の詢という字の名乗り(名前に用いる際の読み方)は「まこと」で、この二字熟語には「誠実な姿勢で親密に交際する」という意味がある。当時は慶應義塾などで教育を受ける人が急増する一方、社会が明治維新という激変期を迎えていた。
そこで、巣立った学生たちがその荒波を乗り越えて実業界で成功するために、彼らが互いに情報交換しながら切磋琢磨する交流の場として設けられたのが交詢社なのである。1880(明治13)年1月の創設時から、約1800名が参加したという。
当初は政治的な色彩も強く、自由党と対立して立憲改進党の支持基盤となっていたが、現在は純粋な社交場となっている。創設者が福翁であるうえ、現理事長にも元慶應義塾長の安西祐一郎氏が就いているように、同校出身者を中心とした集まりというイメージが強いものの、実際には他校出身が占める割合も多いという。
ちなみに、慶應出身者によって構成されている社交場は「慶應連合三田会」だ。こちらは数々の大手企業で、有力派閥として存在感を発揮している。
古きよき時代の社交界がそのまま現代にタイムスリップした異空間
交詢社内部に招き入れてくれたのは、10年程前から同社の社員となっている岡田正之氏(仮名)だ。談話室を離れて内部を一通り案内して回る最中、彼はこう語る。