本記事は、伊庭 正康氏の著書『リーダーの「任せ方」の順番 部下を持ったら知りたい3つのセオリー』(明日香出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

「やったふり」と「不正のワナ」を予防する
プレッシャーが、人を追い詰める
私がリーダー研修で、必ず伝えている法則があります。それは、
「心理的安全性がない職場では、人は本音を隠し、やったふりをする」ということ。
心理的安全性とは、誰が何を言っても“安心・安全”が保証されることを指します。
あなたの職場を見渡してください。
帳尻を合わせるような、報告やレポートはないでしょうか?
もちろん、プレッシャーを感じることは大事です。
ただ、それは心理的安全性が担保されてこそ。
さもないと、「やったふり」が、あなたの知らないところで横行します。
これがエスカレートすると、中には超えてはいけない“改ざん”“虚偽”などの「不正」に足を踏み入れる人も出てくるのです。
生々しい話をしますね。もう、時効になった話なのでOKでしょう。
私が若手課長として、ある会社に出向した時のことでした。
その時、“優秀な営業”として紹介されたのがHさん。
Hさんは、主要な顧客を任され、大きな目標を課されていました。
しかし、私は、すぐ違和感を持ちました。
なぜか、複数の顧客からの入金が数日、遅いのです。彼女の顔色もどこか悪い……。
私が直接、顧客に確認をしたところ―
彼女が顧客に代わって、自分のお金で賄っていたことが発覚しました。「架空受注」です。
その額は800万。消費者金融で借りて払っていました。
会社での事情聴取でHさんは、こう言ったそうです。
「目標を外すわけにもいかず、責任を感じて、ついしてしまった」
Hさんが架空計上に手を染めたのは、私の前任課長の時でしたので、私は懲戒になることはなかったのですが、前任課長は、厳重注意の懲戒処分を受けることに。
理由は、管理不行き届きでした。そして、Hさんも自主的に退職することに……。
心理的安全性をつくる“3つの心得”
こうならないために、やるべきことがあります。
やはり、上司が「安心して話せる空気」を意図的につくることです。
私が現場で実践し、研修でも紹介する対話法を紹介しましょう。
1. 「言い訳」を否定せず、学びに変える
「言い訳するな」と思いたくなるのは普通ですが、あえて「言い訳」を否定せず、5分程度は、聞くことだけに徹してください。「そうか、それで、どうして」とただ聞くだけでOK。「言い訳」は、部下の「言い分」でもあるのです。
「言い分」を一通り聞いたら、「学び」の会話にシフトします。
「そこから、どんなことが考えられる」「次は、どんな風にするのがいいかな」と。
失敗を「学び」に変えて、部下は安心して挑戦できるようになります。
2. あえて「弱み」を見せる
心理的安全性を担保する大きなカギは、「リーダーの自己開示」。
特に、上司の失敗談や恥ずかしい話は、親近感につながり、一気に安心感が芽生えます。実は、完璧さより、「弱さを見せられる上司」のほうが、うまくいきます。
3. 「多様性」を尊重する
たとえば、「仕事がツラい=やる気がない」なんて決めつけないことも大事。
「そういう人もいる、以上」、このように割り切る感覚を持つことも重要です。
「自分が正解」と思っている上司ほど人事からの評価は低い、それが、研修先の人事から伺う実感です。
今は、価値観の違いを否定しないことが、安心して働ける土台をつくるからです。
任せる際は、モチベーションの観点だけではなく、リスクマネジメントの観点からも「心理的安全性」をセットで考えておきましょう。
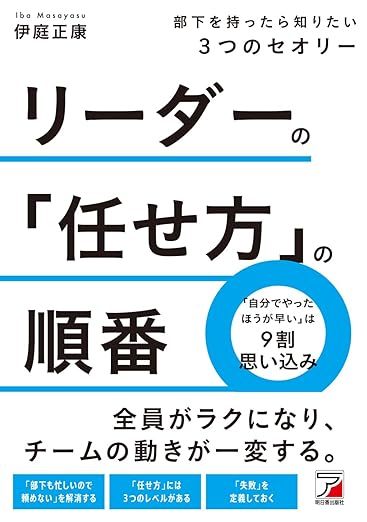
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
