
生前贈与は、相続税対策や資産承継の方法として注目されています。
生前に財産を譲ることで、相続税の負担を軽減し、計画的に資産を移転できるメリットがあります。
しかし、適切な手続きをおこなわないと、贈与税の負担が増えたり、相続時にトラブルが発生する可能性もあります。
本記事では、生前贈与の基本的な仕組みや非課税制度、注意点について詳しく解説します。
- 生前贈与は相続税対策として有効だが適切な手続きが必要
- 暦年贈与や相続時精算課税制度で税負担を軽減できる
- 証拠の残らない贈与は相続時の争いの原因となる可能性がある
相続税とは

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した人が、その財産に対して支払う税金です。
具体的には、現金、土地、建物、株式など、金銭に換算できる全ての財産が対象になります。
一定の金額(基礎控除)までは相続税はかかりませんが、それを超える部分に税金がかかります。
基礎控除額は、相続人の数や被相続人の配偶者の有無などによって異なります。
死亡保険金の一部や、配偶者への生前贈与などは、一定の金額までは非課税となります。
相続が発生した場合、相続人は、一定期間内に相続税の申告をし、税金を納める必要があります。申告が遅れると、延滞税などが発生する場合があります。
相続税を安くする方法
相続税を安くする方法としては、生前贈与をおこなったり、相続財産を分割したりする方法などが考えられます。
しかし、これらの方法には、贈与税がかかる場合や、相続人の間でトラブルになる可能性もあるため、専門家にご相談することをおすすめします。
生前贈与とは

上述した「生前贈与」について詳しく解説します。
生前贈与とは、生きているうちに、自分の財産を誰かに無償で譲り渡すことを指します。
たとえば、子どもや孫に住宅資金を渡したり、老後のために財産を整理したい場合などにおこなわれます。
メリットとしては、相続税の負担を減らすことができる点や、贈与を受けた人がその財産を有効活用できる点が挙げられます。
しかし、デメリットとして、贈与税がかかる場合があることや、贈与後の財産は戻せないことなどが考えられます。
生前贈与における6つの非課税

ここでは、生前贈与における非課税制度を6つ解説します。
また、制度を利用するにあたっての注意点も解説します。
1.暦年贈与
暦年贈与とは、贈与税の非課税枠を利用した贈与の方法です。
この制度を利用することで、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計が110万円以下であれば、贈与税がかかりません。
この非課税枠は、贈与を受ける人ごとに適用されるため、複数の人に贈与することで、年間110万円以上の贈与を非課税でおこなうことが可能です。
たとえば、親が子どもに毎年110万円ずつ贈与すると、10年間で合計1,100万円を非課税で贈与できます。
これにより、相続時の財産を減らし、将来の相続税負担を軽減することができます。
関連記事
贈与税は110万円以下でもかかることがある?生前贈与の注意点を解説
・暦年贈与の注意点
ただし、注意点もあります。
贈与を受けた側が複数の贈与者から贈与を受けた場合、合計額が110万円を超えると贈与税が課税されます。
また、2024年からは、相続開始前7年以内におこなわれた贈与が相続財産に加算されるルールが適用されるため、早めの対策が求められます。
計画的に暦年贈与を活用することで、相続税対策を効果的におこなうことができます。
2.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与に適用される税制です。
この制度を利用すると、贈与を受けた金額が2,500万円まで非課税となります。
贈与者が亡くなった際には、贈与した財産の価額が相続財産に加算され、相続税が課税されます。
この制度の大きなメリットは、贈与税がかからずに多額の財産を早期に贈与できる点です。
贈与税が非課税となる範囲を超えた場合、超過分には一律20%の贈与税が課税されますが、相続時には贈与額と相続財産を合算して相続税が計算されます。
・相続時精算課税制度の注意点
ただし、一度この制度を選択すると、暦年課税に戻すことはできません。
また、贈与を受けた財産が相続時に相続税の対象となるため、計画的な贈与が求められます。
2024年からは、相続時精算課税を選択した場合でも、年間110万円の基礎控除が適用されるため、より柔軟な贈与が可能になりました。
この制度を活用することで、相続税の負担を軽減しつつ、家族に資産をスムーズに引き継ぐことができます。
関連記事
暦年贈与信託のメリットと注意点|生前贈与の手間やリスクを解決できる
3.配偶者への贈与(おしどり贈与)
贈与税の控除の特例の一つに「配偶者への贈与」があり、「おしどり贈与」とも呼ばれています。
贈与税の控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で適用される贈与税の特例です。
この制度を利用すると、居住用不動産やその取得資金を最大2,000万円まで非課税で贈与することができます。
基礎控除の110万円と合わせると、合計で2,110万円まで贈与税がかからないため、相続税対策として非常に有効です。
おしどり贈与を受けるためには、いくつかの条件があります。
| 配偶者への贈与における居住用不動産の適用条件 |
|---|
| ・夫または妻が居住用家屋を所有していること ・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること |
まず、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された不動産に住み続けることが求められます。
また、この特例は同一の配偶者に対して一生に一度しか適用できません。
この制度のメリットには、相続税の軽減や、配偶者が自宅に住み続けられることが含まれます。
・配偶者への贈与(おしどり贈与)の注意点
贈与には不動産取得税や登録免許税がかかるため、コスト面での注意が必要です。
さらに、贈与された配偶者が先に亡くなると、その財産が相続税の対象になる可能性もあります。
おしどり贈与は、計画的に利用することで、家族の財産を守りつつ、税負担を軽減する手段となります。
関連記事
夫婦間の贈与がバレる理由は?罰則や贈与税の回避方法をわかりやすく解説
4.住宅取得等資金の贈与
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例もあります。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた際に適用され、住宅が「省エネ等住宅」に当てはまる場合は1,000万円まで、それ以外の場合は500万円までが非課税となります。
省エネ等住宅とは、以下のいずれかに適合する住宅のことです。
| 省エネ等住宅 |
|---|
| ・断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること ・高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること |
・住宅取得等資金の贈与の注意点
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、いくつかの注意点があります。
まず、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、居住を開始する必要があります。
居住開始が遅れる場合、特例が適用されないことがあります。
また、受贈者の合計所得金額が2,000万円以下であることも条件です。
さらに、贈与税が非課税となるためには、必ず贈与税の申告が必要で、申告しないと特例が適用されません。
これらの要件を満たさないと、贈与税が課税されるリスクがあります。
関連記事
住宅取得資金贈与の非課税はタイミングが重要!その理由と注意点を解説
5.教育資金の一括贈与
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、贈与税が非課税となる制度があります。
この制度は、30歳未満の子や孫が対象で、最大1,500万円まで非課税で贈与を受けることができます。
贈与者は祖父母や父母などの直系尊属で、贈与を受けた資金は教育関連の支出に使用する必要があります。
具体的には、入学金や授業料、学習塾の費用などが対象です。
この制度を利用するには、教育資金専用の口座を金融機関で開設し、贈与契約書を交わす必要があります。
資金を引き出す際には、教育資金に関する領収書を提出することが求められます。
制度の適用期間は2026年3月31日までです。
| 受贈者(贈与を受ける人)の要件 | ・年齢 教育資金管理契約を締結する日において30歳未満であること。 ・所得 贈与を受けた年の前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円を超えないこと。 |
|---|---|
| 贈与者の要件 | ・直系尊属であること 受贈者の父母、祖父母など、直系尊属からの贈与であること。 |
| 贈与の方法 | ・教育資金管理契約 受贈者が金融機関等と教育資金管理契約を締結し、贈与者がその信託受益権を取得する方法。 ・銀行預入 贈与者が、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入する方法。 ・有価証券購入 贈与者が、書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入する方法。 |
・教育資金の一括贈与の注意点
注意点としては、受贈者の前年の合計所得が1,000万円以下であることが条件です。
また、受贈者が23歳を超えると、習い事の費用は非課税対象外となります。
さらに、贈与者が亡くなった場合、残高が相続税の対象となることがあるため、計画的な贈与が重要です。
非課税となるには、銀行や信託銀行といった金融機関などとの教育資金管理契約に基づいて、贈与を受ける人が信託受益権を取得する必要があります。
出典:国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
関連記事
孫へ教育資金を生前贈与するメリットと贈与の方法や注意点を解説
6.結婚・子育て資金の一括贈与
結婚・子育て資金の一括贈与は、直系尊属(祖父母や父母など)から、結婚や子育てのために一括で贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば、贈与税がかからない制度です。
この制度を活用することで、結婚や子育ての費用負担を軽減し、将来の相続対策にもつながります。
この制度の対象となるのは、結婚や子育てに必要な資金を贈与された場合で、贈与を受けた人が18歳以上50歳未満、贈与をした人がその人の直系尊属である場合です。
贈与を受けた資金は、結婚費用、新居の購入資金、出産費用など、結婚や子育てに直接必要な費用に限定されます。
贈与額には上限があり、1人につき1,000万円までが非課税となります。
また、贈与を受けた年の前年分の所得が1,000万円を超える場合は、非課税の対象外となる場合があります。
この制度を利用するには、贈与を受けた人が金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、贈与者がその信託受益権を取得するなどの手続きが必要になります。
この制度のメリットは、結婚や子育ての経済的な負担を軽減できることです。
特に、高額な結婚式費用や住宅購入費用を負担する場合には、その効果は大きいといえるでしょう。
また、将来の相続が発生した場合、相続税の負担を減らすことにもつながります。
・結婚・子育て資金の一括贈与の注意点
ただし、この制度にはいくつかの注意点があります。
まず、非課税の限度額や使途制限があるため、計画的に利用する必要があります。
また、手続きがやや複雑なため、税理士など専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
出典:国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
関連記事
孫に生前贈与する際に活用したい4つの非課税枠を徹底解説
生前贈与のメリット

ここからは、生前贈与のメリット・デメリットについて説明します。
まずは生前贈与のメリットを解説します。
主なメリットは以下の4つです。
1.資産の引き継ぎに関する親族間のトラブルを減らすことができる
自分が亡くなった後で相続がおこなわれる場合は、遺言書がしっかりと作成してあっても、遺言書で触れられていない資産の相続などが原因で、親族間でもめ事が起こる可能性があります。
一方、生前贈与では資産を持っている本人がまだ生きているわけですから、資産の引き継ぎに関する問題について、その都度自分で対処することができます。
2.自分に判断能力があるうちに財産の引き継ぎを終わらせることができる
認知症を患うと、自分の意思で生前贈与を進めることが難しくなるため、相続のための遺言書を作成することもできなくなります。
認知症を患う前に生前贈与をおこなっておけば、このような事態に陥ることを避けられます。
3.早い時期に自分の財産を贈与することで子どもや孫が有効に活用できる
自分の子どもが結婚して家族を持ち、孫が生まれて成長すると、自分が亡くなるよりもかなり前のタイミングで、子どもや孫にお金が必要なときがやってきます。
生前贈与をおこなえば、自分の財産を子どもや孫のマイホーム購入や子育て・教育のための資金として活用してもらえます。
4.暦年贈与などによって税金を抑えることができる
「暦年贈与」などの仕組みを使えば、税金を抑えることができます。
暦年贈与では原則、贈与を受ける側が年間110万円までの贈与を受けても課税されません。
生前贈与のデメリット
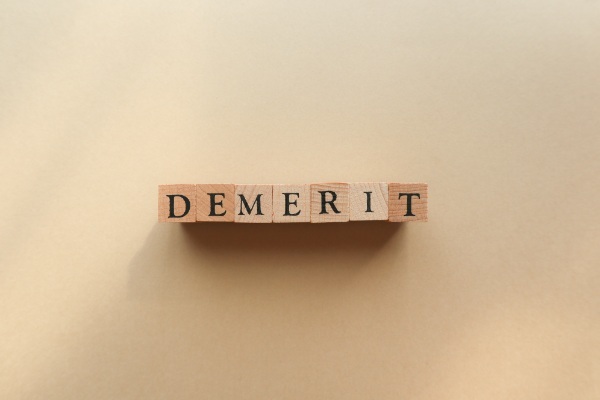
続いては生前贈与の主なデメリットを確認していきましょう。
1.生前贈与後に株式や不動産の価値が下がると損をするケースがある
生前贈与をしても累計2,500万円までは原則として贈与税が発生しない「相続時精算課税制度」を選択すると、価値が変動する株式や不動産などの財産の評価額は贈与時の評価額となります。
そのため、生前贈与後に価値が下落したとしても、財産の評価は下落前の価値でおこなわれるため、相対的に課税負担が重くなります。
ただし、このことはメリットともいえます。
逆に贈与時より資産価値が上がっても、資産価値が上がる前の評価額をもとに課税額が計算されるからです。
2.不動産取得税や登録免許税の負担が重くなる
不動産を生前贈与する場合は、相続で引き継ぐよりも不動産取得税と登録免許税の負担が重くなります。
現在の不動産所得税の税率は、生前贈与の場合は土地が3%、建物が3〜4%ですが、相続の場合は非課税です。
登録免許税は生前贈与の場合は2%ですが相続の場合は0.4%です。
3.課税がおこなわれた場合は相続税よりも負担が重くなる
「贈与税と相続税の負担はどちらが重いか」は一概にはいえません。
ただ、何の対策も講じずにある程度の規模の財産を生前贈与によって引き継ごうとする場合は、贈与税のほうが相続税よりも負担が大きくなる傾向があります。
暦年贈与などの制度をうまく使えば相続税よりも負担を軽くすることができますが、知識がない状態で安易に生前贈与をおこなうと、かえって課税負担が重くなるケースがあるため注意が必要です。
4.自分が亡くなるタイミングによっては贈与が無効になる
デメリットというより注意点として知っておいてほしいのは、自分が亡くなる時期によっては事前におこなって生前贈与が無効になるケースがあることです。
生前贈与をおこなってから3〜7年以内に亡くなった場合、生前贈与がおこなわれなかったことになります。
これまで期間は「3年以内」でしたが、2023年度の税制改正で順次「7年以内」まで延長されることが決まりました。
生前贈与の流れ

続いて、生前贈与の流れについて説明します。大きく分けて3つの工程があります。
1.贈与契約書の作成
「誰に対して何をどういう目的で贈与するか」を決めたら、贈与税の課税方法を「暦年課税」と「相続時精算課税制度」のどちらかから選び、受贈者との合意の下で贈与契約書を作成します。
2.贈与財産を渡す
その後、実際に贈与財産を渡します。現金を贈与する際には銀行振込でおこなうことが推奨されます。
不動産を贈与する際は、不動産の名義変更手続きなどが必要です。
3.贈与税の申告・納付(必要に応じて)
贈与を終えたら、贈与税の申告・納付をおこないます。
ただし、暦年課税の下で受け取った贈与財産が年間で合計110万円以内の場合、贈与税の申告は不要です。
一方、相続時精算課税制度において贈与を受けた財産がある場合は、必ず申告しなければなりません。
【ポイント】
贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告・納付する必要があります。
贈与額が年間110万円以下の場合は、原則として申告は不要です。
贈与の種類や財産の性質によって、手続きが複雑になる場合があります。
贈与税の計算は専門的な知識が必要となるため、税理士など専門家への相談をおすすめします。
【注意点】
贈与税の申告漏れや誤った申告は、ペナルティが課される場合があります。
贈与税の制度は複雑であり、頻繁に改正されることがあります。
関連記事
生前贈与のやり方・流れをわかりやすくゼロから解説!
生前贈与のよくあるトラブル

最後に、生前贈与に関するよくあるトラブルを4つ紹介します。
あわせて、そのトラブルの解決法も紹介します。
1.贈与の証拠がなく、相続時に争いが発生
生前贈与がおこなわれたものの、書面を作成せずに口約束で済ませたため、相続時に他の相続人との間で争いが発生するケースです。
特に、銀行口座からの振込ではなく現金で手渡しされた場合、証拠が残らず「本当に贈与されたのか」「贈与ではなく預かっていただけではないか」といった疑念が生じることがあります。
また、贈与を受けた本人が「もらった」と主張しても、他の相続人が「貸しただけでは?」と異議を唱える可能性もあります。
最悪の場合、贈与を受けた資産が相続財産に含まれ、遺産分割の対象となってしまうため、争族(争いのある相続)に発展することも少なくありません。
・解決法
贈与契約書を作成し、公証役場で公正証書にすることで、贈与の事実を明確にします。
また、振込記録や贈与税の申告書を残しておくと、税務的にも贈与が認められやすくなります。
さらに、家族間で贈与の内容を事前に共有し、誤解を防ぐことも重要です。
遺言書と併用することで、相続時のトラブルをさらに減らすことができます。
2.贈与税の申告漏れによるペナルティ
生前贈与には年間110万円の基礎控除があるため、この範囲内であれば贈与税の申告は不要ですが、それを超えた場合は贈与税の申告が必要です。
しかし、多くの人がこの制度を誤解し、「申告しなくてもバレない」と考えたり、単純に手続きを忘れてしまうことがあります。
結果として、税務調査が入った際に未申告が発覚し、本来の贈与税に加えて延滞税や加算税が課せられるケースがあります。
また、複数年にわたり贈与をおこなっていた場合、一括で課税されることもあり、予定外の税負担が発生するリスクがあります。
こうした税務上のトラブルは、財産管理のミスから生じることが多いです。
・解決法
贈与税が発生する場合は、毎年3月15日までに申告をおこない、期限内に納税することが重要です。
税理士に相談することで、適切な贈与計画を立て、非課税枠や特例を最大限活用できます。
また、暦年贈与ではなく「相続時精算課税制度」などを利用することで、贈与税を抑えつつ相続対策を進めることも可能です。
3.認知症発症後の贈与が無効とされる
親が認知症を発症した後、家族が代わりに財産管理をおこない、生前贈与を進めようとしたところ、後に「意思能力がなかった」と判断され、贈与が無効とされるケースです。
特に、金融機関が口座からの資金移動を認めなかったり、他の相続人が「判断能力がない状態で贈与された」と主張して訴訟に発展することがあります。
贈与契約は当事者の自由意思による合意が前提のため、意思能力が不十分な状態での契約は法的に無効とされる可能性が高いです。
そのため、認知症を発症してからではなく、早めの資産整理が重要になります。
・解決法
認知症を発症する前に計画的に贈与をおこない、公正証書で贈与契約を作成することが重要です。
また、判断能力が低下した場合は「家族信託」を活用し、受託者(家族)が代わりに財産管理できる仕組みを整えると安心です。
成年後見制度を利用する方法もありますが、自由な財産管理が難しくなるため、早めの準備が最善策となります。
4.特定の相続人への贈与が「特別受益」と認定
親が生前に特定の子どもに対して多額の贈与をおこなった場合、相続時に他の相続人から「不公平だ」と主張されることがあります。
このような生前贈与は「特別受益」とみなされ、遺産分割の際に相続財産に組み込まれる可能性があります。
たとえば、一人の子に住宅購入資金として1,000万円を贈与した場合、相続時にその1,000万円が遺産に加算され、他の相続人の取り分が増減することがあります。
そのため、生前贈与を受けた側は、相続時に思わぬ負担を強いられることがあります。
・解決法
特別受益を避けるためには、遺言書で「この贈与は特別受益としない」旨を明記することが有効です。
また、家族全員に贈与の内容を事前に説明し、納得を得ることも重要です。
公平性を保つために、他の相続人にも一定額を贈与するなどの調整をおこなうことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
関連記事
兄弟姉妹の間での贈与に贈与税はかかる?トラブルを回避するための注意点も解説
まとめ

生前贈与は、相続税の軽減やスムーズな資産承継を目的として活用できる制度です。
暦年贈与や相続時精算課税制度、住宅資金や教育資金の贈与など、さまざまな非課税措置があり、計画的におこなうことで税負担を抑えることが可能です。
しかし、贈与契約の証拠を残さないと相続時に争いが起こるリスクがあり、また贈与税の申告漏れによるペナルティにも注意が必要です。
さらに、認知症発症後の贈与が無効とされるケースや、特別受益と認定される可能性もあるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
生前贈与を効果的に活用することで、家族間のトラブルを回避し、円満な資産承継を実現しましょう。
関連記事
生前贈与の贈与税はどれくらいかかる?メリットと節税対策を解説
家を生前贈与する手続きの流れ|注意点やメリット・デメリットと費用を解説

(提供:ACNコラム)