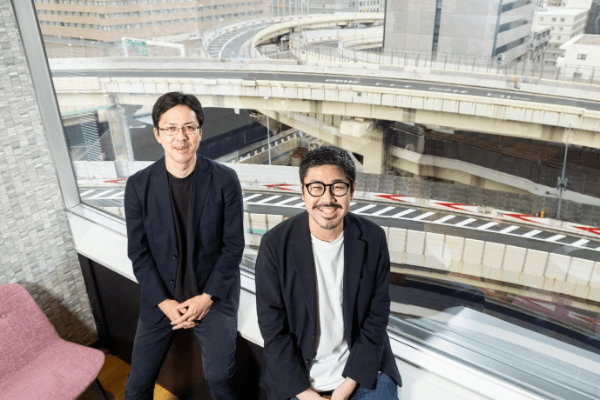
創業期の経営者が意識する「PMF(プロダクトマーケットフィット)」という言葉が示すとおり、ニーズのある市場を探し当て、そこに合うものを提供するまでの間は、新規事業の成否を分ける最重要のプロセスといっても過言ではありません。いまだ知見もリソースも十分でない段階の試行錯誤は、しばしば外部のパートナーと共同で進められますが、同じ会社で別々の新規事業を進めている者同士が手を組む、いわば“社内コラボ”は、相互理解の深さ、近い距離感、さらに内部調整のみで進められる柔軟さから、ときに外部との協業を上回る効果をもたらすようです。
では、社内コラボの実情はどのようなものでしょうか。株式会社シーエーシー 新規事業開発本部の2人、搬入日程調整ツール 「BUILD BOARD(ビルドボード)」担当の明石衛(建設領域新規事業統括)と、ITプロ人材シェアリングサービス「WithGrow」担当の定清奨(同本部 WithGrow事業推進室長)に聞きました。
慶応義塾大学大学院経済学研究科博士課程中退(修士号)。三菱経済研究所を経て入社したBCGで新規事業の立ち上げプロジェクトやコストカット等のプロジェクトに参画。 ビズリーチではサイバーセキュリティ×SaaS事業「yamory」をビジネス責任者として立ち上げる。その後株式会社リテイギにて建設領域のSaaS― 搬入日程調整ツール『BUILD BOARD』を立ち上げ、2024年よりCACに事業を譲渡するとともに籍を移す。(関連記事)
1984年広島県生まれ。博士(理学)。2012年に株式会社シーエーシーに入社。大手製薬企業向けのインフラ構築・運用プロジェクトを経て、海外ビジネス・技術トレンド調査プロジェクトに参画。その後、R&Dセンター(現R&D本部)にて、AIやIoTなどを活用した新ソリューションの企画を推進。2022年より新規事業開発本部に所属。WithGrow事業責任者として企画・推進を担当。(関連記事)
想定外は当たり前。走りながら市場を探る

−お二方の担当事業と近況を、まず簡単にお聞かせください。
明石: 2024年12月にリリースしたBUILD BOARDは、建設業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)が「工事の管理者側にとどまっている」課題を解決しようと開発したツールです。
現場で働く人たちの負担を楽にできるポイントを探った結果、急な日程変更がつきものの搬出入をターゲットに選び、横の連携で作業を効率化できるよう、同じ現場に関わる数十社の担当者が共通で閲覧・編集できるタイプのWebスケジューラーを提供しています。既に、複数の企業で導入が始まっているところです。
定清:リリースから2年が経過したWithGrowは、中小・中堅企業がITに関して抱える課題を、プロフェッショナルIT人材の伴走支援によって解決するサービスです。
システムインテグレーターとしての当社の知見を生かしたコーディネートにより、広く全国で実績を重ねていますが、登録しているプロフェッショナルは関東圏にお住まいの方が多く、必要に応じて出張も交えてプロジェクトを進めてもらっています。
−新たなサービスのニーズを、これまでどのように探ってきたのでしょうか。
明石:建設業界の方から「搬出入の日程調整に現場で使えるデジタルツールがなく、今もホワイトボードに頼っている」と聞いて今回の開発を始めたのですが、リリースしてみると、想定していたメインターゲットである「大都市圏の建物密集地の建設現場」はもちろん、地方展開するハウスメーカーや、プラントを建設する大手メーカーからも良い反響がありました。
新しい事業はどう展開するか分からないのが当たり前なので、困ったとは思っていません。一般論で言うと新規事業のターゲットはなるべく絞るのがセオリーですが、今回は課題感が共通していれば、想定より広い範囲で価値を提供できるチャンスかもしれません。あるいはもしかすると、最優先で課題を解決すべき領域が変わってくるかもしれない。
そこで、お問い合わせいただいた企業をいったん全部訪問し、最も早く定着させられそうな現場がどこなのか探ってみるつもりです。各訪問先でお話を伺うたび柔軟に考え直しながら、当面のターゲットを定めたいと考えています。

定清: 経験豊富な明石さんとは対照的に、私は今回初めて新規事業に携わっています。ターゲティングを含めて手探りで進めてきましたが、昨年半ばからようやく、誰に向けてサービスを届けるかという“顔”が見えてきました。
リリース当初の営業活動は情報システム部門を主な対象としていましたが、中小・中堅企業で実際にニーズが大きかったのは、情報システムの運用よりもDXやWebマーケティングに近い領域でした。そのため私たちがアプローチする先も、部門横断型のDX推進チームや経営企画部門、新規事業責任者などにシフトし、経営者に直接ご提案できるケースも増えています。
紹介するプロフェッショナルの位置づけも変わってきました。当初は「社内のITスキルやリソースの不足を補う存在」と捉えていたのですが、お客様の話を聞くと、むしろ「デジタルツールを入れてみたが利用率が上がらない」「活用アイデアが出てこないので現場の意識変革をしてほしい」といった教育・研修へのニーズが大きかったのです。WithGrowはスキル面の教育・研修はもちろん、一緒に現場に入って「やり方を見せられる」プロフェッショナルに登録されているので、最近は「DX内製化を進めるための外部人材活用」という切り口で提案することが多くなりました。
同僚の目から見た、相手と担当事業の魅力

−お二方は、明石さんが担当事業ごとCAC入りした当初からの付き合いだそうですが、お互いの印象はどのようなものでしたか。
定清:「明らかに絶対面白い人だな」と。ずっと新規事業を立ち上げてきたという事前情報から「気合いで進めるゴリゴリ系」を想像していたのですが、実際にお話ししてみた明石さんはロジカル寄り。新規事業については進め方のロジックが一層明確で、ギャップを感じました。
明石: どんな偏見だ、ゴリゴリ系って(笑)。私から見た定清さんは、会った当時から「真面目」。今も定期的に飲みに行く仲ですが、すごく謙遜する人という印象です。
競合サービスもある中で新規事業をゼロから立ち上げるのがいかに難しいか、僕はよく知っているので、WithGrowがここまで安定した売上を出しているのは本当にすごい、和室*でふんぞり返っていてくれてもいいくらいだと思っています。でも定清さんは「いや、そんなことないです」「目標値まで行けてないし、まだ定常的に回る事業ではない」と、絶対謙遜する。規模や完成度を既存事業と比べたりせず、もっと小さな数字から大喜びしていいのにと思います。
*CAC本社内にある、新規事業開発本部の執務室のこと
−新規事業ならではの価値があるということですね。相手の事業に対する印象や評価を、もう少し伺えますか。
明石: 新たなツールを開発する私たちのすぐ横に、プロフェッショナルを派遣するWithGrowというサービスがあること自体、ものすごいポテンシャルがあると感じています。DXは何かツールを入れただけでは進まず、現場に根付かせる音頭を取る人が必ず求められますが、これをセットで提供できる会社はあまりなく、希有な強みになりえます。
さらに言うと、さまざまな強みを持つ外部のプロフェッショナルとつながりを増やしているWithGrowの取り組みは、会社のために「人材プール」を作っているようなものでもあります。かりに派遣案件としての売上が全くなかったとしても、存在自体が絶対会社の財産になると思います。
定清: 明石さんが持つ経験知を共有してもらおうと、新規事業開発本部では有志のメンバーを集めて月2回の勉強会を開いているのですが、BUILD BOARDについても、リリースから展示会などでの反響、営業の進捗などについて情報をシェアしてもらっています。
明石さんは、私たちに話しているとおりの方法論を徹底して、実際にBUILD BOARDで結果を出しています。プロダクトもさることながら、新たな事業を着実に立ち上げていくプロセスが単純にすごいと感動しているところで、「成功の保証がない新規事業も、これを見習えば断然確度が上がる」という自信にもつながっています。
社内だからこそ、失敗も含めて経験を共有できる

−定清さんが明石さんから聞いた方法論とは何かが気になります。
定清:事業としてやろうとしていることの「Who(誰に)/What(何を)/How(どのように)」を意識し、それらがきちんと連動しているか絶えず見直すようにと、繰り返し教わっています。
どんな事業計画の本も「見直しが大事」と書いていて、みんな知識レベルでは分かっていても、なかなかできない。シンプルですが、徹底するのはすごくきついことです。明石さんのおかげで私はそこに向き合い、「これさえやり切れれば上手くいく」と、時間を取って見直しを考えられるようになりました。
明石:私自身日頃から、商談やミーティングで何か新しい情報が入るたびにWho/What/Howを検証し直すのが頭の中の習慣になっています。ここで振り返りを個人レベルに留めず、リアルな経験を同僚と共有できるところが、社内コラボならではの強みだと感じています。
例えば「自分と別の新規事業をやっている仲間が、隣でうまくいったりいかなかったりしている」というのはなかなか表に出てこない内容で、失敗体験は特に貴重なものです。そもそも何が失敗かも難しいところで、新規事業に対する評価期間は企業によってまちまちな上、あらかじめ年限を決めていても経営判断次第で覆ることがありえます。
そうしたシビアな判断基準に触れ、事業が置かれている状況を把握する意味でも、情報をオープンにしやすい社内という環境を生かし、できる限り多くの経験を共有することが重要だと思っています。
「プロダクト」と「活用の先導役」を一体提供したい

−それぞれ事業を伸ばしていくお二方の今後のコラボレーションについて、最後に展望をお聞かせください。
明石:Webサービスと、使いこなし方を伝える人をセットで展開するビジネスは、大企業向けのITコンサルで一部みられるものの、中堅・中小企業向けとしては、ほとんど聞いたことがありません。それがBUILD BOARDとWithGrowで上手くいったら、すごく理想的だと思います。
「現場が便利になるものを」とツールの側でいくら機能を増やしてみても、それだけでは大半を全く使いこなせないまま終わるのが普通です。だからこそBUILD BOARDは、逆に機能を絞り込んだシンプルな作りにしていて、活用を隅々まで定着させることと、使い方の工夫で価値を感じてもらいたいと考えています。
現場にBUILD BOARDの活用を落とし込んでくれる人をWithGrowからアサインできたら、本当に実効的なDXの事例が作れるだろうという期待があるので、それを定清さんと一緒にやっていきたいですね。
定清:DXに携わるさまざまな業界の方とお話ししてきた中で、推進側の悩みとして圧倒的に多かったのは、「ツールで便利になるといっても使い方を覚えるのが手間」「今の業務プロセスを変えたくない」という現場の抵抗感です。
BUILD BOARDを含め、リーズナブルで有用なデジタルツールは既に豊富にあり、今後も出てくると思いますが、それらツールをご提案する際に、どういうプロセスで・いかに社内を巻き込んで浸透させるかお話しする中で、WithGrowにできることをお伝えしていけば、関係者全員にとってメリットがある、強いアピールになるのではないかと思います。
−社内で手を組む強みがさらに発揮されそうですね。今回は貴重なお話をありがとうございました。
以上
(提供:CAC Innovation Hub)
