この記事は2025年10月20日に「第一生命経済研究所」で公開された「高市氏の連立政権を待つ難関」を一部編集し、転載したものです。
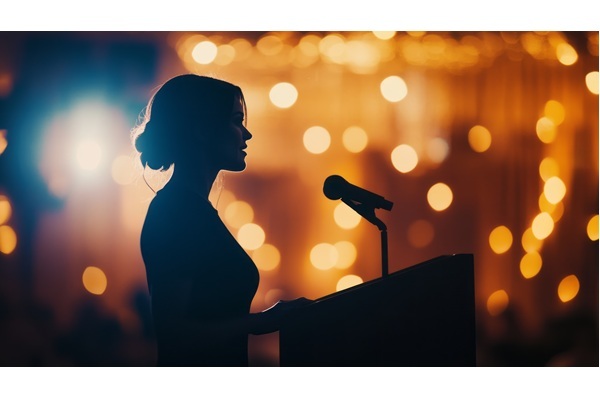
未知なる連立政権の運営
日本維新の会が、10月20日夕刻に自民党との政策協議を行って、連立に合意するようだ。21日の臨時国会で、自民党高市総裁が首相に指名されて、日本維新の会との連立政権が誕生する見通しである。多数派工作により国会で過半数が取れたとしても、ぎりぎりの船出となり、政権運営の不安定さはどうしても続くだろう。特に、就任当初から、多くの国民が期待する物価高対策についても迷走しそうだ。本稿では、予想される具体的な問題点を洗い出して行きたい。
先々を考える上で、重要なのは新政権が年内に大型イベントをいくつか抱えている点である。現在わかっているだけの予定を簡単にリストアップしておこう。

これらはすべてが消化試合ではなく、新首相の力量が試される正念場となる。日銀の会合も、仮に官邸と日銀との対話が憶測を呼べば、そこで円安が急伸する可能性がある。経済対策や来年度予算編成は、マーケットからみれば長期金利上昇リスクをはらんでいる。円安・長期金利上昇といった副作用は無視できない。
連立を組む日本維新の会は、長年意思疎通した公明党との連立とは違って、すぐに賛同してくれる相手ではないだろう。パートナーというよりも、トランプ大統領のように競争相手としてディールで臨んでくるのではないか。そうした相手と経済対策と来年度予算編成を進めなくてはいけないと、財政運営は拡張的にならざるを得ない。マーケットでは、どこまで「高市色」を出すかに注目が集まっているが、新しい連立政権の下ではどんな姿の予算になるかがまるでイメージできていない。これまでの自民党・公明党政権にあった一種の安心感はそこにはない。
鬼門の日銀会合
非常にタイミングが悪いのは、10月29・30日に日銀会合が予定されていることだ。高市氏は、日銀の利上げに反対しているとみられやすい。仮に、「日銀が利上げすべきでない」とでも発言しようものならば、ドル円レートは円安に進むだろう。10月29日は、米国でFOMCが開催されて、0.25%ポイントの利下げをする公算が高い。高市氏が無言を貫けば、円高になる流れだ。
逆に、何か色を出そうとして、高市氏が不用意に発言すれば円安になる。それは輸入物価上昇を招き、物価高対策と言っている主張とは正反対の結果になる。政権発足直後に日銀会合がやってくるのは、まさしく鬼門だ。そこでよもや火中の栗を拾うようなことはしないだろう(しないでほしいと願う)。
1年前(2024年11月)のドル円レートは、1ドル151~156円で推移していた。現状(150円前後)よりも円安が進みさえしなければ、前年との比較で輸入物価には押し下げ圧力が働くだろう。それだけに10月末の日銀会合を高市新政権がどう通過するかは、為替マーケットの参加者への大きなメッセージになる。
何をするのか?物価高対策
日本維新の会との連立協議では、どのような物価高対策が提案されるだろうか。2万円の給付金には、反対してきた経緯がある。ガソリン・軽油の暫定税率を引き下げて、それを対策とするにしても、家計への恩恵は自家用車を多用する人に限られる。東京都、大阪府のような都市部で生活する人には恩恵は乏しい。給付付き税額控除などの減税は、時間がかかる。社会保険料を年間6万円負担減にするのは、具体的な議論を進めて問題点を洗い出す必要があるため、さらに長い時間を要する。食料品の消費税率を2年間だけ8%からゼロにする方針は、社会保障財源を大きく打撃するから非現実的だ(継続協議の扱い)。
そのように考えていくと、自民党も日本維新の会も、幅広い家計を対象にして速効性が期待できる政策ツールを持っていないのが実情である。本来は、日銀が年内利上げをすれば、輸入物価が下がるので、最も早期に食料品価格を押し下げられるが、そこは高市氏の持論が引っかかりそうだ。
物価高対策ではなく、家計減税
自民党が日本維新の会と連立を組むのは、高市氏にとってストレスになるかもしれない。日本維新の会には与党経験がなく、あれもこれもと要求してくるから、同氏が実行したい国土強靱化や経済安全保障に新規の予算を付ける前に、そちらに財政的余裕を奪われかねない。問題なのが、①社会保険料の引き下げ、②食料品の消費税減税、③給付付き税額控除、④教育無償化の拡大がいずれも家計支援を念頭に置いたものであるところだ。これらは、いずれもすぐには実行できないし、財源確保も時間がかかる。消費税減税のように対応しずらいものもある。これらは、日本維新の会が野党だからこそ主張してきた実質的な家計減税策だ。こうした要求を掲げる限りは、高市氏は安心できない。
10月17日に亡くなられた村山富市元首相は、当時の日本社会党を現実路線に変えた人物として知られている。日本社会党が政権を担うに当たって、大きな転身を果たしたことは、今は歴史的決断として讃えられている。日本維新の会には、同じようなことが求められているのだろう。そうした政策方針の転換ができなければ、新しい連立政権は長持ちしないだろう。
逆に、日本維新の会が要求する12項目をみたときに驚くのは、そこに成長戦略のようなものがほぼ見当たらないことだ。筆者は関西発でもっと成長戦略を打ち出すことができてもよいと感じる。少子化対策で苦しむ関西の自治体からの声がもっと反映されていてもよいかと感じる。連立から離脱した公明党が要求していた政治改革と、これから連立を自民党とともに運営していく日本維新の会の政治改革がどう違っているのかもわかりにくい。高市氏は、日本維新の会の立ち位置を改めて問うかたちで、連立運営を進めてほしい。
通商外交が見えない
新政権が誕生したとして、日程の最初のところにアジア外交のイベントが来るのは、少し大変だと思う。高市氏には、豊富な外交経験がある訳ではなく、経済安全保障だけで何か日本経済が成長するという話にもならない。逆に、歴史認識などでアジア諸国からは厳しい目を向けられている。今までの内向きのオピニオンを変えて、トランプ時代にアジア諸国とどう連携していくかをリーダーたちと語り合わないといけなくなる。現在、韓国はCPTPPへの参加に意欲を示している。中国と台湾も同時に新規加盟を求めている問題もある。筆者は、対米依存度を引き下げるために、アジア向け輸出を拡大することが日本の採るべき道だと考えている。
その点、高市氏にはどんな理念があるのか。少し厳しく言えば、経済安全保障という概念は、トランプ時代以前のパラダイムである。例えば、サプライチェーンを中国から、日本国内に戻してきたところで、米国に輸出しようとすれば、15%の相互関税を取られてしまう。これでは企業にうま味は少ない。むしろ、トランプ大統領は、日本企業のサプライチェーンを中国から米国に持ってこいと言わんばかりだ。それは、全く持って日米にWin-Winの関係ではない。バイデン時代の古い経済安全保障の発想を刷新しなくては、アジア外交をWin-Winには持っていけないのではなかろうか。