(本記事は、岡崎かつひろ氏の著書『なぜ、あの人は「お金」にも「時間」にも余裕があるのか?』きずな出版の中から一部を抜粋・編集しています)
「経済的自由人」と「経済的“不”自由人」の4つの違い

どんな結果をつくり出すかは、考え方の違いによって生み出されます。
私の友人の看護師が、面白いことを言っていました。
年末の仕事納めに仕事仲間で飲むそうですが、ビールの入れ物に検尿用の紙コップを使うそうです。一般人にはちょっと嫌な気もしますが気にならないとのこと。ちなみに、私の兄は研究室で働いていますが、「俺はフラスコでビールを飲むよ」と笑っていました。
このように、同じものを同じように見ていないのが現実です。
●経済的自由人と不自由人では、発想が真逆
「成功するかしないかは、考え方の癖で決まる」という言葉があります。
同じものを見ても、それをどう使うか、何がつくり出されるかは、その人の考え方の違いによって決まるのです。
これと同じように、経済的自由人と経済的不自由人では、根本的な考え方が違います。
4つの考え方の大きな違いをご紹介します。
(1)自由か安定か
経済的に不自由な人のほとんどは「安定」を求めます。たとえば福利厚生のよさ、一生働ける仕事かどうか、いかに老後に困らないか、などが大事です。
言い換えるなら「困らないことを大事にしている」と言えるでしょう。保証があることを好み、新しい挑戦には憧れても行動はしません。
経済的自由人は「自由」を大事にしています。経済的な自由、時間的な自由、働く場所の自由、付き合う人の自由です。
困らないことよりも、楽しむことや挑戦することを優先します。
時間をお金に変えるのではなく、人生の価値を向上させることに変えます。
(2)できる・できないを気にするか否か
経済的に不自由な人は、合う合わない、できるできない、で物事を選択します。
たとえば就職先を選ぶときも、自分にできそうな仕事か、その仕事が自分に合うかが判断基準です。いままでやってきた経験が活かせること、自分が好きそうなことをやろうとします。
経済的自由人は、自分にとって価値があるかどうかで選択をします。
合う合わない、できるできない、は気にしません。たとえできないことであっても、できるようにすればいいと考えています。そもそも最初からできることなんてありません。できるできないは、やったかやってないかの違いだけだということを知っています。
いまできないことも、やっているうちに必ずできるようになると信じています。
だから、できるかできないかはまったく気にしていないのです。
(3)リスクを取るか、リスクから逃げるか
経済的に不自由な人は「リスク」という言葉を嫌います。リスクは取りたくない、一切損したくないと思っています。リスクがあるというだけで、考えることを放棄してしまう人も多いです。そして、やらないでいい理由を探します。
経済的自由人は、リスクを取ることで可能性が生まれることを知っています。
もちろん恐怖心はあります。しかし恐怖心があるから知る努力をします。一番のリスクは「知らないこと」ということを、よくわかっているのです。
そして、取れるリスクは積極的に取ります。たとえ失敗に終わったとしても、それが経験になるからです。
やる前から判断せず、取れるリスクであるなら行動し、経験することを大事にしています。そして、どうやったら、取ったリスクの分を利益に変えられるかを一生懸命に考えます。
(4)すぐに見返りを求めるか、先払いをするか
経済的に不自由な人は、働いたらすぐにお金や見返りを求めます。「労働の対価」というように、対価としてお金を得ることを大事にしています。
経済的自由人は、いま手に入れることよりも、将来にわたって手に入れることを大事にしています。すぐに結果にならなくても、将来のために先払いをしています。たとえ先払いして返ってこなかったとしても、経験を積めたことに価値を感じているのです。
問題点を探す前に、可能性を探せ
あるところに、2人の少年がいました。
2人は仲がよく、いつも一緒にいます。
しかし、考え方が違いました。
そんな2人が、あるときドーナツを見つけました。
1人は言いました。
「ほら、このドーナツ、真ん中に穴が空いてるよ」
すると、もう1人は言いました。
「きっとこれは、ドーナツ職人がケチってるんだ」
それを聞いて、もう1人が言いました。
「いや、きっとこうしたほうが美味しくつくれるんだよ」
またあるときは、神様についての話になりました。
「なんで神様は見えないんだろう?」
1人は言いました。
「きっと神様は意地悪なんだよ。だから姿を見せず何もしてくれないんだ」
もう1人は言いました。
「きっと神様はとても優しいんだよ。そして僕らを信頼してくださっている。だから姿を見せずに見守ってくださってるんだ」
2人は同じものを見ていますが、そこから連想しているものが違います。
1人は問題点を探し、1人は可能性を探しているのです。
どちらの少年のほうが、幸せな人生をつくれるでしょう?
ある日、私のメンターと数名の弟子で、景色のいいレストランで食事をしていました。私たちは「すごくいい景色!」と喜んでいましたが、メンターはこう言いました。
「これだけたくさんのビルがあるんだから、みんなが一棟くらい持ってもいいよな。俺も、どうしたらもっと不動産を持てるだろう?」
成功するかしないかは、考え方の癖で決まるとお伝えしました。同じものを見て何を連想するか、それは考え方の癖によるものです。
経済的自由人は「どうしたらうまくいくか?」をいつも考えています。
ビルを見れば「どうやったらそれが手に入るか」を考えますし、繁盛しているお店を見れば「どうやったら同じような商売ができるか」を考えます。
ビルがあるということは誰かが建てたということです。ならば自分にだって建てられるはずだ、という前提でいるのです。
逆に経済的に不自由な人は、挑戦する前から「どうせ自分にはできない」と思っています。
だから、どうやったらできるかという連想ゲームが始まらないのです。
●「困った」をチャンスに変える方法
ちなみに、先ほどの2人の少年。
この2人の少年は、誰の頭のなかにもいるのです。
ただ、どちらの声を聞くかは選択できます。
人間、欠けているものを見るのは当たり前です。その「困った」をビジネスチャンスに変えるか、不満に変えるかの違いが、経済的豊かさの違いを生み出しているのです。
たとえば、ペットボトルだって私が子どもの頃にはありませんでした。誰かが「重たい水筒ではなく、軽くて持ち運べる容器があったらいいのに」と連想してつくったはずなのです。
「なんで水筒って重いんだよ!不便だな!」で終わっていたら、そこにビジネスチャンスは生まれません。
とくに、頭のいい人ほど要注意です。
その頭のよさを何に使うかで、つくり出される結果が大きく異なります。
私の友人にも、東大出身で非常に優秀な人がいますが、彼は前提が非常にネガティブです。私が新しいビジネスモデルを考え、意見を求めると必ず、
「岡崎、いいか?そのビジネスモデルの問題は3つある。1つめは……」
となります。
ネガティブな意見も大事なので話は聞きますが、これでは何も新しいことはできません。
頭がいい人は、いかに難しいかを考えることに頭を使ってしまい、行動できなくなってしまうことがあります。
せっかく地頭がいいわけですから、その頭を問題点探しではなく「どうやったらできるか」にシフトしてみてはいかがでしょうか?
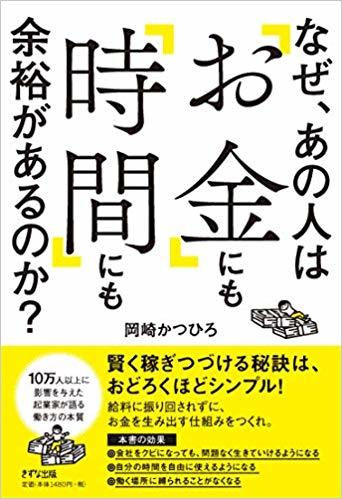
※画像をクリックするとAmazonに飛びます