(本記事は、ジョン・ネフィンジャー氏、マシュー・コフート氏の著書『人の心は一瞬でつかめる』=あさ出版、2021年3月19日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)
非言語コミュニケーションを活用する

「身体は言葉にできないことを伝えることができる」
マーサ・グレアム
(モダンダンスの開拓者一人として知られるアメリカの舞踏家、振付師)
ダーウィンの時代から、研究者たちは人の「立ち居振る舞い」とそれが社会に及ぼす影響力について着目していました。1970年代にUCLAのアルバート・メラビアン教授が行った、感情の伝達に関する有名な実験があります。
メラビアン教授によれば、誰かに話しかけられたとき、私たちはさまざまなシグナル――「声の調子」「表情」「姿勢」「ジェスチャー」「発話内容」――を参考にして相手の気持ちを探ろうとします。
では、これらの中で最も重要な働きをしているのはどれでしょうか?
その答えを探るべく、ある実験が行われました。
しかめっ面をしながら、「お会いできてとてもうれしいです」と言って相手の反応をうかがってみたのです。すると、人々は「発話内容」、つまり「うれしい」という言葉よりも「非言語シグナル」=しかめっ面の表情のほうを信用することがわかりました。
これが俗にいう「メラビアンの法則」です。
メラビアン教授によれば、私たちが判断に用いるシグナルの内訳は、視覚情報(表情やジェスチャー)が55パーセント、聴覚情報(声の調子)が38パーセントであり、言語情報(発話内容)が占める割合はわずか7パーセントにすぎないそうです。
これらの数字は必ずしも正確なわけではありません。詩人の言葉からは通常よりも多くの感情が伝わってきますし、人並み優れて説得力のある声の持ち主もいます。
とはいえ、メラビアンの説は大筋では正しいと言えます。つまり、人々の「感情」をより雄弁に物語っているのは、発話内容ではなく、非言語行動なのです。なぜなら、こうした判断を牛耳っているのは、言語をつかさどる高度な脳ではなく、原始的な「トカゲ脳( 爬虫類(はちゅうるい)脳)」(米国の神経生理学者であり、米国国立精神衛生研究所脳進化と行動研究所所長でもあったポール・マクリーン博士が提唱した「三位一体脳説」において人間が持つとされる3つの脳のうち「反射脳(脳幹)」を指した表現です)。
非言語コミュニケーションは、相手に対する「信頼感」と直結しています。
あらゆるシグナル――「顔の表情」「姿勢」「ジェスチャー」「声の調子」「発話内容」――に一貫性が感じられる場合、私たちはそれらのメッセージが「本物」であることを確信できます。一方、それぞれのシグナルが微妙に食い違っている場合、私たちは相手に対して疑念を抱きます。「何かを隠そうとしているのではないか」といった印象をもつのです。
人は無意識のうちに非言語シグナルの食い違いを察知し、話し手の「自信のなさ」や「弱さ」を嗅ぎつけています。私たちが直感的に相手の人間性を見抜くことができるのは、こうした非言語コミュニケーションのおかげなのです。
ここで、ちょっとした遊びを紹介しましょう。
「はじめに」で紹介した私たちの友人であり、パートナーのセス・ペンドルトンは、クライアントと一緒によくこの遊びをやっています。
「では皆さん、まずOKサインをつくってみてください」
彼はそう言いながら人差し指と親指で輪をつくり、その手を高く掲げます。続いて、
「今度はそれを自分の顎に当ててみてください」
彼は自分の手をゆっくりと顔のほうへもっていき、右頬に押し当てます。すると、部屋にいる全員が、彼と全く同じポーズを取ろうとします。
やがて、部屋中が笑いに包まれます。セスは「顎」と言ったのに、誰もが「頬」に手を押し当てていることに気づいたのです。
思わず吹き出す人もいれば、周りにバレないようにサッと手を顎に押し当てる人もいます。オチがわからず、一体何が起こったのかと部屋の中を必死に見回す人もいます。
この遊びは、シンプルかつ重大な教訓を伝えています。
私たちは視覚的な生き物であり、目から入って来た情報を最優先する傾向があるということです。言語メッセージは視覚メッセージに常に後れを取っています。
つまり、人々の印象を左右するのは、具体的に何を言ったり、やったりしたかではなく、表情や身のこなしといった視覚シグナルによって何を伝えたかなのです。
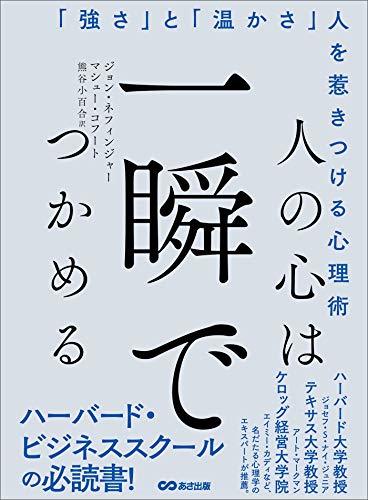
※画像をクリックするとAmazonに飛びます