不動産投資は副業にあたらないってホント? 5つの背景を解説
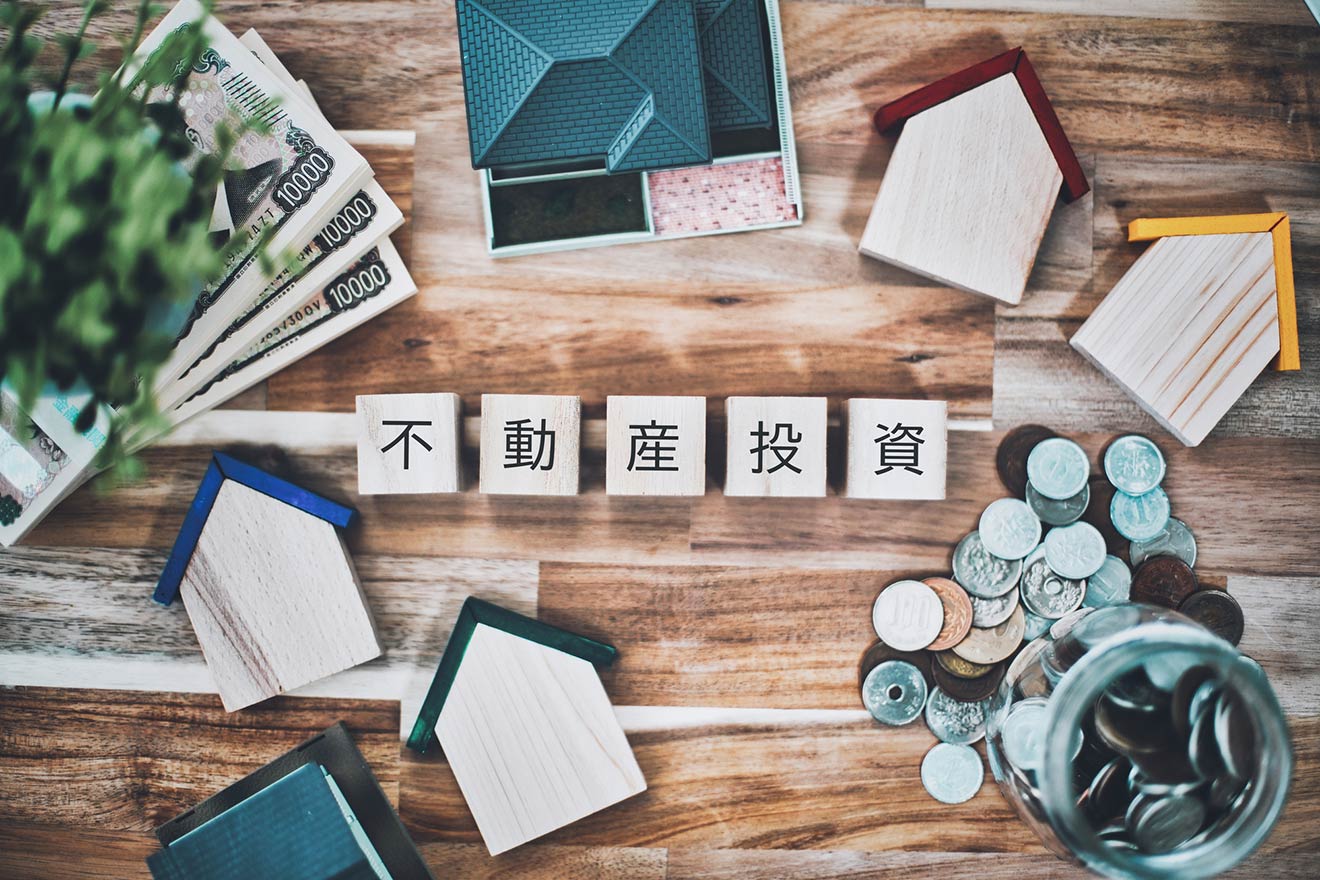
不動産投資が副業に該当するかという疑問は、多くの会社員が抱く不安の一つです。しかし、一般的には、以下のような理由から不動産投資は副業とみなされません。
- 法的に副業の明確な定義がないため
- 相続などやむを得ない事情があるため
- 憲法で職業選択の自由が保障されているため
- 情報漏えいなどの企業リスクが少ないため
- 本業に支障をきたすリスクが低いため
それぞれ詳しく解説します。
1. 法的に副業の明確な定義がないため
現在のところ、法律上「副業」の明確な定義は存在しません。そのため、企業が就業規則で副業を禁止していても、その範囲は曖昧なのが実情です。厚生労働省は「モデル就業規則」において「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事できる。」と副業を認める姿勢を示しています。
また、令和4年7月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン|厚生労働省」では、副業・兼業を安心して行えるようルールが明確化されており、国として副業を推進する方向性が打ち出されています。参照: パンフレット 副業・兼業の促進に関する ガイドライン わかりやすい解説|厚生労働省
副業をすることによって長時間労働にならないよう配慮し、本業に専念するとともに、秘密保持や本業との競業回避に留意すれば、基本的には副業することが可能です。法的な定義が曖昧である以上、企業側も一律に禁止することは困難な状況といえるでしょう。
2. 相続などやむを得ない事情があるため
不動産投資や賃貸経営を一律に禁止してしまうと、親族から収益物件を相続した場合や、転勤でマイホームを一時的に賃貸に出すケースなど、やむを得ない事情も禁止しなければならなくなります。
こうした状況は本人の意思とは関係なく発生するものであり、企業としても従業員のやむを得ない事情まで制限することは現実的ではありません。そのため、多くの企業では不動産による収入を副業禁止の対象から除外しており、不動産投資は容認されるケースが一般的です。
3. 憲法で職業選択の自由が保障されているため
日本国憲法第22条にて「職業選択の自由」が国民の基本的人権として保障されています。この憲法上の権利により、企業が従業員の副業を過度に制約することは原則として認められていません。
実際に、副業禁止の規定違反を理由とした解雇に関する裁判では「副業は原則として自由である」という司法判断が下されており、企業側が敗訴するケースが多く見られます(※)。ですから、本業に支障が出ない限りは、就業規則に違反していることにはならないでしょう。
ただし、この自由も無制限ではなく、本業に支障をきたしたり、企業秘密を漏えいしたりする可能性がある場合は、制限を受ける可能性があることも理解しておく必要があります。※参考: 厚生労働省|【参考】裁判例
4. 情報漏えいなどの企業リスクが少ないため
多くの企業が副業を禁止する理由の一つに、従業員が他社で働くことによる機密情報の漏えいリスクがあります。しかし、不動産投資ではほかの企業に雇用されるわけではないため、このようなリスクは発生しません。
不動産投資は賃貸物件を所有し、入居者から家賃収入を得る仕組みであり、本業で知り得た企業秘密や顧客情報が外部に流出する可能性は極めて低いといえます。また、競合他社との接触機会もないため、競業に関する問題も生じにくいのが特徴です。
5. 本業に支障をきたすリスクが低いため
副業により本業のパフォーマンスが低下することへの懸念も、多くの企業が副業を禁止する理由の一つです。しかし、不動産投資はほかの副業と比べて本業への影響が少ない特徴があります。
不動産投資では、管理業務を専門の管理会社(賃貸管理会社、建物管理会社)に委託することが可能です。入居者対応やメンテナンスなどの日常業務を外部に任せれば、投資家自身が行う作業は最小限に抑えられます。そのため、本業の勤務時間中や休日に不動産関連の業務に時間を取られることはありません。
不動産投資が副業として問題になるパターン
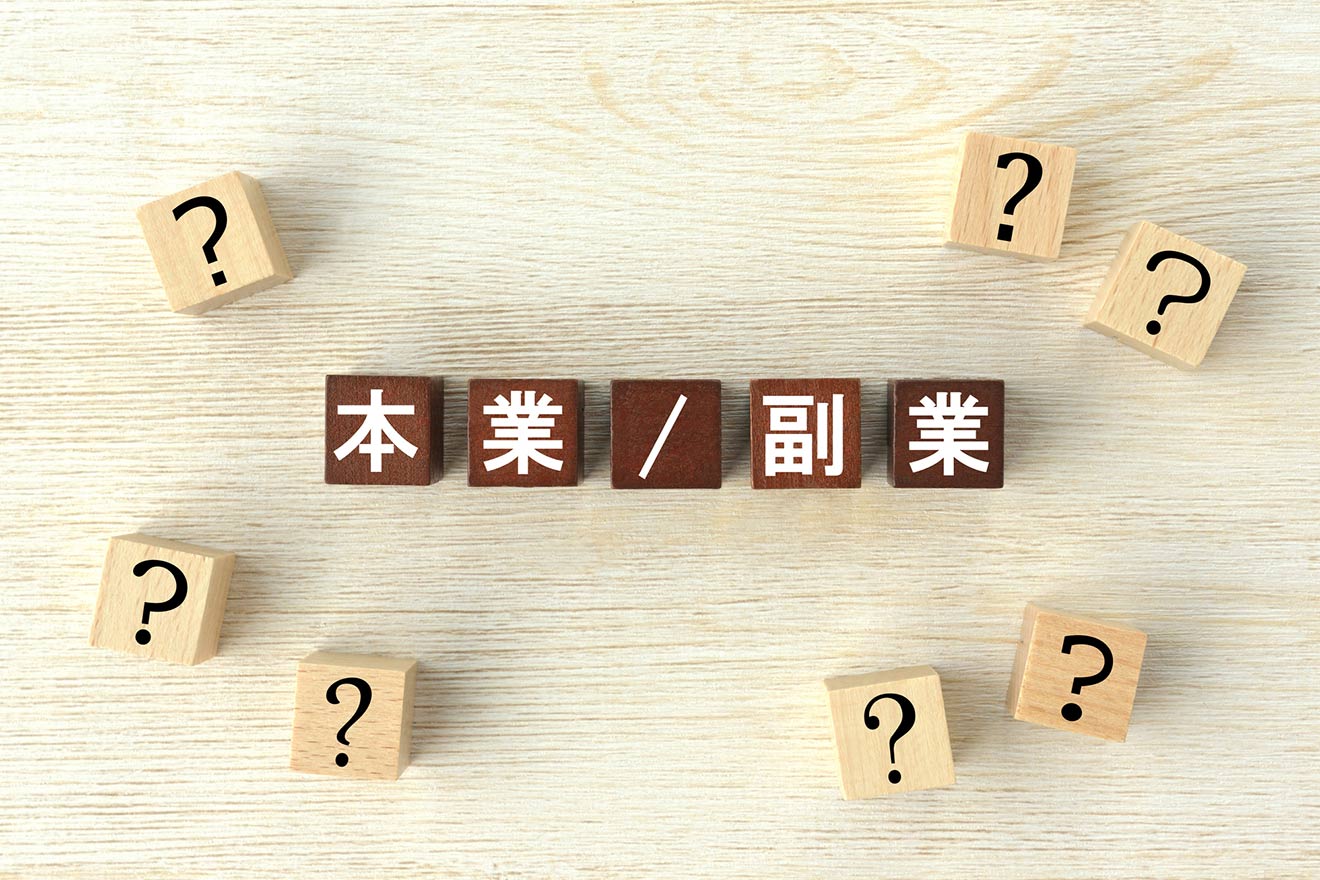
不動産投資が副業として問題になるパターンとして、以下の3つが挙げられます。
- 事業的規模(5棟10室以上)で運営している場合
- 本業が公務員の場合
- 自主管理で本業に支障が出ている場合
会社の副業禁止規定に抵触しないためにも、どのような場合に副業として扱われるのかを理解しておくことが重要です。それぞれ詳しく解説します。
1. 事業的規模(5棟10室以上)で運営している場合
不動産投資の規模が大きくなりすぎると、資産運用ではなく「事業」とみなされ、副業禁止規定に抵触する可能性が高まります。具体的な基準として国税庁が定めた基準は、「5棟10室」以上です。
この基準は、アパートやマンション、一戸建てなら5棟以上、区分マンションなら独立した部屋10室以上を所有している状態が該当します。この規模を超えると、税務上も「不動産所得」から「事業所得」として扱われ、青色申告特別控除(最大65万円)なども適用されます。
ただし、この基準はあくまでも税務上の目安であり、企業によっては独自の基準を設けている場合もあるため、就業規則を詳しく確認することが大切です。小規模から始めて段階的に規模を拡大する際も、常に会社の規定を意識しながら進めることをおすすめします。出典: No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁
2. 本業が公務員の場合
公務員の副業は法令で禁止されていますが、一定の条件を満たした場合は不動産投資も可能です。
国家公務員では、人事院の承認を得たうえで実施することが可能です。
具体的には、年間の家賃収入が500万円以上、または貸与する独立家屋の数が5棟以上、独立的に区画された一の部分の数が10室以上などの場合は、申請が必要となります(※)。これらの職業に就いている方は、事前に人事担当者に相談しましょう。※出典:人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について|人事院
3. 自主管理で本業に支障が出ている場合
不動産投資の管理業務を自分で行う「自主管理」を選択した場合、本業に支障をきたすリスクが高まり、副業禁止規定に抵触する可能性があります。
自主管理では、入居者からの緊急連絡対応、家賃滞納時の督促、設備故障の手配などの業務を自分で処理しなければなりません。これらの業務が勤務時間中に発生したり、休日も賃貸管理に時間を充てて体が休まらなかったりすると、本業のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。
企業が副業を禁止する理由の一つは「本業への支障」であるため、不動産投資により仕事の効率が下がったり、勤務態度に問題が生じたりすれば、副業禁止規定違反として処分を受ける可能性があります。このような事態を避けるためにも、管理会社への委託を検討することが重要です。
不動産投資の副業が会社員に人気な5つの理由

不動産投資は会社員にとって高額なイメージがあるにもかかわらず、なぜ人気があるのでしょうか?その理由は、主に以下の5つが考えられます。
- 働きながらでも続けられる
- 融資が受けやすい
- 生命保険の代わりになる
- 年金対策になる
- 長期運用ができる
それぞれ詳しく解説します。
1. 働きながらでも続けられる
不動産投資を自主管理で行おうとすると、入居者からの連絡にすぐ対応したり、家賃の管理やときには催促、入居退去のやりとり、入居者募集の活動など、日々さまざまな業務に追われます。
この賃貸管理業務を管理会社に委託すれば、本業がおろそかになることはありません。賃貸管理会社が代行してくれる主な業務には、以下のようなものがあります。
- 広告掲載、入居者募集、入居審査、内覧対応
- 賃貸借契約の締結
- 家賃集金、滞納家賃の督促
- 入居者の対応
- 退去時の立ち会い、敷金精算、原状回復工事 など
これらをすべて委託することで、オーナーが行う作業は月1回の収支報告書の確認程度となり、平日の仕事に集中できる環境が整います。物件を購入してしまえば、日頃は不動産投資のことを意識せずに本業に専念できるでしょう。
管理手数料は家賃の5~10%程度が相場ですが、本業への影響を考えれば十分に委託する価値があるといえます。運用の手間がかからないことが、会社員にとって不動産投資の最大の魅力といえるでしょう。
2. 融資が受けやすい
不動産投資の物件を購入するときは、不動産投資ローンを利用する場合がほとんどです。会社員は一定の収入があり、勤続年数が長ければ信用も得られるので、融資が通りやすくなります。
特に上場企業に勤務する会社員は安定的な収入を見込めるため、金融機関からの信用度が高く、より良い条件でローンを組める可能性があります。つまり会社員であることが有利に働くのです。
また、株式やFXなどの金融投資はまとまった自己資金が必要ですが、不動産投資はローンが利用できることで、レバレッジ(ローンを組むことにより少ない自己資金で高額な不動産を購入できること)を効かせられる点も人気の理由です。ワンルームマンション投資であれば、初期費用10万円程度から始められるケースも多いですし、家賃収入でローンを返済していくため、実質的な自己負担を抑えながら資産形成ができる点も、会社員にとって大きなメリットとなります。
3. 生命保険の代わりになる
万が一所有者が亡くなるようなことがあっても、残された家族に不動産投資で迷惑をかけることはありません。団体信用生命保険(団信)に加入しているとローンが完済されるので、そのまま家族の財産となります。引き続き家賃収入を得ることができ、売却すればまとまった資金を得ることもできます。つまり、不動産投資が生命保険と同じ役割を果たしてくれるのです。
生きている間は家賃収入を得られ、万が一の際には団信により無借金の不動産が残るという二重のメリットがあります。
最近の団信では「7大疾病」「全疾病」「がん特約」などの保障が付いた特約を付けられる金融機関も増えています。
4. 年金対策になる
「老後2,000万円問題」が取り上げられて以来、年金以外の収入や蓄えが必要だという考えが一般的になってきました。
不動産投資により月10万円の家賃収入があれば、ローン完済後は年間120万円から税金や経費をマイナスした分が追加収入となり、老後の生活費を補うことが可能です。また、インフレが進んでも家賃は物価上昇に連動して上がる傾向があるため、将来的な購買力の維持という観点からも有効な年金対策といえるでしょう。
不動産投資は、本業以外に時間をなかなか割けない会社員が、老後に不足するであろう資金を補填するのに最適です。このような理由で、不動産投資が年金対策として会社員に注目を集めています。
5. 長期運用ができる
不動産投資は入居者がいる限り、毎月同額の家賃収入が得られます。株式投資では市場の変動により日々価格が上下し、配当金も企業の業績に左右されますが、不動産投資の家賃収入は相対的に安定しています。一度入居者が決まれば、契約期間中は毎月決まった金額の収入を確保でき、長期的な資金計画を立てやすいのも特徴の一つです。
定年退職後や病気などの不安があっても、家賃収入があれば長期の運用が可能です。本業以外の長期にわたる収入源を確保することは、さまざまなリスクの分散になるでしょう。不動産投資は、将来の不安を軽減する手段となることが人気の理由の一つです。
不動産投資を副業で行う際の注意点

会社員が不動産投資をする際に注意しなければならない点は、どのようなものがあるでしょうか? 注意したいポイントとして、以下の2つが挙げられます。
- 就業規則を確認し勤務先へ事前に相談する
- 本業に支障をきたさない運営を意識する
それぞれ詳しく解説します。
1. 就業規則を確認し勤務先へ事前に相談する
まずは、勤務先の就業規則を確認しておくことです。企業によっては副業を禁止しており、不動産投資を副業とみなすところもあります。
副業を認めている企業でも、勤務に支障が出たり、情報漏えいのような秘密保持義務に違反したりすれば、処分を受けることになりかねません。就業規則をしっかりと確認し、勤務先の不利益になるような行動は避けるべきです。
また、副業を行うための申請が必要な会社もあるので、単に就業規則を確認するだけではなく、上司や人事部などに必ず事前相談しましょう。
2. 本業に支障をきたさない運営を意識する
副業が本業のパフォーマンスに悪影響を与え、会社からの信頼を失ってしまうと本末転倒です。そうならないためには、可能な限り管理業務を外部に委託し、副業のための労働時間を最小限に抑える必要があります。
「利益を最大化したい」という気持ちから、自主管理を考える方もいるかもしれません。しかし自主管理では多岐にわたる管理業務に多くの時間を取られてしまいます。
平日の日中に緊急対応が必要になった場合に、会社員では即対応できないケースが多いです。たとえば、給湯器の故障や水漏れなどのトラブルは、入居者の生活に直結するため即座の対応が求められます。
管理委託費用を必要経費として捉え、本業との両立を最優先に考えることで、長期的な成功につながるでしょう。
会社に黙って始めた不動産投資が、副業として発覚するケース
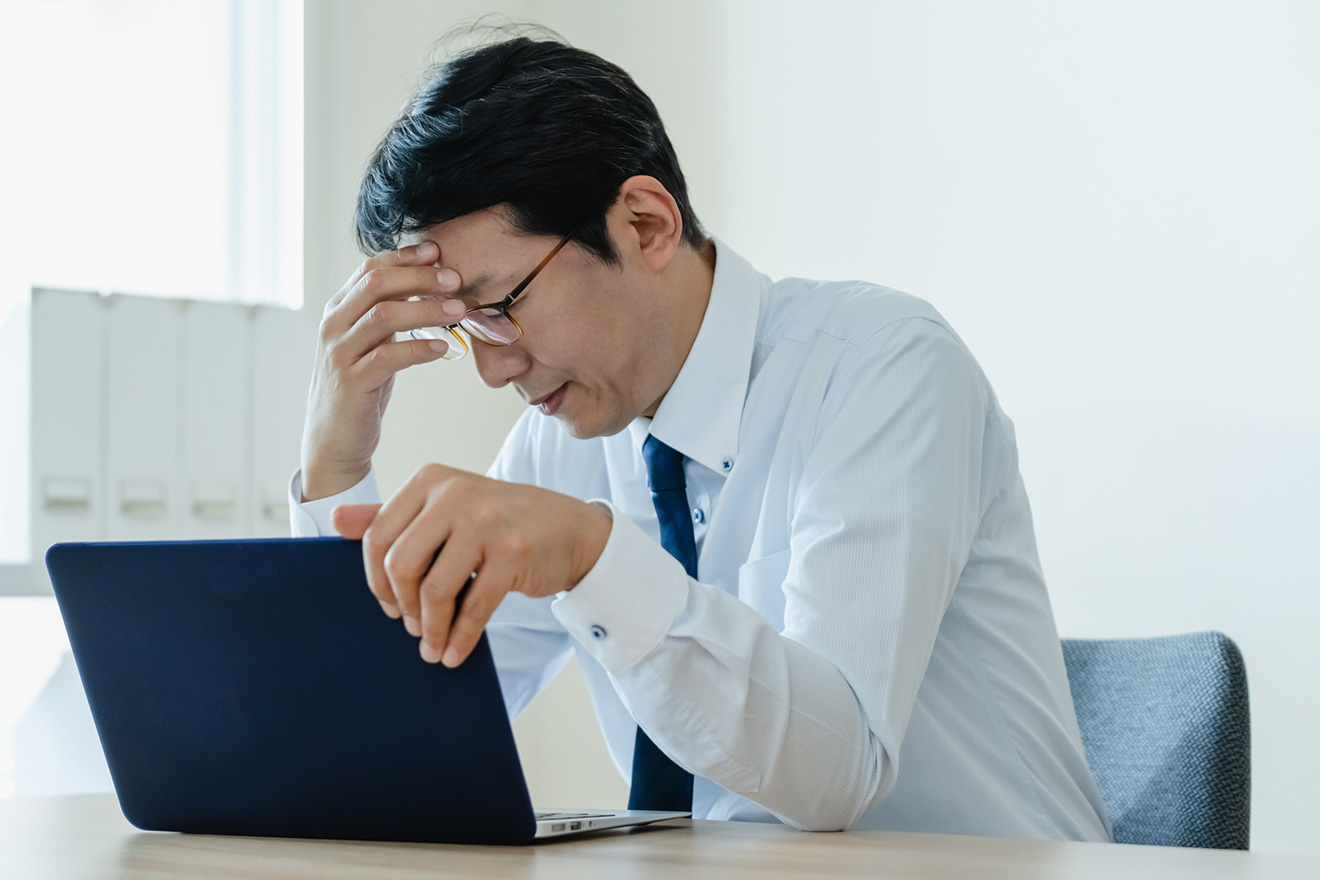
会社に内緒で不動産投資を始めて、「知られるはずがない」と思っていても、思わぬところから発覚してしまうケースが少なくありません。具体的に不動産投資の副業が発覚するケースは、以下のとおりです。
- 住民税の増額
- SNS
それぞれ詳しく解説します。
1. 住民税の増額
会社員の住民税は通常、「特別徴収」という制度により毎月の給与から天引きされています。しかし、不動産所得が発生すると総収入が増加し、それに伴って住民税額も増えます。
経理担当者が住民税の通知書を確認する際に、給与所得だけでは説明がつかない高額な住民税に気づき、「ほかに収入があるのでは?」と疑問を持たれるケースが多いのです。
この問題を回避するには、確定申告時に「住民税に関する事項」欄で、不動産所得分の住民税について「自分で納付(普通徴収)」を選択しましょう。これにより、不動産所得分の住民税は会社を通さず、自宅に直接納付書が送られてくるため、会社に知られるリスクを軽減できます。
住民税の徴収方法に関しては、お住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせください。
2. SNS
近年増加しているのが、SNSからの発覚です。XやInstagram、FacebookなどのSNSで不動産投資に関する投稿をしたり、投資セミナーへの参加写真をアップしたりすることで、会社の同僚や関係者に知られてしまうケースがあります。
会社に知られたくない場合は、SNSでの発信内容には十分注意し、プライバシー設定を適切に行うことが重要です。投稿内容は慎重に作成し、個人が特定されるような情報は控えましょう。
不動産投資は会社員の副業にもおすすめ!
不動産投資は、会社員に非常に向いている投資といえるでしょう。会社員であることで有利な条件でローンが組め、本業が忙しくても管理を任せておけば安定した家賃収入を得られます。会社員にとって、定年退職後や働けなくなったときに安定した収入を得られるのは、かなりの安心材料になるのではないでしょうか。
この記事を書いた人