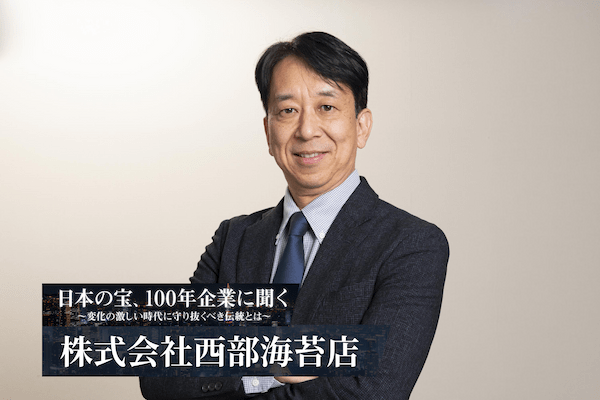
創業大正13年の老舗海苔問屋「西部海苔店」は、三代目社長・西出悟氏のもと、伝統を守りつつも大胆な変革を遂げている。コロナ禍を機に、業務用海苔の加工卸からヘルスケア事業へ参入。さらに海外展開を見据える同社の経営哲学は、「人」を核とした独自の組織文化にある。逆境を成長の機会ととらえ、社員とともに未来を切り拓く西出悟社長に、その真髄を聞いた。
企業サイト:https://www.nishibe-nori.net/
目次
老舗問屋から加工メーカーへの転換とコロナ禍での挑戦
── 取材対応やメディア露出は積極的にしていますか?
西出氏(以下、敬称略) 積極的にやりたい気持ちはあります。最近は、業界紙である週刊粧業さんやKITTE大阪(JR大阪駅に直結したショッピングセンター)での販売をきっかけに、少しずつ取材をいただくようになりました。昨年はKITTE大阪での販売期間中に、化粧品のステッカーを貼ったラッピングカーを10台ほど走らせたこともあります。この企画は、たまたま弊社の記事を見た企業からメールをいただいたことがきっかけで実現したものです。
── 創業は大正13年だとか。
西出 創業101年です。祖父が三重の伊賀から大阪へ修業に来て、海苔屋を始めました。私が社長になるまでに、過去に2回横領があったり、裏切りにあったりといった苦難も経験しています。
もともと屋号は「西部海苔店」ですが、西部の「西」は私の姓である西出の「西」です。祖父が修業した先は服部商店という会社でしたが、その会社が傾いたとき、祖父が実印を握って始めたのが大正13年です。戦争や疎開を経て、もう一度やろうとなったとき、服部さんもおられたので「西部」でやろうということになりました。
私がこの業界に入ったときは、業務用海苔の加工メーカーではなく、乾海苔問屋でした。海苔は焼いてカットし、回転寿司や外食向けに販売しますが、当時は焼いていない乾海苔を入札で落札し、入札権を持たない海苔屋さんに販売する問屋だったのです。付加価値がつきにくく、大手同業他社との競争も激しかったため、利益はまったく出ませんでした。
私が弟と入社した30年前、このままでは将来がないと危機感を抱き、付加価値を付けて販売する加工メーカーへ業態転換することを決意しました。問屋としての販売先をすべてやめ、一時的に売り上げが2億円ほどまで落ち込みました。当時26歳で経営者でもなかった私は、不安もありましたが、ただ頑張ることで乗り切ってきました。
会社が軌道に乗ったのは2018年頃です。売り上げおよび利益もかなり伸び、2019年には業態転換後、売り上げが7億7000万円、経常利益も4000万円ほどになりました。しかし、その翌年にコロナ禍が訪れたのです。
コロナ禍を逆手に取った新規事業と「人」を活かす経営
── どう乗り越えたのですか?
西出 外食産業がどうなるか分からない状況となり、2020年4月から外食がピタッと止まり、弊社の売り上げもたいへんなダメージを受けました。4月から5月半ばまでの1ヵ月半は工場も稼働率が大幅に下落し、雇用調整助成金や持続化給付金など、できる限りの情報を集めて対応しました。
その間、社員全員で「何ができるか」を考えるミーティングを重ねました。当時は巣ごもり需要があったため、スーパーの家庭用海苔が売れているという情報から、スーパー向け商品の開発やテイクアウト業者への営業を検討しました。
また、私自身も社会人になってこれほど時間があることはなかったので、「今やらなければ一生やらないだろう」という思いで、新しいことへのチャレンジを始めました。それがヘルスケア事業です。
当初、何から始めればよいか分からず、銀行に相談し、各都道府県に設置されている経営相談所「よろず支援拠点」を紹介してもらいました。そこから大学との連携を模索し、3つの大学と面談しました。最終的に近畿大学の薬学部の多賀教授と意気投合し、海苔の主成分であるポルフィランを抽出して化粧品化するプロジェクトがスタートしたのです。
現在、化粧品の販売はまだ厳しい状況ですが、このチャレンジは会社にたいへん良い影響をもたらしています。海苔業界は地球温暖化の影響で海苔の不作が続き、たいへんな状況です。
しかし、弊社は2019年のコロナ禍前の売り上げを2022年には回復させ、今では13億5000万円ほどまで売り上げが伸び、利益も過去最高を更新し続けています。
── 目を見張る成長ぶりですね。
西出 成長の要因は「人」にあると私は考えています。海苔の製造は技術だけではありません。弊社では、連絡事項は基本的に対面で行い、風通しの良い社風を大切にしています。野球でたとえるなら、自分のポジションだけでなく、ショートもセカンドもサードも守る「全員野球」です。
在庫管理の事務員も受注対応から発送まで、経理も午前中は受注対応しています。営業も原料選定から細かな対応まで、労を惜しまず行っています。これが社風となり、クローズドにならずにここまで来られました。
社員との信頼関係が築く強固な組織
── 成長の要因である「人」を大切にしているのですね。
西出 人を大切にしながら、この社風を持続していくことには難しさもありますが、弊社ではそれができています。コロナ禍で賞与をカットせざるを得なかったときも、社員に状況を説明すると、「社長、分かっています。言われなくても分かっています。私たちで頑張っていきます」と言ってくれました。過去には横領や裏切りもありましたが、この10年間で仕事が嫌で辞めた社員はほとんどいません。
「人財」と言うのは簡単ですが、実践は難しいものです。弊社のような中小企業だからこそ、そこにフォーカスを置いています。大手企業のような福利厚生や給与体系には及ばない部分もありますが、社長と社員、工場との距離を縮め、コミュニケーションを密に取ることをベースに社員を大切にしています。それが今の西部海苔店につながっているのです。
化粧品事業を始めたのも、新しいことにチャレンジすることで、会社の雰囲気が明るくなると感じたからです。黒い海苔だけを売るのではなく、この事業を通じてKITTE大阪をはじめ、いろいろな方とのつながりが増え、会社を訪れる方も増えました。会社の雰囲気もガラッと変わり、新しい社員も2名増えました。本当に良い効果しかありません。
今後、海苔事業では海外展開を計画しています。チャレンジするには、信じられる社員がいないとできません。零細企業の社長は、投げて打って走って、すべてを一人でこなすことが多いですが、コロナ禍以降、私はそうではなくなりました。新しい事業は当然私が走ってやりますが、基本的な業務は社員がこなしてくれています。同業他社と比べても、社員に恵まれていると強く感じています。
── 代々受け継がれてきた経営において、西部海苔店のDNAと西出社長ご自身の資質、どちらがより大きいのでしょうか?
西出 私は商売人の息子として生まれているので、いつか家業を継ぐだろうという思いがずっとありました。弟も同じです。父親の背中を見て育った影響は大きいと思います。
私がこの業界に入った当時、乾海問屋は利益が出にくい状況でした。入札で落札した乾海を、入札権のない海苔屋に転売するビジネスモデルでは、新海苔の時期になると残った原料を見切って売るため、結局あまり利益が残りません。競争も激しくなり、売り上げボリュームも減り、大手には勝てない状況でした。だからこそ、私は業務改革を進めてきたのです。
今、弟(専務)と話すのは、「よくこんな状況で入社したな」ということです。当時は給料も少なかったですが、嫌だとは思いませんでした。当時はファックス1台で手書きで伝票処理をするような当社でしたが、商売人の息子としての血が騒いだのだと思います。
── 報酬ではなく、内なる情熱に突き動かされているのですね。
西出 はい。弊社の従業員は、誰かのミスも自分のミスととらえ、会社全体が損をしないように全員でカバーし合います。野球と同じで、一人のミスを全員でカバーする。それが弊社の特徴だと思います。
採用基準は「礼儀礼節」と「明るさ」
── そのような組織文化は、人材採用の結果でしょうか、それとも入社後に社員が成長し、変化していく部分が大きいのですか?
西出 これは面白いのですが、弊社では営業職を募集する際、営業として募集しないのです。1年半前に30代の社員を2名採用しましたが、彼らは工場のバックアップ要員として、原料の選別やグレードチェック、商品管理、規格書作成といった業務を重視して採用しました。
当初、大手求人サイトで募集したところ、上場企業出身者など、弊社には合わない経歴の方からの応募が多かったのです。そこで、「明るくあいさつできる人」というキャッチフレーズに変え、社員が登場する動画も入れたところ、応募者の層がガラッと変わりました。アットホームな雰囲気を出し、ノルマがないことを強調した結果、同業他社の平均応募者数が17人ほどのところ、弊社には51人もの応募がありました。
採用した2人は、商品管理や原料管理など、汗をかく仕事も多いですが、全員で荷物を運ぶなど、少人数だからこそ全員で協力してやっています。社員の性格を見て、3ヵ月や半年経ったら、営業担当と同行させてお客様のところへ行かせます。そうすると、仕事が合うか合わないかが見えてきます。そこで、お客様を持たせたり、仕事の幅を広げたりするのです。
採用時はまず「礼儀礼節」を重視します。そこから社員を会社に馴染ませ、成長させていくのです。営業職は飛び込み営業やノルマがあると思われがちですが、弊社では飛び込み営業もしたくなるような環境です。
入社して半年から1年経ち、「このエリアを飛び込みで回ってみないか」と声をかけると、社員は自ら進んで行きます。そして、お客様から話を聞き、実際に購入につながると、それが自信になります。そうした積み重ねを経て、大きな顧客を担当させたり、商社に行かせたりするのです。社員は皆、仕事を楽しんでくれています。
弊社には全国に約400社の卸問屋がありますが、その9割は飛び込み営業で獲得したものです。値上げの際も、海苔の種類は1,000種類以上あり、そのすべてについて見積もりを出すとなると、5月や6月の土日が潰れてしまいます。それでも社員は出社して対応してくれます。朝礼では「忙しいほど快感だ」という声も聞かれます。
仕事量を嫌がる社員はおりません。もしかしたら、私が今一番暇かもしれませんね(笑)。海苔屋は今、まったく暇なのです。3年連続で値上げが続き、コンビニでは海苔が減り、スーパーの惣菜でも海苔を使わないケースが増えています。海苔の品質も落ち、色も緑っぽくなって、良いものがなかなか手に入りません。
国内市場の飽和と海外展開への舵取り
── それでは売り上げに影響があるのでは?
西出 いえ、弊社はその中でも売り上げを下げていません。むしろ増え続けています。これは、労を惜しまず細かなお客様にも丁寧に対応しているからです。商社を通じた多様なニーズにも応えているため、多くの企業が弊社を頼ってくださいます。
また、海苔の原価が倍になっているため、資金面で一年分の海苔を確保できない海苔屋も少なくありません。そうした同業他社の代替メーカーとして頼っていただけます。社員がきちんと対応することで、今、いろいろな良いスパイラルが生まれています。
── 大量生産・大量消費の時代において、礼儀礼節や人を大切にする普遍的な価値観が、企業の強さにつながっていると改めて感じます。
西出 はい。ウォーキングユーザー(飛び込みで来るお客様)もこの数年で増え、取引金額の大小にかかわらず、一件一件のお客様も大切にしているので、会社の基盤はまったく揺らいでいません。
── 新卒採用では大手志向や営業職を避ける傾向が強まる中、貴社のような前のめりに仕事に取り組む姿勢は、若手社員のキャリア形成においても大きな資産となるでしょう。
西出 大手企業や商社、英語を使う会社と比べると、弊社の社員は学力や技術面で劣るかもしれません。しかし、弊社のような零細企業では、そういった人材に注力しても、会社のレベルが彼らの成長についていかず、辞めてしまうのが現実です。
弊社に来るのは、自分に自信がない性格の社員もいます。しかし、うちで活躍すれば良いのです。人と話すのが苦手な子もいますが、弊社に来れば自信を持てて、「自分でも通用する場所がある」と感じられると思います。それは私自身も同じです。
皆が知っている大手メーカーでなくても、弊社のような従業員30人ほどの海苔店でも、今年は13億5000万円の売り上げを見込んでおり、最高益を確保しています。これだけ利益を稼げるのは、やはり人を育て、社員と自分を信頼し合う関係があるからです。
同業者からは「暇だ」と言われますが、世の中が良くないので、弊社も多少は暇だと感じる時もあります。しかし、他社と比べるとまだまだ多くの注文をいただいており、昨年は年間で125%の売り上げでした。会社を整えるという意味でも、今はちょうど良い時期だととらえています。
海苔にも海外展開のチャンスがある
── 経営の意思決定、特にヘルスケア事業のような新規事業や新しい分野への挑戦において、役割分担はどのようにしているのですか?
西出 今回の化粧品事業はコロナ禍で時間ができたときに始まったものです。私が何かを思いついても、社長だからといって社員が反対しにくい部分もあるでしょう。
しかし、専務である弟からは「一回やってみようや」と背中を押してもらえます。また、社員の中から「一緒にやりたい」と手を挙げた者を募り、営業担当者を中心に一緒に進めています。
今後の海外事業部に関しては、英語を話せるのが私しかいないので、私が先頭に立ってやらなければならないと考えています。
── 社長が新しい事業に時間を割けることは、貴社の強みの一つですね。
西出 はい。昔は社長といえば、部屋にこもってじっと座っているようなイメージがあり、それに憧れていました。しかし、実際そうなってみると、やはり暇なのです。だから、自分の時間を使って飛び込み営業もしますし、メディアにメールを打ったりもします。海外に行く準備も進めており、海外用の商品企画もしています。11月にはオーストラリアに行きたいと考えています。
── 今後の事業拡大や成長に向けた経営戦略、またM&AやIPOといったファイナンス関連の戦略を教えてください。
西出 今後の戦略としては、国内市場が飽和し、人口も減少していく中で、国内の売り上げを減らしても海外でプラスにする方向に舵を切りたいと考えています。海外事業を一つの事業として、きちんと利益が出る骨太なものにしていきたいです。売上規模ではなく、会社がちゃんと事業として成り立つことを重視しています。
M&Aに関しては、弊社に対して「M&Aをしたい」というメールをいただくことはありますが、今はまったく考えていません。ファイナンス面でも、昨年から各取引銀行がきっちりと支えてくださり、資金には全く困りません。返済に迫られることもなく、ファイナンスの悩みはありません。
海苔は冬に一年分を買い付けなければならない事業なので、7月決算の弊社では5月末から4月末にかけて在庫が膨らみます。5月に韓国からの輸入コンテナが入ってくると、在庫が10億5000万円ほどまで膨れ上がります。一般的には多いと言われますが、金融機関からは適正在庫と認められています。
海苔が不作の今、一年分の海苔を確保できないと、同業大手から買わざるを得ません。しかし、同業大手が持っている原料は当社の目に合う品質のものがなく、安定供給も難しいため、お客様を失うことに繋がります。弊社は生きた原料で商売をしているため、銀行から在庫について心配されることはありません。
海苔が取れなくなってきている中で、事業を拡大するというよりも、国内の売り上げが減っても海外でプラスにする方向に舵を切りたいと考えています。海外では中国産や韓国産の海苔が多く出回っていますが、日本の初摘みの美味しい海苔は「美味しい」と評価されます。昔は海外で生魚を食べるなんてとんでもないという時代でしたが、今では寿司が世界中で食べられています。海苔も同じように、海外に展開するチャンスがあると考えています。海外出張があるような、当社に新しい風を吹かし、垢抜けた会社にしていきたいです。
── 会社にポジティブな変化を起こすための具体的な計画はありますか?
西出 今、最も大きな計画は海外に出ていくことです。JETRO(日本貿易振興機構)と会ったり、海外営業代行の会社と契約したりと、準備を進めています。新しい風を吹かせるには「新たな一歩」を早く実行すること、とにかくチャレンジすることです。進みながら計画を軌道修正します。
まずはオーストラリアへ第一歩を踏み出し、新しい可能性を私自身が肌で感じて、社内に伝える予定です。
- 氏名
- 西出悟(にしで さとる)
- 社名
- 株式会社西部海苔店
- 役職
- 代表取締役

