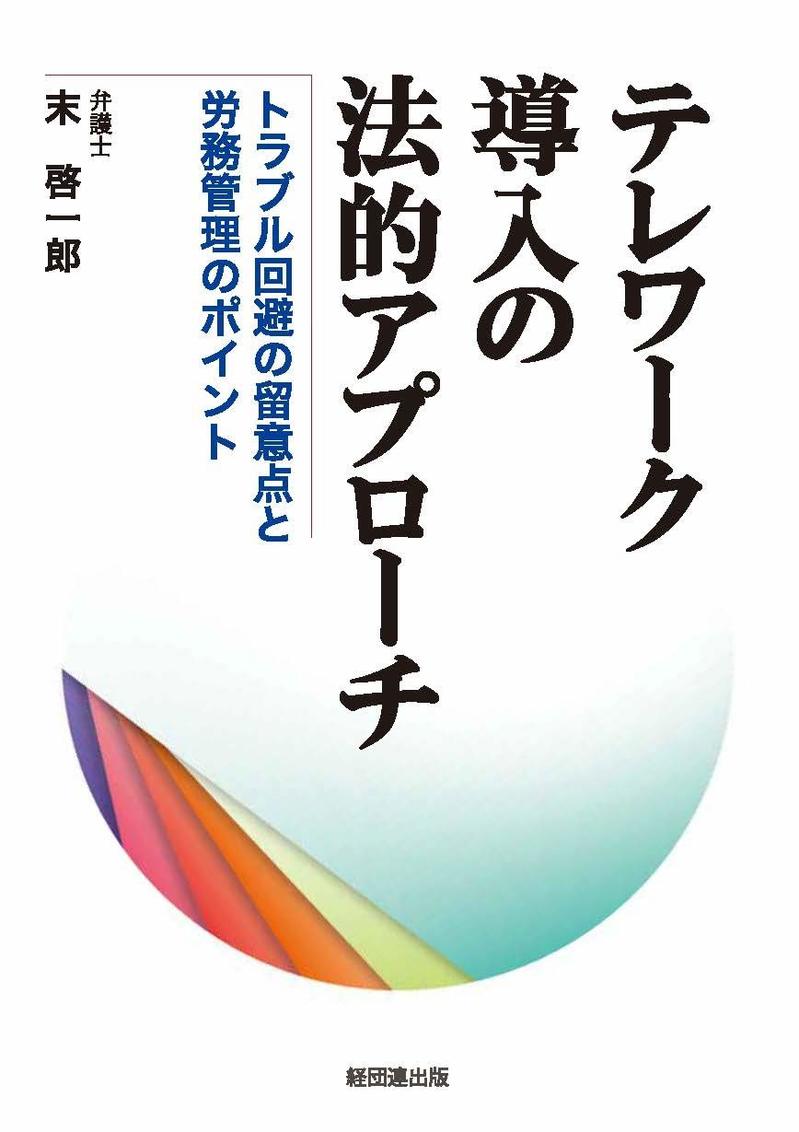(本記事は、末 啓一郎氏の著書「テレワーク導入の法的アプローチ-トラブル回避の留意点と労務管理のポイント」経団連出版の中から一部を抜粋・編集しています)
1.「時間と場所の柔軟性をはかれる働き方」は本当か
テレワークとは、「ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」(総務省ホームページ)であるなどと説明されているが、テレワークの本質を考えるうえでは、これについてさらに踏み込んでとらえることが必要である。
上記の総務省の説明からは、テレワークが本質的に「時間」と「場所」の双方の柔軟性をはかることのできる働き方であるかのような印象を受けるが、この表現は誤解を招きかねない。なぜなら、テレワークとは情報通信技術を活用することにより、就労の「場所」をオフィス(事業場)以外とする働き方であり、働く場所に柔軟性があることはその本質であるといえるが、テレワークによって「時間」の柔軟性が当然に高まるわけではないからである。時間の柔軟性については、一定の形態のテレワークについて、場所的な柔軟性が増加することで、労働時間の柔軟性も副次的に高まることが期待できるというにすぎない。
つまり、時間の柔軟性はテレワークに本質的なものではなく、重要ではあるが、副次的な効果にすぎないのである。
2.通常勤務と違いのない「労働時間の規制」
では総務省のホームページでは、なぜ「時間」と「場所」双方の柔軟性をはかることのできる働き方であるとの表現となっているのだろうか。それは、雇用契約を主とする労働契約関係にある労働者が行なうテレワーク(以下「雇用型テレワーク」という)と、請負・準委任(業務委託)契約を主とする労働契約関係以外により行なうテレワーク(以下「自営型テレワーク」という)の双方を含めて議論をしているからだと考えられる。
確かに、自営型テレワークは企業から独立して自由に働くものであり、労働時間規制の外にある就労時間の柔軟性が高い働き方であるが、それはテレワークであるがゆえに有する特徴ではない。そもそも業務委託や請負にもとづいて役務を提供する場合には、働く時間は自営業者自らが自由に決定できることが原則であり、本質的に「時間」の柔軟性を有する働き方であるといえる。つまり、自営型テレワークの場合は、「テレワーク」だからではなく、「自営業者」だから、時間を柔軟に扱えるにすぎない。これに対して、テレワークといっても、それが雇用型である限りは、労働時間規制が通常勤務と同様に適用され、その面では通常勤務とテレワークとの間に本質的な違いはない(この内容については後述する)。
つまり、雇用型にせよ自営型にせよ、あるいは専門業務型裁量労働制の対象業務をテレワークで行なうにせよ単純労働をテレワークで行なうにせよ、さらには自宅でのテレワーク(在宅勤務)にせよ駅や空港などでの空き時間を利用したテレワーク(モバイル勤務)にせよ、場所的な柔軟性こそが、テレワーク一般に共通する特質であり、これがテレワークの本質であるといえる。
むろん雇用型テレワークであっても、移動中などに、細切れ時間を利用して行なうモバイル勤務などは、その性格上、時間的な柔軟性が高いということができ、また育児や介護との調和をはかるための在宅勤務においては、労働時間を柔軟に運用できる制度的工夫をすることが、そのような働き方を導入した意味を活かす方策であるといえる。
しかし、雇用型である以上、時間規制はテレワークにも当然に及ぶ。モバイル勤務であっても、情報通信技術により、オフィスにいるのと同様またはそれ以上のレベルで時間管理が可能である。逆に、自営業ではなく、テレワークでもない通常のオフィス勤務の場合であっても、フレックスタイム制、裁量労働制、いわゆる高度プロフェッショナル制などを採用することによって、勤務時間の柔軟性は実現できるのである。
このように、「時間」の柔軟性が高まることや柔軟性を高める必要性があることは、テレワークの重要な特長であるとはいえるが、その本質であるとはいえない。
3.「離れた場所での勤務」が本質
したがって、身も蓋もない言い方になるが、雇用型も自営型も含めたテレワーク一般について、その本質を考えるなら、読んで字のごとく「テレ」(「遠い」という意味の接頭語)で「ワーク」するというにすぎない。
ちなみに、日本の法制度のなかにはテレワークについての定義規定はないが、アメリカでは、連邦法としてテレワーク強化法(Telework Enhancement Act of 2010)があり、連邦職員のテレワーク利用促進について具体的な定めをおいている。そこでは、「テレワークとは、職員が、その地位にもとづく権限や責任の行使その他の活動を、その職員がそうでなければ行なうであろう場所以外の承認された場所で行なう業務柔軟性措置をいう」とされている。この定義で示されているのは、場所的柔軟性のみである。
このように、テレワークの本質が「離れた場所での勤務」であるというにすぎず、通常勤務とそれ以上の本質的違いがないということを理解しておくことは、労働時間、安全衛生管理、差別禁止等々についての法規制・行政規制に関する諸問題や、労務・雇用管理等のテレワーク導入の実務的留意事項を考えるうえで有益であり、テレワークを導入するうえで明確に意識しておくべきことである。
ただし、テレワークの本質がそこにあるとはいっても、政府が旗振りを行ない、また巷で議論されているテレワーク概念には、前述のとおり、そこに若干の性格づけがされている。それを端的に示しているのが、厚生労働省の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(以下「雇用型テレワークガイドライン」という)である。このガイドラインの表題で、テレワークは「情報通信技術を利用した事業場外勤務」とされており、情報通信技術の利用という性格は、テレワークに本質的なものではないものの、このガイドラインでは、テレワークを論じる場合の当然の前提とされている。
この点は、テレワークの周辺概念や、テレワークの類型などをみてゆくと、さらに明らかになってくる。