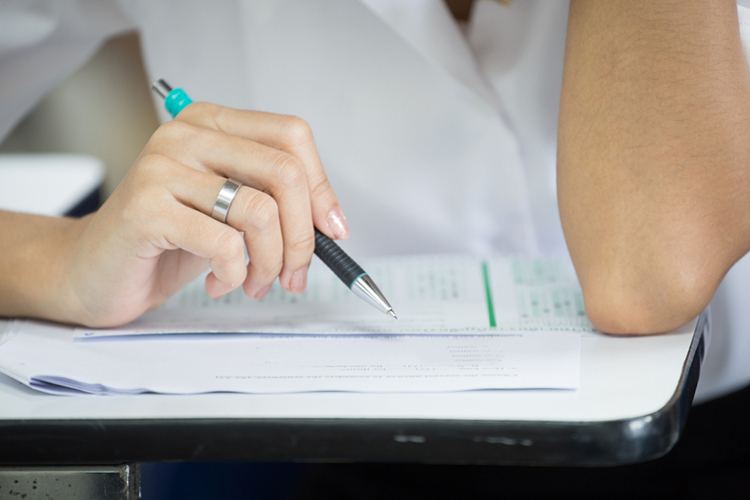不動産投資における法人化とは

不動産投資は、不動産会社に限らず個人でも行えて、サラリーマンが本業と並行して収益物件の運営をするケースも増えてきました。ただし、不動産投資を開始して、利益が出ている場合は年度末の確定申告が必要になり、所得税を納税しなければなりません。所得税は累進課税のため、利益が多くなればそれだけ所得税額も増えていくことになります。
そこで、不動産所得が多い投資家は、税金対策のために法人化の方法をとっているケースがあります。たとえば、サラリーマン投資家が本業となる勤務先企業の許可をとり、「働きながら不動産会社を経営する」といったケースです。
個人と法人で不動産投資するときの違い

不動産投資をするうえで、個人で行うのと法人として行うのは、何が違うのでしょうか。一般に不動産投資での法人化とは、節税を主たる目的として個人事業を行い、個人事業として行っていた不動産投資を「株式会社」もしくは「合同会社」を設立して運営することをいいます。
法人化の具体的な方法は、以下のとおりです。
- 法人で新たに不動産を購入する
- すでに個人で取得した不動産を法人に移管(譲渡)する
まず税制面では、個人と法人でかかる税金の種類が異なります。個人に対しては不動産投資が小規模の場合には所得税・住民税のみがかかるのに対し、法人には規模を問わず法人税・地方法人税・法人住民税・事業税等がかかります。
| かかる税金(納め先) | |||
|---|---|---|---|
| 個人の場合 | 所得税・復興特別所得税 (国) | 住民税 (地方) | |
| 法人の場合 | 法人税・地方法人税 (国) | 法人住民税 (地方) | 法人事業税・地方法人特別税 (地方) |
税制
個人と法人それぞれの税制の違いは、以下のとおりです。
| 課税対象 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 主な税金 | 所得税・住民税 | 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税 |
| 課税方式 | 総合課税(給与等と合算) | 法人単独で課税 |
| 税率構造 | 所得税:累進課税(5%〜45%)住民税:一律10% | 法人税(中小法人):2段階税率(年800万円以下の部分は実効税率約23%、年800万円超の部分は実効税率約35%) 実効税率:法人税・地方法人税・法人住民税・事業税などの総合的税率 |
| 利益がない場合 | 税金なし | 法人住民税均等割(約7万円)が必要 |
※令和7年7月時点の情報
所得税に関して、個人の場合は、不動産所得は「総合課税」対象となります。日本は累進課税制度をとっているため、不動産所得とそれ以外の所得の合計金額に応じて5〜45%の税率が課せられます。住民税と合わせると最大55%の税率となり、所得が増えるほど納める税金も増えるため、不動産投資における法人化は、規模が増すほど重要な問題といえるでしょう。
(詳しくは「節税になるって本当!? 不動産投資が節税対策と言われる仕組みと注意点」の不動産投資が節税対策になる仕組みをご覧ください)
法人の場合は、所得税と異なり2段階の税率構造となっており、所得が年800万円以下の部分の実効税率が約23%、年800万円を超えた部分の実効税率が約35%です。
法人住民税は法人税割と均等割の2つで構成されており、法人税割は法人税額の7.0%(都道府県:法人税額×1.0%、市町村:法人税額×6.0%)です。なお、税率は都道府県・市区町村によって異なるため、法人を設置予定の場所ごとで確認しましょう。法人住民税均等割は、利益が出なくても原則として最低約7万円の納税が必要です。資本金の規模や従業員数によって、支払額が異なります。
また、法人事業税は、法人の業種によって都道府県に納める税金です。たとえば資本金1億円以下の会社の場合、所得に応じて以下のように3段階の税率が適用されます。
- 年400万円以下の金額:3.5%
- 年400万円を超え年800万円以下の金額:5.3%
- 年800万円を超える金額:7.0%
法人税と法人事業税は所得があれば課税されるため、不動産所得が0円ならば支払う必要はありません。ところが法人住民税は、たとえ不動産所得が0円であっても課税されます。
不動産投資で法人化する5つのメリット

不動産投資で法人化するメリットは、以下の5つです。
法人化のメリット
- 10年間損失の繰越控除ができる
- 経費計上できる範囲が広がる
- 年収によっては節税になる
- 減価償却費が任意償却できる
- 短期売買の場合は個人よりも税率が低い
それぞれ詳しく解説します。
1. 10年間損失の繰越控除ができる
法人で不動産投資事業で損失(赤字)が出たとき、最長で10年間損失の繰越控除ができます。個人の場合は3年間です。
2. 経費計上できる範囲が広がる
法人化すると個人の場合のときより経費として計上できる範囲が広がります。
保険料は、個人の場合、生命保険や個人年金を合わせて12万円までしか経費計上できません。また生命保険だけではなく、個人年金、介護医療保険も合わせ、それぞれで4万円までという決まりがあります。
しかし法人の場合には、上限がありません。法人でいわゆる節税生命保険に加入した場合、保険料を払った年に計上できるのは原則として支払った額の50%、保険料が実際に支払われる年に50%を計上することが可能です。
保険料のほか、次のような項目を経費計上できます。
- 役員報酬
- 退職金
家族を役員にして役員報酬を支払った場合も、経費として計上できます。退職金も同様です。
3. 年収によっては節税になる
個人で不動産投資を行う場合、得られた所得は給与所得などと合算され、課税所得額によって累進課税制度により高い税率が適用されます。最高税率が適用された場合には、住民税と合わせて約55%もの税金が課されます。
一方、法人化した場合の課税は800万円以下の部分の実効税率が約23%、800万円を超えた部分でも実効税率は約35%です。そのため、個人の所得が高く、所得税率が高い人にとっては税率の低減につながり、節税効果が期待できます。
さらに、オーナーの家族を役員とすることにより、その家族に役員報酬を支払うことができます。これにより、適用される所得税率の高いオーナーの不動産所得を法人を通して所得税率の低いオーナー家族へ分散でき、一般にオーナー家トータルでの税金を低くすることができます。
4. 減価償却費が任意償却できる
減価償却費とは、その不動産購入代金を数年間に分割して毎年経費化していくという考え方です。減価償却費は建物の構造ごとに法律で定められた耐用年数があり、耐用年数により償却率が異なります。建物の取得価格に償却率をかけて割り出された金額が減価償却費となります。
個人の所得税では、毎年必ず減価償却費を計上しなければいけません。しかし法人の場合は任意償却が許されており、経営状況に合わせた税務戦略が可能です。赤字傾向の年度は減価償却費を抑え、黒字幅が大きい年度には減価償却費を最大限に計上することが可能です。
注意すべき点は、年間の減価償却費の上限は決められていることと、過去の減価償却不足分を損金算入額に加算することはできません。
5. 短期売買の場合は個人よりも税率が低い
不動産を売却した場合、その所得に税金がかかるというのは、個人も法人も同じです。しかし、短期で売却する場合は、個人よりも法人の方が有利です。
というのも、個人の場合、申告分離課税扱いとなり、不動産の保有期間が5年以内に売却した際に得た所得は「短期譲渡所得」となり、税率が30%になります(他の所得とは分けて課税される「分離課税」)。所得税と住民税を合わせた税率は39%です。
これに対し法人は、総合課税・分離課税といった扱いはなく、税率も通常の法人税率と同様に計算されるため、個人より税率は低くなります。
ただし、所有期間5年以上経過して保有する物件を売却する場合は、個人の税率は20%(所得税+住民税)と法人よりも低くなります。売却の予定がある人はどちらがメリットが大きいか、考えてみてください。
不動産投資で法人化する5つのデメリット

個人よりも法人の方が優遇される印象ですが、デメリットも見ていきましょう。法人化するかどうかは、デメリットをきちんと理解したうえで判断してください。具体的なデメリットは、以下のとおりです。
法人化のデメリット
- 法人を設立する費用がかかる
- 赤字でも法人住民税の支払いが発生する
- 個人の物件を法人所有にするとき税金が発生する
- 法人の維持費用がかかる
- 長期保有した際の税金面での優遇がない
それぞれ詳しく解説します。
1. 法人を設立する費用がかかる
たとえば「合同会社」として法人を設立する場合、設立報酬と税金を入れて約15万円かかります。
法人化する場合、次のような項目が必要になります。
- 資本金
- 法定費用
- 雑費
資本金は使ってしまうのではなく、会社に持たせるお金なので費用とはいえませんが、会社設立時には必要です。とはいえ、近年では1円からでも株式会社と認められます。
ただ法人設立時に、会社設立の報酬である「定款認証手数料」(株式会社の場合)、税金の「登録免許税」がかかり、その他の費用も合わせ株式会社で25万円程度、合同会社で15万円程度必要になります。紙の定款を使うなら「収入印紙代」もかかるので注意してください。
また、法人化して規模を拡大する場合は、役員や従業員の社会保険加入や年末調整の実施なども検討する必要があります。設立者自ら手続きを行えますが、内容が複雑ですし手間や時間がかかるため、顧問弁護士や税理士、コンサルタントなどの外部の専門家に頼るのがおすすめです。なお、外部の専門家に依頼する場合は継続的な報酬が発生するため、個人の場合と比べてランニングコストも大幅に増加する可能性があります。
2. 赤字でも法人住民税の支払いが発生する
法人について課される税金のうち「均等割」と「法人税割」で構成される法人住民税のうち、「均等割」は収益がゼロの場合でも納めなければなりません。
東京23区にあり、資本金1千万円以下・従業員50人以下の法人なら、支払い金額は収益の有無にかかわらず7万円になります。
3. 個人の物件を法人所有にするとき税が発生する
個人所有の物件を法人所有にする際は、通常の売買と同様の契約書を作ったり、税金を払ったりする必要があります。税金としては不動産取得税、登録免許税を再び支払わなければなりません。登録免許税・不動産取得税の負担がかなりの負担になることは留意すべきです。
登記移転に伴う司法書士への報酬も発生するので、法人への移転にかかる費用をきちんと計算しておきましょう。
4. 法人の維持費用がかかる
法人にした場合、税金以外にも、法人を維持するための費用も考慮しましょう。
たとえば、法人後の確定申告や税務処理は複雑になります。せっかく時間をかけて自力で確定申告を進めても、間違ってしまうと、再申請の手間がかかったり延滞税の支払いを求められたりする可能性があります。そのため、法人後の税務関係は、自力で行うよりも専門家である税理士に依頼するのがベストです。
税理士に依頼することで顧問料が発生するため、法人の維持にはコストがかかります。また、法人化することで社会保険への加入が義務付けられるため、事務作業の量が増加する点は理解しておきましょう。
5. 長期保有した際の税金面での優遇がない
個人で不動産投資を行う場合、所得は給与所得や事業所得など10種類に区分されます。不動産の売却による利益は「譲渡所得」として扱われ、特有の税制が適用されます。
個人の所得税は所得が増えるにつれて税率が段階的に上昇する仕組みですが、不動産の譲渡所得は「分離課税」として扱われるため、ほかの所得とは別枠で税金を計算しなければなりません。
この制度では、物件の所有期間によって税率が大きく変わります。所有期間が5年以内の売却は「短期譲渡所得」となり、所得税30%と住民税9%を合わせた合計39%の高い税率が課されます。一方、5年を超えて保有したあとに売却すると「長期譲渡所得」となり、課税されるのは所得税15%、住民税5%の合計20%です。
しかし法人の場合、このような所得区分は存在せず、不動産売却益も通常の事業所得と同様に扱われます。普通法人では課税所得800万円以下の部分に実効税率約23%、800万円超の部分に約35%の法人税率が適用され、さらに法人事業税や法人住民税も加わります。そのため、長期保有した不動産を売却する予定がある場合は、個人名義で所有し続けたほうが税負担を大幅に抑えられる可能性が高いです。
不動産投資で法人化するベストなタイミングと目安

不動産投資で法人化を考えるのは、不動産投資による所得が増え、納める税金の額を重く感じたときではないでしょうか。不動産投資を法人として行いたい、と決めたら気になるのはタイミングです。タイミングによってメリット・デメリットも変わるので、慎重に決めてください。
法人化するベストタイミングの一つが、物件購入時です。
いままで個人で購入した物件を法人へ移行しようとすると、費用がかかります。
登記について、個人名義の不動産を法人名義に変更しなければなりません。すでに支払った「登記にかかる費用」「不動産取得税」を再び支払わなければならないので、あとから法人に移行すると無駄なお金がかかることになります。
しかし法人化が適しているのは不動産所得が多く見込める場合です。まずは少額の不動産からスタートする人や、そこそこの利益しか見込めない人は、不動産所得が増えてきてから検討を始めても遅くはありません。
また、サラリーマン大家と専業大家でも適したタイミングが異なります。
サラリーマン大家の場合
サラリーマン大家が法人化を検討する最適なタイミングは、給与収入が2,000万円を超える場合です。
課税所得1,800万円超から、個人の場合は所得税と住民税を合わせた税率が約50%に達します。一方、法人の場合は実行税率約23%~35%の税率が適用されるため、法人税率のほうが個人税率よりも大幅に低くなります。結果として、法人化することで税負担が軽減され、手取り収入を増やせる可能性が高まります。
ただし、課税所得が1,800万円を超えていても、保有不動産が会計上赤字である場合は法人化を慎重に検討すべきです。個人であれば、不動産の赤字と給与所得を損益通算できるため、課税対象となる所得を減らせるからです。
専業大家の場合
専業大家の場合、不動産事業所得が330万円を超えるかどうかが法人化の判断基準となります。不動産所得が330万円を超えると、個人の税率は所得税と住民税を合わせて30%以上になります。一方、法人税率は実効税率約23%か約35%であるため、法人化することで税負担を軽減できる可能性が高いといえるでしょう。
ただし、不動産所得が330万円以下の場合は、個人の所得税と住民税を合わせた税率が20%以下に低く設定されています。この収入帯では法人税率よりも個人税率のほうが低いため、法人化はおすすめできません。
また、所得が330万円超695万円以下の範囲では、個人税率30%と法人税率約23%の差はあるものの、法人設立や維持にかかる諸経費を考慮すると、実質的なメリットを感じにくい可能性があります。
上記はあくまでも目安で、実際には総資産額や家族構成などによって総合的な判断が必要となります。
不動産投資で法人化する流れ5ステップ

不動産投資では、適切な手順に従って進めることで、スムーズに法人を設立できます。具体的なステップは、以下のとおりです。
- 会社設立に必要な準備
- 定款(ていかん)の作成と認証
- 登記書類の作成と申請
- 会社設立登記
- 税務署に開業届を提出
それぞれ詳しく解説します。
Step1:会社設立に必要な準備を行う
法人設立の第一歩として、以下の準備を行います。
- 代表者印・社印・銀行印の作成
- 社名・本店所在地の決定
- 事業目的の決定
代表者印は、代表取締役や代表社員が契約書などに押印するための印鑑です。社印は会社の正式な印鑑で、社名が刻印されています。請求書や領収書などの日常業務で使用します。
銀行印は、法人口座の開設や金融取引に使用する印鑑です。社名は自由に設定できますが、社名の前後に「株式会社」や「合同会社」がつきます。
Step2:定款(ていかん)の作成と認証を行う
続いて、会社の基本規則となる定款を作成します。定款とは会社の憲法ともいえる文書で、以下のような事項を記載します。
- 会社名
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金額
- 役員 など
株式会社の場合は公証役場での定款認証が必要で、認証手数料が必要です。一方、合同会社では定款認証が不要なため、この手続きと費用を省略できるのが大きな違いです。
近年は紙でなく電子定款が普及しており、電子署名を用いてオンラインで認証を受けられるため、印紙税が不要になるメリットがあります。また、この段階で資本金の払込みも行います。資本金の払込みは定款作成の前後どちらでも構いませんが、払込証明書は登記申請に必要です。資本金は会社の信用力にも関わるため、事業規模に合わせた金額を設定するとよいでしょう。
Step3:登記書類の作成と申請を行う
登記申請は専門知識が必要なため、司法書士への依頼が一般的です。
登記申請書の記載事項は商業登記法で定められており、法令に従った正確な記載が求められます。会社の商号や本店、資本金額、事業目的、役員に関する事項などを漏れなく記載します。
作成した申請書と添付書類は、本店所在地を管轄する法務局に提出します。申請方法は窓口での直接申請のほか、郵送やオンラインでの申請も可能です。
Step4:会社設立登記を行う
会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日となります。登記が完了すると、登記完了を証明する登記完了証が交付されます。会社設立登記に必要な書類は、以下のとおりです。
- 申請書
- 定款
- 発起人の同意書
- 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
- 設立時取締役(及び設立時監査役)の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 本人確認証明書
- 払込みを証する書面
- 資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
など
会社設立にかかる費用は株式会社で20万〜25万円、合同会社で10万〜15万円ほどです。
Step5:税務署に開業届を提出する
会社設立登記が完了したら、税務署への届出が必要です。同時に青色申告承認申請書も提出しましょう。青色申告を提出することで、欠損金の繰越控除を受けられるようになります。欠損金の繰越控除とは、赤字が発生した場合に、10年間にわたって利益と相殺できる制度のことです。
また、このタイミングで都道府県税事務所や市区町村の税務課にも「法人設立届」を提出し、地方税の納税義務も確定させます。これらの届出を適切に行うことで、税務上のトラブルを防ぐことが可能です。
不動産投資で法人化を検討する際の銀行融資

不動産投資をするうえでローンを組む方は珍しくありません。ただし、個人が不動産投資ローンを受ける審査と法人のローン融資では審査内容が異なります。
個人の不動産投資で重視されるのは、物件の価値と個人の信用力です。法人の場合は、その法人の業績が重視されます。本章では、銀行融資の種類と審査ポイントについて詳しく解説します。
銀行融資の種類
銀行融資の種類には、以下の3つがあります。
| 融資の種類 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| プロパー融資 | 銀行が独自の責任で行う直接融資で、信用保証協会などの保証を必要としない |
|
| 信用保証協会の保証付き融資 | 信用保証協会が債務保証人となって融資する |
|
| ビジネスローン | 事業資金を融資する用のローン商品 |
|
それぞれの融資タイプには特徴があり、企業の状況や目的に応じて選択することが重要です。
銀行融資の審査ポイント
不動産投資ローンを借りる場合、一般的には個人よりも法人の場合の方が金利は高く、借入期間も短くなります。過去の業績をみて融資可能かどうかを判断されるため、初めて不動産投資物件を所有すると同時に法人化を検討する場合、さらに金利が高くなる可能性もあります。
融資を受ける際には、法人として直接銀行との交渉が必要です。不動産会社がすすめる銀行があるかどうか、不動産会社に相談してみることもおすすめします。
不動産投資で法人融資を受けるための決算書を書く際のポイント

不動産投資で法人化するためには、金融機関に決算書を提出しますが、ここでも融資を受けるためのポイントが3つあります。
- 多くの資金があること
- 返済原資が豊富なこと
- 事業が好調であること
それぞれ詳しく解説します。
1. 多くの資金があること
資金が多いことをわかってもらえば、その分融資を受けやすくなります。資金の多さは自己資本比率で判断されますが、高い場合は返済しなければならない負債が少ないため健全性が高く審査に有利です。
原則として、自己資本は各会計期間の収益から積み上げていくことが望ましいですが、急速に資本を増強したい場合には、家族や親戚からの資金調達という選択肢も考えられます。
2. 返済原資が豊富なこと
返済能力の豊富さは、純利益と減価償却費の合計額が大きければ大きいほど優位性があります。金融機関は財務諸表をもとに返済能力を評価しますが、減価償却費は実際に現金が出ていかない費用項目です。
そのため、使途自由な資金は純利益と減価償却費を足した金額とみなされ、この金額が多いほど企業の自由裁量で活用できる資金が豊富だと判断されます。
3. 事業が好調であること
保有不動産の収益力の高さを強調することも重要なポイントです。金融機関は融資先としてオーナー個人の資産や投資歴ではなく事業そのものを評価するため、事業の好調さを明確に伝える必要があります。
たとえば、高い入居率を維持していれば、安定した賃料収入を得られるため事業が順調に推移しており、事業の安定性が高いと評価されやすくなります。さらに、物件の資産価値がローン残高を上回っている状況であれば、万が一の売却シナリオを想定しても、金融機関に安心感を与えることができるでしょう。
不動産投資において、複数法人を利用した融資隠しは非常に危険

不動産投資を法人化する際に、気をつけなければならないポイントがあります。それは、1物件1法人スキームで融資を受ける際、借入れ情報を隠してしまう、ということです。
1物件1法人スキームとは何なのか、どのようなリスクがあるのかについて説明していきます。
複数法人を利用した悪質な借入れ
1物件1法人スキームとは、一つの物件につき会社を設立するやり方です。たとえば3つの不動産を購入するときに、3つの法人を設立して、3つの異なる金融機関から融資を受けます。
不動産投資では通常、個人で金融機関から借入れを行うと、信用情報(借入状況)が登録されるため、よほど多くの資産や年収がない限り、他の金融機関から融資を受けにくいとされています。金融機関は貸し倒れのリスクを重くみることが多いことが理由です。
しかし、物件一つにつき一つの法人を設立すれば、それぞれの会社の信用情報は何も登録されていない状態なので、複数の金融機関から融資を受けられるといわれています。個人で融資を受けるよりも、物件の数だけ利益を上げられますが、投資に失敗すると大きなリスクがあります。既存の債務を隠して新規に融資を受ける方法であるため、グレーゾーンの手法です。
失敗すると非常に大きなリスク
1物件1法人スキームは、個人よりも多くの融資が受けられ、その分収益性やスピード感がありますが、失敗すると非常に大きなリスクがあるのがデメリットです。
このやり方は、いわゆる多重債務にあたるので、金融機関が知ってしまうと融資の一括返済を求められるケースがあります。こうした場合、複数の物件の売却や資金を調達する必要があるなどして、複数の金融機関に対応しなければならないので大変です。
一括返済までとはいかなくても、金融機関からしたら貸し倒れリスクを防ぐために、金利の引き上げが行われるかもしれません。十分注意しましょう。
不動産投資の法人化に関する気になる2つの疑問

不動産投資の法人化に関する気になる疑問は、以下の2つです。
- 不動産投資で法人化するときは、何に注意したらよいの?
- 副業しているサラリーマンでも法人化していいの?
それぞれ詳しく解説します。
Q. 不動産投資で法人化するときは、何に注意したらよいの?
法人化のタイミングに迷ったら、税理士など専門家に相談するのもおすすめです。スムーズな話し合いのためには、以下のポイントをクリアにしておきましょう。
- 不動産投資はメインなのか副業なのか
- 将来の物件の規模や数はどのくらいか
- 現在のキャッシュフロー、将来目標とするキャッシュフロー
具体的に考えたことがないという方は、これを機に将来のビジョンをよく考えてみてください。目的や計画がはっきりすれば、専門家のアドバイスも受けやすく、法人化の適切なタイミングもわかりやすくなります。目的や計画を決め、専門家に相談しましょう。
Q. 副業しているサラリーマンでも法人化していいの?
会社によっては、副業を禁止しているところも少なくありません。副業が禁止されている場合における法人化の方法には、以下の2つがあります。
- 家族を代表にして株主になる
- あらかじめ職場に確認しておく
副業が会社の規定に反する人は、自分は出資するだけの株主となり、事業主を家族にするのも一つの方法です。また、あらかじめ会社の規定等を精査し、兼業についての項目を確認しておきましょう。調べてもよくわからない場合は職場にきちんと確認し、あとあと問題にならないようにしておくと安心です。
給与所得が2,000万円を超える場合には不動産投資で法人化を考えよう
不動産所得が増えるほど、法人化して不動産を管理した方が節税効果は高まります。とはいえ会社を立ち上げるのですから、手間や費用がかかるうえ、その後の財務処理等も非常に時間がかかるようになるでしょう。
法人化を検討している人はメリット、デメリットを自分のケースで考え、自分の所得や税率を計算し、法人化した場合にどのくらいのメリットがあるかを把握することをおすすめします。将来的にも無理のないプランとタイミングで、法人化を行ってください。
この記事を書いた人