本記事は、内藤 誼人氏の著書『戦略的に24時間を自分のために使う 大人の時間術』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

時間管理のうまい人は、時間の推測も正確
タイム・マネジメント能力という用語があります。時間の使い方のうまさに関する能力のことです。
そういう能力のある人は、これから自分が取りかかる作業について、どれくらいの時間をかければ完了できるのかをほぼ正確に予測することができます。
英国オックスフォード大学のJ・フランシス=スミスは、とある教育研究所に勤める研究員48人に、3ページのテキストを読んで、スペルに誤りがないかどうかをチェックする、という作業をしてもらいました。
ただし、作業に先だって、「自分なら何分で終わらせられると思うか」を予測してもらいました。
その結果、タイム・マネジメント能力の高い人(能力については別の心理テストで測定しておきました)ほど、自分が完了できる時間の予測が正確であることがわかりました。
たとえば、「自分なら8分で終わらせることができそうだな」と予測したとき、タイム・マネジメント能力の高い人の場合には、7分50秒ですとか、8分5秒というように、ほぼ自分の予測通りに終えることができたのです。
だいたい私たちは、自分の能力に関しては、水増しして評価することが少なくありません。
本当はできないのに、「自分ならできる」と誤って思い込んでいることがあるのです。
仕事の能力に関しても、100点満点で本当は30点くらいなのに、「私の仕事の能力は80点」というように、たいていは自分の能力を勘違いして高く評価しがちです。
その点、タイム・マネジメント能力の高い人は、自己評価に関してとてもシビアです。
「自分にはそんなに仕事をこなす能力などない」と厳しい目で自分のことを見ています。
そのため、「予測の時間を大幅にオーバーしてしまった」という事態を避けることができ、ほぼ正確に作業の終了時間を予測できるのです。
タイム・マネジメント能力を磨きたいのであれば、できるだけ厳しい目で、客観的に自分自身の能力を評価し、仕事量を予測してみましょう。
作業に取りかかる前には、必ず、どれくらいの時間がかかるのかを先読みしましょう。作業が終わったところで、自分の予測と実際にかかった時間のズレを確認するのです。
これを何度もやっていると、自分の正確な能力や仕事量もだんだんわかってきます。最初のうちには大幅に予測が外れるかもしれませんが、そのうちに正確な時間が読めるようになるのです。
タイム・マネジメント能力の高い人は、何をするにしても時間の予測が正確です。
玄関を出てから会社に到着するまでの時間、ランチにかかる時間、プレゼンテーション用のスライドを作成する時間、寝つくまでの時間など、自分の生活のすべての時間が予測できるので、時間を管理できるのです。
タイム・マネジメント能力は、生きていく上で非常に重要ですから、何をするにしても時間の予測をしてから取り組み、できるだけ正確に判断できるように努力を重ねるとよいでしょう。
やりたくないものから片づける
タイム・マネジメント能力が高い人には、面白い共通点があります。
それは、「面倒くさいな」「やりたくないな」と感じることほど、さっさと片づけようとするという点です。
辛く、苦しいことほど先に、楽しみや面白いことは後に、という順番をきちんと守るのが、タイム・マネジメント能力の高い人の特徴です。
米国ニューヨーク市立大学のヘファー・ベンベナッティは、45人の大学生に、タイム・マネジメントのうまさを質問する一方、大好きなミュージシャンのライブや、大好きなスポーツ観戦など、「楽しいこと」を先にやりたいと思うか、それとも勉強など「苦しいこと」を先にやろうと思うかを尋ねました。
するとタイム・マネジメントがうまい人ほど、「勉強が先」と答えることがわかりました。
当然のことながら、そういう学生ほど実際の学業成績も高い傾向も確認されました。
苦しいことと楽しいことがあるときには、楽しいことは後回しにしましょう。
そうすれば、楽しいことが苦しいことに対する「ご褒美」となり、苦しいことを片づけるモチベーションを高めてくれます。「本当は面倒くさいけど、その後に楽しみが待っているのだから」と思えば、だれでも意欲が湧くはずです。
タイム・マネジメント能力の高い人は、そういうことをおそらく経験的に学んできたのでしょう。ですので、ごく自然に苦しいことから片づけようとするのではないかと思われます。
読者のみなさんは、苦しいことから片づけるタイプでしょうか。
だとしたら、タイム・マネジメント能力もそれなりに高いはずです。苦しいことを後回しにする人は、たいてい時間の使い方がうまくありません。
食事もそうです。食べられないわけではなくとも、積極的にあまり食べたくない料理を先に食べて、好きな料理は後でじっくり味わって食べるようにしたほうが、食事の時間が好きになり、好き嫌いもなくなります。子どもには、そういう順番で食事を食べるように教えてあげてください。
小さな頃からそういう指導をすれば、他のことに関しても、イヤなものから先に片づけるという習慣ができます。
いくつかの仕事を抱えていて、それぞれに取り組む面白さが異なる場合には、最もやりたくない仕事から、自分がとても楽しいと感じる仕事までを順番に並べ、やりたくないほうからひとつずつ片づけるようにしましょう。
やりたくない仕事が片づいていくのは、心理的に嬉しいものです。そのほうがモチベーションを高く維持できます。
「あらゆる仕事が苦痛」という人もいるでしょうが、そういう人はやりたくない仕事を終えたら、自分にご褒美をあげることにしましょう。
日中に頑張って仕事を片づけたら、夜にキンキンに冷えたビールを1本自分へのご褒美とする、などです。そういうご褒美があると、苦しい仕事もけっこう何とかこなせるものです。
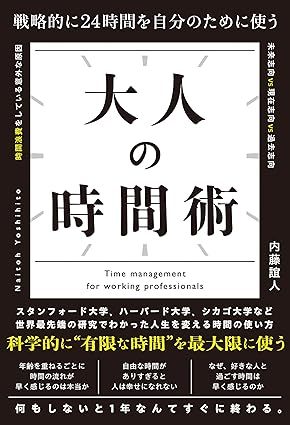
慶應義塾大学社会学研究科博士課程修了。
社会心理学の知見をベースに、ビジネスを中心とした実践的分野への応用に力を注ぐ心理学系アクティビスト。
趣味は釣りとガーデニング。
著書に『世界最先端の研究が教える新事実心理学BEST100』(総合法令出版)、『人も自分も操れる! 暗示大全』『「人たらし」のブラック心理術』(すばる舎)、『人と社会の本質をつかむ心理学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
