本記事は、内藤 誼人氏の著書『戦略的に24時間を自分のために使う 大人の時間術』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

働いている時間が長くなればなるほど、気を抜かない
当たり前の話ですが、勤務時間が長くなればなるほど、それだけ仕事のミスは増えます。
働きはじめの最初の1時間は、まだそれほど疲れていませんし、注意力も判断力も鈍っていませんので、仕事は順調にいきます。
ところが、2時間が経ち、3時間が経つと、どんどんミスは増えていきます。これは専門家でもそうです。
米国ハーバード・メディカル・スクールのジェフリー・リンダーは、204人のお医者さんが、風邪をひいてやってきた2万1,867人の患者に抗生物質を処方するかどうかを調べてみました。
日本人はお医者さんにお薬をもらうのが大好きですが、風邪には抗生物質は効きません。風邪の原因はほとんどがウィルスですが、抗生物質は細菌を殺すお薬なのです。
リンダーが調べた病院では、お医者さんは午前中に4時間(朝8時から正午まで)、午後にも4時間(午後1時から5時まで)診察することになっていたのですが、診察を始めて(あるいはお昼の休憩後)1時間目までを基準とし、診察を開始してから2時間目、3時間目、4時間目の抗生物質の処方の比率を検証してみました。
すると、時間が進むにつれその比率は、1.01、1.14、1.26とどんどん増えていったのです。お医者さんは、患者の生命を預かるプロですが、そんなプロでさえも疲れてくると、あまり考えずに意味もない抗生物質を処方してしまっていることが判明したといえます。
連続して働く時間が長くなるときは、注意しましょう。
勤務時間が長くなると、よほど気をつけていないと「うっかりミス」をしがちだからです。
どんなプロでもそうなのです。
ごく普通のデスクワークをしているのなら、多少はミスをしても許されるかもしれませんが、大きな事故につながるような危険を伴う仕事に従事しているのなら、相当に注意しなければなりません。
普段はきちんとルールを守る人でも、勤務時間が長くなるほど、いいかげんになってしまう、というデータもあります。
米国ペンシルベニア大学のヘンチョン・ダイは、4時間の勤務シフトで働く35の病院のスタッフ4,157人について、「手洗い消毒をするかどうか」を調べました。
すると手洗いルールをきちんと守る人の割合は、仕事が始まって1時間以内では42.6%。それから1時間が経過するごとに、39.1%、37.8%と減っていき、最後の1時間では34.8%と最低になることがわかったのです。
手洗い消毒は、自分だけでなく患者さんの生命を守るために非常に重要なルールですが、勤務時間が長くなると「まあ、いいか」と気が緩んでしまうようです。
1時間に1度は軽く休憩を取ることを心がけないと、重大なミスを犯してしまう危険が高まりますのでくれぐれも気をつけてください。
待たせる時間も時には必要?
お客さんをなるべく待たせないことが商売のコツです。
待たされて嬉しい人はいないからです。銀行や病院に対する不満が、他の業種に比べて異様に高いのは、お客(患者)さんを待たせる時間が単純に長いからです。
それでは、「待ち時間がゼロ」ならお客さんは満足してくれるのかというと、そうでもありません。
たとえば、弁護士や探偵のような仕事では、お客さんから電話がかかってきたときにすぐに電話に出たりすると、「この人はヒマを持て余しているのだろうか」と勘繰るお客さんもいます。
実際にはそんなことはないのに、事務所の電話に早く出てしまうと、人気のない弁護士なのではないかとお客さんを不安にさせてしまいかねないのです。
したがって、すぐに電話に出るのではなく、何回かコール音を聞いてからゆっくりと受話器を取ったほうがよいということもあるのです。
ほんのちょっぴり相手を待たせたほうが、「流行っている事務所なのだな」とか「たくさんのクライアントを抱えている事務所なのだな」と安心してもらえます。
米国コロンビア大学のシルビア・ベレッツァは、お昼ご飯を食べる時間がないほど忙しい人と、スケジュールがスカスカで時間を持て余している人について架空のプロフィールを300人に見せ、それぞれどれくらい社会的なステータスが高いと思うのかを聞いてみました。
すると忙しくて時間に追いまくられている人ほど「ステータスが高そう」と判断されることがわかりました。
というわけで、かりに仕事がまったくなくとも、忙しいふりをしたほうが仕事はうまくいく場合があるのです。
私の場合は、仕事の依頼に関する電話がかかってきても、すぐに出るということはしません。
必ず30分なり、1時間ほど経ってから折り返しの電話をします。メールもそうです。すぐに返信してもかまわない状況でも、少しだけじらすようにしています。
本当は喉から手が出るほど仕事がほしくとも、そういうホンネを見透かされると、安く使われてしまうことになります。
仕事の依頼の電話があったときに、すぐに応じてしまうフリーランスの人は、利益も出ないつまらない仕事しか回してもらえない可能性もあるので気をつけましょう。
私は、単行本の執筆依頼を受けたときには、スケジュールがスカスカでも、「すぐに取りかかることができます」とは言いません。「今、ご依頼いただければ半年……、いや8カ月後に執筆できるかもしれません」のように返答するようにしています。そうやってじらしたほうが、結果として自分を高く評価してもらえることを経験的に学びました。
相手を待たせることが、いつでも必ず悪いことなのかというと、そんなこともないのです。たまには相手を待たせたほうがよいケースもけっこうあるものです。
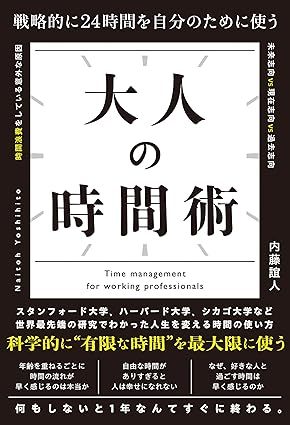
慶應義塾大学社会学研究科博士課程修了。
社会心理学の知見をベースに、ビジネスを中心とした実践的分野への応用に力を注ぐ心理学系アクティビスト。
趣味は釣りとガーデニング。
著書に『世界最先端の研究が教える新事実心理学BEST100』(総合法令出版)、『人も自分も操れる! 暗示大全』『「人たらし」のブラック心理術』(すばる舎)、『人と社会の本質をつかむ心理学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
