本記事は、堀田 秀吾氏の著書『とりあえずやってみる技術』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。
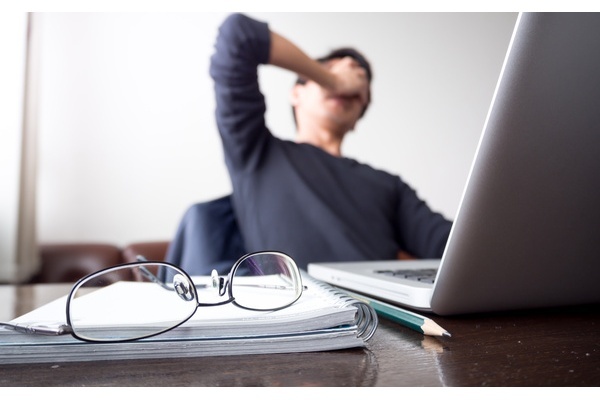
「成功するかも」より「失敗したらどうしよう」が勝る理由
「失敗したらどうしよう」
「人から変に思われたくない」
「恥をかきたくない」
そんな気持ちが強いあまり、何か新しいことに挑戦しようとしたときに、心にブレーキがかかってしまった経験はないでしょうか。
こうした感情は、個人の気の小ささの問題ではありません。実は現代社会においては、誰もが抱きやすくなっているごく自然な心理反応なのです。
現代では、恥がネットを通じて簡単に可視化、拡散されてしまいます。SNSや動画投稿サイトにより、ちょっとしたミスや不注意も記録、保存、共有されるようになり、「取り返しのつかない恥になるのでは」という恐怖が、私たちの挑戦意欲を削いでいきます。
この背景にあるのが、心理学でいう「スポットライト効果」です。
これは、「自分の行動や失敗が、他人にとっても強く印象に残るに違いない」と思い込んでしまう現象です。
たとえば、コーネル大学のギロビッチらの研究では、被験者にダサいTシャツを着てもらい、学生の集まりに参加させました。当人たちは、「こんなダサいTシャツを着ていたら笑われる。絶対に注目される」と感じていたものの、実際に覚えていた人は全体のわずか24%に過ぎなかったという結果が出ています。
この研究結果から言えることは、自分が感じているほど、他人は自分の失敗や振る舞いに注意を払ってはいないのです。
それでもなお、「目立ちたくない」「変な人だと思われたくない」という思いが、私たちを動けなくしてしまいます。
ここにさらに拍車をかけるのが、「損失回避バイアス」という人間の傾向です。
行動経済学のプロスペクト理論に基づけば、人は得をすることよりも損をすることをずっと強く恐れる性質があります。
つまり、「成功するかも」という希望よりも、「失敗したらどうしよう」という不安のほうが行動を止める力として圧倒的に強いのです。
このように、失敗、恥、批判といったリスクが強調される社会構造のなかで、とりあえずやってみることはますます難しくなっています。
「行動すれば失敗するかもしれない、叩かれるかもしれない」と思い、「何もしなければ、とりあえずは安全」と思う。この構図が挑戦そのものを特別なことにしてしまい、行動のハードルをどんどん上げているのです。
しかし、心理学者たちはこうも言います。
「思っているほど、他人はあなたに注目していないし、失敗を覚えていない」と。
自分にとっての大きな恥も、他人にとっては一過性の話題に過ぎません。
「失敗=恥」という感覚を強固にしている背景
日本人がこれほどまでに失敗を恐れる根底には、「失敗は恥ずかしいことだ」「できる人間は失敗しないはずだ」といった無意識の思い込みがあるように思われます。そしてこの思い込みが、私たちの行動を静かに、しかし確実に制限しているのです。
もちろん、すべての日本人がそうとは限りません。
たとえば、東京大学の高野の研究では、「日本人は必ずしも集団主義的ではない」という結果も示されています。しかし、それでもなお、多くの人が他者の視線や世間体を気にしながら行動しているのは事実です。
高野も指摘しているように、たとえ実際の行動傾向がそうでなくとも、「日本人は恥ずかしがり屋で、失敗を嫌う」という文化的なステレオタイプが、社会的な期待や自己イメージとして深く根づいているのです。
この「失敗=恥」という構図は、特に組織のなかでは顕著になります。
日本社会では、多くの人が大人になると企業や学校、団体といった組織のなかで生活するようになります。そこでの失敗は、もはや個人だけの問題ではありません。
「自分のせいでチームに迷惑をかけてしまった」「上司や同僚の評価を下げてしまうかもしれない」と感じる場面が増え、結果として「ミスできない」「目立てない」という空気が強まっていくのです。
加えて、現代社会ではSNSなどを通じて失敗が可視化されやすくなっており、恥の影はさらに濃くなっています。
昔であればうっかりした失言もその場限りで流れていったでしょう。
しかし今では、スクリーンショットや動画で半永久的に保存され、広く共有される危険があります。そのことが、「やらないほうが安全」「出しゃばらないほうが傷つかない」という心理をさらに強化してしまうのです。
また、ネット上では、他者の成功や充実した日常ばかりが目に入り、自分との比較によって劣等感や不安を感じやすくなります。
これは、スタンフォード大学のフェスティンガーが提唱した「社会的比較理論」によっても説明されます。
人は自分の行動や立場を他人と比べることで自己評価を形成する傾向があり、それが過剰になると、「失敗=自分の価値の低下」と結びついてしまうのです。
こうして、「他人の視線」+「組織の空気」+「SNSでの比較」という三重のプレッシャーが、「失敗=恥」という感覚をますます強固なものにしています。
そしてその結果、多くの人が「動くこと自体がリスクだ」と感じるようになり、行動しないことが常態化してしまうのです。
こうして私たちの社会は、今まさに、失敗しないことを第一にする風潮に包まれています。
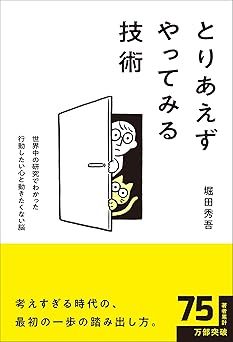
専門は、司法におけるコミュニケーション分析。言語学、法学、社会心理学、脳科学などのさまざまな分野を横断した研究を展開している。
テレビのコメンテーターのほか、雑誌、WEBなどでも連載を行う。
おもな著書には、『科学的に元気になる方法集めました』(文響社)、『最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方』(サンクチュアリ出版)、
『科学的に自分を思い通りに動かすセルフコントロール大全』(木島豪氏との共著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。
科学的な知見をもとに問題解決のヒントとなる書籍を執筆し、これまでの累計部数は75万部を突破している。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
