本記事は、堀田 秀吾氏の著書『とりあえずやってみる技術』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

成長に必要なのは、リスクではなく「コスト」を見極める目
「リスクがあるからやめておこう」
そう思って行動を先延ばしにしてしまうことは、誰にでもあります。
しかし、ここで注意したいのは、「それは本当にリスクなのか?」ということ。
実は多くの場合、私たちがリスクと呼んで避けているものは、厳密には「コスト」にすぎません。
リスクとは、未来の出来事についての「不確実な損失の可能性」を指します。
たとえば、交通事故に遭う、仕事で大失敗する、大金を失う。
こうした事態はたしかにリスクです。
しかし、英語で“cost”と表現されるコストとは、時間、労力、あるいは金銭といった、ある成果を得るために確実に必要な対価のことを指します。
たとえば、資格の勉強を始めるとき、「毎日30分勉強するのはしんどいな」「数万円の講座費がもったいない」と感じるかもしれません。
しかし、これは「損をするかもしれない不確実性」ではなく、「達成のために払う必要のある投資」です。
にもかかわらず、私たちはこのような確実に発生するコストに対しても、無意識にリスクと錯覚してしまい、やらない理由として使ってしまうのです。
このような心理的な誤認について、デューク大学のアリエリーは、人は「即時の痛み(=目の前のコスト)」を過大評価する傾向があると述べています。
未来に得られる利益よりも、今感じるわずかな負担のほうが大きく見えてしまうため、成長のチャンスを逃してしまうのです。
ほとんどの成長は、「確実なコストを払う」ことから始まります。
時間を使う。労力を注ぐ。少しのお金を投じる。
それで得られる経験やスキルは、長い目で見ればリスクを取る以上の価値をもたらす場合があります。
もちろん、何も考えずにコストを払い続けることが良いとは限りません。
しかし、「この時間やお金は、未来の自分にどんな価値をもたらすか?」と考えることで、行動の選択は大きく変わります。
自分の将来に投資する意識を持つことで、目の前のしんどさやめんどうくささは、ただの障害ではなく「通過点」として意味を持ち始めるのです。
成長とはギャンブルではありません。
たいていの場合、それは「コストを支払うこと」を避けなかった人が、ゆっくりと、しかし確実に手にしていくものなのです。
リスクには2種類あり、それぞれ特徴が異なる
私たちがリスクを語るとき、その質には2つの異なる種類があることを知っておく必要があります。
それが「客観的リスク」と「主観的リスク」です。
客観的リスクとは、数値化・定量化が可能な、比較的予測しやすい危険のこと。
たとえば「この業務には1%の事故率がある」といったように、過去のデータや統計に基づいて判断できるものです。このタイプのリスクには、保険や予防策などの対応がしやすいという特徴があります。
一方、主観的リスクとは、感情や直感によって生じる「不安」に近いものです。
「失敗したら恥をかくかもしれない」「みんなに笑われるかもしれない」など、事実ではなく想像や思い込みによって大きくふくらむリスクです。
これは認知バイアスの1種である「損失回避バイアス」とも深く関係しており、人間は得をするよりも、損をすることのほうを強く避けようとする傾向があるといわれます。
この2つは、「合理性」と「理性」の違いとしても説明できます。
数字に基づくリスク(合理性)は冷静な対応ができますが、感情によるリスク(理性)は過大評価しやすく、行動の妨げになりやすいのです。
ただ実際には、「リスクに見えるものの正体は、単なるやったことがない不安」ということも少なくありません。
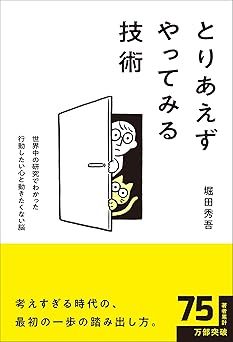
専門は、司法におけるコミュニケーション分析。言語学、法学、社会心理学、脳科学などのさまざまな分野を横断した研究を展開している。
テレビのコメンテーターのほか、雑誌、WEBなどでも連載を行う。
おもな著書には、『科学的に元気になる方法集めました』(文響社)、『最先端研究で導きだされた「考えすぎない」人の考え方』(サンクチュアリ出版)、
『科学的に自分を思い通りに動かすセルフコントロール大全』(木島豪氏との共著、ディスカヴァー・トゥエンティワン)などがある。
科学的な知見をもとに問題解決のヒントとなる書籍を執筆し、これまでの累計部数は75万部を突破している。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
