本記事は、三冨 正博氏・中谷 昌文氏・川島 優貴氏の著書『AI時代!「ワクワク仕事」の成功法則』(セルバ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

勘違いが生む抵抗感
「AIは危ない!」という幻想と並んで、AIに対するもう1つの大きな「勘違い」が存在します。それは、先ほどの恐怖とは正反対の、ある種の「過度な期待」から生まれるものです。
すなわち、「AIは、私の欲しいものを、言わなくても、あるいは少し言っただけで、完璧に察して、全自動で何でもやってくれる魔法の道具だ」という思い込みです。
一見すると、これはAIに対するポジティブな期待のように思えるかもしれません。しかし、実はこの「全自動・おまかせ」という幻想こそが、多くの人をAI活用から遠ざけ、かえって「AIなんて使えないじゃないか」という強い抵抗感を生む、非常に厄介な罠なのです。
AIは「神様」でも「エスパー」でもない
ChatGPTをはじめとする生成AIと初めて対話したとき、その能力の高さに誰もが驚嘆します。まるで、こちらの心を見透かしたかのように、的確で、示唆に富んだ答えを返してくれる。その体験は、私たちに「このAIなら、私の考えていることを全部わかってくれるかもしれない」という、甘い期待を抱かせます。
しかし、忘れてはならないのは、AIは神様ではないということです。AIは、私たちの心の中を直接読み取ることはできません。あくまで、私たちが入力した「言葉」を手がかりにして、その背後にある意図を「推測」しているに過ぎないのです。
にもかかわらず、多くの人が無意識のうちに、AIを「何でもお見通しのエスパー」や「痒いところに手が届く完璧な執事」のように捉えてしまいます。「ちょっとヒントを与えれば、あとはいい感じにやってくれるだろう」「私の漠然としたイメージを、完璧な形にしてくれるはずだ」。そんなふうに、AIに過度な「忖度(そんたく)」を期待してしまうのです。
そして、その期待は、多くの場合、裏切られます。AIから返ってきた答えが、自分のイメージと少しでも違っていると、「なんだ、AIってこの程度か」「全然、わかってないじゃないか」と、途端に失望し、AIに対する興味を失ってしまう。この「期待」と「失望」の落差こそが、AIへの抵抗感を生み出す、1つの大きな原因となっています。
欲しいものを考えるのは、いつだって「人間」
ここで、私たちはAIとの関係における、最も基本的で、最も重要な原則に立ち返る必要があります。それは、「結局、何を欲しいのかを考えるのは、人間の仕事だ」ということです。
AIは、私たちが欲しいものを「形にする」手助けはしてくれますが、「何を欲しいか」そのものを、私たちの代わりに考えてはくれません。それは、AIの能力の問題ではなく、役割の問題です。
例えば、あなたがレストランに行って、「何か美味しいものをください」と注文したとします。腕利きのシェフは、あなたの好みや気分を推し量り、いくつかの料理を提案してくれるかもしれません。しかし、最終的に「今日、私が本当に食べたいもの」を決めることができるのは、あなた自身しかいないのです。
AIとの関係もこれと同じです。私たちが「何を創りたいのか」「どんな答えが欲しいのか」「どんな未来を実現したいのか」。その「欲しいもの」の解像度をどこまでも高めていくことこそが、AIを使いこなす上で、最も創造的で、最も重要な人間の役割なのです。
この最も面白い部分を放棄して、「AIが何とかしてくれるだろう」と受け身になってしまうのは、自らの思考と創造の可能性を、自ら手放していることに他なりません。
「AIが生み出すもの」と「私が求める完璧なもの」の混同
AIに抵抗を感じてしまうもう1つの要因は、「AIが生み出す、無限の選択肢」と、「私が求める、たった1つの完璧な答え」とを、混同してしまうことにあります。
例えば、あなたが画像生成AIに「夕暮れの美しい海の絵を描いて」とお願いしたとします。AIは、瞬時に何枚もの美しい夕暮れの海の絵を生成してくれるでしょう。しかし、あなたはそれらの絵を見て、こう思うかもしれません。「悪くはないけど、私のイメージとはちょっと違う。空の色がもっと紫がかっているはずだし、波の形も、もっと穏やかな感じなんだ」。
このとき、多くの人は「AIは、私のイメージを完璧に再現してくれなかった」と、AIに対して不満を感じてしまいます。しかし、これは大きな勘違いです。AIは、あなたの頭の中にある「完璧な一枚の絵」を知る由もありません。AIができるのは、あくまで「夕暮れの美しい海」という言葉から連想される、無数の「可能性のバリエーション」を提示することだけです。
「正解」は、AIの中にはない。あなたの心の中にしかない
ここで、私たちは決定的な事実に気づきます。
それは、あなたが求める「正解」は、AIの中には存在しない、ということです。
AIが生み出すのは、あくまで「素材」や「ヒント」であり、選択肢の束です。その中から、「これこそが、私が求めていたものだ」という「正解」を選び取り、あるいは、それらを組み合わせて新しい「正解」をつくり上げていくのは、あなた自身の「感性」であり、「価値観」なのです。
つまり、AIとの対話のプロセスは、「AIに正解を教えてもらう」プロセスではありません。それは、AIが提示してくれる無数の選択肢を鏡として、自分自身の心の中にある「本当の正解」を発見していく旅なのです。
「この空の色は違うけど、この雲の形はイメージに近いな」
「この波の静けさは素晴らしい。これに、あの夕日の色を組み合わせたら、完璧かもしれない」
そうやって、AIとの対話を通じて、自分の「好き」や「こだわり」を再発見し、解像度を高めていく。その試行錯誤のプロセスそのものが、AI活用の醍醐味であり、創造性を育む源泉となります。
「全自動で何でもやってくれる」という勘違いを手放し、AIを「自分の内なる正解を発見するための、最高のパートナー」として迎え入れること。その意識の転換こそが、AIへの無用な抵抗感を乗り越え、あなたを真の「創造主」へと変えていくための、最も確かな一歩となるでしょう。
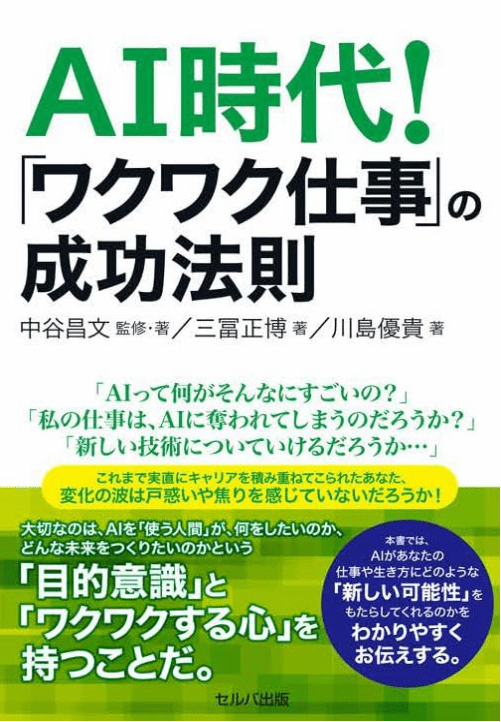
経営者や従業員のAI教育分野を中心に、AIを活用した学びとビジネス支援に取り組む。
子ども向けAI教育「ロジカルAIスクール(ロジスク)」を主宰し、小学生を含めた幅広い世代にAI時代を生き抜く力を育む活動を展開。
企業研修や講演も多数行い、実践的かつわかりやすい指導に定評がある。 最新のAI活用法をわかりやすく伝えることで、多くの人が「ワクワクする未来」を切り開くことを目指している。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
