本記事は、三冨 正博氏・中谷 昌文氏・川島 優貴氏の著書『AI時代!「ワクワク仕事」の成功法則』(セルバ出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

組織が陥る“やらされ感”とベテラン社員の疲弊
AI導入の失敗は、単にコストの無駄遣いや期待した効果が得られないといった経営的な問題にとどまりません。
より深刻なのは、それが組織全体の雰囲気や社員のモチベーションに与える負の影響です。「目的不在」のままトップダウンでAI導入が進められたり、「流行りだから」という理由だけで新しいツールが次々と現場に投入されたりすると、社員たちは「また何か新しいことをやらされるのか」「結局、自分たちの仕事はどうなるのだろう」といった「やらされ感」や「将来への不安」を募らせることになります。
特に、長年会社に貢献し、豊富な経験と知識を持つベテラン社員ほど、こうした状況に強いストレスや疎外感を覚えやすい傾向があります。彼らがこれまで培ってきたスキルや勘が軽視され、AIという「よくわからないもの」に振り回されているように感じてしまうと、仕事への意欲や誇りが失われ、組織全体の活力が削がれてしまうのです。
「上からの指示」だけでは、心は動かない
多くの日本企業では、依然としてトップダウン型の意思決定が主流です。経営層や一部の推進担当者が「AIを導入するぞ」と号令をかければ、現場の社員たちはそれに従わざるを得ません。
しかし、その導入目的やビジョンが十分に共有されず、ただ「AIを使え」という指示だけが現場に下りてきた場合、社員たちはどう感じるでしょうか。
おそらく、「なぜAIを使わなければならないのか」「AIを使うことで、自分の仕事はどうよくなるのか」「会社は私たちに何を期待しているのか」といった疑問や不信感が先に立つでしょう。
そして、その疑問が解消されないままでは、AIの活用は「やらされ仕事」の1つとして認識され、主体的な取り組みや創意工夫は生まれません。
人間は、意味を感じられないことや、自分自身の成長に繋がらないと感じることに対して、本気でエネルギーを注ぐことは難しい生き物です。
AIという強力なツールも、使う人間の「心」が動かなければ、その真価を発揮することはできません。
「上からの指示だから仕方なくやる」という姿勢では、AIは単なる監視ツールや、新たな業務負担としてのしかかってくるだけです。
ベテラン社員の「経験」が「抵抗勢力」に変わるとき
ベテラン社員は、組織にとってかけがえのない財産です。彼らが長年培ってきた経験、知識、人脈、そして何よりも「現場感覚」は、AIには決して代替できないものです。
しかし、AI導入の進め方次第では、この貴重な財産が、変化を阻む「抵抗勢力」と見なされてしまうことがあります。
例えば、AIが出してきた分析結果や提案に対して、ベテラン社員が自らの経験則から「それは現実的ではない」「現場の実情をわかっていない」と異議を唱えたとします。
これは、本来であればAIの提案をより実践的なものへと磨き上げるための貴重なフィードバックとなるはずです。
しかし、AI導入を急ぐあまり、「古い考えに固執している」「変化に対応できない」と一方的に決めつけられてしまうと、ベテラン社員は深く傷つき、心を閉ざしてしまうでしょう。
彼らは、決して変化を恐れているわけではありません。むしろ、これまでの経験から、新しいものが導入される際に現場で起こりうる混乱や、理想と現実のギャップを誰よりもよく理解しているのです。
その知見を尊重し、AI導入のプロセスに主体的に関わってもらうことこそが、AIと人間の協働を成功させるための鍵となります。
「AIに使われる」のではなく「AIを使いこなす」ための対話
では、組織の中で「やらされ感」を生まず、ベテラン社員を含むすべての社員がAIを前向きに受け入れ、活用していくためには、何が必要なのでしょうか。
その答えは、やはり「対話」にあると私は考えます。
まず、経営層や推進担当者は、AI導入の「目的」や「ビジョン」を、現場の社員1人ひとりに丁寧に説明し、共感を醸成する必要があります。
「AIによって、私たちの会社はこう変わりたい」「皆さんの仕事はこう豊かになる可能性がある」という未来像を共有することで、社員たちはAI導入を「自分事」として捉え、主体的に関わる意欲を持つことができます。
そして、AIの導入プロセスにおいては、現場の声を徹底的に吸い上げ、ベテラン社員の経験や知恵を最大限に尊重することが不可欠です。
「AIに何ができるか」だけでなく、「現場は何に困っているのか」「どんなサポートがあればAIを活用しやすいか」といった問いを重ね、AIと現場のニーズをすり合わせていく。そうした双方向のコミュニケーションを通じて初めて、AIは現場に受け入れられ、真に役立つツールへと進化していくのです。
AIは、決して私たちを「使われる側」に追いやるものではありません。むしろ、AIを「使いこなす」ことで、私たちはこれまで以上に創造的で、人間らしい働き方を実現できる可能性を秘めています。
そのためには、組織全体でAIに対する正しい理解を深め、オープンな対話を通じて、AIと人間が互いの強みを生かし合う「共創関係」を築いていくことが何よりも重要なのです。
「ワクワク」が組織を動かすエネルギー源
最終的に、組織におけるAI導入の成否を分けるのは、技術的な優劣や導入コストの多寡ではありません。
それは、社員1人ひとりが「AIを使って何か新しいことをやってみたい」「AIと共に成長したい」という「ワクワクする心」を持てるかどうかです。
「やらされ感」からは、決してイノベーションは生まれません。しかし、「ワクワク」からは、無限のアイデアと行動エネルギーが湧き出してきます。
AIという新しいテクノロジーに対して、社員たちが好奇心を持ち、主体的に関わり、試行錯誤を繰り返す中で新しい価値を生み出していく。そんな「ワクワクを軸としたAI活用」こそが、これからの時代に組織が持続的に成長していくための、最も確かな原動力となるのです。
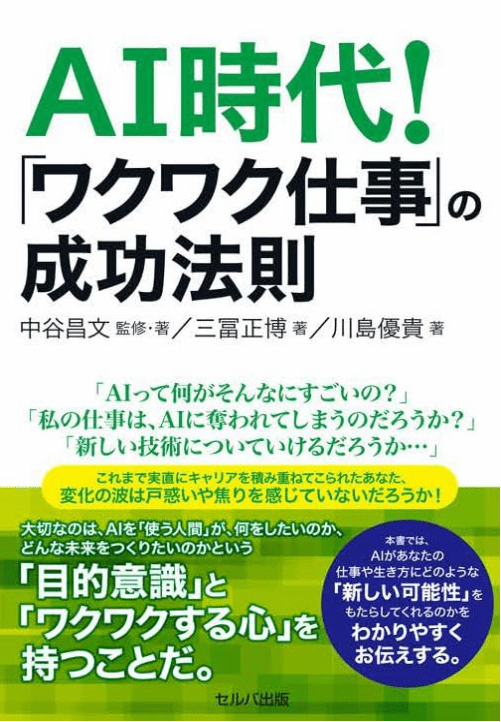
経営者や従業員のAI教育分野を中心に、AIを活用した学びとビジネス支援に取り組む。
子ども向けAI教育「ロジカルAIスクール(ロジスク)」を主宰し、小学生を含めた幅広い世代にAI時代を生き抜く力を育む活動を展開。
企業研修や講演も多数行い、実践的かつわかりやすい指導に定評がある。 最新のAI活用法をわかりやすく伝えることで、多くの人が「ワクワクする未来」を切り開くことを目指している。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
