本記事は、岡本 康平氏の著書『“また会いたい”と99%思われる 『人たらし』のコツ100』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

信頼されている第三者を使って心を動かす
説得しても相手がなかなか応じてくれない場合は、方向を変えてアプローチすると効果的です。それは自分ではない、第三者から伝えてもらうという作戦です。
第三者から本人に伝えることで、当事者間の対立していたストレスが軽減され、聞く耳を持ちやすくなります。相手も構えずに聞けるので新しい視点に気づいたり、力強い後押しになったりします。ウィーン大学のヘルムト・レダーは当事者でない人間が交渉を調整する際、その人の信頼度を上げることで成功率が上がると説明しています。
新しい視点が力強い後押しを加えてくれる
そのときの第三者は、相手が信頼している人物であったり、相手と自分のどちらにも偏りがなく、公平な立場で判断してくれる人物がいいでしょう。
たとえば、部下が上司から任されたポジションを拒否している場合、別の社員に後押しの言葉をかけてもらいます。「〇〇さんから聞いたけど、引き受けるのを拒んでるんだって? 〇〇さんはキミを買ってるからこそ、そのポジションを任せたいと思ってるんだよ。必ず次のステージにつながるから引き受けてみたらどう?」というように伝えてもらうといいでしょう。
当事者同士では伝え切れない意図や真意にも気づきやすくなるため、意外とすんなり受け入れてくれる可能性があります。
やってほしいことは二者択一の質問で選ばせる
問いかけられたら、ついつい考えて答えてしまうのが、人間の心理。「いかがですか?」と漠然と言われるよりも、「どちらのほうがいいですか?」と二者択一で言われると、その気もないのにどちらか一方を選びたくなってしまうものです。
その心理を応用して、商品を売りたいときは、AとBの違いを説明しながら差し出し、「どちらのほうがお好みですか?」と聞いていきます。「どちらかと言えば、Aかな」などと答えてくれたら、こっちのもの。自然と購入する方向へと相手の思考が進んでいきます。
シカゴ大学のユーリ・グニージーは二者択一を迫られたときに、その2つ以外の選択肢を考慮しないことを証明しています。つまり、この場合「断る」ということがなくなるわけです。
“選びたくなる”心理で思わずOKしてしまう
プライベートで家族にお願いするときは、「ちょっと手伝ってほしいんだけど、洗濯干すのと、たたむのとどっちがいい?」と不意打ちのごとく、問いかけます。すると、思わず「たたむほうがいい」と言ってしまうかもしれません。
ここで大事なのは、「相手の意思で選んでもらう」こと。相手が悩んだときに「もし私なら、Aのほうを選びますかね」などとこちらの意思で誘導してしまうと、「選ばされた!」と感じ、不満が出てくる可能性があるのでご注意を。
拒否されても「だからこそ」と肯定する
説得しようとしても、相手が難色を示すときもあるでしょう。もし、相手が否定的な言葉や不安なことを漏らしたときに、その言葉を捉えて、「だからこそ、いい!」と肯定すると相手は驚き、一歩踏み出すきっかけを作ることができます。
カリフォルニア大学のカレン・ゴンサルコラレは拒否されることによる心理的な影響について研究しており、負の影響をどう解消できるかという成果を発表しています。
肯定して「一歩踏み出すきっかけ」を作ってあげる
たとえば「未経験だから自信がありません」→「だからこそ、経験者にはない斬新な意見がもらえるかと思っているんです」や、「複数の仕事を同時進行で抱えていて、とても引き受けられません」→「だからこそ、そんな有能なあなたに頼みたいのです」と相手の能力を褒めてあげる。
「少し値段が高いですね」→「この価格だからこそ、品質にはこだわり抜いています。短期間での故障の心配もなく、長期的に見たらこちらのほうがお得です」というように、相手の言葉を逆手にとって、プラスに変えます。相手は、断ろうと思ったら、意外にもそれを受け入れてくれるので、一瞬、肩透かしを食らったような気持ちになりますが、「それでもいいんだったら……」と考えを変えてくれるかもしれません。
「あなただからこそ、いい!」という限定的な褒め方も、功を奏す場合が多いです。特に、自信がなさそうな相手にはその一言が効くでしょう。
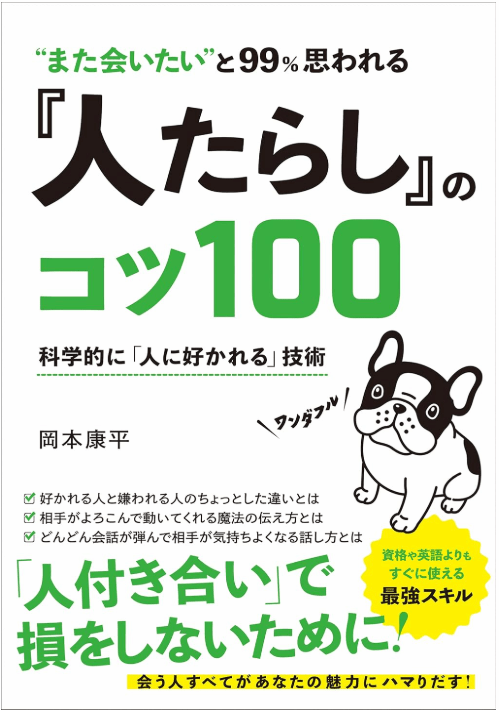
両親が営む会社で働き始めるも業績の悪化により倒産、多額の借金を背負う。
転職活動で悩んだことをきっかけに、コミュニケーションや心理学を研究。
その後、不動産会社の営業として再就職を果たし、7年で借金を返済。
現在は、コンサルタントとして企業の人材育成や社内コミュニケーションの活性化支援をライフワークとしている。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
