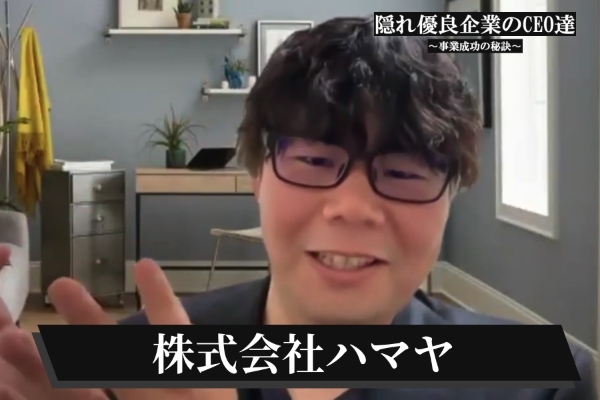
京都で50年以上の歴史を持つ手芸用品の老舗卸問屋、株式会社ハマヤの代表取締役CTO・若井信一郎氏。平均年齢60代、手書き伝票が当たり前という超アナログ企業を、わずか数年でDXの旗手へと変ぼうさせた若き経営者だ。9割の社員が反対する中、若井氏は社員たちにどう寄り添い、いかにして改革を成し遂げたのか。そして今、彼が見据える次なる挑戦とは。
目次
50年の歴史を持つ老舗問屋に訪れたDXの波
── 卸業を創業されてから50年以上の歴史がおありとか。
若井 以前は手芸の需要が高く、事業も大きく伸びていたものの、近年は手芸をする人が減り、業界全体がゆるやかに減っています。このままではいけない、何か改革を起こさなければならないという危機感が常にありました。
── そうした中で社内改革、特にDX化を進めたのですね。
若井 改革の必要性は感じていたものの、2018年にDX化を始める前は、弊社は非常にアナログな業務体制でした。長年手芸材料一筋でやってきたこともあり、ITに詳しい人間が社内にほとんどいなかったんです。
平均年齢が60代で、中には80代の方も活躍する職場で、ITという言葉自体に抵抗がある人がほとんどでした。受注伝票は手書きの5枚複写伝票で、管理はすべて紙と頭の中。お客様とのやり取りも電話やFAXが中心でした。
「9割がDX化に反対→7割がIT人材」になった理由
── DX化を進めようとした際、社員の反応はいかがでしたか?
若井 「やりたくない」「ITなんて嫌いだ」という猛烈な反対が9割でした。予算もゼロに近く、セキュリティやクラウドに対する不安も根強く、当時の社員にとっては未知の世界だったため、反対されるのは当然だったと思います。
── 9割の反対をどのように乗り越えていったのでしょうか?
若井 わずか5%ほどいた「ちょっと触ってみてもいいかな」という社員に声をかけ、ダブルクリックやドラッグ&ドロップから丁寧に教え始めました。
すると、彼らは元々手芸分野で探究心と熱心さを持っていたため、IT分野でも驚くほど早く上達していったんです。
最初はGoogleスプレッドシートの軽いマクロから始めましたが、最終的にはプログラミング言語をマスターし、自分で業務効率化のためのアプリを開発するようになりました。
その時感じたのは、社員たちはただ「ITに触れる機会がなかった」ということ。長年培ってきた「勉強熱心さ」や「上達の早さ」が、ITという新分野に変わっただけでした。この社員が開発したアプリが社内で共有され、「ITって簡単で便利なんだ」と発信してくれたことで、DX化の波が社内に伝播していきました。
最終的には100以上のアプリが開発され、年間で5,760時間もの業務改善につながり、社内のIT人材は7割にまで増えました。
卸問屋とITコンサルティングの二刀流経営
── その結果、どのような変化があったのでしょうか。
若井 DX推進で業務が大幅に効率化され、空き時間が生まれたので、その時間を活用して、新たな価値創造に取り組み始めました。
一つは、手芸用品の卸業におけるビジネスモデルの変革です。手書き伝票から脱却し、10万種類以上ある商品の在庫や顧客情報をすべてデータ化。詳細なデータ分析が可能になり、効率的なマーケティング施策を実行することで、9%ほどだった粗利率が大幅に向上しました。
もう一つは、DX化の成功事例の外部発信です。ノウハウを社外向けの講演やITコンサルティングで提供し始めたところ、老舗企業などから相談が殺到しました。このニーズにこたえる形で、ITコンサルティングを新事業として立ち上げました。
現在、弊社の事業の柱は2つで、手芸用品の卸業と、ITコンサルティング事業です。売上高では卸業が大きいですが、利益率の高いITコンサルティング事業が急速に成長しており、利益ベースでは同等の規模にまで近づいています。
弊社の最大の強みは、「老舗企業がDXに成功した」という実績そのものにあります。予算もノウハウもゼロの状態から9割の反対を乗り越えて改革した事実は、他社にはない圧倒的な説得力です。
DX化推進で乗り越えた「四つの壁」
── DX化推進でどんな壁にぶつかり、どう乗り越えられたのでしょうか。
若井 当時、私たちは四つの壁に直面しました。
一つ目は「時間の壁」です。
当時、社員たちは日々の業務で手いっぱいで、新しいことに時間を割く余裕がありませんでした。私たちはまず、より大きなインパクトのある業務から優先的に改善することにしました。例えば、業務プロセス全体を洗い出し、工数や売上、利益に直結する部分を特定し、そこから効率化を図る。これによって早期に業務時間が削減でき、社員も「DXをやれば、こんなに楽になるんだ」と実感したことで、協力的な姿勢に変わっていきました。
二つ目は「予算の壁」です。
予算をかけられなかったので、Googleワークスペースのような無料ツールを最大限に活用しました。手作業で行っていた業務の自動化を試みました。これは、結果的に初期のハードルを下げる上で非常に重要でした。
三つ目は「スピードの壁」です。
DX化は「生もの」だと考えています。ゆっくりと進めすぎると社員が飽きてしまい、関心を失ってしまいます。私たちはインパクトだけでなく、スピードも重視しました。短期間で成果を出し、その成果を社内で共有することで、モチベーションを維持することができました。
四つ目は「否定と反対の壁」です。
これは最大の壁でした。新しいことへの不安や抵抗から、多くの社員が否定的な意見を口にしました。この壁を乗り越えるために重視したのは「未来を見せること」。一人ひとりの社員やチーム単位で、「この業務を改善することで、どんな未来が待っているのか」を具体的に説明しました。「残業時間が減るよ」「いつも嫌がっていた定型業務から解放されるよ」といった、社員たちが直接メリットを感じられる言葉で語りかけました。
もちろん、全員が納得したわけではありません。中には、改革のスピードについていけず、会社を去っていく人もいました。しかし、私たちは諦めずに説明を続け、まずは改革に興味を持ってくれた人たちから順番に協力を仰ぎました。この地道な努力が、最終的に社内全体の文化を変えることにつながったのだと思います。
「老舗企業の事業承継」という社会課題への挑戦
── 今後はどのような事業展開や投資領域を考えていますか?
若井 「京都ファンド」の組成を本格的に進めていきたいですね。京都には弊社のように何十年、何百年と続く老舗企業が多いのですが、事業承継が大きな課題です。「昔ながらの古いビジネス」というイメージからか、家業を継ぎたがらないケースが非常に多いのです。
弊社のDX化の成功事例は、老舗企業が持つ伝統やブランドを活かしつつ、若者が「継ぎたい」と思えるような新しい企業体へと変革できることを証明しました。私たちはこのノウハウと実績を活かし、京都の老舗企業に特化したファンドを組成することで、事業承継を支援したいと考えています。
具体的には、M&Aによって企業を買収するのではなく、私たちが培ってきたDX化のノウハウを提供し、次世代が「継ぎたい」と思えるような企業に生まれ変わらせるというモデルを考えています。その上で、弊社のIT人材教育の仕組みも提供していきたいですね。
── IT人材教育の仕組みとは、具体的にどのようなものでしょうか。
若井 IT未経験の社員をIT人材に育成するノウハウを体系化してきました。今ではAIや機械学習の導入も進めており、最新の知識と技術を兼ね備えた人材を育成する仕組みができています。しかも、この仕組みは属人化しておらず、誰でも質の高い教育を提供できるように構築しています。
私たちは、この教育ノウハウを事業承継を検討している企業に提供することで、社員をDX人材へと変革させ、組織全体を活性化させていきたい。社員が自らアプリを開発したり、AIを活用したりすることで、企業はより強い組織体となり、後継者にとっても魅力的な企業へと生まれ変わるはずです。
京都ならではの「ものづくりの文化」や「伝統」に、最新のIT技術を掛け合わせることで、日本の伝統産業全体にイノベーションを起こしていきたいですね。この京都ファンドは近年中のファーストクローズを目指しています。
「隠れ優良企業」が「時代を動かす優良企業」へと成長するためには、これまでの歴史や伝統に甘んじることなく、常に新しい価値を創造し続けることが不可欠です。もし弊社のビジョンに共感し、一緒に挑戦していただける方がいれば、SNSなどを通じて気軽に連絡していただきたいですね。
- 氏名
- 若井 信一郎(わかい しんいちろう)
- 社名
- 株式会社ハマヤ
- 役職
- 代表取締役CTO

