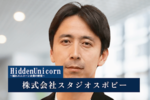スマートフォンから得られる膨大な位置情報ビッグデータをAIで解析し、人流を可視化するプラットフォームを提供するクロスロケーションズ。デジタルガレージやGoogle Japanで要職を務めた小尾 一介氏が率いる同社は、コロナ禍の困難を乗り越え、小売、外食、観光、金融、行政など多岐にわたる業界でデータ活用を推進している。生成AIとの融合による新たな価値創造と、グローバル展開を見据えた「プラットフォームフォーマー」としての野望に迫った。
位置情報ビジネスへの着想、コロナ禍で「人流」が共通言語に
── 現在の位置情報ビジネスに至るまでの経緯と、着想の原点を教えてください。
小尾氏(以下、敬称略) 私のキャリアはインターネット以前から始まっています。インターネット以降の話をしますと、デジタルガレージで取締役として事業育成を担当していました。当時はインターネットインキュベーターのような事業で、カカクコムやTwitterを日本に導入するなど、いくつかの会社を上場させました。
その後、Googleからスカウトを受け、2009年から数年間在籍し、技術面や広告ビジネスにおける提携関係をすべて担当していました。広告ビジネスではドコモさんやソニーさんといった大企業との事業提携も手掛けました。
当時はまさにスマートフォンが立ち上がる時期で、2008年にiPhone、2009年にAndroidが登場しました。検索の責任者も務めており、Android端末を製造するメーカーや販売するキャリアとの連携も重要な仕事でした。2010年頃には、Googleの検索エンジンは圧倒的な地位を確立し、ヤフージャパンでさえも我々のエンジンを使うようになるなど、大きな変化の渦中にいました。
そのとき強く感じたのが、スマートフォンがもたらす最大の変化は「位置情報」が取得できることだという点です。
PCは家や会社で使うものですが、スマートフォンは常に持ち歩く。その端末がどこにあるかという位置情報は、非常に大きな価値を持つと考えました。日本ではガラケー時代からありましたが、“位置ゲー”と呼ばれるような限定的な使われ方でした。
しかし、スマートフォンでは移動経路などの詳細な情報を活用し、アプリ会社がユーザーに便利なサービスを提供できる。これは決定的な違いです。今では当たり前のGoogleマップや、近くのお店を知らせてくれるアプリなど、位置情報は便利な機能を支える重要なインフラであり、巨大なビジネス資源なのです。この着想が、クロスロケーションズの設立につながりました。
── 当初はどのような事業から始めたのでしょうか。
小尾 創業当初は、位置情報を使った広告配信サービスが中心でした。たとえば、先週末にキャンプ場にいたお父さんのスマートフォンを特定し、その人にキャンプ用品の広告を表示するといったものです。
広告主にとっては、購入確度の高いユーザーにアプローチできるメリットがあります。この事業は、シンガポールに本社を置くニアインテリジェンスというグローバル企業と提携して展開していました。
しかし、私は広告ビジネスだけにとどまるつもりはありませんでした。ユーザーが意識しない裏側で、アプリ会社には膨大な位置情報データが集まっています。このデータを集めて分析すれば、世の中の人がどこにいて、どこから来ているのかが手に取るように分かる。これは非常に面白いと考え、2018年から人の動きを分析・可視化するシステムの自社開発を始めました。
これは巨大なデータとの戦いです。日本国内だけでも約9,000万台の端末から得られる移動位置データを扱っており、その総量は1兆件を優に超えます。この膨大なデータをAI技術の一分野である機械学習を用いて数理処理し、分析するエンジンを構築したのです。
── 分析システムが完成したのが2020年とのことですが、その直後にコロナ禍に見舞われました。事業にどのような影響を与えましたか?
小尾 まさにシステムが完成した途端、コロナ禍が始まりました。我々のサービスは人の動きを可視化するものですが、その「人」がいなくなってしまった。顧客である店舗や公共団体は営業停止や活動自粛を余儀なくされ、弊社のサービスを必要とする状況ではありませんでした。事業としては、まさに“冬眠状態”に陥りました。
しかし皮肉なことに、社会では「人流」という言葉が流行語大賞になるほど注目を集めました。「人流を抑えろ」「気のゆるみだ」といった言葉が飛び交う中で、その実態をデータで客観的に示すことが求められたのです。
そこでニュース番組にデータを提供しました。たとえば、コロナ禍が明けた頃、2019年を100とした場合、栃木の日光東照宮の人出は緊急事態宣言下で3%まで落ち込み、その後71%まで回復したといった、具体的な数値を初めて示しました。
当時はまだベンチャー企業でしたが、様々なメディアに取り上げられ、「人流」という言葉と共に我々の技術の価値が社会的に認知されるきっかけとなりました。この3〜4年間の暗黒時代は苦しかったですが、結果的に我々の市場を大きく拡大させる要因になったのです。
進む人流データの活用、生成AIとの融合による進化
──コロナ禍を経て、人流データ市場は大きく変化したのですね。現在の事業内容と、具体的な活用事例を教えてください。
小尾 コロナ禍が明けた2023年頃から、お問い合わせが急増しました。ある調査レポートでは、人流データ市場は2023年度で約324億円、そこから毎年10%以上の成長が見込まれているそうです。数年後には1000億円規模になる可能性も指摘されており、我々はその中心にいると自負しています。
事業の核は、自社開発した分析エンジン「Location Engine」です。これをベースに、企業様には月額サブスクリプション型のクラウドサービス「Location AI Platform」をご提供しています。これは、お客様自身がウェブブラウザ上で様々な人流分析を行えるツールです。
データの仕組みを簡単に説明しますと、我々は複数のアプリ会社などから、匿名化された位置情報データを仕入れています。データの中身は「端末のID」「緯度経度」「時間」の3要素で、個人情報は一切含まれていません。このデータをエンジンで解析し、「このお店には、どのエリアから多くの人が来ているか」「時間帯による変化はどうか」といったことを可視化します。
── インバウンド客の分析もできるそうですね。
小尾 その通りです。我々は世界のデータを集めている会社からもデータを仕入れています。これにより、日本を訪れている外国人観光客を分析できます。
たとえば、ある端末のIDが「先週はパリの緯度経度を発信していた」と分かれば、その持ち主はフランスから来たと推測できます。これによって、「今、京都に集まっている訪日客はフランス人が多い」とか「韓国人が多い」といったことが分かり、その人たちの端末に母国語で広告を配信することもできます。
── 多様な活用法がありそうですが、特に導入が進んでいる業界はどこでしょうか。
小尾 最も典型的なのは多店舗展開されている小売・外食産業などです。
新規出店の際、これまでは土地勘や経験に頼ることが多かったのですが、我々のツールを使えば「この場所は昼間は主婦層が多く、夜はビジネスマンが多い」「商圏は半径何kmで、何丁目からの来店が中心」といったことがデータで裏付けられます。出店の成否は事業に大きな影響を与えますから、その精度を高めるために活用されています。
次に、商品を店舗で販売しているメーカーです。たとえばビール会社が、営業先の居酒屋の客層を事前に把握できれば、「このお店は若者向けだから、ビールよりもこの新製品のサワーを提案しよう」といった、より的確な営業活動が可能になります。
そして、これらの小売・外食、メーカーといった領域に加え、金融業界での活用も進んでいます。これらは「オルタナティブデータ」と呼ばれる分野で、投資判断に新たな視点をもたらし、アメリカのヘッジファンドなどでは非常に盛んです。
また、不動産投資信託(REIT)では物件価値の評価に貢献するなど、多岐にわたる業界でデータ活用を推進しています。
たとえば、自動車工場の周辺の人流や物流トラックの動きを分析し、「この工場は計画通りに生産が進んでいないかもしれない。業績に影響が出る前に株を売ろう」といった投資判断に使うのです。不動産投資信託(REIT)では、投資対象の商業施設やホテルの周辺人流がその物件の価値を測る重要な指標になるため、大手REITのお客様にもご利用いただいています。
その他、行政の都市計画策定支援や、全国各地の観光事業者・観光協会による観光地の現状分析や市場調査など、非常に幅広い分野で活用が始まっています。
── 技術の会社として、今後プロダクトはどのように進化させていくのでしょうか。
小尾 我々は、単に分析を請け負う会社ではなく、企業が自らデータを活用できる「道具」を提供するプラットフォームフォーマーを目指しています。その進化のカギとなるのが「生成AI」の導入です。
これまでの分析ツールは、可視化されたデータを見て、それが何を意味するのかを人間が解釈する必要がありました。専門家でなければハードルが高い面があったことは否めません。
そこで今年から、我々のプラットフォームにChatGPTのような生成AIを実装しました。契約企業様は、分析画面に出てきた人流データをChatGPTに読み込ませ、「このデータが示唆することは何か」を文章で自動的に解説させられます。
さらに進化は続きます。将来的には、分析ツールを操作する必要さえ、なくしてしまいます。ユーザーが「渋谷のこの土地にドン・キホーテの隣に出店しようと思うんだけど、勝算はある?」とAIに自然言語で問いかけると、AIが自動的にツールを操作して分析し、「このエリアの特性を考えると、成功確率は高いでしょう。理由は……」と答えてくれる。いわば「AIエージェント」のような機能です。
もう一つの進化の柱は「統合データ分析」です。これまでは我々が蓄積・更新している位置情報ビッグデータをつかって出力した人流データの世界で分析が完結していましたが、企業が独自に持つ会員データや売り上げデータなどを我々のプラットフォームに取り込み、人流データと掛け合わせて分析できるようにしました。これにより、「このエリアは来店客が多いのに、自社のアプリ会員は少ない」といった、これまで見えなかった課題を発見できるようになります。
経営者としての譲れないこだわり、少数精鋭の組織力と今後の課題
── 顧客開拓はどのようにされたのですか。
小尾 創業当初は、私自身もトップ営業として、多店舗展開されている小売・外食企業に直接ご提案にうかがいました。新しいサービスなので、お客様が本当に何に困っているのかを直接聞かなければ、役に立つものは作れないからです。
事業がある程度軌道に乗った現在は、直接営業に加えて、大手企業をはじめとする有力なパートナー企業による代理店販売、そしてオンラインでの情報発信を通じたお問い合わせ、という3本柱で顧客拡大を進めています。最近は「人流データ」への関心自体が高まっており、お問い合わせいただくケースが非常に増えました。
── 経営者として譲れないこと・哲学を教えてください。
小尾 「スケールするビジネスモデル」であることです。私はキャリアを通じて、ウェブサイト制作や営業代行のような、人の労働力に依存する受託型ビジネスでは企業の成長に限界があることを見てきました。人を増やさなければ売り上げが伸びず、利益率も上がりにくい。
私が目指すのは、GoogleやAmazon、Metaのようなビジネスです。彼らは人間が一人ひとり営業しているわけではありません。優れたシステムを構築し、そのプラットフォームが自動的にお客様を惹きつけ、収益を生み出していく。プラットフォーム型のビジネスモデルをとっている企業はそれが価値を認められて拡大し始めるまでは多額の投資が必要で、赤字が続く苦しい時期があります。
しかし、一度黒字化すれば、あとは継続的に収益が積み上がっていく。我々も、テクノロジーの力でこのモデルを確立することに徹底的にこだわっています。
── 組織としての強みと今後の課題は何だと分析していますか?
小尾 強みは3つあると考えています。
一つ目は、トップクラスの能力を持つ多国籍の開発チームです。日本人だけでなくアフリカ出身の若者もいますが、彼らの開発力とスピードがこの会社の価値の源泉です。二つ目は、様々な業界経験を持つ経験豊富なビジネスチーム。そして三つ目は、私やCOOがGoogleやSalesforceといったグローバル企業出身であり、グローバルな知見とネットワークを持っていることです。
一方で課題は、まさに「成長の痛み」です。事業が急拡大する中で、お客様への対応などでどうしても人手が必要になるフェーズに入ってきました。
しかし、安易に人を増やすのではなく、いかにシステム化・自動化を進め、人手をかけずに顧客満足度を高めていくか。この領域においても既に生成AIを導入して人手によらないオペレーション体制を構築しています。
- 氏名
- 小尾 一介(おび かずすけ)
- 社名
- クロスロケーションズ株式会社
- 役職
- 代表取締役