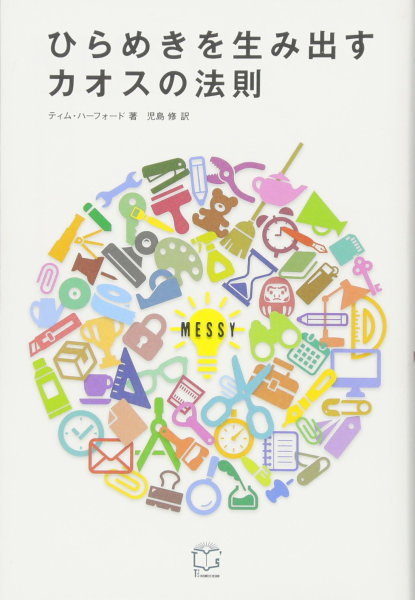(本記事は、ティム・ハーフォード氏の著書『ひらめきを生み出すカオスの法則』TAC出版、2017年12月18日刊の中から一部を抜粋・編集しています)
スティーブ・ジョブズが夢見た究極のオフィス
スティーブ・ジョブズはシンプルさや近代的な直線美を愛し、大衆に好まれる製品をつくる才能に恵まれていた。
ジョブスは30年以上にわたり、一流デザイナーに厳しい要求をし、コンピューターやスマートフォン、タブレットなどの他に類を見ないほど美しい工業製品を次々とつくり出した。
『トイ・ストーリー』などの映画を制作したアニメーションスタジオ、ピクサー社の大株主だったジョブズは、同社のビルも設計している。
ジョブズは健康で仕事も順調だった時代、ピクサーの本社ビルの設計に並々ならぬ意欲を燃やした。
ジョブズの死後に「スティーブ・ジョブズ・ビルディング」と命名されたこのビルの設計には、アップルショップの設計者でもある建築家のピーター・ボーリンもかかわっていた。
一流のデザイナーがそうであるように、ジョブズはデザインだけはなく機能にも気を配った。
「スティーブは優れた建築が社風をよくすると確信していて、このビルが社員のコラボレーションを促すことを望んでいた」
ピクサーの社長エドウィン・キャットマルは言う。
偶然の出会いがもたらす力に魅了されていたジョブズは、社員同士が本社ビル内で偶然に顔を合わせやすくするために、トイレをメインロビー付近の一カ所のみに設置するという妙案を思いついた。
生理的欲求を満たすためには誰もがロビーに向かわなければならなくなるので、そこで見知らぬ社員と出会ったり、しばらく顔を見ていなかった社員と会ったりしやすくなるはずだ、と。
しかし、これらのケースは、ごく単純かつ重要なポイントを見逃している。それは、「その空間を、働く人にとって快適かつ楽しいものにすること」だ。実は、「創造性や生産性をいかに高めるか」という現代のビジネスにつきまとう課題は、洗練されたオフィスや意匠を凝らしたインテリアでは解決できない。
それは、建物の外観の美しさや社内の整然さとはほとんど関係がないのだ。
なにより重要なのは、“好きなように空間を使えること”
オフィスに遊具を設置したり奇抜な装飾を施したりすることは、特に、クリエイティブな業界では流行している。
企業の本社としてこの10年間でメディアに最大の注目を浴びたのは、カリフォルニア州マウンテンビューにあるグーグルの「グーグルプレックス」だろう。
雑誌やテレビは、卓球台や滑り台のあるこのオフィスを、従来型の職場の概念を変える革新的なものだとして頻繁に紹介してきた。
しかし、勘違いをしてはいけない。遊び心に満ちたグーグルプレックスが建設されたのは、グーグルが大成功を収めたあとだった。
グーグルのオフィスの歴史をたどってみれば、それは派手さよりも、地味さに似ていることがよくわかる。
創業者のセルゲイ・ブリンとラリー・ペイジがグーグルを立ち上げ、ビジネスの核となる革新的なコンセプトを構想していた2年間、オフィスはなかった。2人はまだスタンフォード大学の学生だった。
1998年9月、グーグルはベンチャー企業が最初のオフィスとして選ぶ定番の場所に移動した。そう、ガレージだ。
さらに、ブリン、ペイジ、エンジニア2人は、メンロパークのサンタマルガリータストリートにある民家を借り、この部屋を作業場にし、ガレージをサーバーの置き場にした。
デスク机は、2つの木挽台の上にドア板を横に置いただけという、これ以上ないほど簡素なものだった。ブリンたちはオフィスにあるものを自由に組み合わせ、改造し、快適な作業環境をつくった。
ある日、この家の所有者のスーザン・ウォジスキが帰宅すると、ウォジスキ家が注文していた冷蔵庫をグーグルの社員たちが勝手に受け取り、自分たちのオフィスに置いて飲み物や軽食を詰め込んでいた。
グーグル黎明期の“なんでもあり”の精神を物語るエピソードだ。ウォジスキは気にしなかった。彼女はグーグルに入社し、後にユーチューブのCEOになっている。
1999年の春、グーグルは再び引っ越しをした。
場所は、自転車店が店を構えるビルの上階だった。ここでも横に置いたドア板を机にし、オフィスには卓球台も持ち込んだ。
赤や青のバランスボールも転がっていたが、それは見た目を華やかにするというよりも、単に運動をしたいからだった。
グーグルはほどなくしてマウンテンビューにあるオフィスパーク施設に移転した。このオフィススペースはグーグルプレックスの前身となるもので、後にヌルプレックスと呼ばれるようになった。
ただし、オフィスはまだ雑然としていた。このオフィスのことを、施設管理者のジョージ・サラは“ごちゃ混ぜ”、グーグルの非公式の歴史家であるジャーナリストのスティーブン・レヴィは“雑種風”と表現している。
新オフィスでまず取り組むべき重要なプロジェクトだったのは、グーグルのサイトでの検索結果に最新ニュースを敏感に反映させることだった。
このプロジェクト専用の作業室がつくられたが、それは5、6人のエンジニアが会議室を占拠し、コンピューターを好みの位置に配置しただけという簡易なものだった。
あるとき、サラが社内を歩いていると、あるオフィスの壁がなくなっていた。このオフィスを使っていたエンジニアが、壁が気に入らないという理由で取り外してしまったのだ。
サラはなにも言わなかった。しばらくしてそのエンジニアの気が変わり、壁を元に戻した。そのときもサラは腹を立てなかった。
むしろ、グーグルらしいと考えていた。
マサチューセッツ工科大学(MIT)のビルディング20(※若手建築家のドン・ウィストンがMITから依頼され一日で設計、短期間で建設。1998年に解体され、一番創造的な空間にふさわしい建物とされる)で長いあいだ働いていた研究者なら、このように試行錯誤しながら職場にあれこれと手を加えていくことの価値を高く評価するだろう。
2001年にグーグルの会長に就任したエリック・シュミットも、「今までのやり方を変えないようにしてほしい。学生寮のような雰囲気を保つように」とサラに念を押した。
“デスク周りをきれいにさせたい”という誘惑にあらがう
オフィス環境については、「“会社が望む通りの見た目の場所”でなければならない」という方針とグーグルのオフィスのように「見た目がどのようなものであるかは関係ない」という方針のまったく異なる管理の方法がある。
人はスペースを自分の好きなように使えるときに、最高のパフォーマンスを発揮する。
しかし、オフィスを厳しく管理することが従業員の生産性を落としてしまうのなら、なぜ会社はこれほど熱心に職場を美しく保とうとするのだろう?
放任主義は、なぜ創造性を高めるのだろう?
その答えを解く手がかりを得るために、ロバート・プロプストの偉大なキャリアに目を向けてみよう。
彫刻家、画家、教師であり、垂直型の木材収穫機や機械読み取り式の家畜識別タグなどの発明者でもあったプロプストは、第二次世界大戦で化学エンジニアとして南太平洋の上陸拠点での後方支援を担当したのち、1958年にオフィス家具メーカーのハーマン・ミラー社に就職した。
ハーマン・ミラーの幹部は、プロプストに天才的な能力があることに気づいた。
プロプストは独立心が強く、ミシガン州ゼーランドにある本社から200キロメートル離れたアンアーバーの自宅で仕事をすることが多かった。その後、会社を説得してアンアーバーに研究部門を設立させ、そこで働くようになった。
プロプストは同社で発明をつづけ、新製品「アクションオフィスⅡ」を開発してオフィス家具業界にその名を轟かせた。
1968年に発売されたこの製品はモジュール式になっていて、オフィスワーカーのニーズに合わせてデスクや仕切りのレイアウトを柔軟に変えられるという画期的なシステムだった。
従業員は子どもがレゴで遊ぶように、好みのオフィス環境をつくることができた。
プロプストは、平等主義的な理想を抱いていた。
上司が祭壇のような場所に陣取り、残りの社員は奴隷のように狭苦しく抑圧された場所で働くといった構図を改善したいと願っていた。
誰もがその場の責任者として権限をもって行動できる、自律的な職場を実現させたかったのだ。
しかし、オフィスの管理者たちは、このシステムに変更を加えた。
120度まで広げて文書をピン止めするスペースを確保していたアクションオフィスⅡの仕切りの角度を90度に制限し、システム同士をぴったりと隣り合わせに並べられるようにしたのだ。
この仕切りを壁ではなくオフィス家具と見なすことができるのも税制上で有利だったため、企業にとっては都合がよかった。こうして、現在の企業で広く普及している、フロアを四角い仕切りで区切った「キュービクル」が誕生した。
プロプストは、働く人たちに権限を与えたかった。
そして、柔軟に職場をレイアウトできるオフィス家具によって、それを支援できると信じていた。だが企業が関心を持っていたのは、費用削減だった。
その結果、プロプストはキュービクルの生みの親として「地獄の穴」「鶏卵箱」「味気ないネズミ穴」といった非難の言葉を浴びることになった。
プロプストが2000年に亡くなったとき、キュービクルは企業のオフィスに深く浸透していた。「労働者に自由を実現する権限を与える」というプロプストの夢はある意味で実現された。
だが、企業が従業員の自由ではなく、節税効果や経費削減のためにキュービクルの採用を推進したことも事実だ。
プロプストはまた、企業は整然としたオフィスは価値があると信じていることも、キュービクルが普及した要因だと考えていた。
プロプストは1968年にこう書いている。「人間が交流しやすい有機的な空間は、厳密な秩序のある空間と矛盾する。それが問題だ」
現在のところ、ビジネスの世界で優勢なのは、厳密に管理されたオフィスの方だ。私たちは一種のフェティシズムと呼べるほどのレベルで整然さを好んでいる。
乱雑さや不規則性は、生産性にとっての敵だと見なされている。実際には、これらは価値をもたらしているにもかかわらず、だ。
前提になっているのは、オフィスが雑然としているのは悪く、整然としているのはよいという考えだ。
整然とした環境が本当に効果的だという証拠はあるのだろうか?
サイコロジー・トゥデイの編集者を務めるベテランジャーナリストのT・ジョージ・ハリスは、“よいデザイン”が従業員の生産性に与える影響についての信頼できる研究を追い求めるうち、問題の立て方が間違っていることに気づいた。
鍵を握っていたのは、“よいデザイン”ではなかった。人々が好んでいたのは、生活や仕事の場を好きなように使える権限を与えられることだった。
フロアの端にある管理職の席から全体を見渡すと、乱雑なデスクは目障りだろう。散らかり具合は一目瞭然だ。だが忘れてはいけないのは、社員の生産性を上げる“権限を与えられているという感覚”は目には見えないということだ。
つまり、管理職が心がけるべき教訓は単純だ―そう、それはデスク周りをきれいにさせたいという誘惑にあらがうことだ。
部下のデスクが散らかっていても放っておくこと。小言を言わないこと。整然としているか、散らかっているかは問題ではない。
生産性を上げるためになにより大切なのは、社員が好きなようにデスク周りを使えることなのだ。
自律性が職場を活気づける
スティーブ・ジョブズが重要なアイデアを思いついたとき、説得してそれを止めさせるのは至難の業だった。
そして、社員同士の偶然の出会いを促すために、ピクサーの本社にトイレを1つだけしかつくらないというアイデアは、ジョブズにとってとてつもなく重要なものだった。
“ランダムなつながりは大切だ”というジョブズの考えは正しかった。
そしてそれを実現するために、一日に数回、生理的欲求を満たすために社員が必ずロビーを通らなければならないようにすることほど、効果的な方法はないように思えた。
ピクサーのゼネラルマネージャー、パム・カーウィンも、「ジョブズはこのアイデアの有効性を固く信じていた」と言う。
ジョブズは会議でこのアイデアの価値を力説したが、社員からは猛反発を食らった。カーウィンが回想する。
「妊娠中の社員が、トイレに行くために10分も歩かなければならないなんてまっぴらご免だと言った。それをきっかけに、議論が白熱した」ピクサーのクリエイティブディレクター、ジョン・ラセターも妊婦の意見を支持した。
ジョブズは苛立った。誰も、自分の素晴らしいビジョンを理解してくれない、と。
だが、ジョブズは立派な行動をとった。妥協案を受け入れたのだ。スティーブ・ジョブズ・ビルディングには、4つのトイレがつくられることになった。
幸い、正面玄関やカフェ、ゲームエリア、郵便受け、3つの劇場、会議室、試写室につながるアトリウムがあったおかげで、ジョブズが意図したような偶然の出会いが頻繁に起こることになった。
ラセターは、ジョブズの直感は正しかったと言う。
「何ヵ月も顔を見ていない社員に偶然出くわすことも多かった。これほどコラボレーションや創造性を促す建物はないだろう」
ピクサーの社長エドウィン・キャットマルも同意見だ。
「社員は一日中、社内のあちこちで顔を合わせる。その結果、よいコミュニケーションの流れが生まれ、建物内には活気が満ちていた」
偶然の出会いがよい効果を生んだのは間違いない。だが、ほかにも重要な要素があった。それは、自律性だ。
ピクサーの社員は、会社の所有者であり、生きる伝説であり、なんでも自分の思いのままに物事を進めなければ気がすまないスティーブ・ジョブズに立ち向かうことができた。
トイレを1つしかつくらないというアイデアに、反対意見を述べることができた。それは重要な要素だった。
ある日、キャットマルはピクサーのメイン会議室にある豪華なテーブルについて思いを巡らせていた。このテーブルは、ジョブズ好みのデザイナーが選んだもので、細長く優雅な形をしていた。
会議ではいつも、30人ほどのメンバーが細長いテーブルの両側に半分ずつ分かれて座った。全員の話がよく聞こえるように、幹部は真ん中の位置に座ることになった。
キャットマルやラセター、当該の映画監督やプロデューサーたちだ。それは、非公式ではあるものの、参加者の序列を如実に物語っていた。
身分の低いスタッフは、会話から遠く離れた場所に座らされ、言葉を聞き取ることも難しかった。やがてこの会議では座席札が置かれるようになり、皆、定位置に座るようになった。
それによって、序列も強化されていった。
キャットマルは、この問題を10年以上も自覚していなかった。重役であり、テーブルの中央に座っていた彼にとって、会議はうまくいっているように思えたからだ。
しかしあるとき、カジュアルなテーブルが置かれたほかの会議室の方がはるかに活発な議論が行われていることに気づいた。
キャットマルは、メイン会議室の豪華なテーブルを撤去させた。その次のクリエイティブミーティングでは、上級ディレクターのアンドリュー・スタントンが、座席札をランダムに配って参加者をいつもとは違う場所に座らせた。
私たちは、何事においても、慣れ親しんだ都合のいい順番を使いたがる。だが、ときにはそれをシャッフルすべきなのだ。
ピクサー社員の自律性は、いまでも健在だ。その象徴的な例が、「ラブ・ラウンジ」と呼ばれる隠し部屋だ。ラブ・ラウンジに通じる通路は、もともとは空調設備用に設計されたもので、這って移動しなければならないほど狭い。
この小部屋に通じる秘密のパネルを発見したピクサーのアニメーターは、このスペースをクリスマスライトや溶岩ランプ、動物柄の家具、カクテルテーブル、バーや紙ナプキン、「ラブ・ラウンジ」のロゴで飾り立てた。
ジョブズもこの隠し部屋がお気に入りだった。
「ここで働くアニメーターは、作業スペースを好きなスタイルに自由に飾ることができる。むしろ、それを奨励されているんだ」キャットマルは言う。
天井にミニチュアのシャンデリアがつり下げられた、おもちゃの家風のピンク色のオフィス。竹でつくられたポリネシア風の小屋。岩をくり抜いたように見える高さ5メートルの砲塔。精巧に色を塗られた城。
そう説明されると、そこは相当に混沌とした職場のように思える。だが、社員たちはそんなオフィスで生き生きと働き、高い生産性を発揮している。