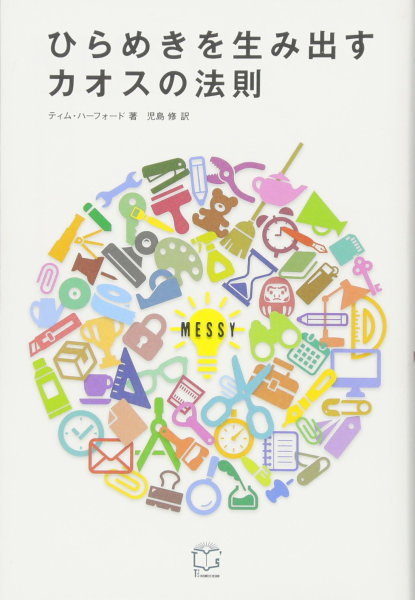(本記事は、ティム・ハーフォード氏の著書『ひらめきを生み出すカオスの法則』TAC出版、2017年12月18日刊の中から一部を抜粋・編集しています)
左利きが戦いに強い理由
競争で勝つには、相手を打ち負かさなければならない。
もちろん、相手を意識せず、自分のパフォーマンスのみに集中できるケースもある。
陸上の100メートル走の選手が、ライバルのことは気にせず、フィニッシュラインだけを見て走るような場合だ。とはいえたいていの場合、競争では相手を無視することはできない。
そして、相手を負けやすい状態に追い込むことも、勝つための重要な戦術になる。
映画『ロッキー2』で、左利きの挑戦者ロッキー・バルボアは、チャンピオンのアポロ・クリードと戦うために、いつもとは逆のオーソドックス(右利き)の構えをとった。
そのため、試合の大半でサンドバッグのようにアポロのパンチを浴びてしまう。だが、最終ラウンドでサウスポー・スタイルに戻し、困惑したアポロをノックアウトする。
そんなことは映画のなかでしか起こらないと思うのなら、ウラジミール・クリチコに尋ねてみればいい。
ウクライナ人のクリチコは、偉大なボクシング・ヘビー級チャンピオンとして知られ、2015年の時点で11年間無敗、18試合連続でタイトルを防衛していた。
この年の11月、クリチコはイギリス出身のタイソン・フューリーと対戦した。試合前の記者会見にバットマンの衣装を着て登場するなど、奇矯な言動で知られるフューリーの下馬評は低かった。
だがフューリーは試合中、ロッキーのようにサウスポーにスイッチする戦術でクリチコを幻惑し、ベルトを奪取した。
実際、「左利きの人が、右利きに比べ生まれながらに不利な面が多いにもかかわらず右利きが優位な世界で生き延びつづけているのは、右利きの人が左利きの人と戦うことに慣れていないからである」と主張する理論さえある。
いずれにせよ、私たちが学ぶことのできる教訓とは、競争で勝つためには、自分が何をするかだけではなく、“相手にどのような影響を与えるか”がとても重要だということだ。
チェスの世界に目を向けてみよう。世界最高のチェス・プレーヤーは誰かという議論については、ほとんど疑いようがない。
それは25歳の世界チャンピオン、マグヌス・カールセンだ。
ノルウェー人のカールセンは、13歳のときに元世界チャンピオンのアナトリー・カルポフを破った。
チェスの実力を示すレーティングでは、史上最年少で世界1位に輝いた。史上最高点も記録している。
とりわけ、終盤の詰めに強いことで知られている。
しかし、カールセンについてはほかにも興味深い点がある。
それは、これほど優れたチェス・プレーヤーでありながら、カールセンの指し手がそれほどよくはないということだ。
しかし、誰が世界一のプレーヤーの実力のほどを評価できるというのか?そう、答えはコンピューターだ。最高レベルのコンピュータープログラムは人間のチェス・プレーヤーをしのぐ能力を備えている。
この能力を使えば、コンピューターが考え得る最高の指し手と人間の指し手を比較できる。
ニューヨーク市立大学バッファロー校教授で元プロのチェス・プレーヤーのケン・リーガンは、ソフトウェアを使って人間のチェス・プレーヤーを評価してきた。
リーガンはカールセンの指し手が優れていることを明らかにしたが、ほかにも優れたプレーヤーは大勢いた。
それなのに、なぜ彼らは世界チャンピオンではないのか?
その答えは、カールセンの指し手が優れているかどうかではなく、指し手が相手に及ぼす影響だった。カールセンは、相手に能力を最大限に発揮させないような手を打っていた。
それは相手が感じる不安(実際、カールセンは相手がおびえるほど強い)や疲労(カールセンは体力があり、長時間の試合に耐え得るスタミナがある)のためだけではない。
カールセンは指し手そのもので、相手を混乱させていたのだ。
同じくコンピューターを用いてチェスの分析をしているガイ・ハワースは、カールセンの戦略の特徴は、複雑な状況をつくり出して相手に長い時間考えさせ、持ち時間を減らしてミスを誘発させることだと指摘する。
プロの試合では通常、持ち時間は「40手120分、41手目に60分追加」というように定められている。
ハワースはチェス・プレーヤーの1試合あたりの平均的ミス数(「ミス」というのは、コンピューターが計算した最善手から外れた指し手を意味する)を調べたところ、カールセンの試合では、持ち時間が少なくなる40手の直前に両者のミスが急激に増えていた。
カールセンは、持ち時間が減り、お互いにミスが生じやすい状況にあえて相手を引き込んでいた。つまり、完璧な手ではなく、相手を不利な立場に追い込む手を打っていたのだ。
ジェフ・ベゾスのスピード経営
1994年の前半、ワールド・ワイド・ウェブはニッチな分野だった。
史上最大のソフトウェア企業であるマイクロソフト社も、当時はまだウェブブラウザを提供していなかった。それどころか、自社のウェブサイトすら持っていなかった。
それでも、ウェブのトラフィック量は前年から2000倍以上も増加していた。その爆発的な成長は、企業にとってこのチャンスをものにできる期間がわずかしかないことを意味した。
実際にそのチャンスに挑んだのは、ウォール街で働いていた若きコンピューターエンジニア、ジェフ・ベゾスだった。
「会社がアイデアを思いつくと、混乱が起こるものなんだ」
ベゾスは、自らの伝記(『ジェフ・ベゾス果てなき野望』日経BP社)の著者であるブラッド・ストーンにそう語っている。その発言は、意外なものに思える。
消費者にとって、アマゾンは効率化や整然さの代名詞と思える企業だからだ。人々はなにかを買いたいと思い、アマゾンでその商品を検索し、見つけ、購入し、そして商品が届く。
そこではすべてが完璧に管理されている。
競合他社にとって、アマゾンと戦うことは機械と戦うようなものだ。アマゾンではあらゆる行動が計算され、すべての戦略が定量化されているように思える。
まるで、痛みすら感じない兵器ロボットのようだ。このような喩えは、たしかに的を射ている。だが、それは真実を部分的にしか映し出していない。
アマゾンの物語は、無謀な目標、過酷な戦い、大金の浪費、そして完全な混乱の連続だったからだ。
ベゾスは壮大なビジョンを抱いていたが、それを実現するためのアイデアは漠然としていた。
社名の「アマゾン」は、アマゾン川が世界一長い川であるという事実からインスピレーションを得たものだ。
ベゾスはこの会社を、消費者が想像し得るあらゆる製品を売り、素早くそれを届ける、アマゾン川のように大きな、地球最大の小売企業にしたかった。
だが、1995年にアマゾンがビジネスを立ち上げ、オンラインの書籍販売を始めたとき、その夢を実現させるための準備はまったくできていなかった。
最初の1週間で1万2000ドル相当の本が売れたが、発送できたのはそのうち846ドル分だけ。2週目には7000ドル分の本を出荷したが、さらに1万4000ドルの本が売れていた。
ベゾスは創業直後、いきなり修羅場に追い込まれた。
小切手を現金化するよりも早くビジネスが成長するので、銀行の残高いっぱいまで現金を引き出さなくてはならなかった。マネジメントチームは、夜遅くまで本の発送作業を続けた。
彼らは床に座って作業した―誰もテーブルを買いにいく時間をつくれなかったからだ。
ベゾスは顧客に、100万冊の本を選べる、30日以内なら商品を返品できる、といった大きな約束をしていた。だが、それを実現するための方法は明確ではなかった。
「社内の誰かがうまい方法を見つけてくれるだろう」と漠然と考えていただけだった。
起業して間もない時期なのだから、アマゾンは顧客への約束を実現するために、じっくりと足場を固めることに集中した方がよかったのではないかと思う人もいるかもしれない。
しかし、ベゾスは態勢を整えることよりも、目の前のチャンスをつかみにいった。
アマゾン創業から2週目、ベゾスは黎明期のインターネット界で高い人気を誇っていたウェブサイト、ヤフーの創業者デヴィッド・ファイロとジェリー・ヤンから電子メールを受け取った。
ヤフーのトップページに、アマゾンのウェブサイトへのリンクを掲載したいというのだ。コンピューターに詳しいベゾスの側近は警告したが、ベゾスはそれを無視し、ヤフーの申し出を受け入れた。
アマゾンにはさらに注文が増え、プレッシャーも高まった。スタッフの仕事量は溢れ返った。
後にジャーナリストのブラッド・ストーンがアマゾンの歴史をたどるために当時の状況を尋ねたとき、社員はあまりこの頃のことを覚えていなかった。当時はほとんど寝ておらず、頭がまともに働いていなかったからだ。
創業から2週間も経過していないときにヤフーの提案を受け入れたのは、ベゾスらしい判断だった。
アマゾンを立ち上げるときも、家族から「せめて次のボーナスをもらうまでは報酬のいいウォールストリートの金融機関で働きつづけるべきだ」と言われたが、ベゾスは、チャンスは今しかないと聞く耳を持たなかった。
1999年、ベゾスは台所用品の販売を開始した。
書籍の保管や仕分け、発送用に設計されていたアマゾンの倉庫で、突然キッチンナイフがシュートの下を通り、仕分け機に向かっていくようになった。
まだ書籍以外の処理に対応していなかったデータベースの画面は、このナイフがハードカバーかペーパーバックなのかを尋ねていた。
1999年は、アマゾンがおもちゃの販売を開始した年でもあった。
同社はそれに先立ち、ニューヨークで記者会見を開いた。そこでは、販売する商品をテーブルに並べて展示することになっていた。だが、ベゾスは用意された商品が少ないと激怒した。
「競合にビジネスを取られたいのか?これでは話にならない!」
幹部たちは急いでマンハッタンの「トイザラス」の店舗に向かい、自分のクレジットカードを使ってできる限りたくさんの商品を買い込んだ。
クリスマスが近づくと、アマゾンの社員はアメリカじゅうのコストコやトイザラスで商品を大量に購入し、アマゾンの倉庫に運んだ。トイザラスが立ち上げたばかりのウェブサイト「ToysRUs.com」からも、ポケモン関連の商品を買い漁あさった。
アマゾンのシステムには重い負担がかかった。
倉庫はポケモンのキャラクター「プリン」やマテル社の犬のキャラクター「ウォークン・ワッグ」の人形で溢れ返った。広大な流通センターのどこかで商品が紛失すれば、データベースに混乱が生じた。
未出荷の商品が仕分けエリアのシュートを詰まらせ、さらなる遅延を誘発した。
キャンペーンを開始していた同社には注文が殺到し、スタッフは倉庫の近くのホテルに泊まり込み、2週間帰宅できなかった。クリスマスが終わると、おもちゃは在庫の4割が売れ残った。
小売店で買ったおもちゃをウェブサイトで価格を割り引いて販売するのは、馬鹿げたことだった。それでも、同社は生き残り、顧客は満足していた。
2000年の夏、ドットコムバブルの勢いが陰り始めた。
アマゾンはすでにインターネット世界の先駆者であり、ウェブビジネスでもっとも成功した企業といえる存在でありながら、大きな打撃を受けた。
それは、ベゾスがさらなる成長を積極的に求めた結果、大きな損失を出していたからだ。
アナリストはアマゾンの資金不足を指摘し、それが世界に知れわたるようになった。アマゾンの財務部門は、同社に懐疑的になった金融市場から融資を得るのに苦労した。
金融情報誌は、「Amazon.Bomb」(アマゾンは爆弾)という見出しの記事を掲載した。サプライヤーは、アマゾンが倒産した場合に備えて、前払いの要求を検討し始めた。
実際、アマゾンは2001年のクリスマスを迎えられなかったかもしれなかった。それでも、ベゾスは攻めの姿勢を止めようとしなかった。
アマゾンは、ファイナンス・ディレクターがキャッシュフローを巧みにやりくりしたことや、いくつかの共同事業があったことでかろうじて救われた。
本当に際どかった。ブラッド・ストーンが書いているように、「アマゾンは、信念、即興、運で生き残った」のだ。
たいていの企業なら、この時点で事業の拡張を抑えようとしただろう。だがそれから数年間、アマゾンは次々と新たな製品やサービスを発表していった。
「キンドル」(アマゾンが製造に手間取ったこともあって、新しいバージョンを発売するたびに売り切れになった電子書籍リーダー)、「アマゾン・メカニカル・ターク」(クラウドソーシングの先駆けとなったジョブマッチングサービス)、「ファイア・フォン」(不格好で、奇妙で、残念だと各所で酷評された携帯電話)、「マーケットプレイス」(アマゾンが販売する既製品よりも低価格の中古品を、他社がアマゾンのサイトで販売するサービス)などだ。
なかでも、2006年にクラウドコンピューティング・サービスの先駆けとして提供された「アマゾン・ウェブ・サービス」は、マイクロソフトのAzureよりも4年、グーグルのコンピュート・エンジンよりも6年も前にベゾスが打った、大胆かつ先進的な一手だった。
ベゾスは1998年から99年にかけての激変の時代に、よくこう言っていた。
「今の環境のなかで、なにかを計画するのに20分以上もかけるのは、時間の無駄だ」スピードを重視していたベゾスが、あれほどの混乱をつくり出したのも不思議ではない。