本記事は、門賀美央子氏の著書『この先の、稼ぎ方がわからない。50歳から考えるお仕事図鑑』(清流出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

なが~い年金生活。足りない分はどうする?
暗い予測の源になったのは政府発表のデータ
厚生労働省の資料「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、現時点でも公的年金受給者の半数弱が月額10万円未満しかもらえていません。さらに男女別でみると、男性の約6割が月額15万円以上受給しているのに対し、女性は逆に6割以上が月額10万円未満になっています。
女性の平均値が低くなるのは、専業主婦率が高かった時代に「妻」をやっていた人たちの多くが第三号被保険者で、厚生年金であっても受給年額が下がるためです。令和5年度(2023)の厚生年金の平均月額受給額は14万6,429円ですが、夫が亡くなった場合、第三号被保険者の受給金額は4分の3に減額されます。平均値で換算すると12万円弱になるので、いきおい女性の平均値が押し下げられるわけです。また、女性の賃金が男性に比べて低いのも理由のひとつです。
月収10万円。
生活費はこれで十分ですと言える人はどれぐらいいるのでしょうか。
家賃の心配がなければなんとかなるかもしれません。
データ(総務省統計局「住宅・土地統計調査」2023年)でみると世帯の持ち家率は60%程度。ですが、別の資料によれば75歳以上の単身女性となると69%にまで上がります。
家賃がいらない分、支出は抑えられます。しかし、細々とした修繕費や改装費、固定資産税、マンションだとさらに管理費や修繕積立金などは必要ですから、そうした支出を勘案するとやはり2~3万円はプラスして考えておきたいところ。すると、たとえ持ち家でも月3万円程度の住居経費が発生します。
つまり年36万円、100歳まで生きるとしたら1,260万円の住居費が必要です。私の5,000万円弱に比べたらまだしもですが、それでも大金には変わりありません。
では、みんなそんなに貯蓄があるのでしょうか。
金融広報中央委員会が発表している令和6(2024)年版「家計の金融行動に関する世論調査」によると、単身者の平均貯蓄額は50代で1,087万円、60代で1,679万円、70代で1,634万円となっています。
みなさん、結構持っているのねえ……とため息が出そうになりますが、ちょっと待ってください。
ここに統計の罠があります。
この数字、あくまでも「平均」なんです。つまり、とてつもない貯蓄額を持っている人が1人いるだけで、全体が上方にひっぱられるのですね。
案の定、中央値、つまり調べた人たちを順番にならべてちょうど真ん中になる人の金額となるとまったく違う数字が出てきました。
50代で30万円、60代で350万円、70代で475万円。驚くほど低くなります。半数以上の人が、老後を支えるには不十分な貯蓄しかないのです。
これが2人以上世帯、つまり家族と住んでいる人たちになると50代で250万円、60代で650万円、70代で800万円と増えますが、人生100年時代の貯蓄としては不十分なのは前出の数字をみても明らかです。
老齢人口の半分以上が余命をまっとうするには不十分な貯蓄しかない上、もし生活に困窮する人が続出しても、政治はそうそう簡単には救済策を立ててくれはしないことでしょう。なにせ、今後の日本はもはや尻すぼみが決定しているのですから。
これは困ったことになりました。
私のような単身女性高齢者(予備軍)の老後は真っ暗闇っぽいのです。
ですが、もうお気づきのように、ここまでの試算はあくまで「年金しか収入がない場合」に限った話でした。ほかに収入を得る手段があればまた違ってきます。
この恐ろしい試算を覆す方法はただひとつ。
元気に働けるうちは働く。
これしかありません。
国が目指すのは、「老いも若きもみんなで高齢社会対策」
実は、日本国政府はもうとっくに政策を「生涯現役」路線に切り替えています。
高齢社会対策基本法、という法律があるのはご存じでしょうか。
平成7(1995)年に公布された法律で、直近では令和3(2021)年に改正法が施行されました。
内容は名前の通り、政府が高齢社会対策をするための基本となる法律です。これを読めば、政府がどのように高齢社会対策を進めていくつもりなのかがはっきりとわかります。ですので、この法律の内容をチェックしてみようと思います。
さて、法律にはその理念をざっくりと要約する「前文」がつきものです。もちろん高齢社会対策基本法にもあります。比較的短いので、以下に全文を引用したいと思います。
我が国は、国民のたゆまぬ努力により、かつてない経済的繁栄を築き上げるとともに、人類の願望である長寿を享受できる社会を実現しつつある。今後、長寿をすべての国民が喜びの中で迎え、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれる。そのような社会は、すべての国民が安心して暮らすことができる社会でもある。
しかしながら、我が国の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれているが、高齢化の進展の速度に比べて国民の意識や社会のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわたるが、残されている時間は極めて少ない。
このような事態に対処して、国民1人1人が生涯にわたって真に幸福を享受できる高齢社会を築き上げていくためには、雇用、年金、医療、福祉、教育、社会参加、生活環境等に係る社会のシステムが高齢社会にふさわしいものとなるよう、不断に見直し、適切なものとしていく必要があり、そのためには、国及び地方公共団体はもとより、企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力しながらそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要である。
ここに、高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国を始め社会全体として高齢社会対策を総合的に推進していくため、この法律を制定する。
―高齢社会対策基本法(平成7年法律129号)「前文」より
要約すると「日本は長寿社会になって、国民全員がそれを幸せに享受できるようになるべきなんだけど、現実は追いついていないから社会全体で高齢化対策を進めていきましょうね」というところでしょう。たいへん結構なことだと思います。
- 第2条
高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。
- 国民が生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会
- 国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会
- 国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会
しかし、実際にはどのように進めていくつもりなのでしょうか。
根本となる理念は次のようなもの、であるようです。
さて、ここで注目したいのが高齢社会対策基本法基本理念の「1」が「生涯にわたって就業その他の多様な社会的活動に参加する」社会を目指すことになっている点です。「定年後は隠居して安閑と暮らせる」社会を目指していないのです。
さらに、国民は「生涯にわたって社会を構成する」一員であり「自立」していなければいけません。ぼんやりと他人様頼りの生活をする高齢者は国として望ましくないのです。しかも自助と共助は明記されていますが、公助については特にみえず、です。私などは「3」こそが第一に持ってくるべき〝基本理念〟であり、それを実現する責任の主体は国家であると宣言してもらいたいところなのですが……。
こうしたことを踏まえ、前文の主旨を私なりに国の本音バージョンに意訳しますと次の通りになります。
《我が国は世界に類をみない高齢社会になった。良し悪しはともかく、こうなることは数十年前からわかっていたにもかかわらず、国も社会も個人もほとんど準備ができていない。そのため、老人といえどもギリギリまで現役でいてもらわないと立ち行かなくなる。高齢者だろうがなんだろうがボケーっとさせずにキリキリ働かせる社会を作らなくてはならない。》
こんなところだと思うのですが、どうでしょう?
飛躍し過ぎと感じられるかもしれませんが、私は本当にこうなのであろうとみています。というのも、各省庁が行っている個々の政策は自立促進政策ばかりなのです。ですので、政策を確認しながら、21世紀老人はどんな働き方ができるのか、あるいはしなければならないのかを考えていきたいと思います。
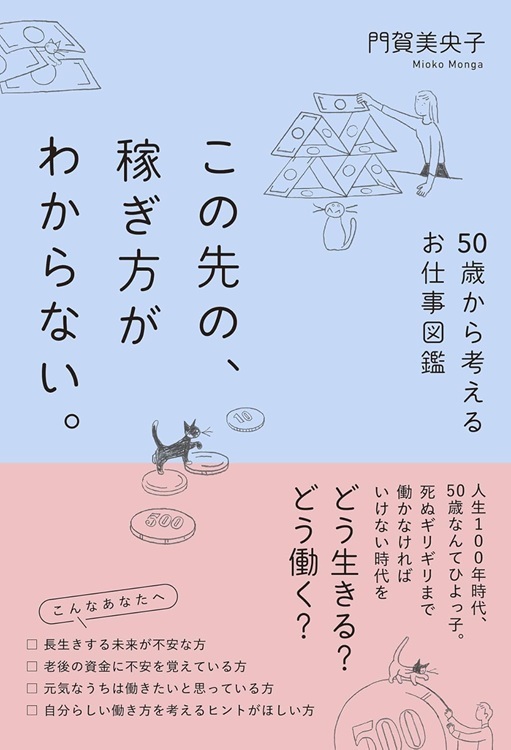
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
