(本記事は、財産ドック氏の著書『税理士が知らない不動産オーナーの相続対策』クロスメディア・パブリッシングの中から一部を抜粋・編集しています)
40年ぶりの相続法改正
ご存じの通り、2019年に40年ぶりに相続法が改正されました。資産家だけでなく、一般のご家庭の自宅の相続にも大きな影響がある改正です。40年間変わることのなかった法律が大きく変わることになったわけですから、これまで行ってきた相続対策も見直しが必要になったと言えます。
これまでの相続対策が通用しなくなるかもしれないのですから、大きな反応があると思っていましたが、多くの不動産オーナーはこの相続法の改正についてあまり関心がないように見受けられました。私たちが想像していた以上に、危機感を抱いている方は少なかったようです。
私は、今回の相続法の改正は大きなターニングポイントだと考えています。相続対策をしっかりと行ってきた不動産オーナーも、その対策が本当に適切なのかを改めて確認する必要があるのです。というのも、これまでの相続対策が通じなくなるどころか、それが裏目に出て揉め事になるかもしれないからです。今回の相続法の改正がそういった現実を引き起こす可能性があるということを不動産オーナーはしっかりと理解しなければなりません。
例えばこれまで定められていた「遺留分減殺請求」という制度。これが今回の改正で「遺留分侵害額請求」という制度に変わりました。もともと遺留分減殺請求というのは、相続の際に法律で定められた最低限度の財産の相続分を得られなかった相続人が、自らの財産を請求する権利でした。
この請求を受けた場合、これまでは金銭ではなく物、つまり不動産であれば建物や土地の権利などを渡すことで解決することができました。
しかし、それが今回の改正により遺留分侵害額請求と名称が変わり、原則として物権ではなく金銭で支払うことが定まりました。つまり「遺留分はお金で解決してください」そう決められたのです。
これまでは遺言などで全財産を一人に承継させて、裁判になったとしても、分けることができる不動産を遺留分だけ渡せばよかったのですが、これが全て現金で渡す必要が出てきたということですから、非常に大きな問題です。今後は遺留分のトラブルになった場合には、現金を持っていなければ対処できないことになります。
先祖代々守ってきた土地を承継させたいと考えていたとしても、自分が死んだあとに子どもたちの間で遺留分に関するトラブルが生じた場合、現金がなければ、土地を売却してでも現金を作らなければならないということです。土地を守れないというのは、土地の承継を第一と考える地主には大きな問題になります。
また、今回の改正で大きな目玉として取り上げられている配偶者居住権についても、同じく対策の見直しが必要です。
配偶者居住権とは、自宅に住んでいた配偶者が仮にその自宅の所有権を相続しなかった場合であっても、そこに住み続けることを認める権利です。自宅を「所有権」と「居住権」に分けることで、所有権は子どもが相続し、居住権を配偶者が相続することができるようになります。つまり、相続資産をこれまで以上に柔軟に分けることができる制度です。
配偶者居住権が制定された背景には、高齢の配偶者や、長年住み続けた家を離れたくないと考える人への配慮があります。夫や妻が亡くなり、残された配偶者が住み慣れた自宅を相続した結果、現金などの金融資産は子どもたちが相続することになり、結果的に高齢の配偶者の生活が苦しくなる、そんなトラブルを防ぐために配偶者居住権は作られたのです。
こういった背景を見ると配偶者居住権は歓迎すべき制度だと考えられます。
しかし、問題もあります。例えば、父親が亡くなったあと、残された母親が配偶者居住権を取得し自宅に住み続け、子どもが所有権を持ったとします。この母親が認知症になり、どうしても施設に入所する必要が出てきた場合どうなるでしょうか。
配偶者居住権は原則として事前に定められた配偶者居住権の存続期間が終了するまでか、配偶者が亡くなるまで権利が有効となります。例外として、配偶者自身が配偶者居住権を放棄した場合は権利を消滅させることができますが、配偶者本人が認知症になってしまった場合、意思確認ができないと見なされてしまうため、権利放棄をすることが難しくなってしまうのです。
子どもたちの経済状況に余裕がない場合、自宅を売却して現金化することができれば認知症になった母親の面倒をもっと見ることができたのに、結果的に経済的な理由で十分な対応をとることができないという、不幸な事態を招いてしまう可能性も否定できないのです。
勘違いしてもらいたくないのですが、私は改正前と改正後どちらの相続法が良いかということを議論したいわけではありません。相続法が大きく改正されたことで、相続における前提が変わったことに注目してもらいたいのです。今までは正しいとされていた対策が、今までとは全く異なる結果を招いてしまう可能性も出てきたということです。
今後は相続の際にどのような点に重きをおくのか、今まで以上に慎重に考える必要が出てきました。これまで相続対策をしていた方も、改正された法律を踏まえて改めて資産全体を見渡した上で、子どもたちへ財産の承継をどのように行うのか、ご自身の想いをどのような形でつなぐのかということについて考えなければなりません。
相続に対する考え方は時代の変遷とともに変わってきています。ここ最近の相続を見ると、昔のように家督を継ぐという考え方自体が少なくなっていることがわかります。昔は長男が両親の面倒を見て、自宅などの資産を承継するといった考え方が一般的でした。
しかし時代とともにそのような考え方が希薄になっているのが現状です。その家を誰が守っていくのかは、なかなか簡単に決めることはできません。法改正を経た今、これまで行ってきた相続対策、そしてそのために書いた遺言書なども、もう一度改めて確認して、適切かどうかをチェックする必要があると言えるでしょう。
公平に分けることができない不動産
不動産は現金化することが難しい資産です。しかもその特性上、一つとして同じものはありません。そのため相続に関してトラブルが生じる場合には、必ずと言っていいほど不動産が関わっています。「あの土地の方が立地が良い」「あそこの賃貸物件の方が入居率が高い」「あの土地と建物は相続したくない」など、それぞれの家によってトラブルの火種は異なりますが、結局のところ公平で満足いくように分けることが難しいため、資産を相続する人たちの間で納得できないという問題が生じてしまうのです。
では、どうして公平に分けることができないのでしょうか。もちろん物理的に建物や土地を分けることができないという理由もあります。しかしそれよりも、土地をはじめとした不動産の評価について、様々な尺度が存在していることが大きな要因として挙げられるのです。
例えば以前、こんな相談を受けたことがあります。お父様が亡くなり土地を相続した相談者の方の話です。相続した土地の評価が、路線価で評価すると1億5000万円とかなり高額になり、突然とんでもない相続税が発生することになったと相談を受けました。「売るにも売れなくて、どうしたらいいものか……」と、相談者はかなり困っている様子でした。
しかし、話を聞くとその土地は全く使っておらず、今後も使う予定もないとのこと。「すぐにでも売って現金化すればいいのでは?」と思ったのですが、なんと100万円で売りに出しても誰も買ってくれないというのです。詳しく話を聞いてみると、そこは傾斜角30度の崖地にあり、宅地造成すると1億円以上費用がかかる、そんな土地だったのです。
しかも運悪く、土地の北と南、二方向に大きな道路があったことで、路線価も高く、現場に足を運ばなかった税理士が勝手に路線価で計算して申告書を作成してしまったという、なんともお粗末な状況でした。
事情を聞いた私はすぐに不動産鑑定士にその土地を鑑定評価してもらいました。結果、評価額は2000万円になり、路線価の1億5000万円からぐっと下がったのです。しかし、100万円でも売却できなかった土地です。この土地の状況を考えると2000万円でも割高だと感じました。そのため過去の急傾斜地評価の事例を洗い出し、その事例に沿って評価をしてみると、なんと最終的に評価額は6万円まで下がったのです。
路線価評価では1億5000万円、不動産鑑定士が鑑定評価すると2000万円、税法上の事例を適用すると6万円。相続税で使う数字だけ見ても不動産にはこれほど尺度の違いがあるのです。何も知らない相続人たちが、それぞれの尺度を持ち出してきたら収まるものも収まりません。
しかも相続では、自分が生まれ育った思い入れのある自宅や土地を分けることになるため、感情的な面も絡んできます。「公平でみんなが納得いくように不動産を分ける」ということは簡単にはできないというのがわかっていただけるかと思います。
余談ですが、本来、建築基準法上は道路認定されない道に面した土地に路線価がついていたという事例もありました。これを税務署に指摘したら、翌年には路線価が外されていました。路線価だけをもとにした土地の評価を信じきってしまってはいけないということです。
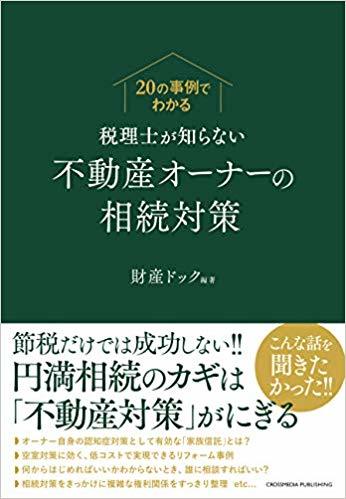
※画像をクリックするとAmazonに飛びます

