本記事は、茂木健一郎氏の著書『 眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』(日本文芸社)の中から一部を抜粋・編集しています
大脳の働きでさまざまな記憶がつくられる

記憶は、覚えておける期間によって、短期記憶と長期記憶に分けられます。
短期記憶は、たとえば、出前を注文するときに一時的に覚える店の電話番号のようなもので、何かの作業をするときだけの短い期間の記憶です。
長期記憶は内容によって陳述記憶と、非陳述記憶に分けられます。
陳述記憶は、言葉でいい表すことができる記憶で、エピソード記憶と意味記憶に分けられます。
エピソード記憶は、実際に体験した出来事の記憶です。感覚や感情も深く関連する長期間忘れない記憶です(脳の発達が未熟な3歳ごろ以前の幼児にはありません)。意味記憶は、くり返し反復して覚えた記憶、いわば「知識」のことです。使わないでいると思い出せなくなります。
こうした記憶の形成には、大脳辺縁系の海馬が深く関わっています。
見たり聞いたりして脳に入った情報は、海馬に短期記憶として一時的に保存されたのち、消去されます。しかし、海馬は、記憶を整理して覚えるべきものとそうでないものを選別し、覚えられるべきと判断した情報を大脳皮質に送ります。そこで記憶が固定され、長期記憶として保存されることになります。
脳をコンピュータにたとえるとすれば、海馬はメモリー、大脳皮質はハードディスクに相当するといえるでしょう。
一方、非陳述記憶は、運動が伴う記憶で、手続き記憶と呼ばれます。こちらは海馬でなく、大脳基底核と小脳が中心となって記憶を形成します。

忘れたり、思い出したりする記憶のメカニズム
海馬から大脳皮質に送られた陳述記憶の情報は、神経細胞を刺激し、たくさんの神経細胞とシナプスが組み合わされます。そうしてできた記憶の回路が大脳皮質に保存されます。記憶を引き出す際は、その回路に電気信号を送ることで呼び覚まし、思い出すことができるのです。ただし、長く思い出されないでいる記憶は消去されていきます。
年を取ると物忘れで記憶をすぐなくすと思う人がいるかもしれませんが、そうとは限りません。
物忘れは、老化により記憶を引き出そうとする電気信号のエネルギーが弱くなって記憶の回路に信号が届かなくなるのが原因であって、記憶自体が消えることで起こるのではありません。
忘れたくない記憶は、思い出すようにすることが大切です。
最近の研究により、記憶の種類によって保存される脳の場所が異なることがわかりつつあります。エピソード記憶は前頭葉に、意味記憶は側頭葉に、感情に関わる記憶は扁桃体に保存されます。
一方、非陳述記憶(手続き記憶)は大脳基底核の線条体と小脳に保存されます。
大脳基底核は脳が体の筋肉を動かしたり止めたりするときに、小脳は筋肉がスムーズに動くように動作を細かく調整する働きをします。人がこの働きを使って体を動かし、何度もくり返すと、そのうち、線条体と小脳では神経細胞ネットワークがつくられます。これで正しい動きを学習し、記憶される仕組みになっているのです。
このようにしてできた神経細胞ネットワークは消えるはことなく、いつまでも残ります。

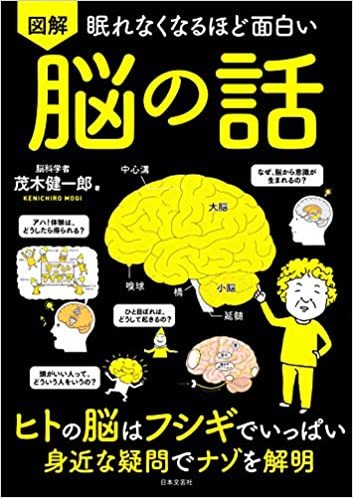
※画像をクリックするとAmazonに飛びます
