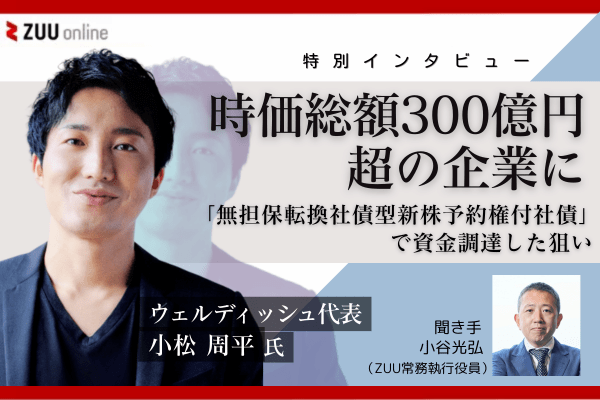
「ミネラ〜ル麦茶!」というTVCMのフレーズでかつて広く知られた食品メーカー・石垣食品は、一時、債務超過に陥るなど危機に瀕していたが、昨年、代表取締役社長に小松周平氏が就任、社名をウェルディッシュに変更。スピード感あふれる経営改革を実践して、業績を回復させつつある。さらなる成長を期して「無担保転換社債型新株予約権付社債」による資金調達という一手を打った小松社長に、ZUUの小谷がその狙い、そして今後の展望を聞いた。
米系投資銀行やヘッジファンドで約10年間、トレーディング業務に従事し、ニューヨーク、シンガポール、ロンドンで海外赴任生活を送る。帰国後は、エンジェル投資家、起業家として医療系、AIやドローンなどのテクノロジー系スタートアップの立ち上げに参画。2023年、SBCメディカルグループホールディングスアドバイザーに就任。2024年、ウェルディッシュ代表取締役社長に就任。
1995年明治大学商学部卒業後、さくら銀行(現三井住友銀行)の神田、渋谷、横浜支店で、大企業から中小企業まで幅広く担当。その後は本店営業部にて不動産、ゼネコン、保険会社を担当した。2009年から約5年半、タイ・バンコクに駐在し、タイ国内のみならず周辺国も含め、日系企業の起業支援や企画開発に従事。帰国後は青山支店、証券会社出向、本店営業部等を経験し、2020年1月にZUU入社。
デリバティブトレーダーの経験があったからこそ
──今回の資金調達で使われた「無担保転換社債型新株予約権付社債」は、御社の現状を考えると秀逸なスキームだったと思いますが、このアイデアは、以前からお持ちだったのでしょうか?
小松 長年、金融業に従事してきた結果、身についた経験と知識があったからだと思います。過去にトレーダーとしてデリバティブを担当したり、ヘッジファンドで働いたりする中で、アメリカやシンガポールなど海外の金融市場を見る機会が非常に多くあり、日本と違って海外ではさまざまな手段や手法が用いられていますから。
──トランプ政権の関税施策の発表で、米国も日本も株式市場が大きく値を下げています。株価変動が価格と連動する社債の発行体である御社にとっては、必ずしも良い相場環境とは思えませんが、どのようにお考えですか?
小松 ウェルディッシュの株価は心配しておらず、いずれ戻ってくると思いますが、より重要なことは、付帯されている「GC」(ゴーイングコンサーン=継続企業としての重要な疑義)の注記が次の決算発表で外れるかどうかです。市場の予想通りGC注記が外れれば、いよいよ機関投資家がウェルディッシュの株式を買うことができるフェーズに突入します。そのとき、株式の流動性が高まるので、その前に社債を発行できたのはすごくポジティブなことです。
──御社の株価だけではなく、市場全体も回復していくと見ていらっしゃる。
小松 今の状況は一時的なものであり、悲観する必要はありません。むしろ、「みんながお金持ちになるチャンスが到来した」と思いました。長年、金融市場に携わり、何度も相場の「クラッシュ」を見てきましたから、「いま買わないでいつ買うの?」とすら思いますね。
(編集部注:取材が行われた4月18日時点での見解です)
時価総額300億〜400億円企業に
──会社の時価総額や株価の目標はありますか?
小松 資本政策は当面しないでしょうから、発行済み株式数がほとんど変わらないとすると、時価総額は300億円〜400億円を目指していきたいですね。
──その根拠は?
小松 昨年11月に発表した中期経営計画(中経)でお示しさせていただいた当期利益は8〜10億円です。食品会社のPER(株価収益率)はおよそ30倍弱ですから、これを踏まえて、時価総額は300億円台半ばくらいを目指したいと考えました。
──時価総額が300億〜400億円になると、需給の観点からすると、今の流動性ではハードルが高そうです。さらなる株主の創出のための対策、株式の流動性を生むための対策は何かお持ちですか?
小松 「株式インセンティブ報酬」を正式に導入したいと思っています。これはグループ会社も含めた役員など、幹部すべてが対象です。そうするとある程度、株式が市場に供給されることになります。
なぜかというと、(報酬に対する)税金を支払わなければならないからです。実際にそのフェーズに到達したときに、企業としてどのような資本政策を取るべきなのか。株式分割などいろいろな方法があるので、流動性は確保したいと思います。
機関投資家と個人投資家に配慮したIRに
──時価総額が300〜400億円規模になり、機関投資家がつくようになったら、IRはどう変更されますか?
小松 GC注記が外れれば比較的小型のファンドとお付き合いすることになるでしょうから、そこで求められる情報が提供できるよう、IRの仕方は変えようと思います。
これまでのIRで用意した資料は、個人投資家を意識した文章の内容や表現でしたが、決算報告用の説明資料だけでなく、中経の説明資料なども、よりプロに伝わりやすい、機関投資家を意識したIRにします。

──日本では老後資金を資産形成して用意される個人が増え、株式市場でも個人投資家の重要性は高まっており、企業経営では機関投資家と個人投資家のバランスの取り方が重要になると思います。その点については、どのようなお考えをお持ちですか?
小松 企業としてオフィシャルなIR情報やイベントはプロ向けにして、英語版資料も準備し、海外の投資家向けにも発信していかなければなりませんが、個人投資家の皆さんとのつながりも大切にし続けます。そろそろSNSもやろうかなと考えています。
ウェルディッシュはこの1年間、個人投資家を対象としたオフ会という位置付けでQ&A会を実施してきており、これは続けていきたいですね。
「分かっていても買えない」のが株式投資
──企業経営者であると同時に個人投資家でもある小松社長が、投資で失敗した経験は?
小松 相場が下がったとき、「戻るのを見越して買うべきだ」と思いつつも、怖くて買えない時期が長かったことですね。金融業界で、サブプライムローンによる金融危機、リーマン・ショック、世界的な景気後退、ギリシャ・ショック、チャイナ・ショックを経験しましたが、チャイナ・ショックのときから、ようやく暴落の後に買えるようになりました。
ただ私はトレンドフォローが苦手で、上昇中の株式を買うと損をしてしまうケースがほとんどです。
──どういうことですか?高値づかみしてしまうんでしょうか?
小松 私の投資スタイルが原因なんでしょうが、上昇中の株式を買うと、気が付いたら下落していたなんてことが起きる(笑)。「下がっているものを買ったら放置する」というのが、自分の投資スタイルかなと思っています。現在はリスク性資産のほとんどを安全な債券にしましたし、自身の資産運用のために株式相場を見る機会は減りました。
組織と経営体制を相次いで整備した理由

──最近の会社の変化はいかがですか?
小松 従業員が増えています。代表取締役に就いたときは4〜5人だった企画部署は、12人になりました。中国の子会社も20人から40人に増えています。グループ全体では100人ほどになりました。
──企業買収で増えた人員だけではなく、新しく採用もされているんですよね?
小松 かなり採用しています。この先、人材ビジネスは「売り手」市場から「買い手」市場になると思っています。景気が落ち込むと、採用を見送る企業が増えるからです。同時に「勝ち組」企業と「負け組」企業が明確に分かれて、雇用できる企業が人材を選べるような状況になるとみています。
──コーポレートガバナンス強化や投資委員会を設置されたそうですね。
小松 会社を引き継いだとき、「なぜ経営が失敗してしまったのか」を分析して気付いたのが、「コーポレートガバナンスが弱い」ということでした。「ある一人の人間の意見がすべて通ってしまう」「不正行為があっても周りが関心を持たない」といった状況にあったので、変えようと思いました。
ただ、資金繰りが厳しい段階でコストをかけてまでやることではないので、まずは業績の黒字化に専念したんです。そして、採用を増やすようになったら、ガバナンス強化が必要になると思い、このタイミングでコーポレートガバナンスを整備しました。その結果、CEO、CFO、役員の中でも業務分担が明確になりました。
──なるほど。それぞれが責任を持って、役割を果たせるようになったんですね。
小松 M&Aをするにしても、取締役会で全部を決めるのではなく、投資委員会を設置してDD(デューデリジェンス)などを実施してから、取締役会で取り上げて議論するほうが、業務効率は上がるので、投資委員会を設置しました。
監査等委員会は既にありますし、リスクコンプライアンス委員会も始めました。あとは報酬委員会でしょうか。ただ、それは「もう少し人数が増えてから設置すればいいかな」と思っています。
──報酬委員会の設置は従業員の「やる気」や人材採用にもプラスに働きそうです。
小松 そうですね。ただ今すぐ設置してしまうと、数字や成長度合いの定量的な結果からどう考えても客観的に私の報酬が高くなり過ぎてしまうので、設置を先送りしているんです。業績が良くなるまではコストを抑えたいですから。
──その分も企業再生のための投資に振り向けるということですね。
小松 そうです。もう少し人員が揃ってきたら、用意していた制度を承認して報酬委員会を設置しようと思います。
「面白い」経営者と「理想」の経営者
──プロ経営者としてキャリアを積まれていますが、これまで目標にしてきた経営者、尊敬している経営者はいますか?
小松 私が「面白いな」と思う経営者は2人、「この人みたいになりたいな」と思う経営者が1人います。「面白いな」と思っているのは、株式会社じげんの平尾丈さんと、株式会社エアトリを創業した吉村英毅さんです。2人とも年齢が近く、昔から親交があります。
──お二人は、小松社長と考え方や経営スタイルは似ていますか?
小松 まったく似ていないですね(笑)。平尾さんはビジネス感覚が非常に優れていて、直感的に「これだ」というところを見つけて集中で追求するタイプです。これに対して吉村さんは徹底的に調べ上げるタイプ。そんな彼らに対して、私自身はインスピレーションを働かせて選択しますが、同時に取り組むべきことを複数用意する分散型です。だから3人ともまったく違うんですよ。
──小松社長は「リスクヘッジ」型なんですね。それでは「この人みたいになりたい」という経営者は誰ですか?
小松 SBCメディカルグループの相川佳之さんです。もう別格です。近くで相川さんの経営手腕を見てきましたが「こうやって企業再生させるのか」と感心します。24時間、仕事のことを一番に考えていて、しかも忍耐強くて、ルーティンをきちんと守られる方です。私はついサボりがちで、あの忍耐力はありません(笑)。
一緒に仕事をする前は、「仕事のできる側近がいて、その人が支えているんだろう」と思ったら、全部一人でやっていらっしゃった。もちろん、医療という実務面ではドクターとして支えてくれるエキスパートはたくさんいますが、企業経営やビジネス面ではすべてご自身でやられていました。そのことにすごく衝撃を受けました。
──そうだったんですね。今日は面白いお話をどうもありがとうございました。
小松 こちらこそありがとうございました。