この記事は2024年5月14日に「第一生命経済研究所」で公開された「これからの日米交渉の行方」を一部編集し、転載したものです。
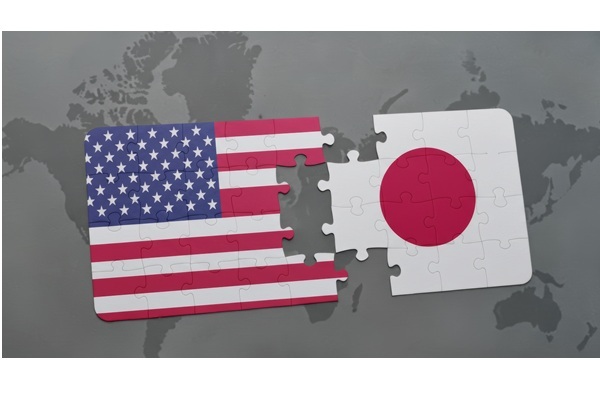
二次波及の警戒は緩和
日本は、各国が行っているトランプ関税交渉のフロントランナーから後退した。すでに日米関税交渉は2回を数えるが、成果らしきものはない。そこで、本稿では日米関税交渉の行方について考えたい。
5月12日の米中合意には、本当に驚かされた。両国が▲115%もの関税率の引き下げに合意したからだ。これで関税率は、米国が30%(相互関税のベースライン10%+合成麻薬対応20%)、中国が10%にまで下がる格好だ(90日間)。同盟国・友好国である日本に譲歩せず、覇権競争の相手国中国にこれだけ譲歩するのは誠に不可解だ。まだ、そのディールの中身は公開されていない。中国が何を条件として飲んで、米国が何を提案したのかが見えていない。ひとつ言えるのは、中国が米国からの輸入品に125%の関税率をかけていると、中国が輸入拡大する余地すらなくなるから、順序として米国が最初に関税率を引き下げて、中国がそれに同調するかたちになったのだろう。トランプ大統領が言っていた「リセット」とは、輸入拡大の余地を作り、貿易収支の改善に取り組むということなのだろう。トランプ大統領が各国に課している相互関税のベースラインに中国も並んだだけというのが、「リセット」の意味なのかもしれない。
その結果として言えることは、日本経済にとって、米中が互いに高関税をかけて共倒れする悪影響が回避されそうだということだ。2024年の貿易統計では、日本から米国向け輸出のシェアは約20%、中国向けは約18%、これに香港を併せると合計約43%にもなる。これらの地域の貿易取引量が著しく減り、米中経済が冷え込むと、その二次波及効果(間接効果)によって日本経済は大きな影響を受ける。この心配は、米中合意によって従来に比べて低減している。株価のリバウンドはそれを反映したものだと理解できる。
メイン・シナリオ
トランプ関税の影響は、間接効果だけではなく、直接効果もある。直接効果とは、米国が日本の輸出に課している(さらに課そうとしている)関税による輸出下押しの効果である。自動車・部品関連、鉄鋼・アルミには25%、他の部分には相互関税の基準税率10%が課されて、90日間の猶予後はこの部分が24%に跳ね上がる。
この直接効果を低減すべく、石破政権は5月後半以降に3回目の関税交渉を検討している。そして、6月15~17日にかけてのカナダG7に合わせて日米首脳会談で一応の合意を目指しているようだ。
これまでの米国との関税交渉で見えてきたのは、米国側が相互関税の基準税率10%は維持しようとする姿勢だ。相互関税の上乗せ14%は、交渉次第で可変的に設定されるが、基準税率が例外的に下げられることは今のところなさそうである。5月8日の米英合意でも、自動車関税には10%が残った。英国は、相互関税の上乗せ分が設定されず、基準税率10%で交渉が行われていたという経緯もある。日本にとって、交渉がうまく行ったとしても、すべての輸出品目に追加関税率10%というラインで決着する可能性は高いのではないか。これがメイン・シナリオになる。
では、直接効果が基準税率の10%になるときに、経済的なインパクトはどれくらいになるだろうか。2025年4月のIMF世界経済見通しでは、2025暦年の日本の実質GDP成長率が1月見通しよりも▲0.5%ポイントほど下方修正されていた。これはほとんどトランプ関税の悪影響のせいだとみられる。
日本がトランプ関税で課される負担増は、従来の関税率で計算して年間5.2兆円になると計算できる。これが仮に全品目10%になったとすると、2.1兆円にまで下がる。この割合で計算すると、交渉後の経済的なインパクトは、4割程度(=2.1兆円÷5.2兆円)になり、▲0.5%ポイントの下押し圧力は▲0.2%ポイントに変わるだろう。二次波及効果まで厳密に計算はできていない限界はあるが、ラフな計算では▲0.2%ポイントであれば、相当にトランプ関税の影響力は小さくなると言える。
腹案を考える
もしも、相互関税の基準税率10%を引き下げることができなかったならば、日本政府には何ができるのだろうか。米中合意と米英合意が成立し、日本の合意は後回しになっている感がある。トランプ大統領には、昔の日米貿易摩擦の記憶が強烈に残っていて、日本には安易な妥協を許さない印象が強いのかもしれない。石破政権は、夏の参議院選挙(観測では7月20日に投票日)を控えて、関税交渉ではたとえ10%の相互関税でも、あまり成果として誇ることができない情勢であろう。本当に難しい舵取りが求められる。
敢えて腹案を考えると、例えば、日本の自動車輸出に対して、無関税枠の50万台を認めてもらうのはどうだろうか。相互関税10%のラインは変更されなくても、別に無関税枠が認められれば、米国側は建前を変えずに済む。現在の輸出台数は138万台(2024年)なので、10%が残りの88万台にはかかってしまう。それでも関税の打撃を緩和することはできるだろう。
ほかには、90日の猶予期間をさらに個別品目ごとに延長するという手はある。企業が米国への工場進出を決めるのには、7月上旬までという期間はいかにも短かすぎる。実務的にそうした意思決定に時間がかかるので、自動車、鉄鋼・アルミ、半導体などは、猶予期間の延長を認めさせる。トランプ政権にとって、功を焦っているのは見え見えである。実体面で90日の猶予期間にこだわる合理性は全くない。直接投資を増やす計画は、もっと腰を据えて、米国側が進出企業に別途優遇措置を講じてくれるかどうかも、要求した方がよい。




