本記事は、金田 博之氏の著書『最高のリーダーは気づかせる 部下のポテンシャルを引き出すフレームワーク』(日本実業出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

社外の人との打ち合わせでもファシリテーションする
魅力的な営業担当者は「質問」がうまい
ファシリテーションというと、社内会議を円滑に進めるスキルと捉えがちですが、じつは、社外の顧客とのミーティングや商談での提案時にも非常に有用なスキルです。
私は重要な顧客に対してプレゼンをする機会が多い一方で、意思決定者として外部の営業やコンサルタントからプレゼンを受けることも頻繁にありました。魅力的な提案をしてくれる営業担当者やコンサルタントかどうかは、すぐに見極められます。それは、相手が自社の製品やサービスを「売りたい・伝えたい姿勢」で接してくるか、あるいはこちらの話を「真摯に聞く姿勢」を持っているかどうかで一目瞭然だからです。魅力的な提案をしてくれる相手は「質問」がとても上手です。
一般的なプレゼンテーションは、最初に自社紹介や自社製品・サービスの紹介から始まり、そのあとに提案へと進む流れが多いです。しかし、このプレゼンでは話し手がどれだけ話し方が上手でも、一方的な情報提供にすぎません。顧客の「目指す姿」と「現在の姿」について十分に理解していないと、提案や解決策(アクション)が的外れになってしまうことがあります。これでは、「我が社のことをよく理解してくれている」「この会社に任せたい」という信頼感を得て成約につなげることは難しいでしょう。
それに比べて、「ファシリテーション型」のプレゼンテーションを行う人は、一方的な情報提供ではなく、双方向の対話型で話を進めます。そのために事前準備の段階から相手企業の競合状況やIR資料などを徹底的にリサーチします。しかし、これらの情報は社外向けに発信されたものであり、必ずしも相手企業の社内で共有されているとは限りません。そのため、商談相手が企業の「目指す姿」と「現在の姿」をどこまで意識しているかを直接確認する必要があります。とくに経営陣や経営幹部、部長クラスのマネジャーたちは経営戦略を理解しているので、質問をすれば答えてくれることが多いでしょう。
トライアングルを描いてから提案する
商談を進めるうえで重要なのは、相手企業の「目指す姿」と「現在の姿」を理解し、そのギャップを埋める「アクション(手段)」として自社の商品やサービスを提案する視点です。つまり、「ギャップ分析のトライアングル」をここでも活用します。
まず、打ち合わせの「目的」と「アジェンダ」を明確に設定し、対話を通じて進めていきます。多くの打ち合わせでは、こうした目的やアジェンダの設定や説明(あるいはプレゼン資料での記載)がなく、自社紹介や自社製品・サービスの紹介から始まってしまうことが多いです。
顧客への質問と対話を通じて相手の「目指す姿」と「現在の姿」を把握したうえで自社が提供できる「解決策(アクション)」を提案します。具体的にはつぎの点を重視します。
- 顧客が「目指す姿」と「現在の姿」およびその「ギャップの原因」は何かを明確に示す
- 自社サービスを通じてどのように相手の課題を解決できるかの「全体像」を示す
- いつまでに、どのように計画を進めるかの「時間軸」を明確に示す
- それを実現するうえでの「投資対効果」を示す
- 次回の打ち合わせまでにフォローすべき「ネクストアクション」を示す
具体的なイメージを持っていただくために、私が実際に使用している資料のポイントを本書向けに一般化・簡略化してご紹介します。
① 本日の目的とアジェンダ
まず、本日の目的とアジェンダを明記したスライドを用意します。たとえば、「よりよい提案をするために、御社の現状と目標について意見交換をさせていただきたい」といった言葉で、あくまで「対話」を重視する姿勢を示します。顧客が考える目的や期待感とズレがないかを質問で確認します。
② 貴社のビジネスの理解
顧客は「相手が自社のビジネスをどこまで理解しているのか」に関心があります。そのため、IR資料や中期経営計画、新聞記事などから得た情報をもとに、「ビジョン」「重点施策」「現状と課題(仮説)」「自社が提供できる価値」といった項目を体系化した一枚のスライドを作成し、私たちが理解している内容の全体像を共有します。
このスライドはとくに重要で、これをもとに顧客に「質問」を投げかけ、情報を引き出していきます。顧客がこちらの理解を修正・補足してくれることもありますし、具体的な課題を議論することもできます。このプロセスによって、顧客のビジネスに対する解像度を高めることができます。
そのスライドのあとは、その内容に連動した解決策や自社サービスの説明、あるいは投資対効果へと続きます。
③ ネクストアクション
最後に、今後のスケジュールや支援体制、マイルストーンなどの具体的な計画を提示します。そして顧客が考える計画の時間軸や支援体制における期待を「質問」で把握します。ここまでのヒアリング内容に合わせて、提案内容を柔軟に議論しながら進めていきます。
このように顧客への質問を重ねることで、顧客と自社の目線が合致し、的外れな提案をして失敗することはありません。何より、「売り手と買い手」という関係性から、「共に価値を創造するパートナー」へと関係が深化し、顧客からの信頼も大きく向上します。
社内での打ち合わせだけでなく、顧客との打ち合わせでも、しっかりと質問をして、目線を合わせてファシリテーションしていくことを心がけましょう。そうすることで、一方的な提案をする他社とは一線を画し、顧客に真の価値を提供する提案ができます。
このように、プレゼンテーションに「ギャップ分析」と「ファシリテーション」を組み込めば、社外の人を相手にしても魅力的な提案ができるようになるのです。
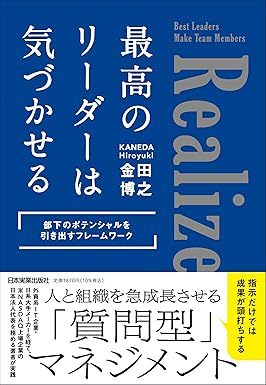
2014年、日本の大手製造・流通企業のミスミグループでGMとしてグローバル新規事業を推進した後、2018年に世界のAI・チャットサービスをリードする外資系IT企業のライブパーソン株式会社(米NASDAQ上場)」の代表取締役に就任。2020年12月、クラウド型ネットワークセキュリティ分野で10年連続グローバルリーダーに選出されているゼットスケーラー株式会社(米NASDAQ上場)にて日本法人の代表取締役に就任。
プライベートではセミナー、企業研修、大学などで講演し10年以上の講師経験を持つ。これまで10冊の書籍を出版。プレジデント、ダイヤモンド、東洋経済、日経ビジネスなどメディア掲載実績多数。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
