本記事は、水野 俊哉氏の著書『世界の一流が読んでいるビジネス書100冊』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

日本のシン富裕層
なぜ彼らは一代で巨万の富を築けたのか
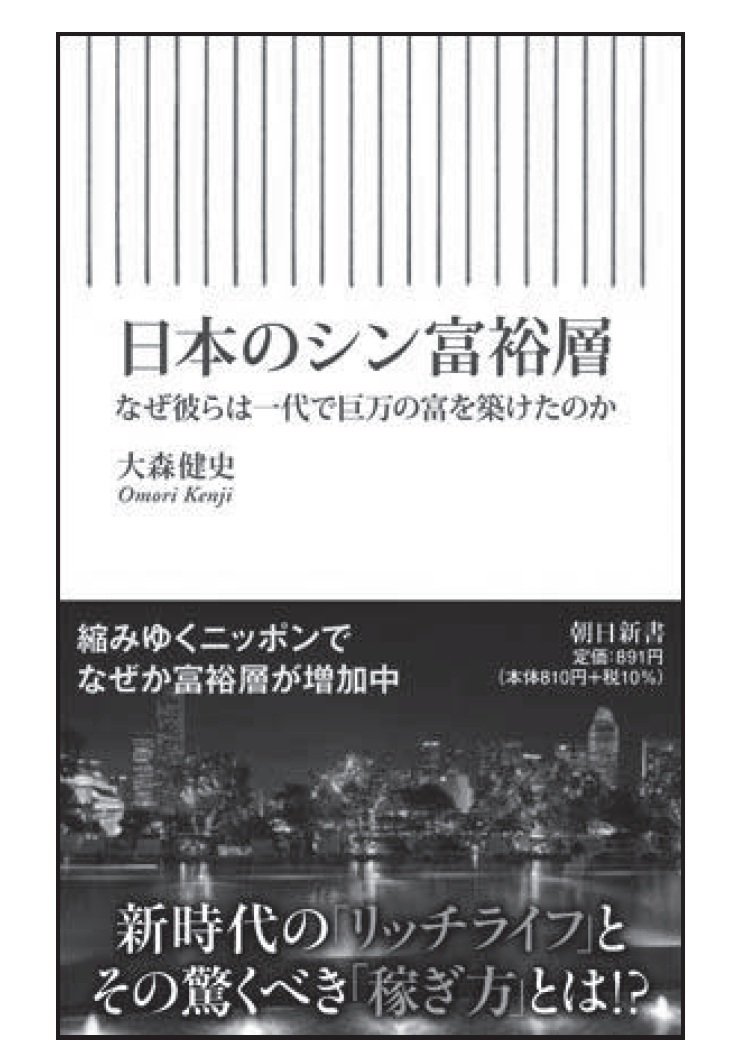
発売●2022年10月出版元●朝日新聞出版
普通の人が大化けする「シン富裕層」
親の代からの資産家こそが富裕層であるという常識は、2000年代を境に崩れ始めた。本書の著者・大森健史氏は、国際証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券)にて資産運用コンサルティング業務を経験した後、留学・旅行業界を経て2004年に海外移住やロングステイ支援を目的とした株式会社アエルワールドを設立。以来、2万人以上の顧客から海外移住や長期滞在に関する相談を受け、総投資相談額は66億円を超える。その豊富な知見から見えてきたのが、「普通の人が突然大化けする」新たな富裕層像である。
著者が注目するのは、ここ数年で台頭した“シン富裕層”と呼ばれる新タイプ の成功者たちだ。彼らは親が資産家だったわけでも、特別な家柄に生まれたわけでもない。むしろ、ごく普通の家庭出身者が、暗号資産、情報ビジネス、動画配信などを通じて、短期間で億単位の資産を築いている。
大森氏は、こうしたシン富裕層を5つのタイプに分類する。
1つ目は「ビジネスオーナー型」。自ら企業を立ち上げて富を築くが、一つの事業に固執はしない。複数の小さなビジネスを立ち上げて経営は任せつつ収益を分散的に得る“アメーバ経営”が特徴。不動産にも関心が高いが、単一の所有ではなく、事業の一部として機能させている。
2つ目は「資本投下型」。高収入の本業(医師・外資系社員など)で得た資金を、株式・不動産などに戦略的に投じ、資産を膨らませていく手法。自宅マンションの買い替えや、税制特例(居住用財産の3,000万円控除)を活用した資産拡大にも長けている。
3つ目は「ネット情報ビジネス型」。いわゆる“名もなきファーストペンギン”たちで、少人数で構築するマイクロビジネスを、情報収集と外注活用によって展開するのが特徴。オタク的なノウハウであっても、オンラインサロンや有料ノートなどを通じて収益化できるスキルを持っている。
4つ目が「暗号資産ドリーム型」。仮想通貨の急上昇で生まれた富裕層で、数億から数百億円単位の暗号資産を所有する者も存在する。共通するのは、高騰しても売らずに持ち続ける忍耐力である。独学の者とメンターを得て成長した者の両タイプがいる。
5つ目が「相続型」。本来の意味での資産継承者だが、近年は日本の将来に不信感を持ち、収入が不安定な現状を考え、資産分散を志向するケースが目立つ。
面白いのは、これらのタイプが固定的ではないことだ。仮想通貨で得た資金を不動産に投じて“資本投下型”に移行したり、投資から企業経営に移る例もある。つまり、“稼ぐ型”はあくまで入り口であり、その後の展開次第で資産形成のルートは多様に変化していく。
シン富裕層は何で稼いでいるのか?
また、大森氏が強調するのは、「シン富裕層の武器は情報」だという点である。
なかでも注目されているのが、「マイクロビジネス」としての情報ビジネス。たとえば、YouTube運営ノウハウ、暗号資産投資術、Instagramマーケティングなど、短期で収益化可能なスキルを教材化し、販売する手法が急拡大している。情報の陳腐化が早いため、半年〜1年でアップデートが必要だが、それもまた継続収入につながる仕組みになっている。
- 水野所感
- 富裕層の海外富裕層研究本としては、『となりの億万長者』や『日本のお金持ち研究』などに比べ、グッと時代が新しくなり、まさにシン富裕層の生態が学べる本だ。シン富裕層のタイプ分けも興味深いが、彼らがどうやって富裕層になったのか資産形成術は特に興味深い。著者の本業が富裕層の海外移住のサポートだけに、日本人におすすめの移住先やビザ取得の情報は特に詳しい。
スマホ脳
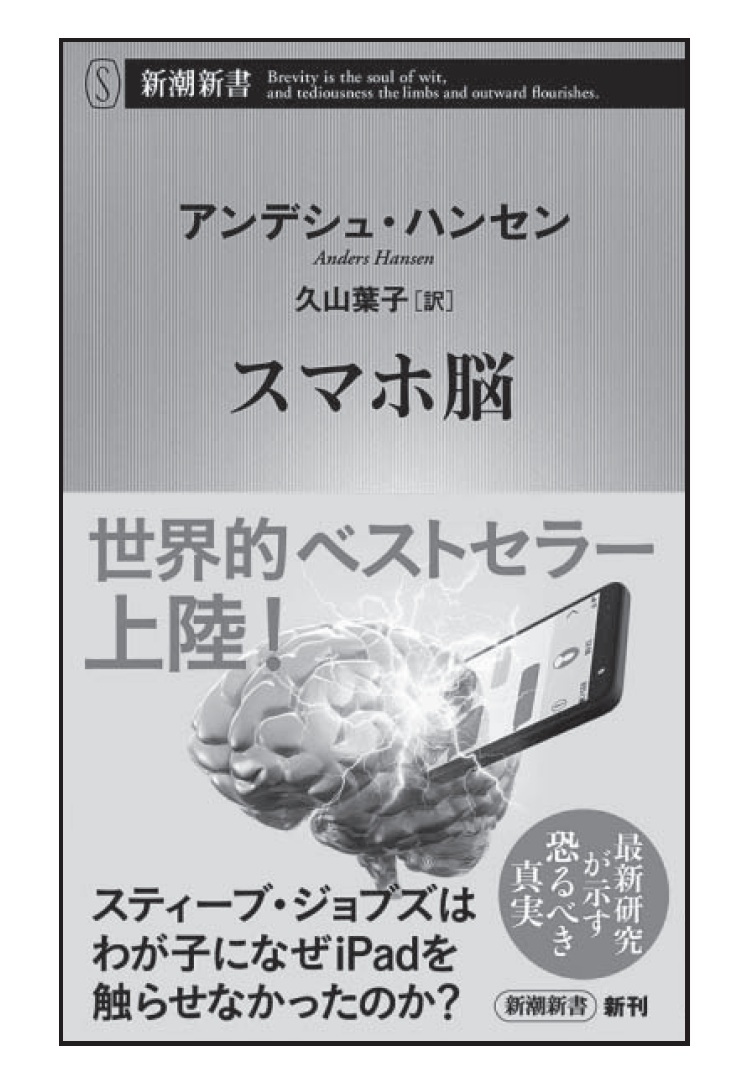
発売●2020年11月出版元●新潮社新潮新書
狩猟時代の構造の脳が情報化時代に適応できるのか?
スマートフォンがこれほどまでに生活の中心にある時代に、果たして僕たちの脳はついていけているのか? それが当書のテーマだ。
著者のアンデシュ・ハンセンは、精神科医でありながら、脳科学と進化心理学の両方の視点から、スマートフォンが脳に及ぼす影響を鋭く描き出す。その語り口は穏やかであるが、その内容はむしろ警鐘に近い。
「スマホは現代のドラッグである」 ―― この比喩は決して誇張ではない。私たちの脳では、通知音が鳴ったり、動画を見たり、SNSを扱うたびに脳内の報酬系が反応する。スマホには神経伝達物質ドーパミンを刺激する情報に溢れている。スマホを見るたびドーパミンが分泌され、さらなる“報酬”を期待し、より強い刺激を求めるようになる。私たちの脳はスマホを見ることで、一種の依存状態を引き起こしているのだ。
ここで重要なのは、「私たちの脳は、現代に最適化されていない」という事実だ。当書によると、脳の基本構造は数万年前の狩猟採集時代からほとんど変化していない。狩猟時代の飢餓や危険への対処のため、脳の報酬系は刺激に敏感に反応する。ところが、狩猟時代からいきなり24時間アクセス可能な情報洪水に晒されることになればどうなるのか。それが、現代人の集中力の低下、不安感を招くそして慢性的なストレスの根本的な原因であると分析する。
集中力の喪失が、生産性の喪失につながる
スマホを一度チェックするだけでも、脳は再び集中状態に戻るまでに長い時間を要する。つまり、スマホを“ながら見”しているだけで、深い思考は成立しない。これは創造性を要するビジネスパーソンにとって致命的な問題だ。
さらに、SNSの“いいね”や通知の仕組みは、まさに「人の注意を売るビジネスモデル」であると著者は断言する。人間の社会的承認欲求を巧みに刺激し、“つながっている感覚”を演出するが、それが裏目に出ると、自己評価の低下や比較による不安を招く。
実際、若年層を中心に、うつや不安障害の発症率がここ10年で急増している。当書では、スマホ利用の時間とメンタル不調の因果関係を示す多くのデータが紹介されており、単なるライフスタイルの問題ではなく、社会問題として取り組むべき段階にあることが明らかにされている。
では、どうすればスマホ脳から抜け出せるのか?
当書が提案するのはシンプルな処方箋である。睡眠時間を増やし、運動をし、スマホの利用時間を制限するというものだ。まずはスマホを見る時間を意識して減らしてみよう。たった1日で「脳の余白」が取り戻せた感覚があるはずだ。余白があることで、新しいアイデアや問題解決の糸口が生まれる。これは単なる精神論ではなく、脳の“ワーキングメモリの処理能力”の問題なのだ。
脳をスマホに適応させるためにもスマホを始めとするテクノロジーを正しく “管理する”力こそが、今後の人生の質を左右すると言ってもいいだろう。
- 水野所感
- 脳はドーパミン刺激に依存し、支配されやすい。この仕組みをアルゴリズム化して応用し、利用者数を増やしているのが巨大SNS企業である。今やIT企業はAI開発に全力で取り組んでいる。SNSとAI技術が一体化した際にそのプラットフォームであるスマホは人間脳の脳をハックして支配する。逃れたければ本書の警告に従うべきだし、スマホと一体化して身を任せてしまえば、もしかすると違ったユートピアが待っているのかもしれない。
なぜ働いていると本が読めなくなるのか
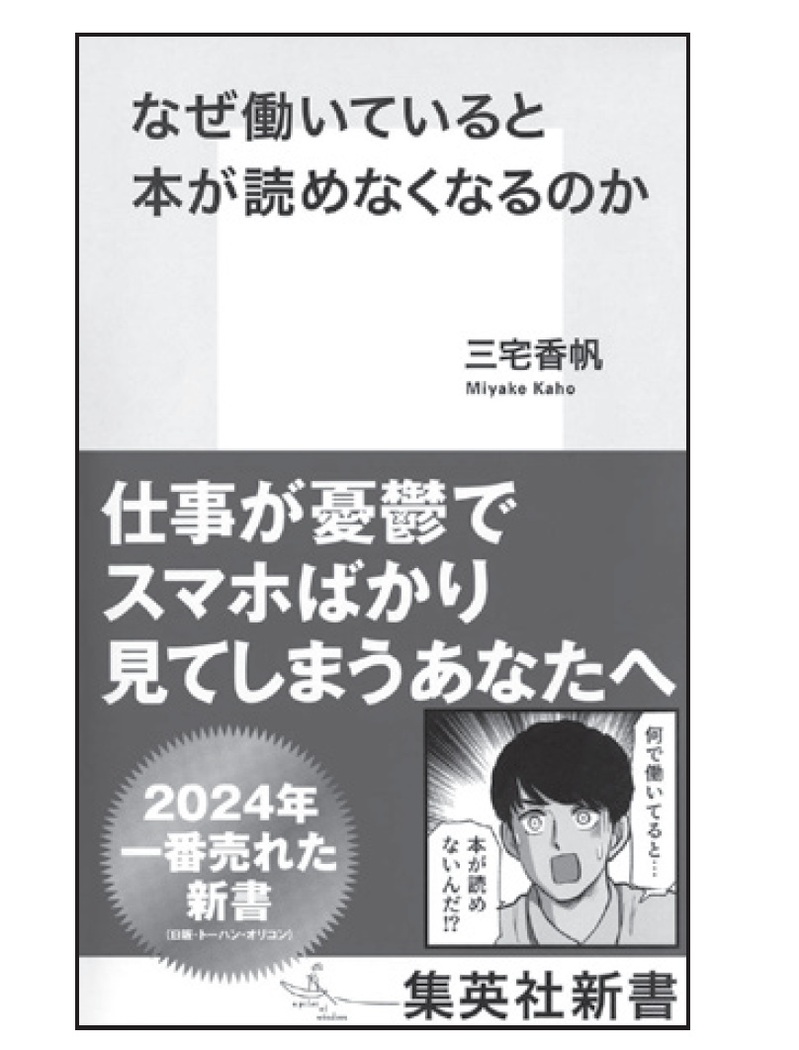
発売●2024年4月出版元●集英社集英社新書
好きな本を読むために働いたのに、働くと本が読めない
本が大好きで、「正直いって、たくさん本を買いたいから就職したようなも の」と語る著者。しかし、いざ社会人になってみると、「仕事をしていると本を読む時間がなくなる」という現実に直面したという。著者にとって本を読む時間は、人生にとって大切な「自分の時間」だった。その時間が、仕事によってすべて奪われるのが「普通」だとされているなら、それこそが異常なのではないか。
当書は、「仕事と趣味を両立できないのはなぜか?」という問いから始まり、日本人の働き方と読書の歴史をたどっていく。明治、大正、昭和、そして2000年、2010年代と、時代ごとのベストセラーを手がかりに、社会の変化を読み解いていく。普通に考えれば、長時間働いているから本を読む時間がなくなるのだと思うかもしれない。しかし著者によれば、明治のころから日本人はずっと長時間働いてきたのだという。つまり、読書離れの理由はそれだけではない。
実際、いくら忙しくても、スマホでゲームをしたり、SNSを見る時間はあるという人も多い。にもかかわらず「本だけが読めない」というのは、単純に「時間がない」だけでは説明できない現象なのである。
読書が「ノイズ」になる時代へ
著者は、1990年代に入ってから「読書ができない社会」へと変わっていったと考える。なぜなら、この頃から、本の売り上げ全体は減りはじめたが、自己啓発書だけは売れ続けている。これは「社会の中で成功するにはどうすればいいか」という関心が、「社会全体を知ること」から「自分をどう変えるか」へとシフトしたことを意味する。
つまり、以前の読書は「知識を得るため」だったのが、今の読書は「自分を改善するため」に変わった。必要ない情報や想像できない世界に触れるよりも、目的に合った“使える本”だけを求めるようになったのだ。
その結果、予測できない内容が書かれている物語やエッセイ、小説のような本は、「ノイズ」になってしまったのだ。
働きながら本を読むための6つのコツと「半身の働き方」
では、忙しくても読書の時間を確保するには、どうすればいいのか。著者はあとがきで、6つの工夫を紹介している。
- 自分と趣味が合いそうな読書アカウントをSNSでフォローする
- iPadを買う(電子書籍でスキマ時間を活用)
- 帰り道にカフェで読む習慣をつくる
- 書店に足を運ぶ
- 今まで読まなかったジャンルにも手を出してみる
- 無理をしない(疲れた日は読まなくてもOK)
そして、本を読むための時間を確保するために必要な考えは、「半身で働く」というシンプルかつ画期的な方法だ。「半身」とは、仕事とそれ以外のこと ―― 育児、趣味、読書 ―― に均等に時間やエネルギーを分散する働き方を指す。全身全霊で働くことが理想とされてきた昭和や平成の常識があったが、全身全霊を仕事に注いで疲弊した人間ほど、斬新なアイデアや創造的な成果から遠ざかってしまうことも少なくない。
- 水野所感
- 学生時代にはあった趣味や文化に耽った時間が、社会人になると「労働」のための時間に置き換えられていく。当たり前といえば当たり前なのだが、当時30歳の著者の等身大の目線が、読者のハートを掴んだ1冊。戦後から2020年代にいたるまでの本を読むという行為の歴史的な変遷を踏まえながらもその時々のベストセラー、世相も解説してくれている。ちなみに私のデビュー作の裏テーマは、「なぜ成功本を読めば読むほど貧乏になるのか?」であった。懐かしい……。
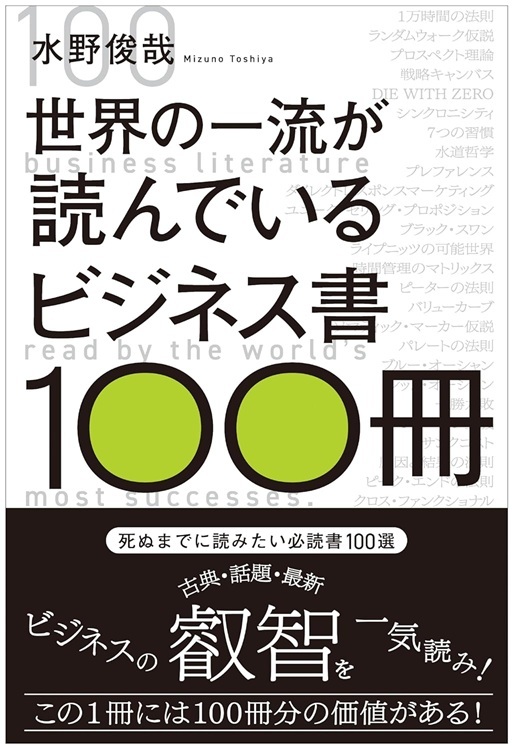
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
