本記事は、水野 俊哉氏の著書『世界の一流が読んでいるビジネス書100冊』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。
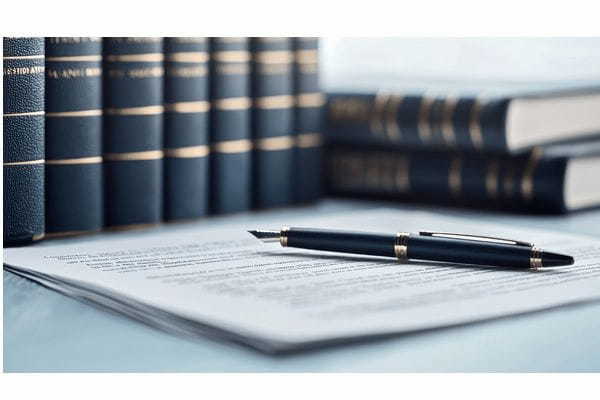
[新装版]ピーターの法則
創造的無能のすすめ
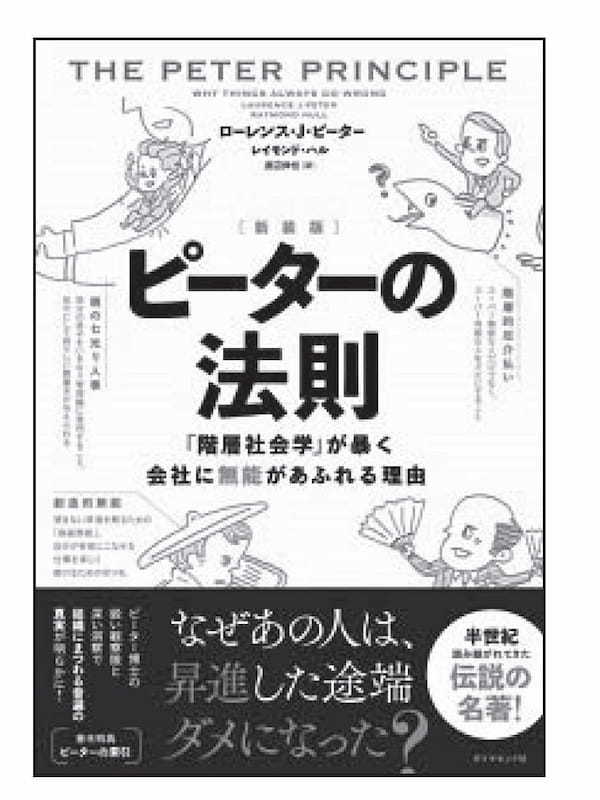
訳=渡辺伸也
発売●2018年3月出版元●ダイヤモンド社
ピーターの法則
ピーターの法則とは組織構成員の労働に関する社会学の法則であり、「階層社会では、すべての人は昇進を重ね、おのおのの無能レベルに到達する」とされている。当書の主張を要約すると、
「能力主義の階層社会に於いて、人間は能力の極限まで出世する。すると有能な平構成員も無能な中間管理職になる。 ―― 時が経つに連れて人間は
ピーターの必然
「ピーターの必然」とは、やがて、あらゆるポストは職責を果たせない無能な人間によって占められることを指している。また、仕事は、まだ無能レベルに達していない人間によって行われているという。
[有能なレベルから昇進し、その次のレベルでも有能でいられるケースも、一度や二度であれば、多くの人が経験しているかもしれません。しかし、新しい地位で有能と認められるということは、さらに次の昇進が待っているということです。
つまり、すべての個人にとって ―― あなたにとっても、私にとっても ―― 最後の最後の昇進は、有能レベルから無能レベルへの昇進となるわけです。もしも十分に時間があれば ―― そして組織に十分な階層があるなら ―― すべての個人は、その人なりの無能レベルに行きつくまで昇進し、その後はそこに留まり続けることになります]つまり、次の役職に昇進するほど有能ではないから、そこに留まるというわけだ。では、ごく一部の本当に優秀な人材であればどうなるか?
[通常の無能人間は、(中略)クビの対象にはなりません。たんに出世できないだけです。ところがスーパー有能人間は、解雇されてしまうことが少なくありません。なぜなら、スーパー有能人間は階級社会を崩壊させ、それゆえ、「階層は維持されなければならない」という「階層社会第一の掟」に違反するからです]
「無能」にならないためにはどうするか?
当書ではなぜ誰もが最終的に「無能」の域に達してしまうかを説いている。
[もしかすると、ここまで読んで、あなたにはピーターの法則が絶望の哲学のように思えてしまったでしょうか? 終点到達というのは、肉体的にも心理学的にも惨めな徴候を伴うし、職業人生の終わりを通告されるようなものだと尻ごみをしてしまったでしょうか? みなさんの心配はごもっともです]
とある。さまざまな事例を解説されていくうちに、階層社会で働いているビジネスパーソンは間違いなくこのような不安を抱くだろう。
しかし、著者はこの後に、[この哲学的難題をばっさり切って落とす強力なナイフを差し上げることにしましょう]と述べている。
「哲学的難題を切り落とすナイフ」がどのようなものであるかは、ぜひ本書を読んでいただきたい。
- 水野所感
- ピーターの法則は、階層が固定化された組織においては無敵の正しさを誇る法則である。学校、病院、会社、軍隊その他、組織と名がつくところではピーターの法則や必然から逃れるのは困難だ。ここから逃れるには、フリーランスになるしかない。しかし、最近は外資系金融機関のように、トップ総取りの「トーナメント制」も増えており、この場合、文字通り有能な人間だけが出世して巨額の報酬を受け取ることになる。一体、どちらがいいのか、難しいところだ。
ユニクロ
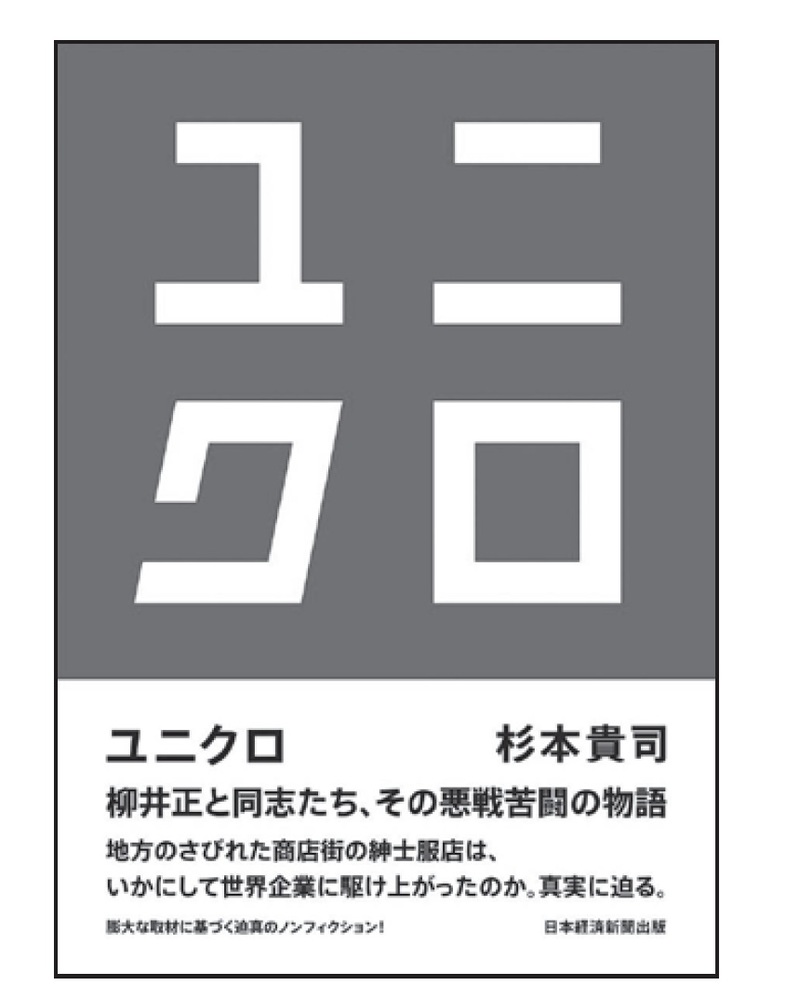
発売●2024年4月出版元●日本経済新聞出版
山口県の小さな紳士服店からの脱却
当書『ユニクロ』は、世界企業となったユニクロの軌跡を生き生きと描き出している点にある。物語は、山口県宇部市のローカルな紳士服店小郡商事から始まる。後継者であった柳井正は、店の将来に希望を持てず、新たな業態への変革を決断。1984年、広島に開店した1号店「ユニーク・クロージング・ウェアハウス」が、のちの「ユニクロ」となる。「いつでも誰でも好きな服を選べる巨大な倉庫」というコンセプトを実現した店は大成功を収めた。彼がユニクロを立ち上げたきっかけが、マクドナルド創業者のレイ・クロックの言葉だ。「勇敢に、誰よりも先に、人と違ったことを」。柳井はこの言葉を手帳に書き写し、その後、何度も読み直したという。
全国規模のフリースブーム
ユニクロが日本全国にインパクトを与えたのは、1998年のフリースブームだ。当時、フリースはユニクロでも主力商品で、年間80万点が売られていたという。性別や年代を超えて誰にでも着てもらえるユニクロらしさを代表する商品でもあった。また、他社なら1万円以上する商品を香港の工場を使うことで自社企画にして半額の格安で販売することに成功した。そこで、原宿店のオープンに合わせて、1階全てを色とりどりのフリースで並べるという奇策を思いついた柳井らはすぐに実行した。店内に入りきれないほどのお客が列をなして並び、むしり取るようにしてフリースを購入していった。大量に販売されたこの製品は、単なる流行で終わらず、ユニクロという存在そのものを“安くて良い”という言葉の代名詞に押し上げた。こうして自社で製品を企画し、製造し、店舗で売ることで、品質管理と価格競争力の両方を握ったユニクロは、日本のアパレル市場の構造自体を変えたのである。フリースブームは全国規模になり、2,600万枚を売り上げ原宿店オープンからわずか2年後には、売り上げ規模が4倍に膨れ上がった。
だが、成功の裏には当然苦悩がある。ブランド力を持って世界へ飛び出したユニクロだったが、最初の海外進出 ―― イギリス・アメリカ市場では大きな壁にぶつかる。現地の気候や文化、価格帯の感覚に対応しきれず、失敗も経験した。だが柳井は撤退ではなく、学習と修正を選んだ。この柔軟な経営判断が、のちのアジア圏での拡大戦略に結びつく。
グローバルブランドへ
2000年代以降、ユニクロは「単なるアパレル」から「情報製造小売業」への進化を模索する。顧客データ、購買履歴、SNSからのフィードバックを商品開発や供給計画に取り入れ、デジタルと物流を統合したインフラ構築を急速に進めた。これにより、全世界規模での需要予測が可能となり、「売れる商品を、売れる時に、売れる場所へ」届ける精度が飛躍的に向上した。
また当書では、ユニクロの企業文化 ―― 徹底した現場主義、言い訳を許さない成果主義、そして柳井の“有言実行”の哲学 ―― が描かれる。働く者にとっては苛烈とも言える環境であるが、それは「結果でしか評価しない」「変化を恐れるな」という強烈なメッセージの表れでもある。注目すべきは、ユニクロがグローバルブランドとして成長してからも、“日本発”の強みを一度も捨てなかったことだ。縫製、素材、機能性へのこだわり、そして清潔感ある接客文化は、どの国でもユニクロらしさとして浸透している。これは、日本的な品質と世界的スケールを両立させるための“標準化の美学”と言える。
- 水野所感
- 昭和40年代男の筆者(水野は原宿に突然できたユニクロがフリースブームで全国区になり、ファストファッションという言葉の意味が変わり、海外旅行でパリのオペラにユニクロができて驚いた世代だ。いわば自分の人生の節目にユニクロが姿を変えて現れ、今や生活の一部にすらなっているが、その裏側にここまでのドラマがあったのかと感嘆する。ユニクロの発展に人生を重ね合わせたくなった。
アイデアのつくり方
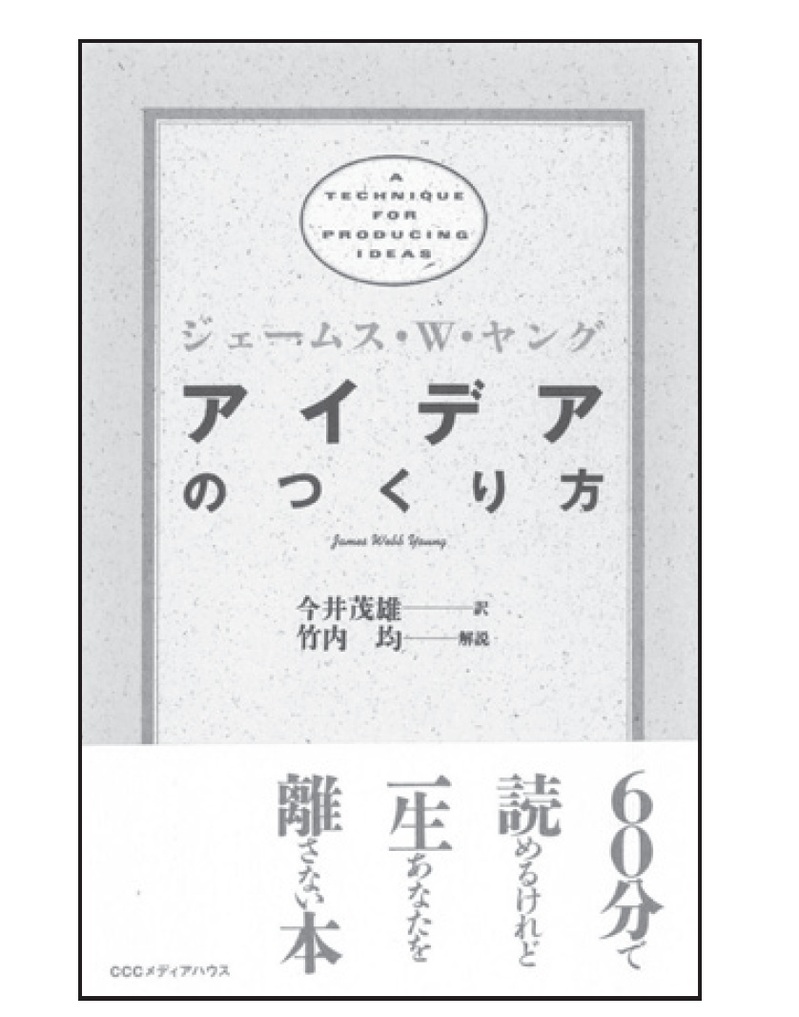
発売●1988年3月出版元●CEメディアハウス
アイデアは1つの新しい組み合わせである
ビジネスにおいてアイデアは重要だ。
新商品や新事業のプランニングにおいて、アイデアという目に見えないものを自由に生み出すことができれば、目覚ましい業績を上げることができる。
多くの人は、アイデアとは突然ひらめくものだと思っているだろう。しかし著者は、修練を積むことでアイデアを作り出しうる心を生み出せると説いている。
著者によると、アイデアとは、[既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない]と定義されている。例えるなら、それは珊瑚礁のようなものであり、突然出現したように見える環礁であっても、「実は無数の目に見えない珊瑚虫の仕業であるということを科学者たちは知っている」のである。
そして、アイデアを生み出す才能は、「事物の関連性を見つけ出す才能に依存するところが大きい」ため、ごく少数のアイデアマンと呼ばれる人達は、「新しい組み合わせの可能性に常に夢中になっている」タイプの人間なのだ。
アイデアを生み出す心の技術
ヤングによると、アイデアの作成に際して私たちの心は、[フォードの車が製造される方法とまったく同じ一定の明確な方法に従う]のだという。
別の言葉でいうと、アイデアの作成には明確な技術があり、アイデア作成には常にこの技術が意識的か無意識的かはともかく用いられている。その心の技術は以下の5つの段階を経過してはたらく。大切なのはこの5つの段階の関連性と、私たちの心はこの5段階を一定の順序で通り抜けるという事実を認識することなのだ。
第1 資料集め
集める資料は2種類。1つは特殊資料(アイデアの対象となる専門資料)。もう1つは一般的な知識に関する資料。これらはアイデアの「原料」だ。アイデアは、「製品と消費者に関する特殊知識と、人生とこの世の種々様々な出来事についての一般知識との新しい組み合わせから生まれてくる」ものであり、万華鏡がガラス片で幾通りもの模様を描くように、アイデアの破片となる知識の収集が大事なのだ。
第2 諸君の心の中でこれらの資料に手を加えること
この段階をヤングは「心の消化過程」であるとして、集めた資料を「消化しようとする食物をまず咀嚼するように」する段階だと述べている。部分的なアイデアが生まれた時にメモをとり、脳が疲れ果てるまで考えることが大事だとしている。
第3 羽化段階
もはや直接的にはなんの努力もしない。あえて意識を他に移し、音楽を聴いたり、映画を見たり、本を読んだりして構わないという段階。
第4 アイデアの実際上の誕生
[それは諸君がその到来をもっとも期待していない時 ―― ひげを剃っている時とか風呂に入っている時、あるいはもっと多く、朝まだ眼がすっかりさめきっていないうちに諸君を訪れてくる]とヤングは書いている。
第5 現実の有用性に合致させるための最終的にアイデアを具体化し、展開させる段階
企画書などにして人の目に触れさせることで、アイデアは自ら成長し始め、完成する。
- 水野所感
- 僕もこれまでアイデアに関する本を何十冊と読んできた。その中でも優れた部類に入る本はいっぱいあるし、これからも発売されるだろう。しかし、どんな優れたアイデア本だとしても、その本質はすでにヤングに書かれてしまっている。我々にできるのは細かいシチュエーションをつけ加えたり、道具や手法のアップデートをする程度だ。「60分で読めるけど一生あなたを離さない本」という帯のコピー文はまったく大げさなものではない。
【COLUMN】
学びの多いビジネス書、学びの少ないビジネス書
本を選ぶ場合、誰でもつまらない本、役に立たない本を摑みたくない、と思うものだろう。ビジネス書を読む最大の目的は、仕事や人生に役立つ知恵を手に入れることにある。だが実際は、読み終えても「得るものがなかった」と感じる本も少なくない。僕がこれまで読んできた中で、そうした“学びの少ないビジネス書”には、いくつかの共通点がある。
たとえば、「誰でも簡単に◯千万円儲かる」といった類の本。こうした本に限って、著者だけが儲かっているケースが多い。つまり、“お金持ちになる方法を書いた著者が、お金持ちになっただけ”という仕組みだ。さらに、本の内容が薄く、読者を高額セミナーや情報商材に誘導することを目的とした“フロント商品”タイプの本も散見される。無料CDや限定特典付きで購買意欲をあおるものの、実態は顧客リスト獲得が目的だったりする。
また、著者が自身のブランディングや店舗の宣伝だけを目的に書いたケースもある。こうした本に共通するのは、内容よりも話題性を優先している点で、読後に残るものが乏しいことだ。なぜこうした本が増えるのか。それは、ビジネス書の著者が出版時に“明確な目的”を持っているからだ。僕はこれを「ゴールセッティング」と呼んでいる。とはいえ、僕はこうも思っている。「読む価値がない本はあっても、買う価値がない本はない」。本との出会いは一期一会だ。内容が薄かったとしても、「こういう本は避けるべきだ」という“審美眼”を磨く経験になる。外れを知ってこそ、当たりの一冊に出会ったときの感動が際立つ。読書とは、知識の収集だけでなく、“選ぶ力”を養うプロセスでもあるのだ。
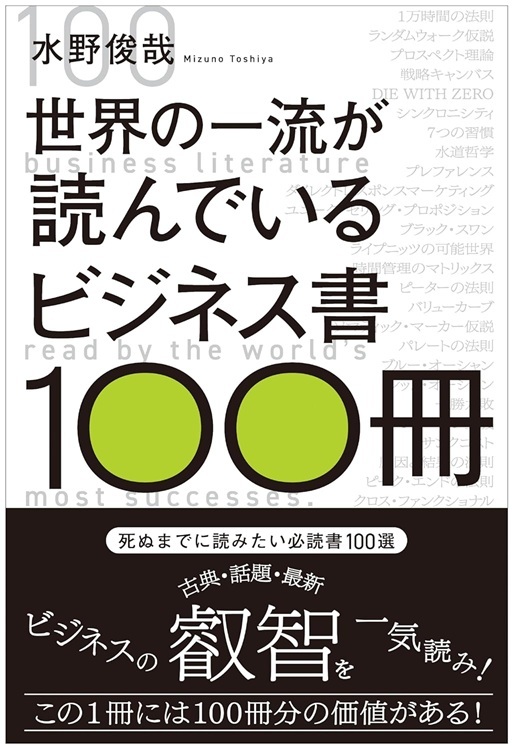
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
