本記事は、水野 俊哉氏の著書『世界の一流が読んでいるビジネス書100冊』(総合法令出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

わが投資術
市場は誰に微笑むか
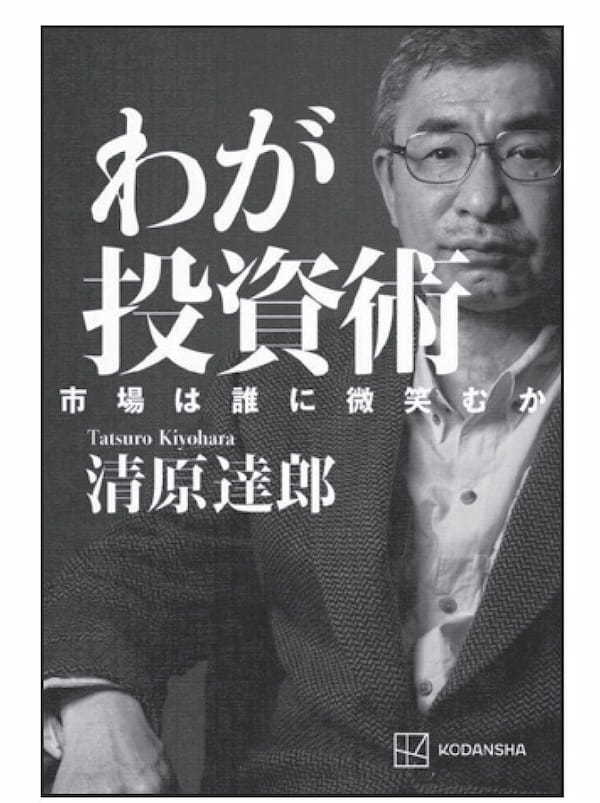
発売●2024年3月出版元●講談社
市場は学習する者に微笑む
当書は、個人資産800億円超、長者番付1位という実績をもつ清原達郎氏による初の著書である。2023年、咽頭がんにより声帯を摘出し、引退を決めたタイミングで執筆された当書には、「全ノウハウをぶちまけてしまえ」という強い意志が込められている。
冒頭から貫かれているのは、「市場は才能に報いるのではなく、学習する者に微笑む」という哲学である。清原氏は、長期的に市場で勝ち続けるには、失敗を糧にし、常に自分の過去を見直す姿勢が不可欠であると説く。
清原氏はもともと野村證券に新卒で入社したが、証券会社の仕組みに強い違和感を覚え、外資系運用会社を経てヘッジファンド「K1ファンド」を創設する。
ここでの運用成績が高く評価され、「日本最強の個人投資家」と称されるまでになった。こうした経緯が当書では淡々と語られる。
特に第2章のヘッジファンドへの長い道のりという著者のキャリア形成のくだりも、面白い。高値づかみをして損をする個人投資家のパターンを会社員時代の具体的な事例とともに紹介したり、当時の上司となったSBIホールディングスのCEOである北尾吉孝氏との思い出、中東のバーレーン支店で日本株をアラブ人に売る話など実践的な投資にも役立つ話がたくさん盛り込まれている。
投資対象としては、一貫して「日本の割安小型株」に焦点が当てられている。とくにPBR(株価純資産倍率)やPER(株価収益率)といった指標を鵜呑みにせず、業界のイメージや市場からの過小評価を逆手に取る手法を重視している。清原氏は、人気のない銘柄こそ宝の山だと断言し、ESG銘柄や未公開株投資には手を出すべきでないと明確に述べている。
投資のカギはネットキャッシュ比率
例えば、清原氏はその株式の価値を調べるために、PBRではなく、ネットキャッシュ比率こそ分析するべきだと示唆する。なぜならPBRには、市場で売ることができないその会社のガラクタ資産も含まれているからだ。
[見るべきは会社が赤字になろうがなるまいが同じ値段で売れる資産がどれほどあるかということです。それに会社が持っている現金を足して全負債を差し引いた数字がキーなのです。それがネットキャッシュです]
清原氏は、ネットキャッシュ比率を次のように導き出している。
①ネットキャッシュ=流動資産+投資有価証券×70%-負債
②ネットキャッシュ比率=ネットキャッシュ/時価総額
=(流動資産+投資有価証券×70%-負債/時価総額)
[ネットキャッシュ比率が1というのは、「会社がただで変えるほど割安」ということです。数字が大きいほど割安ということになります]
さらに、情報との向き合い方についても鋭い見解が示されている。清原氏は 「高価な情報にはバイアスがかかっており、むしろ無料でアクセスできる開示情報の方が信用できる」と語る。つまり、情報の質よりも、情報をどう扱い、どう判断するかが投資家の真価を分けるというのである。
- 水野所感
- 個人資産800億円強。長者番付1位にもなったことのある清原達郎氏が自身のトラックレコード、ネットキャッシュ比率を重視する投資法を語る。従来のというか、ほとんどの投資、金融本の著者は評論家の類いか個人投資家だが、プロのファンドマネージャーが実名、顔出しで書いている部分が画期的である。トータルでは大儲けしている清原氏だが、勝率はさほど高くない点も投資の本質というか相場の厳しさを感じさせてくれる。投資家である前に、学び続ける人間であれ――それが清原氏の最終講義である。
経済は感情で動く
はじめての行動経済学
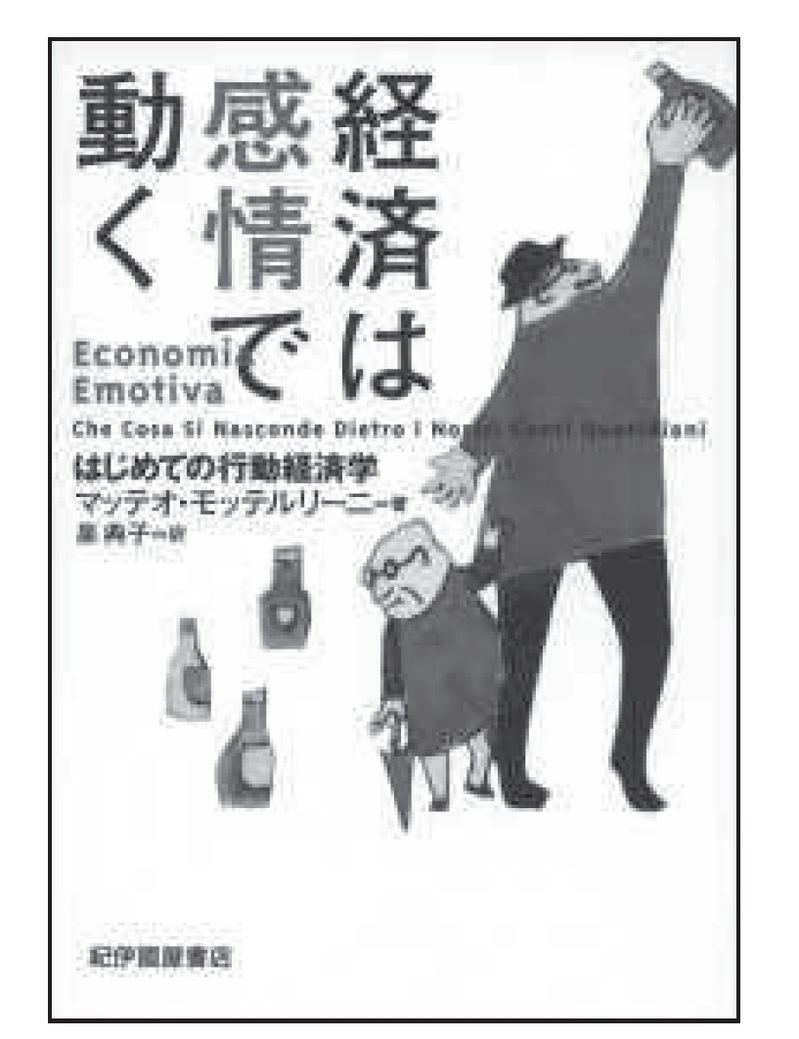
発売●2008年4月出版元●紀伊國屋書店
はじめての行動経済学
行動経済学の開祖と呼ばれるダニエル・カーネマンは、長年の共同研究者である、エイモス・トベルスキーと発表した「プロスペクト理論」の功績により、ノーベル経済学賞を受賞した(トベルスキーは死去)。
プロスペクト理論の重要な部分である有名な「価値関数」が示しているのは、我々が経済活動やギャンブルで得した時の感情よりも、損をした時の感情の方が2倍以上も強いということであった。
当書は、「プロスペクト理論」、「フレーミング効果」、「アンカリング」、「サンクコストの過大視」、「ピーク・エンドの法則」、「ソマティック・マーカー仮説」など、行動経済学や神経経済学の用語をわかりやすく学ぶことができる。
我々がどんな風にして、非合理な決定をしてしまうのか?
そのメカニズムがわかれば、「ビジネスマンとしても、生活者としてもお金に対して賢くつきあえる」はずである。
クイズ形式で行動経済学、神経経済学がわかる
当書が秀逸なのは解説の仕方であろう。なにせ、すべてクイズ形式になっている。たとえば、フレーミング効果の設問を見てみる。
A 3万円が確実に儲かる。
B 15万円が儲かる確率が25%で、まったく儲からない確率が75%。
あなたはAかB、どちらがいいですか?(答えを出してから次へ行ってくだ さい)
今度は次のなかから選んでください。
C 10万円を確実に損をする。
D 15万円を損する確率が75%、損失ゼロの確率が25%。
さてどちらにしますか?
これは期待値で計算すると前者と後者は同じことを聞いているので、Aを選んだ人はCを選ぶのが従来の経済学の考え方では「正しい」とされている。
しかし、実際にはフレーミング効果により、AとDを選択する人が多い。
これは得をするクイズだと確実な方を選び、損するタイズでは一か八かの選択肢を選ぶ傾向(損失回避性)の解説にもなっている。
ヒューリスティックとバイアス
行動経済学でいうヒューリスティックというのは、判断の傾向のことである。
またバイアスとは、その偏り方のことだ。
つまり、我々の判断は合理的ではないが、その偏りには一定の傾向が認められているということなのである。
当書では、「利用可能性」「代表性」「後知恵」など様々な思考のバイアスが登場し、欄外で丁寧に解説されている。
このような思考のバイアスは、誰もが知らず知らずのうちにおちいっている。
逆に言えば、知っておけば回避もできるだろう。ビジネスに役立つ知識が身につき、知的好奇心も満たされるコストパフォーマンスの高い1冊だ。
- 水野所感
- ダニエル・カーネマンは、ノーベル経済学賞を受賞した初めての心理学者だ。経済も人間の営みである以上、従来の経済学が規定するような合理的なモデルでは説明不可能なのかもしれない。当書で解説される有名な行動経済学や神経経済学の法則の数々は、思わず「あるある!」と膝を打ってしまうケースが多い。続編の『世界は感情で動く』や、ダン・アリエリーの『予想どおりに不合理』と併せて読んでみて欲しい。
経営中毒
社長はつらい、だから楽しい
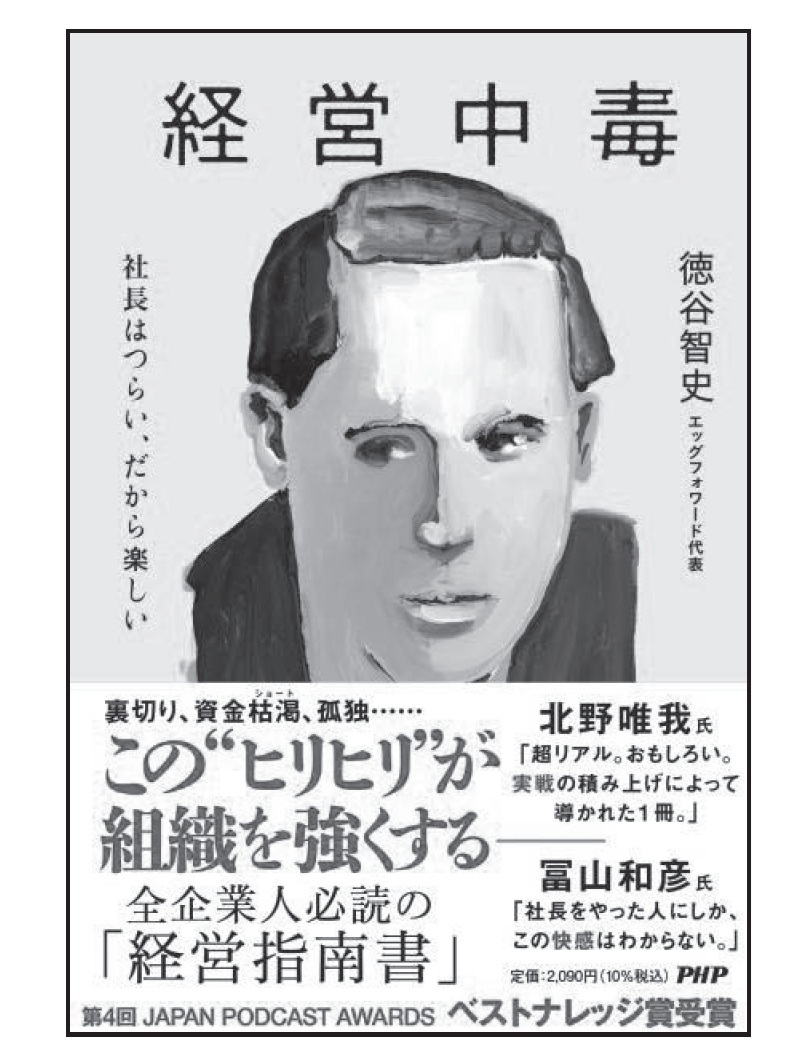
発売●2024年2月出版元●PHP研究所
経営のリアリティを疑似体験できる
社長という響きに人は華やかさと成功のイメージを重ねがちだ。だが当書は、その幻想を一気に崩し、経営のリアルを私たちに突きつける。[書店には、自身のサクセスストーリーを語った社長の本が所狭しと並んでいるが、私自身の経験と大企業からベンチャーまで数々の企業を支援してきた立場から、会社の経営はそんなに甘くはないと言わざるをえません。]と著者本人が語っているように、会社を起業して社長になると想定しなかった誤算が次から次へと起こる。一例を挙げるなら、「自信を持ってリリースした事業が大コケした」、「創業メンバー同士の考えが合わず、仲間割れの末、メンバーが辞めていった」、「資金が枯渇し、給料も外注費も支払えなくなった」、「資金が枯渇し、給料も外注費も支払えなくなった」、「アテにしていた資金調達が環境の変化で受けられなくなった」、「信頼していたメンバーの横領が発覚した」、「引き際を見極められず、事業の撤退を余儀なくされた」などがある。
しかし、こうした問題は[起きる原因を知っておけば、予期せぬ事態が起こっても冷静に対処できる、]と著者は言う。「経営の大変さ」と「稀にある喜び」を疑似体験してもらい、不測の問題が起きても問題に対処できるように「羅針盤」として当書を活用してもらいたいとする。
つらいからこそ楽しさを感じられる
資金繰りや資金調達に悩んでいるとすれば、第1章から読む。例えば、なぜ現金が足りなくなるのか? 1つは、単純に帳簿上に売上や費用が計上されるタイミングと、実際に入金されるタイミングが異なるためです。
だいたい創業初期はカネのマネジメントが計画通りいかず「残念な現実に直 面」するケースが多い。一方で会社の舵取りをすべき社長が資金繰りに奔走すると事業が推進できず、成長は必ず止まってしまう。会社のカネを正確に把握するには、損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を見る。全部見ないといけないと言うことの意味に経営して初めて気づくなど資金繰りに奔走しない方法を提案してくれる。
意思決定に自信がない場合は、第6章から読むべきだろう。「撤退」の判断こそ経営の醍醐味だ、と書かれているように会社の経営が傾くのは、「撤退の遅れ」と著者は指摘する。[出血しているのをわかっているのに放置して、出血多量になってもはや手遅れのケースです。「もう少し早く意思決定できていれば……」そう悔しい気持ちになることも少なくありません。]
経営者はポジティブマインドを持っている人が少なくない。そういう経営者は、「可能性がゼロでない以上諦めたくない」「みんなの努力を無駄にしたくない」という前向きな先延ばしによって経営そのものが傾く可能性があるとも著者は語る。
こうした感情のブレに惑わされないためにも撤退のガイドラインが必要だと著者は提案する。
経営には悩みがつきものだ。しかし、誰かが社長の身代わりになって同じ立場で悩んでくれる人はいない。だからこそ、悩みや孤独がついて回ることになる。
著者は、だからこそ、社長にしか見えない世界があり、社長にしか享受できない喜びややりがいもあるとしている。「社長はつらい、だから楽しい」という中毒とも言える、経営の醍醐味を疑似体験できる一冊だ。
- 水野所感
- 現実はハードモードの経営者RPGではないか。
全経営者が涙したというキャッチコピーをつけたいほどリアルな本。徹頭徹尾、経営者のための本に思えるのだが、会社員にも役にたつ部分がありそうだ。個人的には「社長はツライ、でも楽しい」という著者の言葉を噛み締めたい。これを読んで、経営者って楽しそうと思えたら変態、いや経営者の資質がある。逆にこんなに大変なのかと思うのであれば社長などならず会社員のままがいい。
ハーバードの人生を変える授業
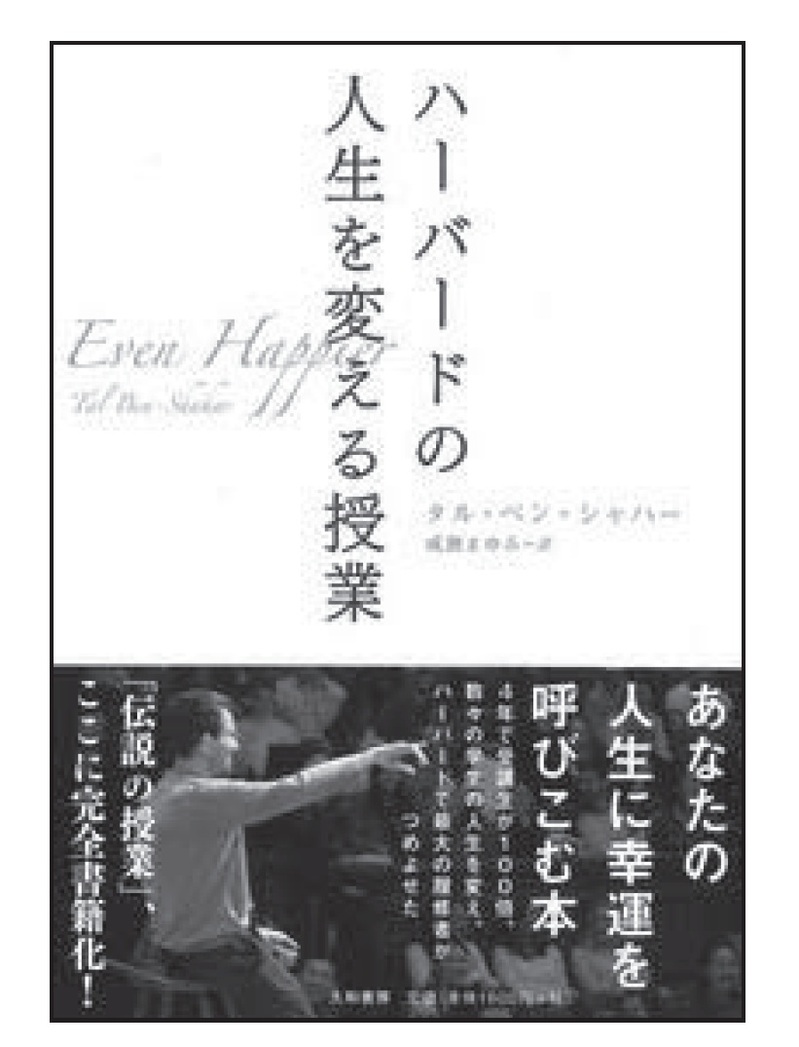
発売●2010年11月出版元●大和書房
幸せになる習慣「運動する」
ポジティブ・サイコロジーとは元アメリカ心理学会会長のマーティン・セリグマンがスタートした学問で、タル・ベン・シャハーはこの「幸せに関する研究」の第一人者である。
当書の魅力は、世界最高学府ハーバード大学でのシャハーの授業が全52講の 形式でまとめられ、それぞれアクション・プランが提示されている部分にある。
その内容は「習慣化する」「運動する」「最高の瞬間をつかむ」「完璧主義を手放す」など、一見、よくある自己啓発書に書かれていることばかりだが科学的な裏付けがある。たとえば「運動する」の項では、[「1日30分の運動をすることは、抗うつ剤を服用するのと同じような効果がある」「自己評価や思考力、免疫力を高める。寿命を伸ばす、よりより睡眠が保たれる、よりよい性生活を行えるといった副次的効果がある」]としてデューク大学やハーバード大学医学部の研究結果が紹介されている。
ハピネスブースター
なぜ、ポジティブサイコロジーが注目されているのかといえば、人生の究極の目標が幸せになることだからだろう。「幸福の国」と呼ばれるブータンへの注目度が高まっているように、今、先進国では国民1人当たりの所得額やGNPよりも、「国民幸福度」とでもいうべき指標を重視する方向になりつつある。シャハーも[富でも名声でもなく、幸せこそが人生の価値を決める究極の通貨である]と説いている。とはいえ、現実的な話をいえば給料を貰えなければ家賃も子供の教育費も払えない。マイホームのローンのために嫌な仕事でも辞めることができない人も多い。
そういった時、生活の中に「ハピネスブースター」を取り入れると日々の幸福感はアップする。
「ハピネスブースター」とは、ちょっとした運動、恋人や妻との会話、好きなラーメンを食べるなど「短期間でできる何らかの意義や楽しみのある活動」のことである。
幸せという究極の通貨
ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンは「富と幸福の関連性は低い」ことを発見した。わかりやすくいうと[収入が人生の満足度に与える影響度は一時的なものに過ぎない]し、驚くべきことに[いったん物質的な富を手に入れると、それを手に入れようと奮闘していたときに比べて精神的に落ち込んでしまう人]すらいるのだ。
これがいわゆる燃え尽き症候群である。会社や職場の競争に勝とうと奮闘している時はまだいいが、もしも最終的な目標に辿り着いた時に、物質的な富では幸せになれないことに気づくと、人生の目標すら失いかねない。
シャハーの講義がもっとも恵まれているはずのハーバードで強く支持されている理由がわかるのではないか。
ハーバードの学生は世界でトップレベルのエリート街道を歩んでいる。しかし、競争社会の勝者であることと、本人が幸福感、満足感を覚えているかはまた別の問題なのだ。
- 水野所感
- 僕はよく、若い読者に「人生において大切なことは、競争に打ち勝つことでも大金持ちになることでもない」ということを話すのだが、「それは一度でも大金を得たことのある人間だから言えるのではないですか」などと言われてしまう。僕はIPOを目指していた経営者時代もその後の負債3億円の借金地獄も両方を経験して、「幸せと収入の額はあまり関係ないよ」ということを身をもって経験したのだが、やはりハーバードの授業で説明してくれると異様な説得力がある。
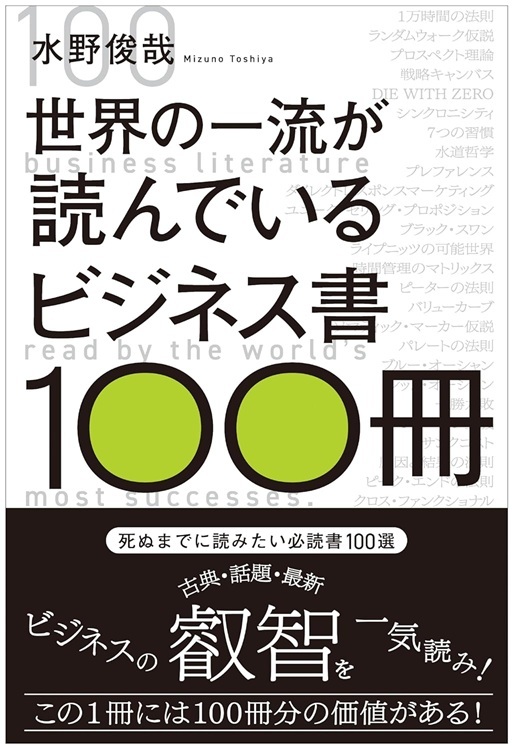
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
