本記事は、宮本 剛志氏の著書『なぜパワハラは起こるのか:職場のパワハラをなくすための方法』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

私も実はパワハラをしていたのかも!?
パワハラは「怒鳴る」「暴力を振るう」「名誉毀損」等、刑事・民事事件になるようなわかりやすいものだけではないのです。
「あれ? 私、これよくやっているかも!」
と思う人もいるかもしれません。実はパワハラの多くは“日常的な言葉や態度の延長線上”にあるのです。
パワハラかどうかを見極めるための「3つのポイント」
「宮本さん、私のやっていることって、ギリ、パワハラではないですよね?」
と自分の行為を正当化したい気持ち、パワハラと言われてしまうのではないかという不安な気持ちから質問される方がいます。私は
「ギリギリを狙わないでくださいね」
と伝えています。なぜなら、パワハラにならないからといって、良いコミュニケーションとは限らないからです。パワハラは最低最悪の人間関係のことです。パワハラに当たらなかったとしても不適切な言動であれば、それは改善する必要があるのです。とはいえ、
職場で起きたやり取りがパワハラに当たるかどうか──
それは気になることだと思います。
冒頭でもご紹介した、いわゆるパワハラ防止法が示す定義の3要素(※4)で判断することになります。
※4 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
〈3要素〉
①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
①~③のすべてに当てはまるものがパワハラとなります。
読んでみてどうでしょうか? なんとなくイメージできるかもしれませんが、「で、つまりどういうこと?」、そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
また、定義には、3要素それぞれについて細かい但し書きがあります。それをそのまま理解しようとすると、途端にわかりにくくなってしまいます。結果として、さらに混乱し、「いったい、自分の言動がパワハラかどうかどうやって判断すればいいのか?」と悩んでしまいます。もちろん、役員・人事・総務・ハラスメント相談担当者は、3要素それぞれの具体的な但し書きも含めて理解する必要があります。
色々と例外はありますが、法律用語はややわかりづらいので、理解しやすいように、パワハラ判断の基準になる考え方をもう少しわかりやすく解説します。次の3つのポイントがすべて当てはまる場合は、ほぼパワハラでしょう。
3つのポイント
①パワーのある関係
上司だけが加害者? 部下・同僚も加害者になるの!?
3要素の第1の要素、「優越的な関係」とはわかりやすく言えば、「パワーのある関係」のことです。
パワハラは「力の差」がある関係で起きることが大前提です。
力の差には、「上司と部下の関係」だけが対象と思われがちですが、実際はそうではありません。
パワーのある関係とは様々です。しかし、「様々」だとよくわからないので、上司と部下以外に次の3つの関係をおさえておきましょう。
「上司と部下」以外のパワーのある関係
- 「経験が豊富な人とそうではない人」の関係
- 「専門性が高い人とそうではない人」の関係
- 「複数人と少人数」の関係
ですから、
- 業務経験が豊富な年上の部下が、異動してきたばかりのまだ経験が浅い年下の上司をあからさまに攻撃している。
- 高い専門知識を持つベテランが、専門知識が低い中途採用の新人に圧をかけ続ける。
- チームの価値観と違う価値観を持っているAさんをチームのメンバー全員で無視している。
等、こうした場面すべてで、「パワーのある関係」は成立します。
つまり、“パワーのある側”に立った瞬間、誰もが加害者になりうるということです。
②自分の権限を超えたことをやってしまう
「部下の性格を変えてやる!」と思っていない?
3要素の第2の要素、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とはわかりやすく言えば、「自分の権限を超えたことをやってしまう」ということです。
例えば、部下がミスをした時に、次のように伝えるとします。
「この件は、マニュアルを確認して、次は対策を立ててみて。困ったら一緒に考えよう」
これは、適切な指導です。業務上の行為であり、上司としての権限の範囲内です。
一方で、
「お前ってさ、本当にどうしようもねぇなぁ! この程度のミスで落ち込むなんて弱い奴だな。その弱気な性格だとうちの会社では使いものにならねぇぞ」
これは、パワハラになる可能性がある指導と言えるでしょう。
なぜなら、社長にも部長にも課長にもリーダーにも、相手の性格や人格を変える権限はないからです。つまり、権限の範囲を超えているのです。
例えば、人事要件上、課長の権限に「部下の性格・人格を変える指導をする」と明記されているでしょうか。そんな会社はありませんね。
「~ができるような指導をする」等、部下の言動・振る舞いを変えることは求められていると思います。
しかし、加害者からこのように言われることがよくあります。
「若い時に先輩が私の性格を変えてくれたおかげで、成果を出すことができるようになった。だから私も恩返しのために、部下の性格を変えてやりたい」
加害者は自分の成功体験をもとに部下や後輩に接しやすいのです。指導の結果として、性格が変わったり人生観が変わることはあります。それは、結果論なだけです。
つまり、業務上与えられている権限の範囲を超えて相手の価値や存在を否定するような言葉になると、パワハラと判断されやすくなります。
不毛な論争を行いがちな加害者
性格や人格の論争をすること自体が非生産的で、職場では不毛です。
例えば、部下が特に理由もなく書類を期日までに提出しなかったとします。
上司「提出が遅れるなんて、やる気がないんだよ」
部下「やる気はありますよ。それは~」
上司「言い訳するな! お前のやっていることは、やる気があるとは言えないんだよ」
部下「そんなことありません! やる気はありますよ」
不毛な会話だということがわかってもらえると思います。私はそんな上司には「やる気があれば、期日までに提出しないでもいいのですか?」と聞きます。そうすると、「いや、それは期日までに出さないといけないです」と言われます。「やる気ではなく、期日までに提出する必要性について改めて伝え、遅れる時にはどうするのか? 振る舞いについて注意する必要がありますね」と伝えるとわかってもらえます。
③繰り返し・継続的にやってしまう
1回ではパワハラにならない?
3要素の第3の要素、「労働者の就業環境が害されるもの」とは言いかえると、「身体的もしくは、精神的苦痛を与えるもの」のことです。
「それって、人によって感じ方は違うのではないでしょうか?」
こんな疑問を持つ人もいるでしょう。その通りですね。良い悪いは別にして、例えば、「アホか!」と言われても、「いつものことだ」と思う人もいれば、とてもショックを受ける人もいると思います。また、相手がパワハラと感じたらパワハラになるわけではありません。第三者が客観的に判断します。ですから、繰り返し・継続的に行われると、平均的・客観的に見て、多くの人は就業環境が悪化したと感じるだろうということになるのです。もちろん、例外はたくさんあります。しかし、基礎的なこととしておさえておきましょう。
例えば、
- 何度も何度も嫌がらせを受けた。
- あの件でも、この件でも威圧行為を受けた。
- 2時間も、3時間も「新入社員以下かよ」とネチネチと怒られた。
- 「昔から使えなかったよな」「2年前にも小学校からやり直せと言ったよな」「このあいだの件でも足引っ張ったよな」と昔のことまでずっと言われ続ける。
等が当たるかもしれません。
もちろん、1回ならばいいということではありません。1回でもこんなことを言われれば、関係性はとても悪くなります。パワハラの基準とより良いコミュニケーションの基準は全く違うからです。しかし、繰り返し・継続的に言われ続ければ、多くの人は精神的にも辛いという判断になるということです。また、権限の範囲を超えたこととも言えるでしょう。ただし、殴る、蹴る等の暴力は1回でもアウトです。当たり前ですね。
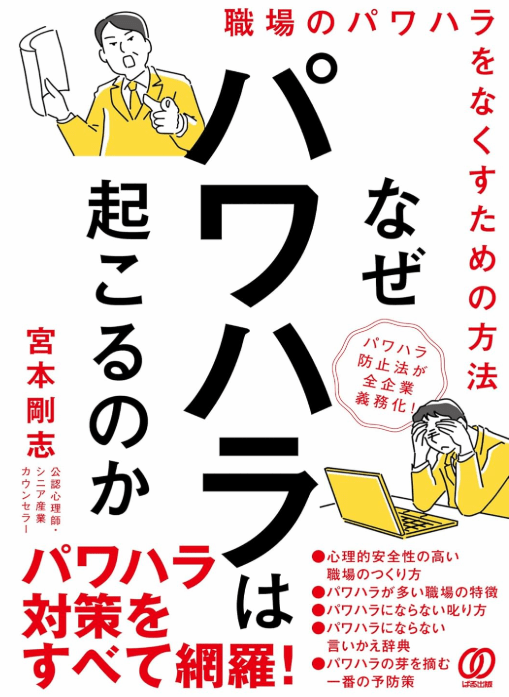
管理職を経験し部下との関わり方に悩んだことをきっかけに、ハラスメントについて学び始めた。
その後、ハラスメント・メンタルヘルス対策を通してより良い職場づくりの支援を行うために起業。
現在は、心理学にもとづく研修やハラスメント被害者・加害者の面談を行う。企業のハラスメント対策委員会外部委員や顧問を務める。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
