本記事は、宮本 剛志氏の著書『なぜパワハラは起こるのか:職場のパワハラをなくすための方法』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

パワハラを生む「認知バイアス」
なぜパワハラが生まれるのでしょうか? 様々な要因があります。例えば、無自覚にパワハラを容認してしまう会社の文化、過去の成功体験、知識不足、コミュニケーション不足等です。それに加えて、どうしてもおさえておきたいことがあります。
それは、「認知バイアス」です。認知バイアスとは簡単に言うと、自分の経験や価値観・考え方に基づいた偏った見方であり、無意識に持っているクセのようなもののことです。誰でもあると言われています。自分の認知バイアスに気づかないまま、行き過ぎると、差別、勘違い、間違い、人間関係のストレス、そしてパワハラにつながることがあります。
大切なことは、自分の認知バイアスを自覚し、決めつけないことです。また、日頃から「もしかして認知バイアスが働いているかもしれない」と、自分で自分に投げかける習慣をつけることをおススメします。
認知バイアスは何気ない日常でもあります。例えば、朝起きてカーテンを開けたところ、雨が降っていたとします。パッと思い浮かぶことは何ですか?
「雨に濡れると嫌だなぁ」「靴が汚れるかも…不安だ」「テレワークにしたいな」等の気持ちが浮かぶ人、「傘を持っていこう」「自転車が使えないから早めに家を出よう」等の対策を考える人、「この雲行きだと午後には晴れるな」等と未来のことを予想する人、様々です。
また、同じ気持ちでもネガティブな気持ちだけではなく、ポジティブな気持ちになる人もいます。例えば、「(花粉症の人)雨だから花粉の心配はなくよかったな」「水やりしなくてよくて嬉しい」「水不足で実家の田畑が心配だったけれどホッとした」等です。
つまり、同じ出来事が起きたとしても、人によって思うこと、感じること、考えることが違うのです。そこには「認知のクセ」もありそうです。認知のクセは、出来事を見るメガネのようなものです。
多くの認知のクセがあり、諸説ありますが、私は次の5つの認知バイアスはパワハラにつながりやすいと感じています。
①確証バイアス
〈概要〉 経験等から、ある結論や物語を作り上げてしまい、その結論や物語に沿った証拠や出来事ばかりを集め、その結論や物語を強化する偏見のことです。
〈例〉 次長が「Aさんは事務作業は苦手なはずである」と思うと、Aさんが事務作業で上手くいかなかったことばかりに目が行き、「いつもできないよね!」「絶対ミスするよね!」と全否定してしまうことがあります。Aさんが事務作業でミスした場面を次長は見たのだと思います。そして頭の中に「Aさんは事務作業が苦手なはずだ」とインプットされてしまい、Aさんができていない時のことばかり目に留まり、耳に入るようになってしまったのかもしれません。思い込みで、「いつもダメだ」と全否定し、「使えない」「この程度の事務作業ができないやつは降格させる」と言って「精神的な攻撃」に発展しないように気をつけましょう。
②合意推測バイアス
〈概要〉 自分の考えや行動・価値観は、世の中の一般的な常識であり、当たり前のことであると思い込んでしまう偏見のことです。
〈例〉 新人の教育係になったBさん(20代後半)が担当する、新人のCさん(30代後半)は同業他社から転職してきました。Bさんは、自分が入社当初にできるようになった仕事について、同業他社から来た30代後半のCさんであれば、当たり前にできることだと思い、「普通、こんなことできますよね。教えなくてもいいですよね」と言ってしまいました。BさんはCさんに気を使ったつもりなのですが、それ以来Cさんは質問しづらくなってしまい、困っても我慢していました。ある日、Cさんが仕事上のミスをしました。その際にBさんは、「え? こんなの常識ですよね? なんでできないんですか!?」と自分が教えなかったことを棚に上げて、何度も何度も繰り返し指摘し続けてしまいました。教えてもいないことを指摘し続けることは、「過大な要求」になりかねない行為と言えそうです。
③正常性バイアス
〈概要〉 いつもと違う状態や危険に遭遇した時、ある程度までは正常な範囲であると思い込み、平然と過ごし安心したい偏見のことです。
〈例〉 店長のAさんは、アルバイトのBさん(大学1年生)が少し元気がない様子を見ても、「まぁ、誰にでもあることだろう」と思い声をかけませんでした。翌日、Bさんの先輩のCさん(大学3年生)が、Bさんに対し「お前、そんななよなよして、ゲイかよ」と笑いながら頭を叩いていました。Bさんも苦笑いしていました。店長のAさんは「大学生ののりだろう。まぁ大丈夫だろう」と全く対策を取りませんでした。Aさんが見て見ぬふりした結果、Cさんは、Bさんのスマホを勝手に触る等行動がエスカレートし、Bさんは適応障害で退職しました。Cさんの親が、お店の本部に苦情を申し出て大きな問題になりました。
店長が見ていたCさんの振る舞い自体もパワハラ(精神的な攻撃・身体的な攻撃・個の侵害)に該当する可能性があるにもかかわらず、「まぁこれぐらい大丈夫だろう」と見て見ぬふりをした結果、Cさんのパワハラがエスカレートしてしまいました。パワハラは、上司と部下だけに起きることではありません。部下や後輩、同僚の「いつもと違う」サインを見つけた際には、声をかけて早めに介入するようにしましょう。
④紋切型バイアス
〈概要〉 性別、年齢(世代)、職業、出身、人種、容姿等、限られた部分からその人を単純化する偏見のことです。典型的なパワハラになりやすいバイアスです。
〈例〉
・営業成績が振るわないAさんに対してベテランリーダーが、「男なんだから、もっと頑張れ!」と何度も激励のつもりで言いました。
・昭和世代のBさんが職場で導入したAIの使い方に苦労している様子を見て、若手のCさんが、「昭和のおじさん、おばさんは私たちの足を引っ張らないで(笑)」とバカにし続けた。
・東南アジア圏から来たDさんが遅刻したことに対して、「Dさん、ここは日本だよ。東南アジアの人は時間を守らないよね」等、外国籍であることをたびたび持ち出して批判していた。
いずれも、個人ではなく、性別・世代・人種をもとにした偏見と言えるでしょう。そのような大枠で人を判断するのではなく、「○○さんは~」と個人を対象に伝えましょう。
⑤行為者・観察者バイアス
〈概要〉 他人の行動や結果についての原因は他人の内面にあると思い込み、自分の行動や結果についての原因は自分の外側にあると思い込む偏見のことです。私は「最も信頼関係を失うバイアスである」と言っています。
〈例〉 部下が目標を達成できなかった時に、課長補佐は部下に対して「あなたのやる気がなかったから達成できなかったんだよ」と内面を責めてしまいました。ところが、翌月は課長補佐が自分の目標を達成することができませんでした。その際、職場の懇親会でお酒を飲みながら、「そもそも今月は部長の目標設定の仕方が悪いんだよ」「業界的には今厳しいのに、経営陣がわかっていないからいけないんだよ」と自分の責任には触れず、外的要因についてばかり愚痴を言っていました。
先月責められた部下は、「もう二度と課長補佐を信用するか!」と心に決めたそうです。そもそもの信頼関係を失えば、パワハラではないちょっとしたことでも不信感から通報されてしまう可能性もあります。また、信頼関係ができていなければチームも上手く回らず、無理やり思い通りに部下を「動かそう」と思ってパワハラ発言をしてしまうかもしれません。また、性格、人格に触れないように心がけないとパワハラに発展することがあります。
部下のことでも上司自身のことでも、外的要因と内的要因を冷静に分析すれば、的確に今後の対策を取ることができ、パワハラに発展することはないでしょう。
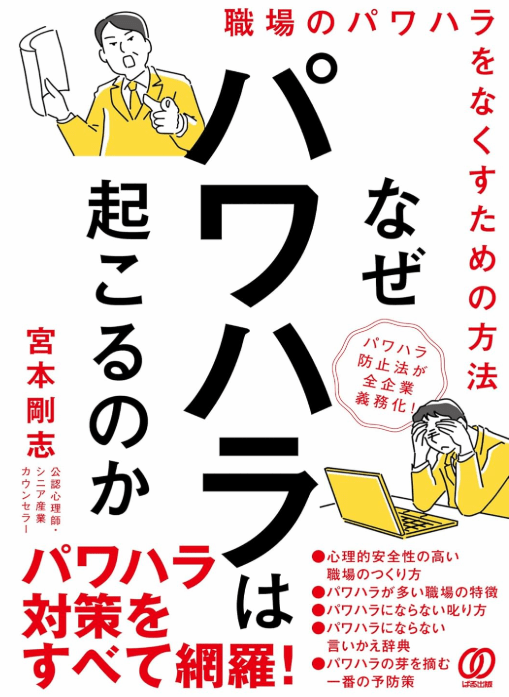
管理職を経験し部下との関わり方に悩んだことをきっかけに、ハラスメントについて学び始めた。
その後、ハラスメント・メンタルヘルス対策を通してより良い職場づくりの支援を行うために起業。
現在は、心理学にもとづく研修やハラスメント被害者・加害者の面談を行う。企業のハラスメント対策委員会外部委員や顧問を務める。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
