本記事は、宮本 剛志氏の著書『なぜパワハラは起こるのか:職場のパワハラをなくすための方法』(ぱる出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

叱らないのもリスク!
実は叱らないこともパワハラ防止の観点からリスクがあるのです。ミスやトラブルの改善につながらないからです。例えば、部下がミスをしたとします。放置していれば、どんどん問題が大きくなります。そして大きな事故等につながった際に、「何やっているんだ!バカか!」「もうやめちまえ!」と我慢していたことを爆発させてしまうかもしれません。
つまり「精神的な攻撃」につながる可能性があるのです。また、ミスがあった時に指導しなければ、部下は「知りませんでした」「教えてもらっていない」と言い訳をし、責任を自覚することができなくなってしまいます。また、放置して責任だけ取らせようとする行為は、「過大な要求」と言えるかもしれません。そのため、早めに叱ることも必要でしょう。
叱るの目的「行動変容」とは?
叱る目的は「行動変容」です。行動変容には2種類あります。
①ミスの改善
ー →0 に戻すイメージです。
②成長
0→+ または、より+にするイメージです。
②は意外に感じる人もいるかもしれません。例えば、部下のAさんは5年目です。Aさんの仕事ぶりは何の問題もありません。任せておけば自己完結してくれます。評価も高いです。しかし、上司はAさんに、後輩のBさんやCさんの様子を確認し、必要な時にはアドバイスができる人になってほしいと思っていました。
つまり、成長してもらいたいと思っていました。叱ることは行動変容を目的としているので、決してマイナスを改善してもらう時のためだけではないのです。Aさんのように更に成長してほしい時に使う手段でもあるのです。
上司はAさんをこのように「叱り」ました。「Aさんにはいつも安心して仕事を任せられるよ。Aさん自身の仕事は何も問題ない。ただ、Aさんにはもっと成長を期待したい。そこで、後輩のBさんやCさんの様子を見てアドバイスをしてもらいたい」と伝えます。0や+から、より+に成長してほしい時の「叱る」は「期待を伝える」に近いでしょう。行動変容の2つの側面を意識して、上手な叱り方を身につけていきましょう。
「叱る」と「怒る」の違い
よくある質問が、叱ると怒るの違いです。これまで紹介してきたように、叱るは未来に向けて相手の行動変容を促進する行為です。目的は行動変容です。そのため、感情的ではなく、具体的で未来に焦点を当てなければ相手に伝わりません。
一方、怒るは感情的な行為です。そのため、相手は怒っている人を見て「怖い」「感情的な人なので話しづらい」という印象を持ちます。そうなれば、行動変容にはつながらないでしょう。少なくても主体的に行動変容しようという気持ちにはならないでしょう。また、感情的になってしまうとパワハラのリスクが高まります。多くのパワハラ加害者は感情的になってしまい、相手を深く傷つけてしまっています。
では、どうやってイライラした感情をコントロールすればいいのでしょうか。
イライラ感情をコントロールする
どんなに上手な「セリフ」で相手に伝えたとしても、イライラした様子を醸し出しながら伝えてしまえば、相手に伝わりません。イライラ感情、ムカッとした時の怒りの感情をどのようにコントロールするのか? たくさんの方法が世の中にはあり、紹介するだけでも1冊の本ができあがるくらいです。本書では、パワハラにならないための方法に絞って紹介します。様々な研究・見解がありますが、一番大切なことは自分に合った方法を探すことです。ぜひ職場で実際にやってみて、自分に一番合う方法を見つけてください。
イライラ感情の生まれる仕組みと種類
そもそもイライラ感情、怒りは自身の「勝手な」期待がきっかけで生まれる感情です。ですから、誰かに鎮めてもらうのではなく、自分でなんとかするしかないのです。勝手な期待がきっかけとなり、怒りは扁桃体から生まれます。よく「怒りの感情をコントロールする」と言いますが、実は怒りを含めた感情には2種類あるのです。
□情動(エモーション)
□気分(ムード)
情動(エモーション)とは、強い感情ですが、長続きしないものと言われています。例えば、カッとなる、イラッとする等が当たるかもしれません。カッとなって、つい暴言を吐いてしまう、人格を否定してしまうような「精神的な攻撃」、書類を投げつけてしまうような「身体的な攻撃」、そんなパワハラにつながることがあります。そのため、まずは情動のコントロールが重要です。
気分(ムード)とは、弱い感情ですが、長続きするものと言われています。例えば、ムカムカ、なんだかモヤモヤとしている等が当たるかもしれません。なんか嫌い、なんか気に食わないと思い、相手を無視するような「人間関係からの切り離し」、そんなパワハラにつながることがあります。
マイナスの気分を抱えていても何の問題解決にもならないという認識を持つことから始めましょう。あなたは、どちらのタイプの感情が課題ですか? 情動か気分かによっても対策が変わってくるのです。しかし、必須は情動のコントロールです。なぜなら、パワハラはイラッとした時にやってしまう言動が多いからです。
では、どんなコントロールがあるのでしょうか? 今回は3つご紹介します。いずれもすぐできることです。時間がかかること、深く考えないとできないことは現実的ではありません。職場ですぐできることから始めましょう。
① 口角を上げてコントロール
イライラした時こそ、口角を上げるのです。表情と心はつながっていると言われます(表情フィードバック仮説)。諸説ありますが、相談を受けた際に紹介すると、「パワハラ防止に役立った」と言われることが多い方法です。最近イライラしたことを思い出してみてください。その上で、3秒でいいので口角を上げてみましょう。どうですか? 少しだけ身体から力が抜ける感じ、少しだけ心が軽くなる感じがしませんか?
イライラして高揚している感じから抜け出せる感覚を持てるかもしれません。逆に、眉間にシワを寄せてじっと本を見てください。なんだかムカムカしてきませんか? いやぁ~な気持ちになるかもしれません。つまり、表情と心はつながっているのです。イライラ感情が生み出された時こそ、口角を上げて情動を鎮めたいですね。
②「呼吸して」コントロール
TBSテレビの人気番組『SASUKE』で、よく参加者同士が「呼吸して」と声をかけ合っています。緊張感や高揚感を落ち着かせ、いつもの自分を取り戻すためなのではないかと思います。イライラ感情が起きるような場面に遭遇したら、自分も『SASUKE』の参加者だと思い、自分で自分に「呼吸して」と投げかけてあげましょう。
5秒吸って10秒吐く
これで十分だと思います。人によって多少違うと思いますので、それは自身に合わせてください。せめて、吐くだけでもやってみましょう。イライラしていた自分からいつもの自分を取り戻し、『SASUKE』のように乗り越えていくでしょう。
③ 筋弛緩コントロール
漸進的筋弛緩法を参考にしたコントロール法です。簡単に言うと、心と身体はつながっているという考え方に基づいています。身体に力を入れた後、緩和します。つまり、あえて力を入れて、力を抜く方法です。その結果、身体がリラックス→心がリラックスとなるのです。カッとなる、イライラしている時には身体に力が入っている状態です。
心を落ち着かせると言っても、心は見えないものなので扱うのが難しいと思います。そこで、目に見える身体を使います。3つの方法をご紹介しますが、私は3つ全部やることをおススメします。ただし、職場で全てやることは難しい時があるので、1つでいいのでイライラした時にやってみましょう。5秒力を入れて、5秒力を抜きましょう。そして、力を抜いた部位に意識を向けてみましょう。「じわじわする」「力が抜ける感覚がする」ことによってリラックスできるかもしれません。
ステップ1:手に力を入れる(グーにする)→力を抜き、手に意識を向ける
ステップ2:腕をたたんで胸に付くように力を入れる→力を抜き、腕に意識を向ける
ステップ3:肩が耳に付くように力を入れる→力を抜き、肩に意識を向ける
どうですか? いずれもすぐできそうですよね。パワハラ加害者になって後悔する前に練習してみましょう。
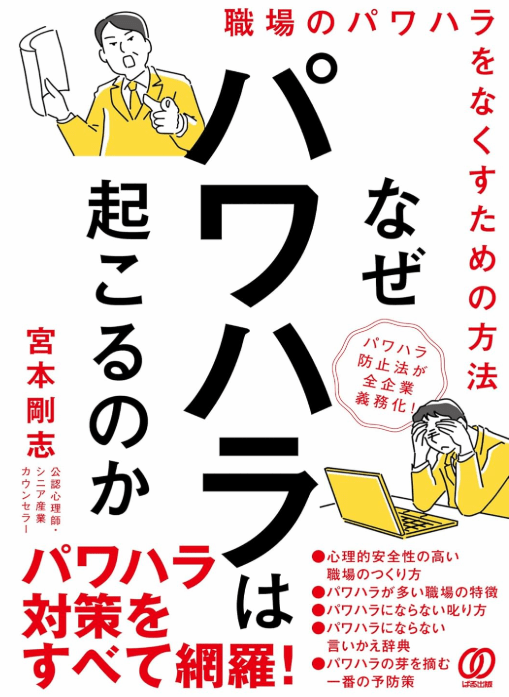
管理職を経験し部下との関わり方に悩んだことをきっかけに、ハラスメントについて学び始めた。
その後、ハラスメント・メンタルヘルス対策を通してより良い職場づくりの支援を行うために起業。
現在は、心理学にもとづく研修やハラスメント被害者・加害者の面談を行う。企業のハラスメント対策委員会外部委員や顧問を務める。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
