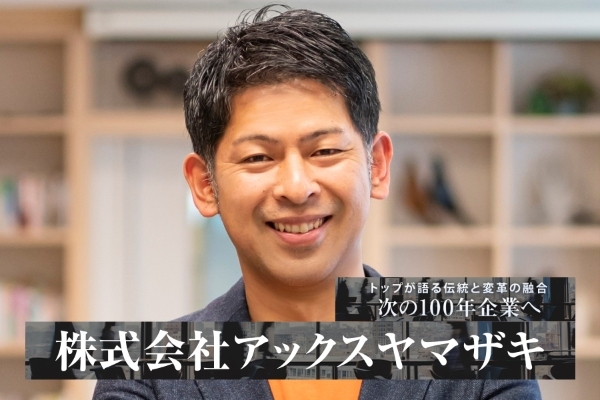
かつて「一家に一台」と言われるほど、どの家庭にもあったミシン。しかし今ではその数は減り、家庭用ミシン市場が縮小の一途をたどっている。しかし、株式会社アックスヤマザキは、三代目社長・山﨑一史氏のリーダーシップのもと、従来のミシンメーカーの常識を覆し、「子供のミシン離れ」や「子育て世代の負担」といった社会課題に寄り添うニッチな製品を開発。さらには、男性用や「脳トレにも役立つ」とのデータを得て、シニア用ミシンも開発し、赤字寸前の危機からV字回復を遂げている。
ファブレス経営とEC戦略を駆使し、ミシンに縁遠かった層を顧客として取り込み、新たな市場を創造する同社の変革の軌跡と展望について聞いた。
企業サイト:https://www.axeyamazaki.co.jp/
背水の陣で臨んだ事業承継とV字回復
── 創業から事業承継、そして現在までの事業の変遷を教えてください。
山﨑氏(以下、敬称略) 1946年に祖父が山﨑ミシン製作所を創業し、国内生産・海外販売を行っていました。従業員も増え、小規模ながら順調に推移していましたが、1980年代に入ると、大手メーカーとの競争激化や、急激な円高により、赤字に転落し、債務超過に陥りました。
その後、父の代になり、ビジネスモデルを海外生産・国内販売へと大きく転換しました。OEMを主体とし、他社ブランド向けに小型でかわいらしいミシンを製造。これにより、倒産寸前だった会社は債務超過から無事回復しました。1999年頃までは順調でしたが、主要なOEM取引先が事業を止めたことで、売り上げが急落しました。私は2005年に家業に入社し、2015年に代表に就任しました。
── そこから輸入型に変わったのですね。
山﨑 そのとおりです。その時に輸入型へと転換しました。祖父の代は海外販売が主だったため、国内での知名度はまったくありませんでした。そのため、世界的な大手ブランドを含む他社ブランドのOEMを当社が受託生産していました。
父の代でOEM事業を進めましたが、その後、主要なOEM取引先が事業解散するなどして、当社の売り上げも急激に落ち込みました。輸入型ビジネスモデルは継続しましたが、私の代になるまでは、父の代のビジネスモデル、つまりOEM主体で事業を行っていました。
しかし、OEM受注も激減し、売り上げは減少の一途をたどりました。会社自体も低収益で、価格競争も激しく、きわめて厳しい状況でした。
私が2015年に代表に就任してからは、社会性や独自性のある、他にはない、社会の役に立つミシンを開発する考えになりました。
たとえば、子供用、子育て用、シニア用など、さまざまなターゲット層に特化しました。単に「ミシンはいかがですか?」と提案するのではなく、子供が小学校でミシンを習い、苦手意識を持つことでミシン離れが起こるという社会課題を解決するため、小学校で習う前に楽しく遊んで得意になれるような、子供用のおもちゃミシンを開発しました。これが私が最初に手掛けた、社会課題を解決し、独自性のあるミシンです。
── 知育玩具のような、教育的な側面もあるのですね。
山﨑 教育的な思いはありますが、販売先は玩具店です。主におもちゃルートを開拓しました。子供たちに広めるには、やはり玩具市場、おもちゃ売り場に置いてもらうのが一番だと考えたからです。
これまで取引のなかった玩具ルートを新規開拓し、おもちゃ売り場での展開を目指しました。初めて発売したのは2015年10月ですが、2ヵ月で2万台を製造しました。これが2ヵ月で完売し、初めてのヒット商品となり、電話が鳴りやまないほどでした。これが2015年に私が代表に就任した直後の出来事です。
代表就任時は、既に1億円規模の赤字になる見込みで、きわめて厳しい状況での事業承継でした。私は就任時に、「翌年には必ず黒字にする。それができなければ、社長失格」と、背水の陣に立ったつもりで、社長交代式で全社員に宣言しました。翌年黒字化できなければ社長失格であり、私ではない別の人が経営を担うべきだと考えていました。
その後、3年前から開発していた子供用の毛糸ミシンが、その年に「これはいけるかもしれない」という手応えを感じ、10月の発売までこぎつけました。それが大ヒットしたのです。翌年には無事黒字化を達成し、小さなV字回復を果たすことができました。
ミシンで脳トレ?実証データが裏付け
── 次に、これまでぶつかってきた課題と、それをどのように変革し乗り越えてきたかを教えてください。
山﨑 国内の家庭用ミシン市場はどんどん縮小し、昔は一家に一台あったものが、市場が縮小していく中で、当社はOEM主体だったこともあり、知名度もありませんでした。
そこで私は、まず自分に能力をつけるためグロービスというビジネススクールに通いました。業界変革のヒントをつかむという具体的な目標を持って入学しました。これ以外にも経営塾など、いろいろな学びの場に参加し、自分の能力不足を補うために、学び、気づきを得るようにしました。
知名度がないという点については、「ミシンです、アックスヤマザキです」と言っても誰も振り向いてくれないので、視点を内向きではなく外向き、つまり社会課題や誰かの役に立つという相手目線に変えました。
この視点転換によって、開発したミシンは、たとえば子供が学校でミシンを苦手になるという課題に対し、その前に楽しく遊んで慣れてもらえるように作りました。
「子育てにちょうどいいミシン」は2020年に発売しましたが、これはお母さんたちが「面倒」「邪魔」「難しい」など、いろいろな理由でミシンを使わないものの、「ちょっとやってみたい」という声があることに着目しました。手作りの喜びを通じて子供たちを喜ばせる手助けができると考え、手作りのハードルを下げるため、本棚に入るようなコンパクトなミシンを開発しました。
また、ご年配の方々には「目が見えにくい」「重たいものが持てない」といった身体的な課題があるので、簡単に糸かけができるミシンなどを開発しました。とにかく、それが脳トレにもつながるという着想を得て、脳トレで著名な川島教授に連絡を取り、実際に研究していただくと、手作りをすると本当に脳が活性化することが分かりました。
脳トレに良いという実証データが出れば、皆さんがミシンを始めるきっかけにもなりますし、作った後も元気になっていただけます。コロナ禍でご年配の方が人と会えず、元気がなくなり認知機能の低下が進むという社会問題があった時に、ミシンが役に立てるのではないかと考えた取り組みで、「孫につくる、わたしにやさしいミシン」という商品です。
男性にもあるミシン需要、コロナ禍にはマスク作りで社会現象
── 多品種少量生産という逆張りですね。
山﨑 さらにミシンをやらない方に向けた製品です。市場が縮小しているとお話ししましたが、逆に言えば、ミシンをやらない方は増えているわけです。
だからこそ、やらない方に「ちょっとやってみようかな」と思っていただけるような、入り口となる製品を広げたいと考えています。やらない方に振り向いていただき、実際に使っていただけるようなミシンをいろいろ開発していこうと、使命感を持って取り組んでいます。
── この発想は社長によるものですか?
山﨑 私は技術者ではないので、どうすればお客様に振り向いていただけるか、どうすればお役に立てるかという点は、実際に多くの方にヒアリングをして、ヒントを見つけ、それを当社の技術者に「これを形にしてほしい」と伝えるスタイルで開発を進めるようになりました。
「TOKYO OTOKOミシン」という名前の製品もあります。ミシンは女性が使うものというイメージが強いですが、男性の中にもレザークラフトなどをやりたい、ブルーシートを縫いたいといった需要があります。
そこで、レザーなども縫えるような、ハーレーダビッドソンのようなごついイメージのミシンを作れば、女性に偏ったミシンのイメージを打ち破り、男性も女性も関係なく楽しんでいただけるのではないかと考え、「TOKYO OTOKOミシン」と名付けました。これも4ヵ月待ちになるほどのヒット商品となりました。
あと、「子育てにちょうどいいミシン」の発売時は、たまたまマスク不足の時期で、当社のミシンは手軽に手作りできるため、「こんなミシンがあるなら私もやってみよう」という方が増えました。
発売時期が2020年3月末だったのです。予約が殺到し、3ヵ月待ちになるほどでした。1ヵ月で新聞全国紙5紙のうち2社の表紙を飾り、会社の電話はパンク状態でした。他の店舗の在庫も空っぽになるほどの社会現象となり、爆発的なヒットとなりました。
── 現在は海外で製造し、OEM先が製造してくれているのですね。企画だけをされているのですか。
山﨑 父の代では台湾の専属工場で製造していましたが、視点を外向きに変え、「作りたいものを、作りたいところでつくる」というスタンスにしました。必要なものを必要なところでつくるというスタンスにしたため、2019年に台湾工場を閉鎖しました。
ファブレス化することで、「このミシンしか作れない」という制約がなくなり、まず「こういう方に、こういうミシンを作ろう」という企画を立て、それをどこで製造するかを考えるようになりました。ファブレス化は、大きな変革の一つです。
「一家に一台」のミシン文化を再創造する未来
── 今後の事業展開や、新規投資などについて教えてください。
山﨑 家庭用ミシン市場が縮小しているとはいえ、「もう一度、一家に一台」という目標を掲げています。昔のように、暮らしの中にミシンがあり、手作りを楽しむ文化をミシンメーカーとして何とか復活させたいと考えていて、現在、「一年一新製品」を掲げ、開発を進め、新たな市場を創造しています。
それとは別に、海外展開も進めており、アメリカでも発売しました。ニューヨーク近代美術館(MoMA)のストアでも販売していただいています。発売直後から売り切れるほどの反響がありました。父の代では9割以上がOEMでしたが、私の代では9割以上が自社ブランドです。
また、EC比率も60%以上に高めました。それまでは卸売が主体でしたが、自分たちで販売できる力を持ち、お客様に振り向いていただけるミシンにしようと、2020年からEC比率を急激に高めました。これにより、手軽にご購入いただける価格も実現できています。
── 脱ミシンというお考えは特にないのですね。
山﨑 ありません。むしろ、当社はミシンで世の中の役に立ちたいと考えています。伝統と変革という話でいえば、自分たちができることを、自分たちらしく、世の中の役に立てるように取り組んでいくということです。
── 社員の方々との変革を進める中で、社歴の長い社員との意見の食い違いなどはありませんでしたか?
山﨑 最初から大反対からのスタートでした。私が子供用の毛糸ミシンを開発したいと社内でプレゼンしたのは2012年で、当時父が社長でしたが、私のプレゼンに対し、父は書類を投げつけ、「会社をつぶす気か」と言って部屋を出ていったほどです。
父は、既存のミシンを改良したり、新機能を追加したりして、どうにかしてほしいと私に期待していたのに、私が突然子供用のミシンで世の中の役に立つなどと言い出したからです。父は「ミシンというものは、そんなに簡単に売れるわけがない」と思っていて、夢物語を語るのではなく、現実的な開発をしろ、という気持ちだったのだと思います。
当時の社長である父が怒ったのは、本当に私に危機感を感じさせ、目を覚まさせるためだったのだと思いますが、私はそれがありがたかった。たしかに喜んでもらえると思っていたのに、まさかの大反対で、しかも「一切関わらない」と言われました。
ただ、逆に腹をくくることができました。格好つけてきれい事を言っても、何も行動していなければ意味がありません。それくらいの社内の反対を押し退けるくらいの気概がなければいけないと、逆に教えられました。
── 今後、どんな会社にしていきたいと考えていますか?
山﨑 どの会社も、社会に必要とされる、自分たちのノウハウや強み、使命感があり、自分たちらしくできることがあるはずです。
当社も市場が縮小し、厳しい状況にありますが、自分たちらしく役に立てることはあるはずだと考え、これからも頑張っていこうと思っています。小さくても輝ける、面白いことができる企業になりたいと考えています。
- 氏名
- 山﨑一史(やまざき かずし)
- 社名
- 株式会社アックスヤマザキ
- 役職
- 代表取締役

