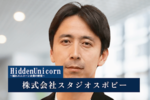最短距離を提示するデジタルマップが主流の現代において、「最高の寄り道体験」という情緒的な価値を提供する位置情報プラットフォームがある。株式会社Strolyが開発・運営する「Stroly」は、手描きのイラストマップをそのままオンラインで利用可能にし、GPSと連動させる世界唯一の技術をもつ。観光地のオーバーツーリズム解消から、未来都市のビジョン共有、さらには個人の思い出の可視化まで、その活用範囲は広がり続けている。
なぜ彼らは、効率とは逆行するような「寄り道」の価値に着目したのか。アートとテクノロジーの融合から生まれたこのユニークなサービスの裏側に迫る。
企業サイト:https://corp.stroly.com/
「最短距離」ではなく「最高の寄り道」をデザインする
—— まずStrolyの事業について教えてください。
高橋氏(以下、敬称略) 私たちは、ウェブ上でイラストデジタルマップを共有できるプラットフォーム「Stroly」を運営しています。2016年に、関西学研都市にあるATR(国際電気通信基礎技術研究所)の社内ベンチャーからMBO(マネジメント・バイアウト)という形で独立しました。本社は京都にあり、東京にも支社を構えています。
このサービスの最大の特徴は、紙のイラストマップがもつデザインや世界観をそのまま活かし、GPSと連動させて現在地を表示できる点です。一般的なデジタルマップ、たとえばGoogleマップが「最短距離」を提示する効率的なツールであるとすれば、Strolyは「最高の寄り道体験」をデザインし、ユーザーの行動を意図的に創り出すことを目的としています。
—— Googleマップで十分ではないか、という声もありそうです。
高橋 おっしゃる通り、最初は「Googleマップがあるのに、なぜこれが必要なのか」とよく言われました。
しかし、両者には明確な違いがあります。イラストマップは、描く人の意図を反映させ、伝えたい情報だけを強調して表現できます。たとえば、歴史的な街並みを歩くとき、コンビニエンスストアの情報は必ずしも必要ありませんよね。Strolyを使えば、そのエリアの独自の魅力や世界観に没入できるマップを提供できるのです。
それにより、エリアの滞在時間や消費額の増加といった経済効果も生まれます。実際に、私たちのマップを利用することで、地域の隠れた名所へ人の流れを生み出し、新たな発見を促すことができます。
観光地の課題解決から、未来の都市開発まで
—— 具体的な活用事例について教えてください。
高橋 国内外で400件以上のプロジェクトに関わっており、現在、プラットフォームには世界中から12,000以上のマップが登録されています。たとえば、京都市の祇園祭や、観光名所である嵐山のオーバーツーリズム対策に導入されています。
嵐山では、混雑するメインストリートだけでなく、地元の人だけが知るような魅力的な小道へ観光客を誘導するマップを作成しました。ライブカメラの映像と連携してリアルタイムの混雑状況を表示したり、ゴミ箱の位置を細かく記載したりすることで、観光客の満足度向上と地域住民の負担軽減の両立を目指しています。
実際にこの取り組みによって、これまであまり人が訪れなかったエリアへの人流を生み出すことに成功し、そのデータは京都市の新たな観光ルート開発にも活用されています。
また、最近では都市開発やスマートシティの分野での活用も増えています。ベトナムのビンズオン省では、現在開発中の未来都市の姿をイラストマップで描き、住民や進出企業に共有するプロジェクトに携わっています。
まだ何もない土地でも、未来の完成図をマップ上で体験できるため、移住促進や企業誘致のツールとして機能しています。さらに、バスのリアルタイム位置情報をマップ上に表示することで、公共交通の利用を促進し、CO2排出量削減にも貢献しています。
アートとテクノロジーの融合が産んだ発明
—— どのような経緯で生まれたのでしょう。ご経歴も関係しているのですか?
高橋 はい、深く関係しています。私は大学時代、アメリカで美術史を専攻していました。当時は美術館の収蔵庫でインターンをしていたのですが、膨大な数の作品が、限られた展示スペースの都合で人々の目に触れることなく眠っている現状に、もどかしさを感じていました。もっと多くの人に、作品に込められた作家の視点や物語を届けたい、そう考えていました。
その後、インターネット業界を経て研究機関であるATRに入所し、そこでStrolyの原型となる技術に出会いました。共同創業者の高橋徹は、AIの研究者で、彼が発明した「イラストマップとGPSを連携させる技術」の特許が基になっています。テーマパークのマップ開発プロジェクトで、世界観を壊さずに来場者を案内したい、というニーズからこのアイデアは生まれました。
まるで美術館の壁にかかっている絵の中を、自分が歩き回れるような感覚。江戸時代の古地図の上を歩けば、現代の街が江戸に見えてくる。この技術に、アートがもつ非言語的なコミュニケーションの可能性と、テクノロジーの新規性が融合していると感じ、事業化を決意しました。
—— 研究機関からスピンアウトして事業を立ち上げるうえで、どのような苦労がありましたか?
高橋 研究所発のシーズ起点のビジネスだったので、マーケットのニーズを見つけるのが大変でした。
創業当初は「Googleマップで十分」という声が根強く、なかなか理解されませんでしたね。海外にも前例のないオリジナルサービスだったため、最初の顧客を見つけるまでが特に大変でした。
転機となったのは、ベンチャーキャピタルからの投資を受け、ピッチイベントなどに参加するようになってからです。そこで、私たちが想定していなかったような使い方を提案してくださる方々と出会い、観光だけでなく、街づくりやイベントなど、さまざまな分野に活用の道が拓けていきました。
目指すは「体験」のインフラ。IPOも見据える
—— 現在のビジネスモデルと、御社の強みについて教えてください。
高橋 BtoBtoCモデルを採用しており、主なクライアントは自治体や観光協会、大手デベロッパーなどです。初期費用としてマップの制作・セットアップ費用をいただき、その後はプラットフォームの月額利用料をいただく形でマネタイズしています。
私たちの強みは、特許技術を基盤とした唯一無二のサービスであることに加え、これまで蓄積してきた「人の行動をデザインするノウハウ」にあります。どのような表現をすれば人が動いてくれるのか、その結果どうなったのか。マップ利用者の人流データを分析し、次の施策に活かすというサイクルを回せる点が、単なる地図サービスにはない価値だと考えています。
—— コロナ禍は事業に大きな影響があったかと思いますが、どのように乗り越えたのですか?
高橋 観光や移動を伴うサービスなので、非常に大きな影響を受けました。コロナ以前は、インバウンド需要の高まりを受けて組織を30人規模まで拡大していたのですが、事業モデルが固まりきる前にチームを大きくしすぎてしまったという反省もあります。コロナ禍を機に一度組織をスリム化し、事業の選択と集中を行いました。
現在は、やるべきことを明確にし、そこに向かって少数精鋭で進めています。この経験を経て、より筋肉質な組織になったと感じています。
—— 今後の展望としてはIPOも視野に入れているのですか。
高橋 はい、将来的にはIPOを目指しています。そのためにも、まずは事業をさらに成長させる必要があります。現在は、観光やスマートシティといった領域に注力していますが、今後はStrolyというプラットフォーム自体がメディアとなり、さまざまなマップ同士が連携していくような世界観も実現したいと考えています。
Strolyは、誰でも無料で世界中のマップを体験できるプラットフォームです。もっと気軽に使ってみてほしいですね。きっと、いつも見ている景色が少し違って見えるはずです。
「デートマップ」のような、個人の体験や思い出を共有するツールとしても大きな可能性があると感じています。人の心を動かし、体験を豊かにするインフラとして、Strolyを世界中に広めていきたいです。
- 氏名
- 高橋真知(たかはし まち)
- 社名
- 株式会社Stroly
- 役職
- 代表取締役社長兼CEO