本記事は、石川 和男氏の著書『要領がいい人が見えないところでやっている50のこと』(明日香出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

要領をよくするためには
1日「35,000回」もの「〇〇」をひとつでも減らせ!
私は、セミナーの準備をするとき、「ネクタイに、今回は2泊なので靴下は2足、レジュメ、ああ、それから税理士バッジを……」と頭の中で思い浮かべながら準備することはありません。代わりに、必要な物を事前にリスト化しています。
例えば、1.名刺 2.置き時計 3.タオルなど、すべてA4の用紙にまとめ、準備のたびにコピーして使っています。あとは、用意ができたものから番号に赤丸をつけていくのです。状況によって必要のないものもありますが、それも番号に赤丸をつけます。
出発ギリギリまで使うスマホや充電器は、青のマーカーで目立たせておき、直前にリストを再確認してカバンに入れて準備完了。これで、忘れ物はなくなり、忘れ物はないかと不安になることもありません。リストを見ながら機械的に準備を進めるので、時間も節約できます。
さらに大きなメリットは、頭を使わずに済むことです。今日は暑いからタオルを持っていこう、今回はこれが必要だ、あれもいるかも……といった考えは、決断の連続です。たとえ小さな決断でも積み重ねると脳に負担がかかり、重要な決断をするときの妨げになってしまいます。
アップルの共同創設者である故スティーブ・ジョブズ氏は、毎日黒のタートルネックとジーンズを着ていました。服を選ぶなどの日常の小さな決断を減らし、クリエイティブな仕事に集中するためです。バラク・オバマ元米大統領も、在任中はグレーか青のスーツを着て、決断の回数を少しでも減らしていました。フェイスブックの共同創設者マーク・ザッカーバーグ氏も、同様の理由で毎日グレーのTシャツを着ています。
心理学では「決断疲れ」と呼ばれる現象があります。これは多くの決断を繰り返すことで疲れがたまり、次第に判断力が低下してしまう現象です。これを防ぐためには、日常の細かい選択を減らすことが効果的なのです。
人は1日に約35,000回の決断をしていると言われています。多くは無意識下で行われていますが、食事の選択から仕事の優先順位、日常の些細な事柄まで含まれます。こうした決断を連続で行うと、意思決定の質やスピードが落ち、疲労感を感じるようになります。
イスラエルの刑務所の仮釈放審査に関する研究では、午前中に行われた審査では仮釈放が認められる率が高いのに対し、午後はその率が劇的に低下しました。これは、審査官が一日中決断を下し続けることで疲労し、午後になるとリスクを避けるために「現状維持」(すなわち、仮釈放を拒否する)という選択をしてしまうからだと考えられています。
ビジネスの世界でも、このような状態のときに、重要な意思決定が絡んでくると、正常な判断ができなくなります。そこで日常の決断を減らすことで、重要な決断に集中するためのエネルギーを温存するのです。そのために、日々の業務をできるだけルーティンワーク化し、決断回数を減らすことが有効なのです。
私も「決断疲れ」を防ぐために、決断を減らす仕組みづくりをしています。
前述したセミナーの用意だけではなく、会社で行うルーティンワークも同様にA4用紙に書き出し、その都度コピーをして使っています。
1.スケジュール確認 2.株価動向 3.メールチェック 4.入出金明細確認……など、ルーティンワークが増えれば書き足して、不要になれば削除しています。
決断を減らす仕組みを作ることも要領がいい人の習慣なのです。
「思い立ったが吉日」か「石橋は叩いて渡る」べきか?
失敗しない行動力!
仕事は即座に取りかかることが大切です。悩んだり、考え込んだり、迷っている時間を減らして、すぐに行動することがポイントです。要領がいい人は、迅速に動くことで仕事をどんどん片づけていきます。
人は、「嬉しいと感じて笑顔になる」「安心してホッとため息をつく」「不安を感じて爪を嚙む」など、このように通常は感情が先に来て行動が後に続きます。
しかし、予想外の出来事に対しては、行動が先で感情が後に続くこともあります。
心理学者のウィリアム・ジェームズ氏とカール・ランゲ氏が提唱したジェームズ=ランゲ説によると、例えば、バスケットボールのスリーポイントシュートが決まってガッツポーズをしてから、喜びを感じる、角を曲がった瞬間に犬に吠えられ飛び上がってから、驚くといったように、行動が先に起こり、その後に感情が生まれる場合もあります。
そこで、毎回面倒に感じる仕事や大変なタスクも、「やりたくない」と感じる前に、素早く取り掛かる。悩んだりためらったりせず、負の感情が湧き上がる前に、行動する。そうすれば、仕事は効率よく片づいていきます。
ただし、注意が必要なのは、何でもすぐに行動すればいいわけではないということです。
速い行動が失敗につながることもあります。その典型的な例が「オレオレ詐欺」の被害です。焦って決断せず、家族に相談したり、本人に確認していれば、被害を防げたはずです。
慌てて行動したことで、大きな損失を被ることになったのです。
会社でも同じです。「めったにないチャンスだ」と飛びつくと、後悔することがあります。
おいしい話に飛びついた結果、詐欺に遭うこともあるのです。
以前勤めていた建設会社での話です。埼玉県を中心に工事をしていた当社に、初めて東京都から大きな工事の依頼がありました。受注額も大きく、その年の売上目標を一気に達成できる案件でした。
景気が悪く会社は赤字が続いていたため、すぐに受けたい気持ちになりました。しかし、初めての工事で、黒字になるか赤字になるかわかりません。そこで、即答せずに、この工事のメリットとデメリットをリスト化し、可視化することを会社に進言しました。
例えば、今まで経験のない種類の工事だが、新しい事業に取り組むために何人の技術職員が必要か? 待機している職員が減るメリットは? 待機が減っても技術者が不足で次の工事が受注できないデメリットは? 工期までの資金繰りは問題ないか? 協力してくれる下請け会社がこの時期に確保できるか? こうしたポイントを整理して検討していきました。
メリット、デメリットを紙に書き出すことで、問題の所在がハッキリします。そして、頭にあることを「見える化」することで、チームで共有し相談できます。
「決断力」とは、正しい判断が速くできる能力です。行動スピードだけ上げても、それ自体が間違えていると、やり直しや損失が生じます。
沖縄旅行に行くのに、速攻で電車に乗り込んだら青函トンネルで函館に行ってしまったようなものです。行動はしているけど、意味のない、いやむしろ目的から離れてしまっています。とはいえ、行動スピードが遅いとライバルに先を越されたり、機会損失になるかもしれません。だからこそ、紙に書き出して、正しく速い判断をすることが重要です。
以前からしていることは「思い立ったが吉日」、速攻で取り組む。初めてのことは「石橋を叩いて渡る」、そして正しい決断を慎重に行ったら速攻で取り組む。これが要領がいい人がやっている方法なのです。
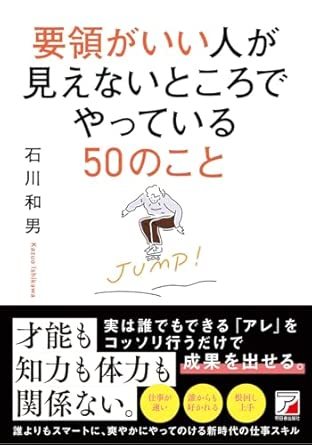
とはいっても仕事漬けではなく、パーティーなど会合の参加、家族との休息などプライベートも充実させている。しかし元々は三流大学を留年して卒業。社会人になってから一念発起し、年100冊ペースでビジネス書を読み漁り、ビジネスセミナーに参加し、いいと思ったコンテンツやノウハウはノートに書きとめ、実践し、習慣化。
自身と同じく元々は仕事も勉強も苦手だった人に寄り添った個人コンサルティングやセミナーを多数手がけ、絶大な支持を得ている。
著書は累計35万部突破で、『仕事が速い人は、「これ」しかやらない』(PHP研究所)、『仕事が「速いリーダー」と「遅いリーダー」の習慣』(明日香出版社)、『Outlook最強の仕事術』(SBクリエイティブ)など。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 決断は「減らす」ほど冴える、35,000回のムダを削ぐ思考法
- いきなり優先順位1位から始めない、成功を生む“助走の習慣”とは
- 会議も料理も“やめて正解”! 成果を生むのは「減らす力」だ
- 「与える人」ほど得をする? ギブが最強の戦略になる理由
- 片づけすぎは非効率? 整理整頓が“成果を下げる”瞬間とは
