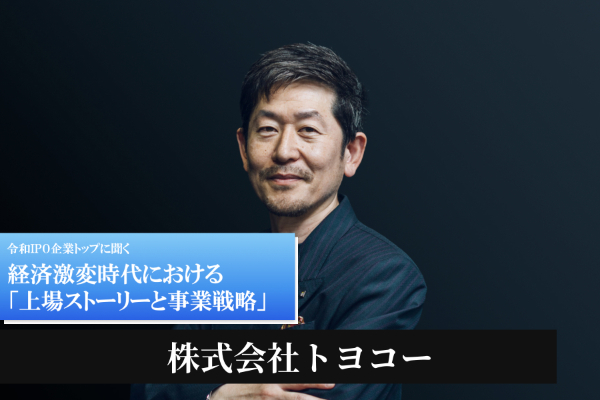
1996年創業、静岡県に本社を置く株式会社トヨコーは、インフラメンテナンス領域において2つの“オンリーワン技術”を生かした事業を展開している。CoolLaser事業は老朽化したインフラのサビや塗膜等をレーザーで除去する「CoolLaser」(クーレーザー)の製造・販売をしており、SOSEI事業は老朽化した工場・倉庫の屋根を3層の特殊な樹脂をスプレーコーティングして強靭に蘇らせる「SOSEI(ソセイ)」の施工を展開している。代表取締役CEOの豊澤一晃氏に、創業から上場までの道のり、そして未来に向けた事業戦略について聞いた。
企業サイト:https://www.toyokoh.com/
目次
「SOSEI」事業──工場屋根の再生と太陽光発電への応用
── 創業から現在までについて教えてください。
豊澤 創業から約30年を迎える企業で、現在2つの事業を展開しています。私が2代目社長で、父が創業した塗装業を継承しました。建設業に分類され、建築と土木の分野をカバーするために、「SOSEI」という工場屋根を再生する工法と、「CoolLaser」という主に土木分野で活用される技術を展開しています。
「SOSEI」事業が先行し、売り上げを支える基盤となっていましたが、直近では、昨年9月に「CoolLaser」の開発が完了し、上場に至りました。これにより納品が開始され、売り上げが大きく積み上がったタイミングで上場でき、今期予想でも売上は昨年度対比増収の見込みです。
創業の地は、東京タワーなどの塗装を手がける職人が多くいた町で、父も次男として独立し、株式会社トヨコーを設立しました。私が会社に入社したのは2003年頃で、それまではデザイン業務などに携わっていました。入社後、「SOSEI」と「CoolLaser」の2つの事業を立ち上げました。
事業を始めたのは、ものづくりの現場、特にイノベーションが起きにくいと言われる建設業界において、現場目線でものづくりをしたいという思いからです。単なるものづくりに留まらず、浸透させるためにはルール作りも重要だと考え、別法人格で「一般社団法人レーザー施工研究会(以下、研究会)」を立ち上げました。
屋外環境でレーザーを用いるビジネススタイルは世界でも前例がなかったため、安全ルールや取り扱い資格の付与などを研究会で行っています。現在、会員数は110社ほどに増えました。
少数精鋭で、光学、建設の経験者が集まっています。「SOSEI」事業は純粋な工事収益が中心で、「CoolLaser」事業は装置の製造・販売、保守・メンテナンス、消耗品販売といった製造業としての側面を持ち合わせています。
── 「SOSEI」事業はどのようなものですか?
豊澤 主に太平洋ベルト沿いの古くなった工場のスレート屋根の再生を得意としています。このスレート屋根はアスベストを含んだ波打ったセメントをベースとした建材で、老朽化が進んでいます。日本の工場のメンテナンスにおいては、実質賃金の上昇や円安といった背景もあり、老朽化が進行している一方で、製造業の国内拠点回帰から屋根の修繕ニーズは非常に高まっています。
気候変動に伴う被害も増えており、台風や地震、ゲリラ豪雨などによる被害は、工場内の製品や設備にも直接影響を与え、大規模な修繕が求められる状況が増えています。
「SOSEI」工法は、瞬間硬化層を含む特殊樹脂を直接吹き付ける工法で、特徴は断熱効果も得られることです。さらに、この工法を発展させたものとして、現在国が進めている太陽光発電のニーズにも応えることができます。特に、スレート屋根への太陽光パネル設置はこれまで困難でしたが、「SOSEI」工法がこれを可能にしていて、今はこの分野を強化するフェーズです。
「CoolLaser」事業──インフラ保全の革新と独自技術
── もう一つの「CoolLaser」事業について、その革新性や独自性について教えてください。
豊澤 「CoolLaser」事業の着想は、アメリカで発生した橋梁崩落事故から得ました。日本も同様に、建設後50年を経過した橋梁が増加していて、設計寿命を迎えているものがほとんどです。壊れてから直すのではコストがかかるため、「壊れる前に直す予防保全」への切り替えの必要性が指摘されています。
従来の橋梁(きょうりょう)メンテナンスでは、橋全体を塗り替えるために錆を除去していましたが、特に橋脚の入り組んだ部分などに発生する錆は、塩分が原因で進行しやすく、適切なメンテナンスが難しいという本質的な課題がありました。我々は、こうした入り組んだ狭い場所を重点的に、高品質なサービスを提供することを目指しています。
弊社の特徴は、単にレーザーを当てるだけでなく、長年の研究開発により、レーザーを回転させながら効率よく除去する特許技術を取得したことです。これにより、分厚い錆に対しても迅速かつ効率的にアプローチすることが可能になりました。
一般的なレーザークリーニング技術は1970年代からありましたが、主に工場内での自動車部品のクリーニングなど、微弱な出力で薄い汚れを対象とするものでした。インフラメンテナンスのような屋外での厚い錆に対応するには、より高出力のレーザーが必要でした。そこで、溶接や切断に用いられる高出力レーザーを活用できないかと考え、着想に至りました。
ただ、そのまま高出力レーザーを使用すると鉄材を溶かしてしまうため、高速回転による円形照射技術で熱影響を回避することに成功し、「CoolLaser」が誕生したわけです。現在、屋外用途で高出力レーザーの開発に成功しているメーカーはほぼなく、弊社は非常に独創的なポジションを確立しています。
ターゲットは、橋梁、鉄道、海洋構造物、プラントといった土木分野です。中でも公共性の高い道路橋のメンテナンスは大きな市場となっています。
── この革新的な技術を広めていくための戦略はどのようなものですか?
豊澤 この業界は新しい技術が生まれにくいため、新たなテクノロジーで変えていくには、業界軸と地域軸の2軸での拡大が必要です。
業界軸を広げるためには、各分野の仕様書に工法が掲載されることが重要です。レーザー処理は世の中に前例がなかったため、仕様書に記載されていませんでした。そこで、キーとなる分野や販売パートナーと連携し、地域を広げながら、仕様書に記載されるための試験施工などを繰り返し行っています。
また、弊社単独では難しいため、インフラオーナーや工事会社への直接アプローチに加え、大手リース会社やレンタル会社をファーストユーザーとして装置を販売し、全国の建設会社に向けてPRしながら貸し出しを行うという位置づけで展開しています。
上場を目指した背景と家族経営からの変革
── 上場を目指した背景を教えてください。
豊澤 建設業界は新しいものが生まれにくい土壌ですが、ベンチャー企業や中小企業にも優れた技術は多く存在します。
しかし、売上規模や実績が重視される傾向があり、新しい技術が浸透しにくいという課題がありました。特に「CoolLaser」は開発に長い期間が必要なため、IPOによって業界における社会的地位を向上させることが、スタートラインに立つ戦略として重要だと判断しました。
もともと父の代から、「人が嫌がることをやる」「困っていることにフォーカスする」という思想があったため、私もその流れを汲み、無駄な争いを避け、高いハードルであっても課題解決に取り組むことで付加価値を生み出すというスタイルで進めてきました。そのため、パブリックカンパニーへの変革も比較的スムーズに進みましたね。
── 上場までの過程で最も苦労したことや、資本調達における戦略についても教えてください。
豊澤 最も苦労したのは、「CoolLaser」の技術開発です。屋外で高出力レーザーを使用するという前例のない中、土木分野の水準を満たす処理能力を実現するまでに、装置開発だけでなく、成果物の品質基準を満たすために多大な苦労と投資を要しました。この開発には15年近くかかりました。
資本調達では、2018年にNHKに取り上げられたことをきっかけに注目が集まり、外部資本調達を始めました。当初は事業会社中心でしたが、IPOを視野に入れ、徐々にVCも取り入れるようになりました。特にシリーズCラウンドでは、投資家を口説くのに時間がかかりましたが、事業会社はインフラメンテナンス分野での技術革新に注目し、比較的スムーズに調達できました。
市場開拓の展望とマーケティング戦略
── 今後の事業展開について、市場のビジョンや、競合優位性について教えてください。
豊澤 代表的な分野として、道路、鉄道、電力関係、特に原子力分野における除染といった社会課題に取り組んでいきます。
弊社の技術は、単に錆や塗膜を除去するだけでなく、鉛やPCB、クロム類といった有害物質や放射性物質を除去する際に、飛散させることなく効率的に回収する機構も有しています。これは他社にはない独自技術です。
従来の工法では、有害物質を含むものの処理に多額の費用がかかり、環境汚染の原因にもなっていました。弊社の技術は、こうした根本的な課題を解決する唯一の手段となり得ます。特に、入り組んだ箇所やメンテナンスが困難な場所への対応に注力し、量よりも質を重視した戦略をとっています。
── マーケティング戦略は、パートナー開拓や展示会への出展をしているのですか?
豊澤 はい。展示会は、大手レンタル会社などと連携し、集客と知名度向上のために行っています。特に注力しているのは、インフラオーナーや工事会社を巻き込んだ展開です。新しいビジネスの出し方や取り組み方を提案し、直接アプローチをかけています。
また、研究会は重要な顧客基盤です。全国の工事会社が会員となっていて、彼らの疲弊した状況を理解し、協業したいと考えています。既存の工法を変えたいが変えられない工事会社の方々をサポートし、共に日本のインフラを支えていきたいと考えています。
オーナー会社とは、共同研究や株主との連携を通じて、水面下で取り組みを進めています。PoC(概念実証)や試験施工を重ね、技術の広がりを増やしていくことが最優先事項です。
── 今後の組織体制の展望と、少数精鋭ならではの強み、そして伸ばしていきたい点についても教えてください。
豊澤 少数精鋭という体制は維持しつつも、組織体制の強化は不可欠だと考えています。特に開発体制と生産体制の強化が急務です。現在、製造拠点の拡大に向けて準備を進めており、優秀なエンジニアの採用も課題です。
弊社の製品は、レーザーヘッドをはじめ、多くの部品を内製またはOEMで製造しています。このサプライヤーとの連携体制も強化し、生産台数をクリアするための体制構築を進めています。
ファイナンス戦略と将来の展望 3Kから3Cへ
── 今後のファイナンス計画と、資本効率の向上について教えてください。
豊澤 上場時の増資もあり、自己資本比率は7割近くを維持しており、財務健全性は高いです。今後は、応用開発を中心とした研究開発への投資を継続しつつ、量産化段階での運転資金は、金融機関からの借り入れも活用しながら、資本効率の良い経営を目指します。
M&Aについては、設計・製造技術を持つ企業との協業や買収も視野に入れており、特に光学分野の技術を持つ企業との連携を検討していきます。
── 将来に向けて、どんな企業、業界にしていきたいと考えていますか?
豊澤 インフラメンテナンス業界を「3K(きつい・汚い・危険)」から「3C(Cool・Clean・Creative)」へと変えていくことが重要だと考えています。これは、担い手の確保にも関わることであり、誇れる職業へと変えることが、日本のインフラを支える上で不可欠です。
弊社の技術は、単に表面的な作業を行うだけでなく、有害物質の除去や環境負荷の低減といった本質的な課題解決に貢献します。この取り組みに共感いただき、インフラオーナー、工事会社、金融投資家の皆様など、多くの方々と共に、この新しい価値を広めていきたいと考えています。
日本はインフラ老朽化という課題先進国であり、弊社のソリューションは他の先進国や、これからインフラを整備していく新興国にも展開できるポテンシャルを持っています。共感いただける方々と共に、この新しい価値を広めていきたいと考えています。
- 氏名
- 豊澤一晃(とよさわ かずあき)
- 社名
- 株式会社トヨコー
- 役職
- 代表取締役CEO

