本記事は、中出 昌哉氏の著書『やりきる意思決定 生成AIという「人間を超える知性」を従える究極のビジネススキル』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。

様々な情報に触れておく
同業種・他業種問わず、様々な情報に触れておくことは課題を見つけるためにとても大切です。経営者が好んで歴史の本を読んだり、知人の経営者との情報交換に出かけたり、会食に行くことも理由は同じなのですが、どこかで知った情報が、アナロジーとして使えるタイミングがあるからです。
言い換えると、様々な経験やインプットしてきた情報が、全く違う文脈でヒントになる瞬間が来るのです。
アナロジーが活きたエピソードとして、個人的にお気に入りのものを例示します。B2C(対個人向け)のビジネスで考えていることが、B2B(対企業向け)でもアナロジーとして使用できるということを示した、個人的に好きなストーリーです。
アメリカにSalesforceという、世界最大規模のITソフトウェア会社があります。Salesforceには、AppExchangeというSalesforceに付随機能を追加できる専用ストアが存在しています(Salesforce上に載る便利機能を簡単に購入できる仕組みです)。
これは、iPhoneのApp Storeのコンセプトがベースとなっており、スティーブ・ジョブズのアドバイスに基づいて作られたという話があります。
スティーブ・ジョブズのアドバイスとは、
- 「アプリケーションの経済圏を築け」(外部の開発者がSalesforceの上でアプリを作って売れるような環境を作れ)。
- 「自分たちのプラットフォームの上で動かせ」(Salesforceのプラットフォーム上で、アプリが構築・配布・運用できる仕組みを作るべき)。
- 「そしてApp Storeを作れ」(iPhoneのApp Storeのように、アプリを探して、試して、インストールして、購入できる場所を作るべき)
だったという逸話になります。
僕個人の習慣としては、毎週本を読みますし、他社の経営陣とも週に2〜3回はお会いさせていただき情報交換をしています。
また直近では、グローバルな生成AI関連ニュースのキャッチアップがマストに近いので、数十種類の情報メディアから、生成AIに関係する情報だけを自動で抜き出し、その要約が自分の元に届くような仕組みを、ChatGPTを使いながら構築しています。
少し話はそれますが、説明させてもらうと、具体的には次に記す方法となります。Web上のどのサイトから、どの情報だけを連携するのか、どういう形で送信されてくるのか、どのような文章なのか(要約なのか、重要なところだけを切り出すのか)を事前に定義・設定しておき、その設定どおりにChatGPTが判断や作業をしながら、自動で送信してくる形をとっています。
僕が実際に構築している「グローバルな生成AI関連ニュースの自動キャッチアップ」は、ざっくり言えば次のように仕組み化をしています。
① 収集元を決める(どのサイトから情報をとるか)
まず最初に、自分が注目している生成AI関連のメディア、ブログ、公式発表サイトなどをリスト化します。
例としては、
- 海外テック系メディア:TechCrunch・The Verge・Ars Technica・VentureBeatなど
- 生成AI企業の公式チャンネル:OpenAI・Microsoft・Anthropic・Google・Meta・Perplexity
- 海外ニュースサイトの生成AIカテゴリー:Reuters・Bloomberg・Associated Press・Forbes・Axios–Technologyなど
- 技術論文(面白い技術論文が出てきた場合)
- Substack(専門家が発信しているメールマガジン)
- X(旧Twitter)のアカウント
ここでのポイントは、「メディアを絞りすぎず、生成AI関連の発信が早いところを押さえる」ということです。
② 情報を抜き出す(RSS+Zapier)
多くのニュースサイトやブログにはRSSフィード(RSSフィードとは、Webサイトの更新情報を自動的に配信する仕組みです。例えば、ニュースサイトやブログが新しい記事を公開すると、その情報がRSSフィードを通じて配信されます)が用意されているので、それを活用します。
- RSSをベースにして、「新着記事が出たら自動で取得」
- Zapierというノーコードの情報連携プラットフォームを使って、「RSSで新着→ChatGPTに送る」まで自動連携
- Zapierを通して、SlackやNotionへ自動送信
また、その後、面白いと思った情報については、スタンプを押すだけで自分の情報をストックしている場所に格納していくという方法をとっています。
自分の頭に入れておいた様々な情報は、何かしらのタイミングで役に立つ瞬間が来るので、常にストックしておくことをお勧めします。
ストックをしておくことで、課題の解決方法の立案にももちろんつながりますが、「課題は、実はこれなのではないか」という課題の洗い出しにも使用可能です。
ちなみに、僕はアナロジーによって現職でプロダクトの新しい使い方を広めて、市場を作ることができました。
テックタッチは、DAP(デジタルアダプションプラットフォーム)と呼ばれるマーケットに属しています。DAPとは、社員やユーザーが新しいシステムを迷わず使いこなせるようサポートする「画面上のガイドツール」です。例えば、システムの操作手順をその場で案内する「ガイド」や、入力欄にカーソルを合わせるとルールを表示する「ツールチップ」などを、リアルタイムで表示します。
これにより、必要なタイミングで必要な説明が自動で表示される環境を実現できるので、わざわざマニュアルを読む手間がなくなります。DAPは、情報量が多く、操作に不慣れなWebサイトや業務システムにおいて、ユーザーがストレスなく使いこなせる状態(=デジタルアダプション)を実現するための重要なツールとして、今注目されています。
僕がDAPのマーケットの調査をしていたときに、グローバルでは、顧客用のWebサイト・システムの中にDAPがビルトインされている事例や、公共セクターでのDAP活用事例が多いということに気づきました。
一方で、日本ではまだまだ黎明期ということもあり、ほとんど使われていない状況でした。
簡単なアナロジーにはなりますが、「日本にも全く同じニーズがあるはずだ」と考えて、顧客インタビューなどを通じてニーズがあることを理解した後に、実際にその市場を開拓しました。
結果として、今ではそのセグメントの売上が、会社全体の売上高の25%以上を占めるようになっています。
こういった、シンプルなアナロジーが力を発揮する瞬間もあるのです。
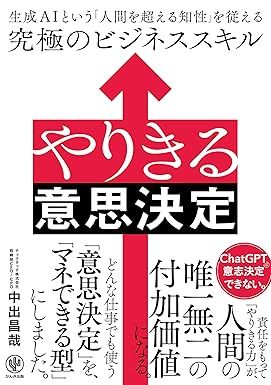
テックタッチでは、「AI Central」(AI技術を活用した新規事業開発を担う専門組織)の事業責任者としてAI戦略をリード。プロダクト戦略責任者(CPO)および財務責任者(CFO)も担う。また、一般社団法人日本CPO協会の理事も務める。
東京大学経済学部、マサチューセッツ工科大学(MIT)MBA卒。野村證券株式会社にて投資銀行業務に従事し、素材エネルギーセクターのM&A案件を多数手がける。その後、カーライル・グループにて投資業に従事。ヘルスケア企業のバリューアップや、グローバル最大手の検査機器提供会社への投資等を担当。テックタッチには2021年3月、CFOとして入社。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
