本記事は、小田 玄紀氏の著書『デジタル資産とWeb3』(アスコム)の中から一部を抜粋・編集しています。

そもそもWeb3とは何か?
デジタル資産の普及と並行して、ブロックチェーン技術を応用した様々なサービスやプロジェクトが登場しています。これらが「Web3」と呼ばれるものです。
Web3はいま生まれつつある新しい産業のトレンドであり、それらが切り開く未知の世界です。そのため現段階では、具体的なイメージや定義は様々ですが、共通して挙げられるのは次の4点だと私は考えています。
①ブロックチェーン技術をベースにしていること
②経済的なモチベーション(報酬)を組み込んでいること
③様々な対象の分散化を目指していること
④スマートコントラクトによる自動執行が可能なこと
①と②はデジタル資産と共通する基本的な要素です。広義または最広義のブロックチェーンには様々なバリエーションがありますが、ブロックチェーンを安定的に運用していく上で②は欠かせない条件です。一方、③と④は、具体的なサービスやプロジェクトによって捉え方や使い方が異なります。
Web3を理解する上で特に重要なのが③の「分散化」です。例えばビットコインなどの暗号資産では、取引データの記録(台帳)を所有したりする権限が参加者(ノード)に分散化されています。
Web3ではこうした権限に限らず、様々な対象が分散化されていくのです。
Web3の鍵を握る「スマートコントラクト」
Web3における分散化と密接な関係にあるのが④の「スマートコントラクト」と呼ばれる仕組みです。
物品の売買や、労働を含むサービスの取引、保険や融資といった様々な経済行為は通常、契約を通して実行されます。また、その過程では契約書への署名捺印や登記、決済、支払いといった手続きを伴うのが一般的です。
こうした手続きをブロックチェーン上であらかじめプログラムしておき、一定の条件により自動的に執行する仕組みがスマートコントラクトです。
これを導入すると、いちいち人手を介する必要がなく手続きがスピーディーに行え、省人化、コスト削減、業務効率化が大幅に進む可能性があります。しかも、手順や実行の条件はブロックチェーン上に記録されているので、透明性や非改ざん性が担保されます。
スマートコントラクトの概念は1990年代には提唱されていましたが、具体的な仕組みとして可能になったのは2014年にイーサリアムのブロックチェーンが稼働してからです。
ビットコインのブロックチェーンでは基本的に、BTC(ビットコイン)の取引データを記録することしかできません。それゆえにシステムの堅牢性が高いのですが、イーサリアムのブロックチェーンでは暗号資産としてのETH(イーサ)の取引に加え、多種多様な情報を一緒に記録することができます。この機能がスマートコントラクトであり、ETH(イーサ)の取引と同時に様々なプログラムやアプリケーションを実行できるのです。
この仕組みを使って何ができるのか、いま様々な試みが進められています。それがまさにWeb3の世界です。
例えば、月末締め・翌月末払いといった支払い処理が、毎日、自動執行(支払い)できるようになるかもしれません。実際に導入するためにはその都度、業務執行の状況確認が必要ですが、そこさえ工夫できれば経理部を通す手間が省略できる可能性があります。
あるいは、いままでなら何度も会議を開き、様々な検討を経て実行されていた投資が、あらかじめ設定されたいくつかの条件がクリアされたことをオンラインで自動的に確認する仕組みによって、より効率的に行えるようになるかもしれません。
これらは、これまで当たり前と思われていたやり方に対する発想の転換です。習慣や常識になっていることを変えるのは抵抗があるものですが、実際にやってみたら案外うまくいったりするものです。スマートコントラクトはそのきっかけを与えてくれる点に大きな魅力があるのです。
まだまだアイデアレベルのケースも多く、実現には様々な課題が立ち塞がっているのが現状ですが、近年のイノベーションの速度を思うと期待が膨らみます。
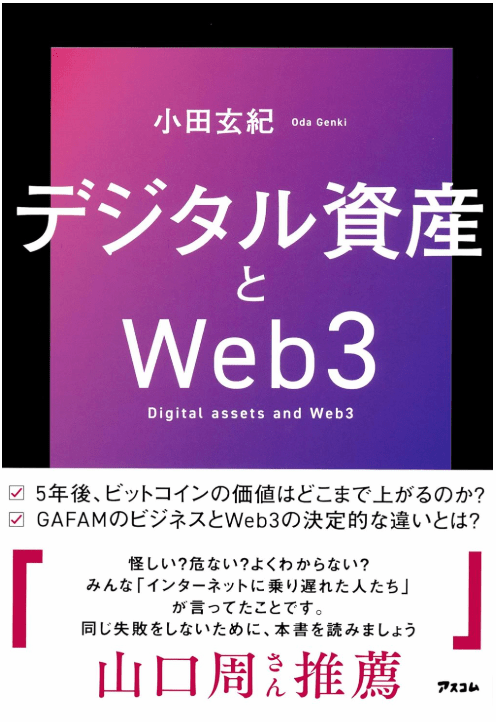
1980年生まれ、東京大学法学部卒業。2016年3月、日本初の暗号資産交換業を営む株式会社ビットポイント(現 株式会社ビットポイントジャパン)を立ち上げ、同社代表取締役に就任。
2018年、紺綬褒章を受章。2019年、「世界経済フォーラム」よりYoung Global Leadersに選出。
2023年から、SBIホールディングスの常務執行役員、日本暗号資産等取引業協会代表理事を務める。
- 暗号資産の「価値」はどこから来るのか?
- これだけは知っておきたい「デジタル資産」と「Web3」の定義
- ブロックチェーンのこれまでの経緯
- そもそもWeb3とは何か?
- 銀行を信用するか、テクノロジーを信用するか
- デジタル資産とWeb3を自分事にする
