本記事は、生井 秀一氏の著書『13歳からのアントレプレナーシップ』(かんき出版)の中から一部を抜粋・編集しています。
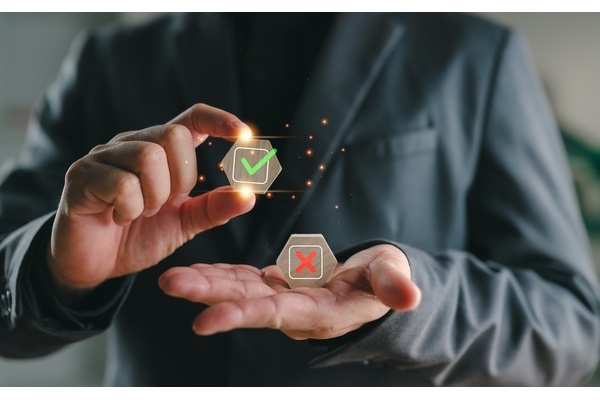
「常識」=「正しい」とは限らない?
常識を疑う姿勢はとても大切です。
きみたちは「本当にそう?」「大人がいっているけれど、本当かな?」と疑う姿勢を持っていますか?
もしかしたら、疑うことが悪いことだと思ってしまっている人もいるかもしれません。しかし、疑うことは常識を問い直す力につながり、「そもそもそれって本当?」と背景を探ることにもつながります。
だから、もしそんな疑問が湧くことがあれば、打ち消さずに大切にしてほしいと思うのです。
教員も保護者もよく「うちの子はすごく素直で」といいます。もちろん、それもすごく素敵なことですが、疑う姿勢を持たないことはリスクでもあります。だから、「ちょっと間違ったことをいってみたらどう?」と先生に促すこともあります。それに対して、子どもたちが「本当に?」と質問をしてきたら、きちんと生徒も考えている証拠です。
僕は生徒たちには「どう思う?」「ここについてなにか意見はある?」と質問を振ります。そうすると、生徒たちは面食らって顔を見合わせてしまう。「え、教えてくれるのではなく、私たちに聞くの?」という顔をするんです。
でも、少し待っていると、「じゃあ、思っていることをいっていいですか?」と話し出します。
この常識を疑う視点は、構想力や着眼点をつけることにつながっていきます。
花王では、ドラッグストアなどに商品を並べてもらうには、とにかくテレビ広告を打てと言われていました。マスマーケティングの発想です。
しかし、社会ではどんどんテレビを観ない人が増え、スマートフォンの世界に移り変わっています。そこで僕は従来の常識を疑ってeコマースを提案しました。
常識を疑う視点によって、すぐになにかの舵が切られるわけではありません。しかし、本質をついていたら、「あれ?」とみんな立ち止まります。そして、「(よくわからないけれど)やってみろ」「面白いかもしれないね?」といわれることも多いのです。
常識を疑う視点は、いうなれば突破への入口です。扉が開けば、新たな構想へとつながっていきます。
動き出したら失敗はつきもの
挑戦するアイデアはたくさん思いつくけれど、どうしぼっていいかわからない。そんな人もいるかもしれない。
どのアイデアを掘り下げるかを検討する際に大切にしてほしいのが、ゴールや世界観を描けるかどうか。アイデアの先に自分の目指すビジョンは見えるでしょうか?
それがサクセスポイントになります。
描きたい未来をカチッと細かく決める必要はありませんが、おおまかな道筋くらいは見えていたほうがいい。すると、自分自身も「いける!」という気持ちになっていくことができるからね。
そして、詳しくは3時間目でお話しするけれど、やりたいことを思い描くと、誰を巻き込めば実現できそうかも見えてきます。
また、こういったイメージを持ったことがない人は、まずは一回、がむしゃらにでもなにかを実現させてみよう。
一度、成功体験を積むと「あのときのあのパターンだな」と転用できるようになっていくんです。僕自身、未知の挑戦であっても、「あのときのこのタイミングに近いな」と経験を振り返りながら進んでいます。
そして、アイデアをしぼり、課題設定をして、動き出したら、失敗はつきものです! 100%の成功なんて、あり得ません。例えば、何人かは反対する人が出てきたり、大きな落とし穴があることに気づいたりする。そういった障害がある中で大切にしてほしいことは、致命傷にならないように対応していくことです。
これは何度も何度も失敗している僕だからいえることかもしれないけれど、失敗を積み重ねていると、そこまで大きな失敗になる前にセンサーが働くようになっていく。
「そろそろ、こうしたほうがいいのでは⁉」となにかをキャッチする瞬間があるんです。
だから、きみもどんどん失敗を重ねていけばいいと僕は思っています。こんなことをいうと、無責任に聞こえるかもしれないけれど。失敗をしていくことが成功へ向かっていく近道だから、どうか許してほしい(笑)。
例えば、探究学習で「こんな感じかな?」とアウトプットしたものの、手応えがイマイチだったということはないかな?
発表会やコンテストの舞台は一度きりだけれど、探究学習はそこで終わるわけではありません。アウトプットに対するアドバイスを受け、修正をしていけば、いい意味で予想外の結果へと辿り着けることもあります。そして、それが大学入試の総合型選抜や大学入学後の研究テーマにつながっていく可能性だってあるんです。
そうやって小さな探究のサイクルを回すことで、どんどん内容をブラッシュアップしていくことができます。
つまりは、「失敗」という概念自体、ないのかもしれないね。
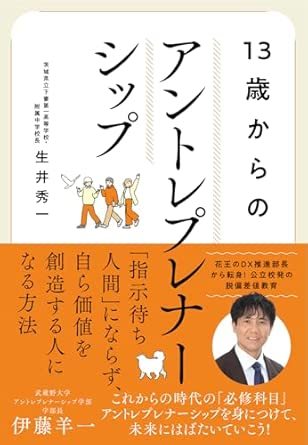
2023年にキャリアトランスフォーメーションに挑戦し、茨城県内の公立中高一貫校の「校長」を教員免許不問で公募するプロジェクトに応募。
1600人を超える応募者の中から合格者3人のうちの1人に選ばれ、2024年4月より民間出身の校長として現職に至る。
民間人校長による学校経営で、「校長就任1年目で過去最高の志願倍率」を記録。花王で培ったマーケティングスキルやアントレプレナーシップ精神を教育業界にも持ち込み、VUCA時代を生き抜くための次世代人材育成に邁進している。
早稲田大学ビジネススクールで経営学修士(MBA)取得。吉本興業に文化人として所属。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 逆境を超える3つの領域「アントレプレナーシップ」とは
- 「それ、本当に正しい?」未来を切り拓くための思考法
- 雑談は無駄じゃない、信頼をつくる「最強の分析力」
- 「やらない後悔」は一生残る、「やった後悔」は未来の糧になる
- 「謙虚さ」が仲間を呼び、「協調」が未来を切り拓く
