本記事は、赤羽 雄二氏の著書『7日でマスター 瞬時(すぐ)に動く技術』(明日香出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

PDCAを回せば必ずうまくいく
仕事を速く進めようとしても、うまくいかないことがいくらでもあります。最初からうまくいかないことはごく普通かと思います。
だからこそ、改善し続けます。まさにPDCAです。
PDCAはPlan(計画し)、Do(実行し)、Check(確認し)、Act(修正する)の略で、常にやり続けます。
サッカーのキックの練習や、カラオケで歌の練習などをするときにいつもしていることです。
改善を次々に繰り返していく、という意味では、何かのスキルを向上させる、精度や品質を上げるあらゆる業務、活動で効果的ですが、うまく活用している人はそれほど多くないように思います。
PDCAという言葉は多くの人が知っていますが、意外に実践できていない、とでもいいましょうか。
仕事ができる人とできない人との違いは、PDCAを回しているか、うまくいかないときにすぐ回せるか、かもしれません。
PDCAを回すとは、「さっさとやってみて、うまくいかなければ修正してもう1回やってみよう」「できるまで繰り返そう」という意味ですね。
そうなれば、仕事はどんどんできるようになっていきます。

PDCAを回せない人
では、PDCAを回すことに慣れていない人にはどういったタイプがあるでしょうか。
まずは、PDCAを回すのを知らない人。やみくもにやってうまくいかず、それであきらめてしまいます。一度でうまくいかないと、おしまいです。もう1回やってみようとは考えません。
次には、うまくいかないとき、なんでだろうと少し考え、もう1回やってみようとされる人。それで少し前に進むこともあります。
さらに、うまくいかないことはある程度想定して2、3度試してみる人。結果が出る可能性は高まりますが、十分ではありません。
また、PDCAという言葉は知っていても、どういう勢いで、どういう流れでPDCAを回していけばいいのかよくわからず、何となく中途半端になってしまう人。
どのタイプももったいないです。
多分、「物事が最初からうまくいくことはない。PDCAを回すことで前進し、続けていけば多くは成功する」という理解と信念、成功体験がないためにひっかかってしまうのだろうと思います。
PDCAを回すとは、「ダイナミックに問題解決をする」ことなので、必ず成果が出ます。「PDCAを回すべきだ」「PDCAを回していけばよりよい結果につながる」という信念があれば、大きく改善していきます。
PDCAを回すポイント
PDCAを回す際に注意すべき点が3つあります。
① 4つのステップを意識しすぎないこと
意識するとぎこちなくなり、力が入り、仮説思考ができなくなっていくので、逆効果です。
計画を丁寧に作ろうとして、エネルギーと時間の大半を失ってしまうことは珍しくありません。やることがある程度見えているときは、Do→Check→ActというふうにまずDo(実行する)から始める手もあります。
Check(確認する)も慎重にやりすぎて、せっかくのDo(実行する)の勢いを殺してしまうことがよくあります。実行して結果がそれなりに出ていれば、それを止めてこれでいいかなと確認することはありません。むしろ走りながら課題を整理し、修正していけば十分なこともよくあります。
② 時間はあまりかけなくても、それなのに準備
あまりにも準備不足で、どうせやり直すから大丈夫、とたかをくくるのもよい結果につながりません。粗があってもいいですが、中途半端だともったいないです。その上で、やってみて結果を見ながら何度かやり直すのがいいです。
③ 失敗を恐れない
失敗を恐れると、すべてに時間をかけ、時間をかけるから勢いが削がれ、動くものも動かず、スピードが遅くなってしまうだけではなく、頓挫してしまうことにもつながります。ともかく高速で回していくこと、スピードを重視すること、リスクは走りながら対処することを最優先に考えてください。
究極は「瞬時に」「高速で」「何度も」回す習慣です。これができるとすごく楽になります。
2度目は倍のスピードで
仕事を進める上で、資料作成でも、分析でも、事業企画でも、営業でも、イベントや会議開催でも、1度目はどこに問題があるかわからないし、全体像もあまり見えないしで、慎重に進めることが多いのではないかと思います。
2度目になると、どこに問題があるか経験済みとなり、最初から最後まで見通すこともかなりでき、かなりスピードアップして進めることができます。
同じ仕事、似たような仕事を2度目にやることになった場合は、ぜひ倍速でやり抜くことを意識してみてください。1割速くではなく、倍速です。
「そんなバカな」と思われるでしょうか。やってみればそこまでおかしなことではないものです。初めてのときは落し穴がどこにあるかわからないので慎重に進めていきますが、2度目でだいたい予想がついて全力疾走できるのでその違いですね。信じて取り組めば、確実に速くなります。
仕事がどんどん加速できれば、精神的に楽になり、さらにスピードアップのアイデアも湧いてきます。上司の見方が劇的に変わるので、上司の反応におびえることもなくなっていきます。無駄に疲れて残業することも減っていくので、ますますいいことだらけですね。
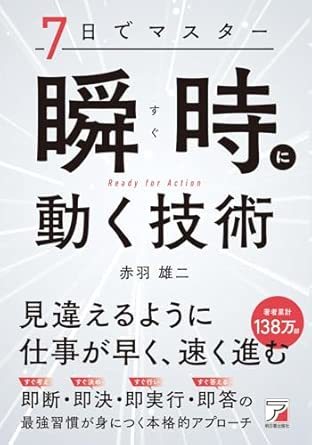
経営戦略の立案と実行支援、新組織の設計と導入支援、マーケティング、新事業立ち上げなど多数のプロジェクトをリード。マッキンゼーソウルオフィスをゼロから立ち上げ、120名強に成長させる原動力となるとともに、韓国LGグループの世界的躍進を支えた。
マッキンゼーで14年勤務した後、「日本発の世界的ベンチャー」を1社でも多く生み出すことを使命として、ブレークスルーパートナーズ株式会社を共同創業。ベンチャー経営支援、中堅・大企業の経営改革、経営幹部育成、新事業創出に取り組んでいる。コロナ前はインド、ベトナムにも3年間毎月訪問し、現地企業・ベンチャーの経営支援に取り組んだ。
東京大学、電気通信大学、早稲田大学、東京電機大学、北陸先端科学技術大学院大学講師としても活躍。下関私立大学客員教授。
著書は、44万部突破の『ゼロ秒思考』を始めとして、国内27冊、海外30冊、計138万部。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 「すぐに動ける人」の秘密! 迷いをなくし結果を出す思考法とは
- 迷わず動く「仮説思考」5つのステップで仕事が加速
- 誰でも仕事が速くなる! スピードアップの4つの鍵
- 仕事がデキる人になるには? PDCAを回す3つのポイント
- 見返りを求めない「ギブ&ギブ」が人生を好転させる
- 踏み出せないのは「思い込み」かもしれない
