本記事は、赤羽 雄二氏の著書『7日でマスター 瞬時(すぐ)に動く技術』(明日香出版社)の中から一部を抜粋・編集しています。

問題把握・解決力って何?
問題把握・解決力とは、仕事でもプライベートでも、何が問題かをすぐに把握し、解決していく力のことです。
すぐに把握と言っても、問題が起きる前に予想し、未然防止することもできますので、そうなれば、さらに初動を早くできます。
- 事業を進めていく力
- 新しい企画を立案・提案する力
- 新事業や新サービスを生み出す力
- 顧客クレームにすぐに対応し不満を満足に変える力
などがまさにこれです。
そういう力は一部の人だけのもの、特に力がある人だけのものと思っていたかもしれません。それがそうでもないのです。ちょっとしたポイントを押さえれば、問題把握・解決力は比較的早く身につきます。
問題把握・解決力で必要な要素は、「分析力」「深掘り力」「洞察力」です。
それがあって初めて真実に近づきます。
・分析力
これは、多角的に見て、数字を集めたり整理したりし、特徴をとらえたメッセージを生み出す力です。言葉は固い印象を与えますが、誰にでもある能力です。「西に黒い雲があるとしばらくしたら雨が降るぞ」とか、「固い地面のある部分が湿っていたら掘り下げると水が出てくるかもしれない」とかそういった能力です。太古の昔からすべての人が持っている能力だと思います。
・深掘り力
分析力のうち、特に物事を深く掘り下げる力を言います。表面的な現象、発言、理由づけなどをすべて疑い、「いや、そうじゃないかもしれない」と検討を進めていきます。
深掘り力があれば、上司に「君の言うことは表面的で、通り一辺倒だね。新しさがないよ」などと言われなくて済みます。
深掘り力と「瞬時に動く」こととは相反しません。スピーディーに深掘りしていけば、どんどん知見が生まれて、成果につながっていくからです。
・洞察力
表面に何が見えるかではなく、本質が何なのか、本当はどうあるべきかを鋭く見抜いていく力のことです。騙されずに真実を把握する力と言ってもよいでしょう。深掘り力に近いですが、どんどん掘って真実に近づくというよりは、鋭く一発で見抜いていく感じです。
この3つは、近い表現ですが少しずつ違う点もあるので、キーワードとしては分けて考えるようにすると、理解が深まっていくと思います。
いつでもすぐに仮説を立てて動く
問題把握・解決力を身につける上で、「いつでもすぐに仮説を立てて動く」習慣がとても大切です。
仮説を立てるとは、「多分こうではないかな」と予想することです。ねらいをつける、と言ってもいいかもしれません。
テレビを見ようとしてつかないと、「あれ? リモコンが故障しているのかな」とまずは思うのではないでしょうか。次には「リモコンの電池がなくなってしまったのか」と電池を替えたり、「テレビのコードが抜けているのかな」と考えて、コンセントを確認したりするかもしれません。
このように「多分こうではないかな」と次々に考え、動いて問題を特定していきます。
次々に考えることで一気に問題の本質が見え、どうすればいいかも見えてきます。
料理でも、スポーツでも、楽器演奏でも、英語学習でも、「どうもうまくいかない」「こうしたらどうかな」「ああしたらどうかな」と考えながら試行錯誤をして、改善していきます。
いつでもすぐに仮説を立てて動くことが習慣になっていれば、仕事もそれ以外もどんどん前に進むので、すごく楽です。
仮説思考は誰にでもできます。仮説思考を本気でマスターする5つのステップをご説明します。
① いつも最初から「こうしたらいいかな?」「ああしたらいいかな?」と考える
いつも最初から「これかな?」「あれかな?」と考えることを習慣にします。そうすると、いつも頭を使い、いつも仮説を考えることが癖になり、楽しくもなっていきます。難しく考える必要はありません。すなおな気持ちで疑問を感じてください。
② 「こうだとするとこうかな、ということはああかな」と推理する
次に「こうだとすると、こうかな、ということはああかな」と推理していきます。
推理をどんどん深めていくことがポイントです。「こうなら、こうかな」と推理できる人は多いと思いますが、それをさらに二度、三度繰り返せる人は少数です。ぜひチャレンジしてみてください。
③ 人の話を常に疑い、どんどん深掘りしていく
人の話を常に疑い、どんどん深掘りしていくことが仮説思考では何より大切です。
人の話はほとんど間違っていると思っても、行き過ぎではありません。ウソをつくつもりは全くなくても間違っていることはごく普通にありますし、本人の利害関係からゆがんでいることもありますし、考えが浅すぎることもよくあります。
④ 表層的な問題ではなく、本質的な問題を常に考える
こういう問題があると聞いたら、表面にとらわれるのではなく、本質的にどういう問題があるのかをいつも考えるようにします。例えば、「会議が多い、長い」と言われたら、「会議の種類が多いから」「会議時間が長い」とだけ考えるのではなく、「役割分担ができていないのではないか」「権限委譲が進んでいないのではないか」「意思決定するべき人がしていないからではないか」とかをすぐに考えます。
⑤ 本質的な問題に対する本質的な解決策を常に考える
本質的な問題が把握できたら、本質的にはどういう解決策が必要かを考えます。本質を押さえているので、間違った無意味な解決策になることは避けられます。そうなると、常に効果的な仮説思考が体現できることになります。
仮説思考が苦手な方もいるかもしれません。
ただ、たぶん、苦手意識があって、本当はできるのに避けていることのほうが多いものです。生真面目だったり責任感が強すぎたりすると、そうなりがちです。
また、いろいろ想像するより、決まったことだけやっていればいい、決まったことだけやっていたい、という方もいます。そういう方には違和感があるかもしれません。
ただ、仮説思考ができると確実に仕事ができるようになりますし、気分もよくなっていきます。すぐに動けるようになり、さらによい結果につながります。そのためには、少し発想を変えてみるとよいかもしれません。世界が急速に広がっていきます。
仮説はいい加減に「エイヤ!」ではなく、常に感度を高く保ち、何に対しても自分なりの考えを持つこと、持とうとすることが大切です。
インタビュー、データの分析なども進めると、新たな仮説がどんどん湧いてきて、仮説を修正し、あっという間に鋭い、確かにそうだろうなと思えるような仮説が立てられるようになります。
このプロセスのスピードとダイナミックさについていけない方もいるので、あなたが気持ちよく仮説を話してもついてこられない部下、友人、後輩がいたら、決してバカにせず、丁寧にステップと仮説を修正していったプロセスを説明してあげてください。
それ自体で仮説の正しさを確認することもできますし、新たな仮説を思いつくきっかけにもなります。
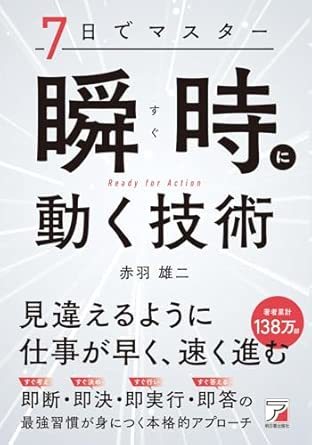
経営戦略の立案と実行支援、新組織の設計と導入支援、マーケティング、新事業立ち上げなど多数のプロジェクトをリード。マッキンゼーソウルオフィスをゼロから立ち上げ、120名強に成長させる原動力となるとともに、韓国LGグループの世界的躍進を支えた。
マッキンゼーで14年勤務した後、「日本発の世界的ベンチャー」を1社でも多く生み出すことを使命として、ブレークスルーパートナーズ株式会社を共同創業。ベンチャー経営支援、中堅・大企業の経営改革、経営幹部育成、新事業創出に取り組んでいる。コロナ前はインド、ベトナムにも3年間毎月訪問し、現地企業・ベンチャーの経営支援に取り組んだ。
東京大学、電気通信大学、早稲田大学、東京電機大学、北陸先端科学技術大学院大学講師としても活躍。下関私立大学客員教授。
著書は、44万部突破の『ゼロ秒思考』を始めとして、国内27冊、海外30冊、計138万部。
※画像をクリックするとAmazonに飛びます。
- 「すぐに動ける人」の秘密! 迷いをなくし結果を出す思考法とは
- 迷わず動く「仮説思考」5つのステップで仕事が加速
- 誰でも仕事が速くなる! スピードアップの4つの鍵
- 仕事がデキる人になるには? PDCAを回す3つのポイント
- 見返りを求めない「ギブ&ギブ」が人生を好転させる
- 踏み出せないのは「思い込み」かもしれない
