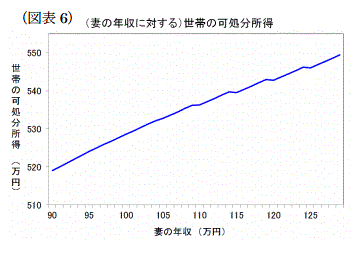就労調整原因となる3つの壁
配偶者控除の見直しに注目が集まっているが、就労調整の原因となっている壁は主に3つある。
3つとは、「①税制上の配偶者控除による103万円の壁、②社会保険料支払いが必要となる130万円の壁、③企業の配偶者手当による103万円の壁」である。それぞれについてどのような壁なのか確認していこう。
◆①税制上の配偶者控除による103万円の壁
ⅰ)所得税・住民税計算について
(夫が会社正社員、妻がパートタイム労働者または専業主婦である世帯を基本に話を進める。)
配偶者控除とは、所得税や住民税を算出する際、納税者に配偶者がいる場合に受けられる優遇措置のようなものである。会社員の夫には年間の給与収入に対して所得税や住民税が課される。住民税と所得税の納税額の求め方は(図表2)のようなイメージとなる。
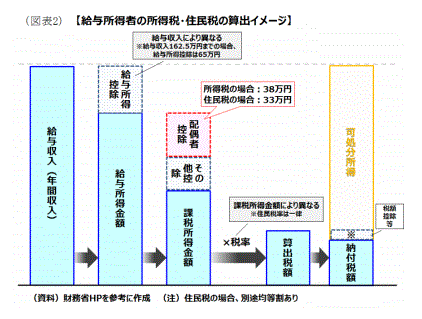
夫の年間の給与収入は、会社員の必要経費という考えから給与所得控除が差し引かれ、給与所得金額が求められる。給与所得金額から配偶者控除やその他の所得控除が差し引かれた課税所得金額に税率(所得税率・住民税)をかけたものが算出税額となる。
そして、税額控除等(*2)を加味し最終的な納付税額が決められる。配偶者控除が所得税と住民税に適用されれば、課税所得金額の金額が少なくなり、最終的な納付税額も少なくなる。
ⅱ)税制上の103万円の壁は既に存在しない
103万円の壁とは、①妻の年収(給与収入(*3))が103万円(*4)を超えると所得税が生じることに加え、②夫の所得税・住民税の計算において配偶者控除の適用が受けられなくなるため、夫自身の年収が少なくなる。このため妻は年収が103万円を超えないように就労調整を行っているというものだ(*5)。
しかし、これには誤解がある。妻の年収が103万円を超えると、“損"をする(=手取りが減る)ということはない。確かに妻年収が103万円を超えると夫の可処分所得は減少するという逆転現象が生じるが、世帯の年収でみれば、それは生じない。
このことを確認するために、具体例として夫の年収が550万円(*6)と一定であると仮定し、妻の年収(*7)が変化に応じて夫・妻・世帯の可処分所得がそれぞれどのように変化するかを確認してみよう。
ⅲ)夫と妻のそれぞれの可処分所得の変化
夫は、妻年収が103万円を超えると配偶者控除の適用が受けられなくなるが、妻年収141万円未満までは配偶者特別控除が受けられる。配偶者特別控除(*8)は、1988年に妻年収が103万円を超えた後も、夫の可処分所得が急激に減少することを防ぐために控除が段階的に少なくなるように導入されたものだ(図表3)。
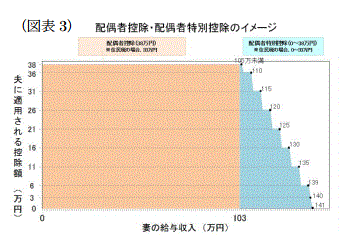
この結果、妻年収103万円超104万円以下であれば、夫は配偶者特別控除を配偶者控除と同額である38万円分の適用を受ける。夫の可処分所得の減少は、104万円超から141万円未満にかけて生じる(図表4)。
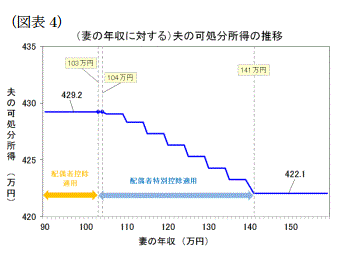
夫の可処分所得は、妻年収が104万円以下の場合429万円だが、配偶者特別控除が受けられなくなる妻年収141万円以上では422.1万円まで減少する。夫の可処分所得の損得だけで考えれば、年収141万円以上とならない妻は104万円以下で働いていた方が夫の可処分所得の減少を招かずに済む。
次に妻の可処分所得の変化を確認しよう。妻年収103万円超となると所得税や住民税(*9)が発生することで就労調整を行うという指摘もある。
税の支払いが生じる年収時点から、妻の年収に対する可処分所得の増加率は、1から徐々に低下するものの限定的である上に、夫のような「逆転現象」は生じない。このため可処分所得の損得の観点からは、働く時間を抑えるよりも働けば働くだけ可処分所得は増加するので就労調整を行うのは合理的ではないことがわかる。
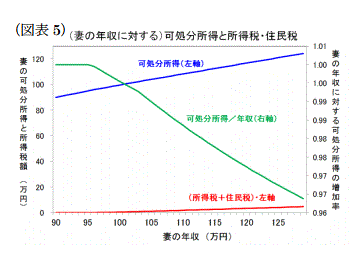
ⅳ)世帯(夫+妻)の可処分所得の変化
夫と妻のそれぞれの可処分所得の変化を確認したが、生計を一つにしている夫婦であれば夫と妻両方の可処分所得を合計した世帯の可処分所得の変化が重要である。夫と妻の可処分所得を合計した世帯の可処分所得の変化をみると103万円に壁は存在しないことが確認できる(図表6)。
妻年収104万円を超えると夫の可処分所得は減少するが、同時に妻の可処分所得がそれを上回って増えるため可処分所得は減少しない(*10)。これは配偶者特別控除が導入され、配偶者控除で受けられていた38万円の控除が段階的に少なくなるようになったからだ。つまり、1988年に配偶者特別控除が導入されたことで、税制上の103万円の壁はなくなっているのである。